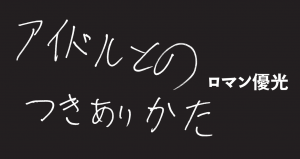[往復書簡]国籍のゆらぎ、たしかなわたし【第一期】|最終回|偏見をなくしていくために(木下理仁)|安田菜津紀+木下理仁
![[往復書簡]国籍のゆらぎ、たしかなわたし 安田菜津紀+木下理仁 じぶんの国籍とどうつきあっていけばいいだろう。 「わたし」と「国籍」の関係のあり方を対話のなかから考える。](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/cc287e0e2124ac6ae65dbe1ccbd8faef-1024x545.png)
[往復書簡/第一期]最終回
偏見をなくしていくために (公開終了)
木下理仁
・・・・・・・・・・
■この連載が本になります(2025年6月23日発売、定価2000円+税)
2021年2月から全6期36回にわたって、「わたし」と「国籍」をめぐって木下理仁さんとゲストが手紙をやりとりしてきた本連載を、2025年6月、『国籍のゆらぎ、たしかなわたし──線をひくのはだれか?』として、書籍化しました。ゲストによる書き下ろしや、書籍のみに収録した特別鼎談など、より充実した内容になっています。「わたし」にとって「国籍」ってなんだろう? 「わたし」たちは「国籍」とどう向き合えばよいのだろう? そんな疑問と真摯に向き合う一冊です。ぜひご一読ください。
また、YouTube番組「本チャンネル」にて、本書の共著者・木下理仁さんへの本書にまつわるインタビューが公開されています。あわせてぜひご覧ください。
木下理仁(きのした・よしひと)
ファシリテーター/コーディネーター。かながわ開発教育センター(K-DEC)理事・事務局長、東海大学教養学部国際学科非常勤講師。1980年代の終わりに青年海外協力隊の活動でスリランカへ。帰国後、かながわ国際交流財団で16年間、国際交流のイベントや講座の企画・運営を担当。その後、東京外国語大学・国際理解教育専門員、逗子市の市民協働コーディネーターなどを経て、現職。神奈川県を中心に、学校、市民講座、教員研修、自治体職員研修などで「多文化共生」「国際協力」「まちづくり」をテーマにワークショップを行っている。1961年生まれ。趣味は落語。著書に『国籍の?(ハテナ)がわかる本』(太郎次郎社エディタス)など。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)