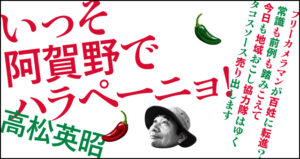保護者の疑問にヤナギサワ事務主幹が答えます。|第4回|学校行事の写真、ほしい?(……よね)|栁澤靖明
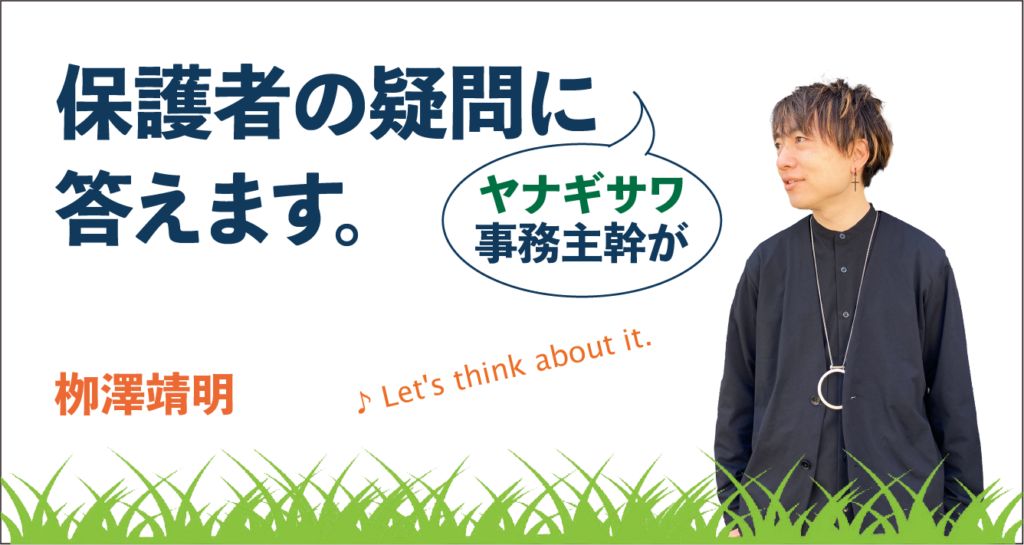
第4回
学校行事の写真、ほしい?(⋯⋯よね)
栁澤靖明
「はい! チーズ」──パシャ。今回は写真の話をしようと思います。
そのまえに、なんでチーズっていうの? って気になりませんか。その疑問から解決しましょう。最近は「教えて、生成AI」の時代ですね。もう、保護者の疑問にヤナギサワ事務主幹が答える時代は終わり、「保護者の疑問に生成AIが答えます。」が始まるかもしれません(笑)。それは冗談として、愛用している生成AI、Copilotさんに聞いてみました(Prompt:「はい! チーズ」の由来を教えてください)。
Copilotさんがいうには、ウェブサイト「日本の年中行事」によれば「由来は英語の『Say cheese!』にあり」、「英語で『cheese』と発音すると、口元が自然に笑顔の形になるため、写真撮影時に使われるようになった」らしいです。日本では1963年に雪印乳業がチーズのコマーシャルで「はい、チーズ!」というフレーズを使い、そこから広まったそうです。他国には「チーズ」以外のかけ声もあって、韓国では「キムチ」、メキシコは「ウィスキー」らしいですよ。日本でも「タラバガニ」や「ずんだもち」があるとかないとか⋯⋯さすがにどうでもいいですね(笑)。
さて。写真は写真でも、撮影ではなく、今回はその販売について考えます。学校で記録用や広報用に写真を撮るのは理解できますが、記念写真の販売ってどうなんでしょうかね~って、ずっと思っていました。今回は、ヤナギサワ(いちおう高校生と中学生の保護者)の疑問に、ヤナギサワ事務主幹がみずから答えます。
♪ Together──Let’s think about it. ♪
前回は、運動会を扱いましたね(第3回「運動会の費用はだれが出す?」)。運動会といえば、ビデオ&写真撮影でしょう。「場所とり」のため、保護者が深夜から校門前に列をつくっていた学校もありました(ヤナギサワ未体験ゾーン)。PTAの広報部はワッペンを肩につけてフィールド内から撮影が許される、というVip待遇の話もよく聞きます(ヤナギサワ体験ゾーン)。また、学校側も次年度に向けた記録として定点カメラでビデオ撮影したり、学校だよりや学級だよりに使う目的で写真撮影したりしています。
運動会だけではなく、あらゆる学校行事に撮影はつきものですね。運動会なら、保護者もフリーで撮影できる場合が多いです(エリア指定などはあっても)。合唱コンクールや音楽祭ともなれば、撮影禁止が多くなります。遠足や修学旅行などでは、学校が委託した業者の撮影がおもでしょうか。
そこで、今回の問題です。保護者に撮影を禁止している行事や、そもそも参加できない行事では、業者による撮影とその写真の販売がなされます(ということが多いです)。最近では見かけませんが、むかしは廊下にズラッーと掲示して、申し込み用紙兼集金袋に希望番号とお金を入れて注文するのがふつうでした。まぁ、保護者なら子どもの活躍を見たいし、思い出に残したいという気持ちもあるでしょう。以下、それを否定したいわけではありませんので悪しからず⋯⋯。
でも、ビデオや写真の「販売」って、教育活動とは関係ありませんよね。いわば卒業アルバムと同じく、「少々ドライに表現すれば、授業で使う教材でもない、完全なる『思い出の品』」です(事務主査エディション・第15回「卒業アルバムって、全員購入しなきゃダメ?」)。そこまでいいきっちゃうと「少々ドライ」ではなく、乾ききっているかもしれませんが。
ただし、修学旅行の写真を事後学習に使うということはあります。「思い出」でもありますが、修学旅行という学びのまとめとして、総合的な学習の時間や学級活動の時間を使うことも多く、授業の一環だととらえられますね。でも、授業で使うなら「販売」ではなく、公費負担するべきでは? という論も出てきそうです。じっさいに、ひとり3枚までという方法で公費負担したことも、学校のプリンターで印刷(公費負担)したこともあります。

(ちなみに、この写真はフリー素材です)
──というように論点はいろいろありますが、今回は販売行為それ自体を考えます。むかしはアナログ注文だったので、集金袋を教室で集めたり、販売業者へ渡したりするような手間がありました。デジタル化が進んだ現在では、オンライン注文です。わが子の顔を登録すると、何百枚という写真から自動的に、わが子が写っている写真だけピックアップできる機能もあるようです。そこからほしい写真をタップして、オンライン決済すれば、自宅のポストに到着です。学校の負担といえば、二次元バーコードが記載された手紙の配付くらいでしょうか。それすらもメール配信であれば、かぎりなく手間がなくなります。だからこそ、販売行為そのものの是非などが検討されにくくなっているかもしれません。
でも、ちょっと考えてみてください。たとえば、個人情報や肖像権の問題があります。学校だよりに写真を載せたくない子どもには配慮しますが、写真自体を撮られたくない子どもは配慮されているのでしょうか。写真を撮られる=販売される可能があります。教職員が撮影するならどうにか対処できるかもしれませんが、販売を前提にする場合は、業者が入ります。「あの子は撮らないでください」というわけにもいかないでしょう。撮影後、販売まえにその確認を学校がするのはたいへんな手間ですし、「働き方改革」進行中の学校に求めることではありません。それこそ学校の業務ではないですし、そんなことやっていたら真っ先に切り離す部分でもあります。
もっといえば、集合写真の問題も生じます。とくに修学旅行などでは、かならずといっていいほど集合写真を撮り、旅行代に組みこむかたちで販売することもあります。集合写真は、L判より大きいサイズがほとんどなので、値段も高いですね。そう、費用面の問題もなくはありません。オンライン決済ではその手数料が必要だったり、送料もかかってきたりします。完全なる受益者負担といわれれば、もちろんそうですけどね(主査エディション・第41回「なんで受益者負担っていわれるの?」)。
さらに、そもそも論を申し上げれば(急にあらたまってみる)、公立学校の行事を商売に提供してもいいのか? という疑問もあります。ワークやドリル、実習材料なども業者から購入しますし、教科書だって採択したメーカーから購入していますが、それは教育活動に直接必要なものです。しかも、学校教育法では「教材[=教科用図書=教科書:筆者注]以外の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる」(第34条第4項)、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律にも「採択されたものを購入」(第3条)という法的根拠もあります。法的根拠こそありませんが、上履きなどの靴(主査エディション・第2回「そんなにいろいろな靴、必要ですか?」)も必要です。このように、ほかと比べるとどうでしょうか。写真自体や思い出の記録には、ひとそれぞれの価値があるでしょう。しかし、教育活動における「写真の販売」は、いろいろなリスクを考慮すると疑問が残ります。
じゃあ、どうするのかというまとめに入りましょう。もちろん、不買運動により販売を停止させよう! と扇動するつもりは毛頭ありません。写真販売は違法だ! と説得できるほどの知恵もありません。⋯⋯なんかいつもと雰囲気がちがうと思われるかもしれませんね。ただ、あらためて教育活動という枠でとらえたとき、見直しが必要な部分かなと考えました。いわば令和時代の「シン・教育活動」を標榜して、古い慣習にとらわれず、いまに即した学校へ生まれ変わるべきではないでしょうか。学校も勇気を出して「シン・教育活動」を展開し、保護者もそれを受け入れていく──今回の話でいえば、動画や写真が手に入らなくなっても大騒ぎしない──ことで、教育活動のありかたが生まれ変わってくる⋯⋯かもしれません。
Let’s think about it.
今回は、1枚〇〇円もするんだし、必要性も低いから見直しましょう! っていう提案ではありません。率直にどうなんだろう?⋯⋯という疑問を書いてみました。正直なところ、ヤナギサワ自身も葛藤があります。しかし、疑問が残る以上は、解決に向けたなんらかの前進も必要でしょうね。 今回の問題提起を受けて、みなさんはどう考えますか? 学校行事の写真、ほしい?(⋯⋯よね)
栁澤靖明(やなぎさわ・やすあき)
「隠れ教育費」研究室・チーフディレクター。埼玉県の小学校と中学校に事務職員として勤務。「事務職員の仕事を事務室の外へ開き、教育社会問題の解決に教育事務領域から寄与する」をモットーに、教職員・保護者・子ども・地域、そして現代社会へ情報を発信。研究関心は、家庭の教育費負担・修学支援制度。具体的には、「教育の機会均等と無償性」「子どもの権利」「PTA活動」などを研究している。
おもな著書に『学校事務職員の実務マニュアル』(明治図書)、『学校徴収金は絶対に減らせます。』『事務だよりの教科書』(ともに学事出版)、『本当の学校事務の話をしよう』(太郎次郎社エディタス、日本教育事務学会「学術研究賞」)、共著に『隠れ教育費』(太郎次郎社エディタス、日本教育事務学会「研究奨励賞」)、『教師の自腹』(東洋館出版社)、編著に『学校事務職員の仕事大全』『学校財務がよくわかる本』(ともに学事出版)など。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)