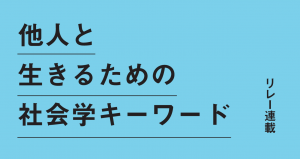いっそ阿賀野でハラペーニョ!|第11回|種まきからはじめます|高松英昭
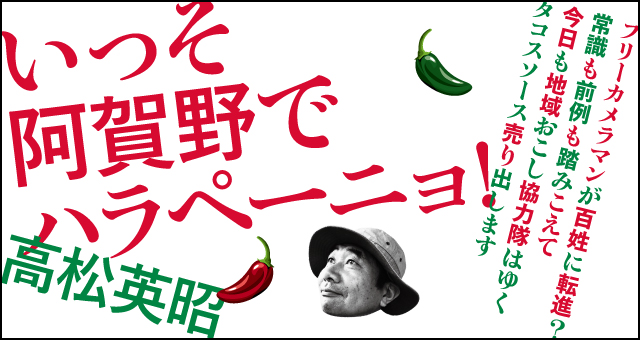
第11回
種まきからはじめます
売り場にレシピを置いてみた
前回書いたとおり、阿賀野市に来るまえには市民農園で栽培したハラペーニョを産直市場で販売していたのだが、はじめは思ったように売れなかった。小さな畑なのではしばしまで手が届き、収穫したハラペーニョは形も大きさも申し分なかった。それに、産直市場でハラペーニョを販売していたのは私だけだったので、そこそこ売れるとたかをくくっていた。だが、実際はちょびちょび売れる程度だった。20袋を店頭に並べて、平日は5袋ほど売れればいいほうで、買い物客が多い週末でも10袋以上売れたら小躍りするほどだった。
どうやら、私にとってハラペーニョは「売れるもの」だが、買い物客が「買いたくなるもの」ではないらしい。だとしたら、買いたくなるようにすればいいのである。そこで、ハラペーニョを使った料理を紹介するPOPを作ることにした。
自宅の台所でまずは定番のハラペーニョのピクルスを作り、それから、ハラペーニョ柚子胡椒やハラペーニョチャーハンなどレパートリーを広げて、その写真をPOPにして売り場に立ててみた。すると、少しずつだが売上が伸びていった。私は調子にのって、ハラペーニョペペロンチーノやハラペーニョカレー、ハラペーニョ焼きそばなども開発した。
ハラペーニョをただ輪切りにしたり、刻んでいっしょに炒めたりしただけだが、買い物客の頭のなかでハラペーニョと料理が瞬時に結びつけばいいのである。スーパーマーケットに無料のレシピ集が置いてあるのも同じ理屈だ。「買った食材をどのように食べればいいのだろう」と悩むのは負担で、みんな、できるだけ悩みを減らしたいのだ。食いしん坊な私は昼食を食べながら夕飯は何を食べようかと悩むほど、1日の大半を「何を食べようかな」と悩んでいるが、多くの人はほかにも悩むことがたくさんあるのだろう。
そもそも、ハラペーニョを使ったアレンジ料理は、どれも美味しかった。辛み成分であるカプサイシンは胎座とよばれる白いワタの部分に多く含まれている。白いワタと種をとり除いて果肉部分だけを使えば、舌を突き刺すような辛みではなく、旨味と辛みが輪になって舌の上をくるくると転がるみたいで、ハラペーニョをしっかりと味わうことができた。とりわけハラペーニョ柚子胡椒は、ワサビがわりに刺身の薬味にすると美味しかった。一般的な柚子胡椒は青唐辛子を使うが、ハラペーニョのほうがさわやかな辛みで、ブリなど脂がのった刺身との相性は抜群だった。
というようなことも書き込み、せっせとPOP作りに励んで、ハラペーニョのわきに立てまくった。効果を確かめようと、納品のついでにしばらく売り場に残り、買い物客の反応をこっそり探っていると、40代ぐらいのカップルとおぼしき二人連れが「ハラペーニョチャーハンだって。買ってみる?」と言ってハラペーニョを手に取ってくれた。ほかの日にも、POPを差し替えているときに「いつもは青唐辛子で自家製の柚子胡椒を作っているけど、ハラペーニョでも作ってみるわ」と年配の女性に声をかけられ、2袋買ってもらったこともあった。
「タコスソースの使い方がわからない人が多いと思うので、レシピも宣伝する必要がありますね」というH課長補佐の言葉はまさにそのとおりなのである。


まずは250苗をどう育てるか
ともかく、宣伝はあとの話で、まずは阿賀野市でハラペーニョを栽培しなければならない。秋から年末にかけては、事業計画を提案して予算案を作成、予算ヒアリング、各課への協力のお願いなど市役所内での活動が多かったが、年明けからは、種まき準備など具体的に動きださなければならなかった。タコスソースの原料となるハラペーニョが収穫できなかったら、それで事業は頓挫である。さいわい、農林課の協力で市が運営する「うららの森農園」で栽培することは決まっていたから、つぎにやるべきことはハラペーニョの苗作りである。
ハラペーニョを育てるには気温20度以上が望ましく、新潟の気候で考えると、5月のゴールデンウィーク前後からハラペーニョの苗を畑に定植できる。発芽してから畑に定植できるまで生長させるには2か月ほどかかるので、逆算すると3月にはハラペーニョの種をまく必要があった。
苗については、おおまかに3つの方法がある。①ホームセンターなどで購入する、②苗を生産する農家に注文する、③自分で種まきをして育苗する。定植する苗が少なければホームセンターなどで購入するのが手軽だが、今回は約250苗を定植する予定なので、ホームセンターなどで購入するのは予算的に論外である。苗農家に直接注文すれば少しは安価に抑えられるが、それでも予算的に厳しかった。そこで、種まきをして苗から作ることにした。自分で作ったほうが面白いし、ハラペーニョもなおさら愛おしくなる。
畑に定植できる苗数を算定するには、畑の面積と畝幅から畝が何本立てられるか、畝と畝との間隔はどれくらいにするか、苗をどのくらいの間隔で植えるかなどいくつもの要素を連立方程式で計算する必要がある。
私は数字が苦手なので「必要な数字を入力するだけで苗数がパパッと出てくる計算表をエクセルで作成できませんかね」と、同じ課にいるデジタル師匠にお願いしてみた。デジタル師匠は大手情報機器メーカーから阿賀野市役所に派遣されているDX(デジタルトランスフォーメーション)専門員で、首都圏の駅構内で開催されていた「阿賀野市物産フェア」を訪れて阿賀野市が気に入り、みずから志願して赴任していた。
「農業のことはよくわからないので、必要な情報を教えてくれればやってみますよ。空いてるときにやるので、少し時間をください」とデジタル師匠は言って、必要な情報をあらかたメモした。それからほどなくして、「畑つくる計算式」というエクセルのファイルを作ってくれたのだった。自分でもネットで農業のことを調べながら、使いやすい計算表を作成してくれたらしい。
約250苗をどのように育苗するかが、ハラペーニョ作りの最大の課題だった。予算面だけでなく、育苗にはいくつものハードルがあった。まずは、気温である。発芽させるには気温が20度くらいは必要だが、新潟の3月は残雪があるくらいなので、発芽に必要な気温にはとうていおよばない。暖かな環境を人工的につくりだすことが必要で、ビニールハウスのなかで加温して発芽させて育苗することになる。そもそも、ハラペーニョはメキシコ原産なのだ。うららの森農園にビニールハウスがあり、資材置き場として利用しているので、少し整理すれば育苗するくらいのスペースは確保できそうだった。
次のハードルは勤務時間である。市に任用されている私の身分は公務員扱いになるので、勤務時間や休日数も細かく定められている。発芽させて育苗するにはきめこまやかな管理が必要で、週休2日というわけにいかないのだ。とはいえ、週末ごとに時間外勤務を申請するわけにもいかない。こっそりやるしかないかと腹をくくりかけたところ、またまた人に恵まれたのである。

またも助っ人あらわる?!
うららの森農園ではICT(情報通信技術)を活用したパイロット事業として、中玉トマトのフルティカを栽培している。同期の地域おこし協力隊員の荒木美和子さんがそこで活動しているので、「フルティカの苗を生産している苗農家さんに、育苗についていろいろ教えてもらいたいと思っているんだけど」とお願いして連絡をとってもらい、ふたりで苗農家を訪ねることになった。
水田が広がる道路を走っていくと、遠くに5棟ほどのビニールハウスが連なっている一角が目に入った。まわりは水田なので見通しが抜群によい。もう3月に入っていて、水田に堆肥を入れる作業も始まっていた。そろそろハラペーニョの種をまかなければいけない時期なので、焦りはじめていた。道中は信号機もないのでスピードメーターを確認しないと、ついつい速度を出してしまう。公務員になってから、スピード違反と一時停止違反にはことさら気をつけるようになった。法令順守である。私はすぐに環境に順応するタイプなのだ。
3月とはいえ冷たい風が山から吹き下ろすように吹いていて、体感で10度もないように感じられた。ダウンジャケットを着ても、まだ肌寒いくらいだ。だが、外気から遮断された育苗ハウス内は暖かかった。育苗ハウスのなかにはビニール状のトンネルが3本ほど縦に連なるように作られていて、そのトンネルのなかに農業用電熱シートが敷かれ、そのシートの上に種をまいた育苗トレイが並べられていた。種まき培土が含んでいる水分が蒸発して、トンネルのビニールを内側から白く曇らせている。発芽をうながすのに適切な気温と水分が保たれているようだった。
苗農家の音田淳さんはほっそりとした体形で、物腰が柔らかく、穏やかな口調で話す人だった。
「やはり、ここまでしないとダメなんですね」。音田さんにすがるような口調で私は言った。
「いやー、ここまでしなくても、意外とピョコンと発芽するものだよ」と音田さんがあっけらかんと答えてくれるのを心のなかで期待していたのだが、「いまの時期は温度を高くしてあげないと発芽しないからね」と、すがるようにつかんだ手をやさしく振り払うように、音田さんは教えてくれた。
「そうですよね」と返答しながら、どのように失敗せずにハラペーニョの種を発芽させて育苗するか、頭のなかではぐるぐると思考が回転していた。「ハラペーニョが発芽しませんでした。ので、今年度の事業はこれで終了です。この失敗を糧にして、来季またがんばります。てへっ!」とは言えない。私にも、オブラートくらいの薄さではあるがプライドや見栄もある。それに予算ヒアリングで指摘があったように、「趣味」ではなく「事業」として取り組んでいるのだ。
思考がぐるぐると回転する脳内で、映画「となりのトトロ」でトトロが頭上に傘をずんずんと持ち上げるごとに、庭にまいた種がピョコンピョコンと発芽するシーンを思い出した。トトロがいてくれたらな、と妄想しながら「音田さんのアドバイスを受けながら、ここでハラペーニョを育苗することは可能でしょうか。そのかわり、できるだけ農作業のお手伝いをさせていただきます」と音田さんにお願いしてみた。音田さんにトトロになってもらうアイデアをとっさに思いついたのだ。

どれも同じ重量になるように、ハラペーニョの大きさを見ながらパズルみたいに組み合わせて詰めた
(つづく)
高松英昭(たかまつ・ひであき)
1970年生まれ。日本農業新聞を経て、2000年からフリーの写真家として活動を始める。食糧援助をテーマに内戦下のアンゴラ、インドでカースト制度に反対する不可触賤民の抗議運動、ホームレスの人々などを取材。2018年に新潟市にUターン。2023年から新潟県阿賀野市で移住者促進のための情報発信を担当する地域おこし協力隊員として活動中。
著書(写真集)に『STREET PEOPLE』(太郎次郎社エディタス)、『Documentary 写真』(共著)などがある。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)