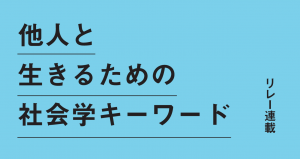いっそ阿賀野でハラペーニョ!|第8回|そうだ、タコスソースを作ろう|高松英昭
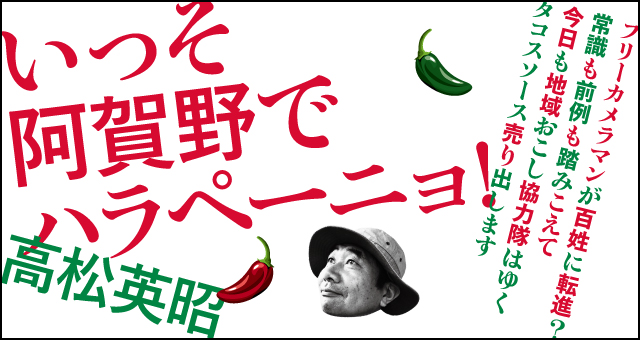
第8回
そうだ、タコスソースを作ろう
来年度はどんな活動をする?
朝、ラジオ体操を終えて席に戻ると、「高松さん、ちょっといいですか」と担当者に声をかけられた。
「来年度の活動計画を考えてもらえませんか。まだ着任して3か月しかたっていないので難しいとは思うのですが、来年度の活動に必要な予算を計上しないといけないんですよ」と、担当者が申し訳なさそうに言った。
「まだ10月なのに?」。あまりにも唐突なので、私は聞き返した。
「そうなんです。いまごろから役所は予算案の作成が始まるんですよ」
「でも、すぐに来年度の活動計画を考えるのは大変かも」
「そうですよね。具体的な活動計画はこれからゆっくり考えてもらえばいいのですが、活動に必要な物と金額だけでも教えてもらえませんか」
「ちょっと考えてみますね」
「よろしくお願いしますよ。いやー、役所ってそういうところなんです」
とまどっている私の顔を見ながら、担当者は自嘲気味に会話を結んだ。
情報発信に使うための機材はiPadと小さな一眼レフカメラがあるだけなので、手軽に動画撮影できるGoProというカメラがほしいと思っていた。YouTubeで動画配信もできるし、インスタグラムでも動画投稿の割合が増えている。
それに、カメラ付きドローンもほしい。映像の幅が広がり、魅力的なコンテンツが制作できる。iPadでAmazonのサイトを開いてGoProやドローンを検索して性能や価格を調べはじめると、なんだか楽しくなった。「なにを買ってもらおうかな」とクリスマスプレゼントを選ぶような感覚で販売サイトを見ているのだ。隣の席にいる担当者がサンタクロースに見えてきた。来年度の活動のキーワードは「動く、飛ぶ」だな、と妄想と欲望だけがふくらんでいく。性能と価格はピンキリで、性能が高いものは価格も高い。よく考えたら、使える予算がわからなければ、どれを購入したらよいか判断できない。
「予算はどれくらいあるんですか」。Amazonのサイトを眺めながら、玩具売り場で「いくらまでなら買ってくれるの」とおねだりする子どもみたいに担当者に聞いた。
「年間の活動費は決まっていますが、いくらまで使えるのかではなく、必要な物と金額を教えてください。それが本当に必要かどうかはあとで検討しますから」と担当者は諭すように言った。
ちょっと間をおいて、「高松さん、税金ですからね」と、いつもの殺し文句も加えて釘を刺しながら小さく笑った。
「ですよね。いつのまにか、サンタクロースにおねだりする気持ちになっちゃいました」
私は湧き出る欲望をなかったことにしようと、大きく笑った。
冷静になって考えると、来年度の活動の輪郭だけでも描いたほうがよさそうである。GoProやドローンを購入しても、「それでなにを撮影するのか」が問われる。これまでのことをふり返ると、私は阿賀野市で暮らす人びとの「Mi pais(私の国)」(第2回参照)を伝えたいと、多くの市民に会い、取材してきた。それぞれの「Mi pais」が移住者促進のための魅力的な情報発信につながると考えていたのだ。あなたも阿賀野市で暮らせばこのような「Mi pais」を創造できるかもしれませんよ、というリアルなメッセージを伝えたいと考えていた。
やりたいことと地域活性化を両立するには
それから数日間、稲穂に囲まれてクサネムを抜きながら、来年度の活動について考えていた。百姓の師匠であるミツグさんとの稲刈りがまだ続いていた。クサネムは田んぼに生える雑草で、種は米粒と似たような大きさなので、稲といっしょに刈りとってしまうとやっかいなのである。午前中は市役所に行き、午後から田んぼで作業する日が続いていた。秋空の下、黄金色の稲穂に囲まれて思考をめぐらせるというぜいたくな時間が続いた。
体を動かしながら考えると、市役所のデスクにいるよりも頭の回転数が飛躍的に上がるようだった。私は思いつきで行動することが多い。頭のなかにはいろいろな雑念がひしめいているが、福引のガラガラを回すように思考をめぐらせると、アイデアが飛び出してくるのだ。なので、大当たりすることもあれば、外れることある。基本、多くの福引がそうであるように、外れることが多いのだが。
そして、すべてのクサネムを抜きとるまでに、アイデアの玉がガラガラ頭脳から飛びだしてきた。「私自身が魅力的な『Mi pais(私の国)』を創造する」である。単純な結論だが、今回は特賞の大当たりが出た気分になった。
地方移住を前提に募集される地域おこし協力隊の制度は、自分のやりたいことを実現する自己実現と、活動をとおして地域課題の解決と向きあうことが重要な要素になっている。「自己実現」だけなら移住してやりたいことをすぐに始めたほうが話は早いし、「地域課題の解決」だけなら地方公務員になるか社会的企業やNPOをスタートアップしたほうがよい。地域おこし協力隊員の任期は「自己実現」と「地域課題の解決」を両輪にして、「Mi pais」を創造するためのモラトリアム期間ともいえる。
私がただ「これをやりたい。これがMi paisです」と企画を出しても、担当課は認めてくれないだろう。「高松さん、それは自分のお金で実現してください。活動費は税金ですからね」ということになる。「移住先で定住する」と「地域課題を解決する」という要素を盛り込むことで、地域おこし協力隊員として「税金を使う理由」ができるのだ。
少し話が脱線してしまうが、私はホームレスの取材をとおして「税金を使う理由」についてリアルな現場をみてきた。知り合いのホームレスの人が生活保護の申請を相談しに役所に行ったとき、窓口で「◎◎区役所のほうが生活保護を取りやすいから、そちらに行ってほしい」と投げやりな言い方で、その区役所に行くための電車賃だけを渡されたことがあった。それに、私の友人は人生を賭して貧困問題と向き合い、生活保護制度の改善を求めて活動している。だから、冗談のようなやりとりのなかでも「税金ですからね」という担当者の言葉を実直に受け止めている。「税金は本当に必要な人やコトのために」ということだ。
タコスソース計画の企画書をつくる
話をもとに戻すと、私にとっての「Mi pais(私の国)」は阿賀野市でハラペーニョを育ててタコスソースを作ることである。学生時代に1年ほどメキシコに留学しただけだが、私の人生を大きく変えた。「自分の知らない世界がある」という単純な経験だが、私は人生の大半を「自分の知らない世界」を知ることに費やしてきた。
スペイン語のほとんどは忘れてしまったが、メキシコで食べたタコスの味は覚えている。私にとってメキシコで毎日のように食べていた「タコスの味」が、人生を変えたメキシコの象徴になっている。「そんなこともあったよね」とメキシコ時代の思い出を客観的に消化できないでいる。だから、阿賀野市で創造する「Mi pais」を、自分にとってのメキシコにしたいのだ。自分で育てたハラペーニョでタコスソースを作って、阿賀野市で美味しいタコスを食べたいと思っている。そして、それが生業のひとつになれば幸せである。もちろん、地域おこし協力隊の活動だから、人口減の課題解決として求められている「移住者促進のための情報発信」という要素を中心に据える必要があった。ただ、それも私にとって願ったり叶ったりである。長年、メディア業界で働いていたので「情報発信」という仕事も好きだった。なので、企画書の作成はスムーズだった。
●タコスソースができるまでの過程を移住者促進や協力隊の活動を紹介するための情報発信コンテンツにする。
●原材料となるハラペーニョを栽培し、加工、流通販売まで一貫して行う農産物の6次産業化に挑戦して、農業、製造、商業領域での体験談を魅力的なコンテンツにする。とくに、新規就農希望者にとって訴求力ある情報にする。
●地域特性を活用した農業をする。
●タコスソースを使って地元の飲食店とコラボして地域を盛り上げる。
●店頭に並ぶ商品自体が地域ブランディングとPRになるようにする。
●任期終了後の生業のひとつにする。
おおまかに以上のような要素を加えて企画書を作成した。
阿賀野市に移住するまえから、ハラペーニョを栽培してタコスソースを試験的に作っていたことがあったので、荒唐無稽な計画だとは思っていなかった。「希望は目覚めている人間の夢である」という言葉をアリストテレスは残している。実現可能な夢が希望になる、ということだ。私はタコスソースにセカンドライフの希望を託すことにした。

この具材をオーブンで焼いて「パストール風タコス」をつくる。試作したタコスソースに豚肉を漬けてある

できあがり。かなりいい味だったが、まだまだ美味しくなるはずだと試作は続いた
いよいよ上司に提案の日
「ざっくりとしたイメージですが、来年度の活動計画の企画書ができたので、時間があるときに説明させてください」と。係長と担当者に声をかけた。
それから、市役所内の通路にある4人掛けの席に向きあって座り、企画書を手渡して説明した。企画書にはタコスソースを中心にして、それが活動や地域にどのような効果が期待できるかをチャート図で描いた。
係長は穏やかな雰囲気で説明に耳を傾けていた。担当者は「これ、大丈夫ですかね」という雰囲気を漂わせながら、ちらちらと視線を係長に向けている。私と担当者は、係長の表情が気になっていた。「さすがに、これは活動の範囲を超えているので無理だと思います」と微笑みながらささやくように言われたら、それでおしまいである。
「あくまでも、移住者促進のための情報発信活動です」。私はきっぱりと言いきって説明を終えた。ここまできたら、揺るがない自信が最大の根拠になる。
「課内で検討しますね」。係長は微笑みながらささやくように言った。
これまでも、情報発信の内容について細かく指示されることはなく、「できるだけ、自由に活動してもらおう」という課内の雰囲気を感じていたので、多少の修正を求められることはあるかもしれないが、企画が通らないことはないだろうと楽観していた。しばらくして、企画をより具体的に検討するために必要な経費を算出して、予算案を作ることになった。課内でどのような検討をしたかはわからないが、門前払いにならずにすんだようだった。

今年、ハラペーニョを栽培する農地。春になっても気温が上がらず、雨も多く、農作業は遅れ気味であせる
(つづく)
高松英昭(たかまつ・ひであき)
1970年生まれ。日本農業新聞を経て、2000年からフリーの写真家として活動を始める。食糧援助をテーマに内戦下のアンゴラ、インドでカースト制度に反対する不可触賤民の抗議運動、ホームレスの人々などを取材。2018年に新潟市にUターン。2023年から新潟県阿賀野市で移住者促進のための情報発信を担当する地域おこし協力隊員として活動中。
著書(写真集)に『STREET PEOPLE』(太郎次郎社エディタス)、『Documentary 写真』(共著)などがある。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)