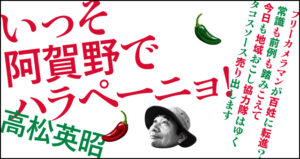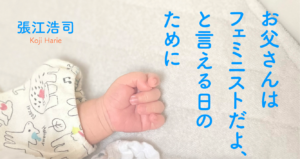雑踏に椅子を置いてみる|第7回|不本意な時間を過ごす理由はない|姫乃たま

第7回
不本意な時間を過ごす理由はない
姫乃たま
居場所で自分らしく振る舞う
………………………………………………………………
■この連載が本になります(2026年2月17日発売)
2024年11月から全10回にわたって綴られた本連載が、書き下ろしを加えて書籍化されます。
姫乃たま『なぜかどこかに帰りたい』
*
居場所は見つけるもの? つくるもの?
誰もがもっていそうなのに探し求めてさまよってしまう、そんな「自分の居場所」をめぐる本。ぜひご一読ください!
姫乃たま(ひめの・たま)
1993年、東京都生まれ。10年間の地下アイドル活動を経て、2019年にメジャーデビュー。2015年、現役地下アイドルとして地下アイドルの生態をまとめた『潜行~地下アイドルの人に言えない生活』(サイゾー社)を出版。以降、ライブイベントへの出演を中心に文筆業を営んでいる。
著書に『永遠なるものたち』(晶文社)、『職業としての地下アイドル』(朝日新聞出版)、『周縁漫画界 漫画の世界で生きる14人のインタビュー集』(KADOKAWA)などがある。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)