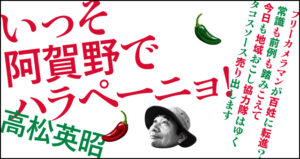お父さんはフェミニストだよ、と言える日のために|第8回|しょぼくれて灰色がかった子育て経験を共有したい|張江浩司
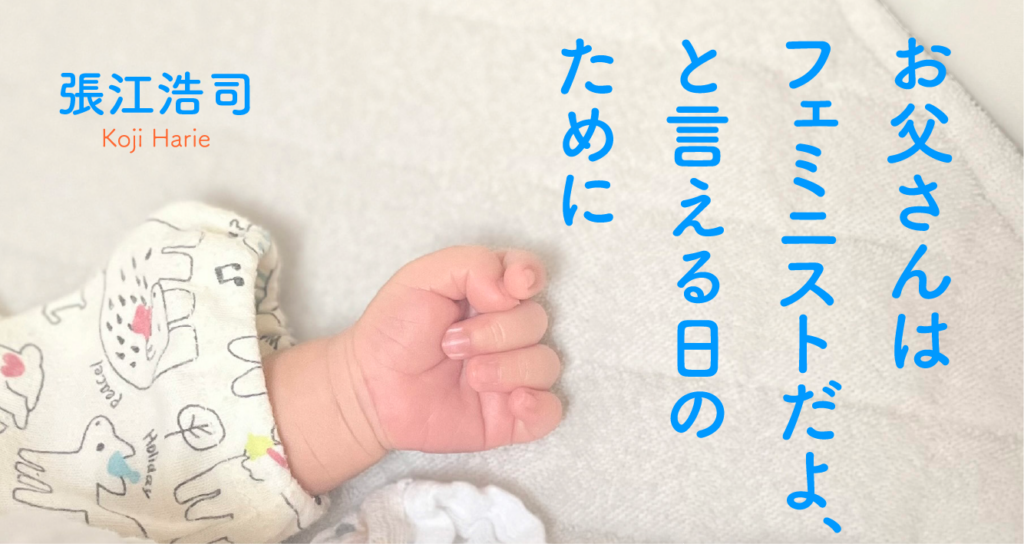
第8回
しょぼくれて灰色がかった子育て経験を共有したい
張江浩司
自由獲得への第一歩
まず子どもが何ができるようになったかを報告するのが恒例になってきましたが、今月は寝返りです。
育児に関するどの本にも動画にも、「生後半年前後から寝返りできるようになります」とあるが、子どもが実際に生まれてくるまで、いや正確にはついこのまえまで、なぜ寝返りに注目するのか見当がつかなかった。寝返りについて思いをめぐらせたことは、これまでの人生で一度もない。強いて言えば、おそらく小学5年生くらいのときに「寝たきりになると寝返りができなくて床ずれになってしまうから、ときどきだれかが体を動かさないといけない」と聞いて、「うわ、大変だなあ」と思ったくらいだろうか。寝返りができない困難は知っているが、できるようになるからといって、なんなんだ。まったくピンとこない。
しかし、目の当たりにしてすぐにわかった。これは「移動」だ。それまでずっと床に仰向けで寝そべっており、抱えられたりベビーカーに乗せられたりしないと動けなかったものが、ゴロリと転がることで半身ぶん、横に自分で移動できるようになる。うつ伏せになって手を突っぱり、方向転換もできるようになった。ずり這いで前進することはまだできないが、その意志はあるようで、どうにかして進もうとモゾモゾしている。けれど、どうにも上手くいかず、手を突っぱったぶんだけ後退してしまって、「違う! そうじゃない!」と言わんばかりにぐずっている。小学生のころにスイミングスクールで平泳ぎを習うも、なぜか少しずつ後ろに下がってしまって大変情けない気持ちになった記憶がフラッシュバックした。
コロナウィルスが猛威を振るい、世界中の都市機能がストップしかけた2020年。イタリアの哲学者ジョルジオ・アガンベンは、権力によって自由が制限され、人びとがそれを無批判に受け入れつつある状況に警鐘を鳴らした。アガンベンが一連の文章のなかで重視したのは「死者が埋葬される権利」、そして「移動の自由」だった。
哲学者の國分功一郎さんがアガンベンの主張をまとめた文章(「コロナ禍と世界の哲学者たち」)を引用すると、「移動の自由は単に数ある自由の中の一つ」ではなく、「移動の自由こそはまさしく自由の基礎」、「あらゆる自由の根源にある」。だからこそ「近代の刑法は罰金刑と死刑の間を、移動の自由を制限する刑で埋めたし」、「いかなる弾圧も移動の自由さえあればそれを逃れることのできる可能性がある」。
そう考えると、寝返りは自由獲得への第一歩ということになる。この子どもの自由はこの寝返りからはじまると思うと、コロンと転がる動作の一つひとつが市民革命だし、そこから近代というものがグングン立ち上がってきそうだ。なんと輝かしい。
広がっていく行動範囲に悩む
そうやってずっと目を細めていたいものですが、そうもいかないのが育児というもので、移動されると難易度がグッと上がる。まだウロウロできるほどではないにしても、さっきまでいたはずの場所にいないというのはそれだけでドキッとするし、手を伸ばせる範囲が広がったということは、その先にあるものをつかんできて誤飲するリスクも上がる。いつの間にか寝返りできるようになったということは、つぎの瞬間に突然ハイハイできるようになる可能性もあり、そうなると段差から落ちるかもしれないし、コンセント周辺をいじって感電するかもしれない。となると、親としてできることはとりあえずリサイクルショップに車を走らせて(私は免許持ってないので、正確には妻が走らせて)、ベビーサークルを調達してくることだ。
買ってきて早々に組み立て、そのなかに子どもを置く。これでいきなりケガをしたり死んでしまったりする危険は遠のいた。でも、ベビーサークルといえば聞こえはいいけれど、シンプルに表現すれば、これは子ども用の檻だ。子どもが自由を獲得したそばから、親は安全と引き換えにせっせとそれを制限している。「アガンベン、ベビーサークルに囲われた子ども見たらどんな顔するだろう」と、岡村靖幸の名曲みたいなフレーズが頭に浮かんだけども、「いやいや、ここは安全を優先させてください!」と心のなかのアガンベン先生にはお帰りいただいた。
自由はなにより尊重したいけれど、子どもの身を守るという責任も当然ある。いまはまだ0.5:9.5くらいの割合で責任を全うすればいいとして、今後はどんどんそのバランスが難しくなっていきそうだ。広がっていく子どもの物理的・社会的な行動範囲に対して、それをどこまで制限するのか。親の権限を自明なものとして支配してしまえば人権侵害に直結するし、かと言って10代前半の子どもにすべてを任せてどこにでも行かせるというのも無理がある。
今年のアカデミー賞で作品賞はじめ5部門を受賞した映画『ANORA アノーラ』には、ロシアのオリガルヒの御曹司イヴァンが登場する。彼は21歳で、ほとんど際限ないくらい親の金を蕩尽し、この世に自分の思いどおりにならないものはないような顔をして生きているが、結局のところ、首根っこは親(とくに母親)につかまれていて、帰らざるをえない場所は決まっている。どんなに酒を飲んでドラッグを決めてセックスしても、イヴァンは広ーい監獄で豪勢に遊んでいるような状態で、根本的な自由をもっていない。イヴァンはそこからなんとか抜けだそうとしてひじょうに身勝手かつ幼稚な行動に出て、主人公のアノーラはそれに巻き込まれる。アノーラは金持ちの親ばなれ/子離れのバタバタに翻弄されちゃって、本当にかわいそう(しかしアノーラも容赦のない暴力を振るっており、そこはまさにスラップスティックでたいへん愉快です)。
都合の綱引き
自由を得つつあるということは、子どもにいよいよ親から独立した個人としての側面が現れるということで、まったく思いどおりにならない。いや、この半年強で思いどおりになった瞬間はそもそもほとんどないが、その思いどおりにならなさのなかに法則性があるというか、動物や自然現象を相手にしたときに感じる断絶ではなく、共感できる思いどおりにならなさに変わってきたのだ。
たとえば、吐き戻したゲロを興味深そうに手でいじくる。本当にやめてほしいが、ネバっとした感触が楽しいのはわからなくはない。買ってきたおもちゃよりも、抱っこひものベルトの部分を熱心にしがんでいる。子どもが子ども向けのものに鼻白むのは身に覚えがある。かなりの行動が「わかる」。だからといって、そのままいろいろやられても困る。同じ世界を生きるものとして、子どものなかにも私のなかにも都合がある状態。両者はしばしば相反する。他者性というやつかもしれない。
こうなってくると、親と子どもがずっと都合の綱引きをしているようなものだ。この綱引きは勝ち負けを決めるものではなく、両方から引きあうことでつねにいい具合に綱が張っている状態を維持しようとする。子どもは都合を調整する術をまだもっていないので、基本的には親が子どもの都合を見きわめることになる。
離乳食を食べさせるにしても、いちばんスムーズなのは子どもが空腹のとき。タイミングをうまく合致させることができれば、野菜でもバクバク食べてくれる。子どもが眠いときに寝かせれば、スルッと寝てくれる(乳児は「眠すぎてぐずっちゃって寝られない」ということもあるので、ひと筋縄ではいかないが)。当たりまえのことだけど、大人の都合で「いま食べてほしい、寝てほしい」となれば、とたんに上手くいかない。
評論家・音楽ディレクターの柴崎祐二さんはSNSにこう書いていた。
「育児をしていると、現在の社会の仕組み全般が、前触れもなくいきなり吐いたり熱を出したりする生き物の存在を、ほぼ全く前提としないところで成り立ってるのを痛感する。『予定』とか、『計画』とか、ないから。その『なさ』を内在化しない社会は、結局のところ未熟な『社会風』の何かでしかないから。翻って、『予定』とか『計画』という概念自体が、(諸学の知見では既に論証されていそうだけど)、そういう思考法の内側で安穏としていられたという意味で、極度に男性的なアイデアなんだろうなと感じたりもする。端的に、人間を舐めている」(https://x.com/shibasakiyuji/status/1901293384364380164
https://x.com/shibasakiyuji/status/1901302068859859329)
予定や計画をバンバン立てるということは、都合の綱引きにおいて自分のほうにフルパワーで引き寄せるようなもので、そうなると子どもは簡単に振りまわされる。そうならないようにするには、子ども側に加勢して綱を引っぱる人が必要になる。その人は自分の都合を捨てなければならず、その役割を担うのは女性が圧倒的に多いだろう。たいへん暴力的なバランスだ。
子育てと引きかえにあきらめたもの
この連載を読んでくれた人からリアクションをいただくことがあり、そのなかに「ライターもやって、バンドもやって、ほかにもいろいろやってるのに、子育てもしててすごいですね」というようなものがある。対面で言われれば「いやあ、まあ、ははは」とはにかんだり、SNS上であればそっといいねを押したりしていたが、私は育児と仕事・自己実現を立派に両立しているわけではなく、じつはいろんなことをガンガンあきらめたうえで、いまの生活が成り立っている。
男性の育児参加というと、「育休をいかに適正に取得するか」「それによってキャリアアップが妨げられないか」が論点になりがちだ。子育てすることで新しい視点を得られた、限られた時間を活かす癖がついて生産効率が上がったなど、「むしろスキルアップできた」系のエピソードも歓迎される。せっかく仕事を休むんだから、子育てはもちろん、ビジネスマンとしても有意義なものにしなければならないという規範が働いているともいえる。
いや、でもさ、全員が全員、そんなにバリバリやれるわけじゃないですよ。育児も家事も育休中の妻と分担してやっとなんとかこなしてる感じだし、そもそも私はフリーランスだから育休ないし。すきま時間を見つけて原稿を書こうと思っても、「あー、なんか疲れたな」とぼんやりスマホ眺めてたら、子どもが泣きだしたりする毎日。どう考えても何かを削らないといけない。
私がとくにあきらめたのは、「なんだか面白い人間」でいること。フリーでライターなんぞをやっていると、周りから「なんだか面白い人間」だと認識されていることが仕事に直結したりする。具体的には、とにかくいろんな現場に「いる」ということだ。さまざまなライブやイベントに出演したり、観にいったり、飲み会にも顔を出す。よく知らないがそこにいて、やたらと知り合いが多い。カルチャー通を自認している人に「張江さん、ここにもいるんですか」と驚かれればしめたもので、話していると「今度何かいっしょに面白いことやりましょう」と高確率で言われる(実際に仕事につながることは相当まれだが)。
ある意味、こうやって自分をブランディングしてきたわけだが、コロナ禍でこういった機会が激減して、復調してきたころに育児となったので、もうこれはあきらめるほかない。なんだか面白い人はもう辞めます。
以前、友人と某音楽レーベルについての話をしていたとき、「あのレーベルはオーナーがとにかくいろんな場所に顔を出して、その場で勢いで新人を発掘したり、イベントを組んだりしていたんだけど、子どもが生まれてからそういう機会が減ったから、最近面白くないんだよね」と言っていた。これは確かにそうなんだろうけど、しょうがないよ。子育てと現場の相性はとにかく悪い。どんなに魅力的なライブやパーティーに誘われても、そもそも予定が立てられないんだから。面識のないこのレーベルオーナーと心のなかで肩をたたきあった。
現場の「ノリ」から離れて
カルチャーに限らず、現場にいることの意義は、ネットがメインの現代だからこそ高まっているような気もしていて、たとえば政治においてデモなどの現場の熱気はひじょうに重要だ。選挙も投票所という現場に行くことが前提になっている。期日前投票も不在者投票もあるけれど、もし私がワンオペで育児をしているとしたら、「今日は疲れちゃったから明日で⋯⋯」と思っているうちに投票日を迎え、その日もバタバタして結局行けず、ということは十分にありうる。
先日、縁あって教会の日曜礼拝に参加した。その日は子ども連れが多く来ていて、牧師さんは子どもたちにもわかるように、簡単かつユーモラスに説教していた。だが当然、乳児には理解できるわけないので、ぐずりはじめた子どもを抱いた親が、礼拝堂を出たところにある簡易的なキッズスペースに集まっていた。私もならって子どもとそこに行くと、ほかは母親ばかり。もちろん各家庭の事情(今日は母親と子どもだけで来ていた、私のようにそもそも母親はクリスチャンではない、など)もあるだろうから一概には言えないが、信仰の現場でもその核の部分に母親は立ち会えていないのだ。「ママは信仰もままならない」というダジャレを思いつき、まったく笑えなくてひとりで動揺してしまった。
カルチャーにしろ政治にしろ信仰にしろ、物事が現場中心に回っていくと同質性がどんどん高まって、そこにいられない人は不可視化されてますますアクセスしづらくなってしまう。現場にいる人びとの共通言語、言い換えれば「ノリ」が最優先される。現場をつくる仕事であるイベンターの大手、キョードー大阪が、ライブ中に痴漢被害を訴えてきた女性客に対してひどい扱いを連発して物議を醸したのも、むべなるかなという気がする。
現場にいられることの恩恵をガッツリ受けて20〜30代をやってきたので、この先どうしたものか、正直わかっていない。毎日酒を飲みながら、目の前で起こっていることにアドレナリンを分泌させていた日々は懐かしくもある。40歳を間近にひかえて先行きも定まらず、過去を思い出したりしているありさまは、仕事も育児も全力投球のイクメンのみなさんに比べると、われながらかなりのしょぼくれっぷりだ。
子育ては多面的で、幸せと不幸せは交互にやってくるどころか、ほとんど同時に存在している。輝かしい面だけに注目すれば、いびつな像を結んで抑圧を生みだしてしまう。これは女性の子育てに関する表象についてさんざん議論されてきたことだから、男性に関しても同じだろう。私たちはしょぼくれて灰色がかった子育て経験をこそ共有すべきである。というか、したい。
日々の生活にまごついているあいだに、現場にいる人たちからは「張江さん、最近見かけなくなった」とか「なんか面白くなくなった」とか言われるようになるかもしれない。むしろそう言われているうちが華で、すぐに話題にのぼらなくなる。でも、それはろくに家事も育児もせずに夜な夜なほっつき歩いて、若い人に「え、張江さんってお子さんいるんですか!? ぜんぜん見えない!」とか言われてなんか得意げな顔をさらしているよりも何倍もマシだと、心の底から思う。

反権力赤ちゃん
張江浩司(はりえ・こうじ)
1985年、北海道函館生まれ。ライター、司会、バンドマン、オルタナティブミュージック史研究者など多岐にわたり活動中。レコードレーベル「ハリエンタル」主宰。
ポッドキャスト「映画雑談」、「オルナタティブミュージックヒストリカルパースペクティヴ」、「しんどいエブリデイのためのソングス」。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)