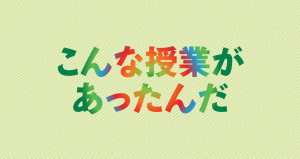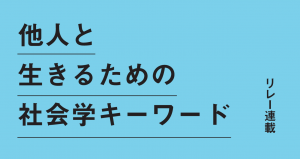お父さんはフェミニストだよ、と言える日のために|第11回|父の葬式で考えた「父親」のこと(後編)|張江浩司
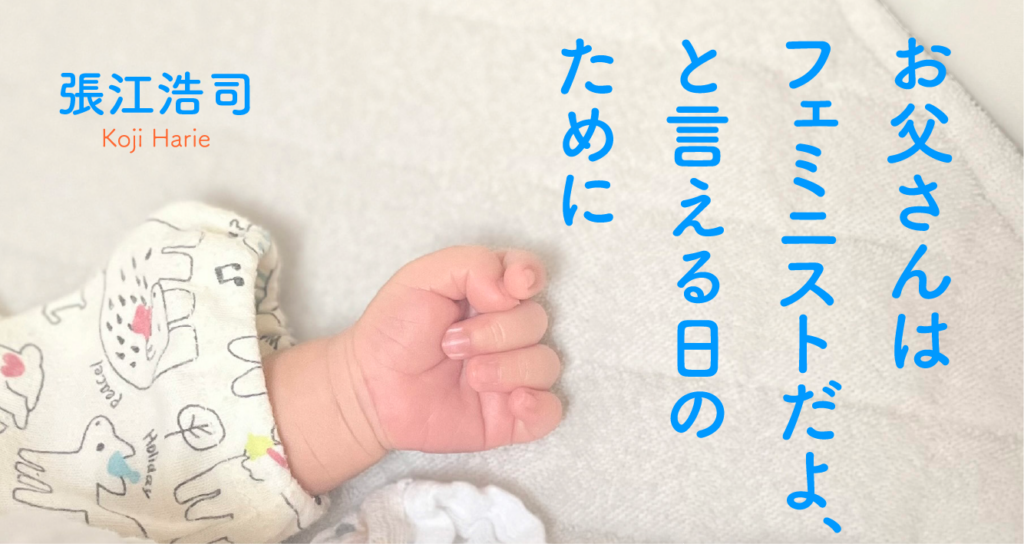
第11回
父の葬式で考えた「父親」のこと
(後編)
張江浩司
旅暮らしだった父の結婚
納棺の日になって、葬儀会社の人と湯灌師がやってきた。テキパキと父の遺体をきれいにして、死装束を着せていく。この作業を目の当たりにするのは初めてではないが、早技ともいえる合理的なテクニックと、六文銭を持たせるような合理性のないしきたりが平然と同居していて感心してしまう。
「故人の手を握れるのはこれが最後です」と言われ、言われるがままに手を触り、「うわ、冷たっ」と驚く。母は父の手を握って、「なんでひとりで先に行っちゃうの。『ありがとう』のひと言くらいあってもいいんじゃない」とつぶやいていた。
父と母はお見合いで、そのときおたがい34歳だった。父は1浪2留のすえに東京の大学を出て、その後は自動車工場の期間工をして金を貯めてアメリカやカナダに行き、資金が尽きたり体調を崩したりしたら実家に帰ってきてひと休みして、また東京で働いて海外に行くという、世界を股にかけたその日暮らしをやっていたらしい。まだフリーターという言葉はなく、自分探しという概念もない時代である。例によって体を壊して実家に身を寄せていたところ、親戚にゲリラ的にお見合いをセッティングされてしぶしぶ参加し、しかしフォーマルな服をひとつも持っておらず、黒いタートルネック(当時ふうに言うとトックリ)にジーンズで臨んだという。近所の喫茶店行くんじゃないんだから。
母は高校を卒業してからずっと、地元の銀行や父親(私の祖父)が興した会社で働いていたので、ちゃんとしてない父が新鮮に映ったらしい。何度かデートを重ねて、母から求婚。母はひとりっ子、父は次男で、「名前を残す」ために父が婿入りした。私の張江姓は母方由来である。ついでに張江の家が営んでいた会社に入ることになり、父は家庭と職をいっぺんに得たことになる。
父は「お見合いを組んだ親戚の手前、何があっても3年は結婚生活を続けるけど、それが過ぎたら出ていくから」と母に告げたそうで、これはいまになってみると、最大限ふらふらと生きてきたのに、突然「夫」という社会性あるっぽい存在になるのが恥ずかしかったんだろうと思う。ダルダルのTシャツで毎日暮らしてきたのに、蝶ネクタイを巻かれるような。その先にあるのかもしれない「父親」なんというものは、さらに想像がつかない。とりあえず考えないようにしたい。
私も妻が「結婚しよう」と言ってくれたのだが、なんともうれしい反面、「思ってるよりも収入低いよ? この先も上がらないと思うし、ご両親にも『ほとんど無職みたいな人だ』ってちゃんと説明してね?」とまくしたててしまった。父子二代にわたってエクスキューズがひどい。
可能なかぎり飄々と
前回から父のどうしようもない話ばかりしているが、私は父が好きだった。アメリカ的な個人主義を素朴に信じているような人で、「こうしなければならない」と言われたことはないし、何をするにも「いいんじゃないか」が基本スタンスだった。「最近の若いヤツは」に続くのは、「俺たちのころよりもみんな優秀だよな」。母や祖母をぞんざいに扱うことはなく、夫婦喧嘩も一度も見たことがない。偉そうな奴が嫌いで、自身も偉ぶるところがなかった。
会社の経営を任されることになり、ちょうどそのころバブル期の真っただなか。いまでは考えられないが、銀行から「金を借りてくれ」という連絡がひっきりなしに来たそうで、周りの企業はどんどん融資を受けて土地や美術品を買ったりしていた。ほどなくしてバブルははじけて、莫大な借金が残ることになり、潰れる企業、首を吊る社長で死屍累々。父は「そんな大金、何に使っていいかわからないし、いらない」と断っていたので、首の皮一枚つながった。「俺は臆病だから続けられただけ」とも言っていて、子どもながらにいい言葉だなと思った。
いわゆるシラケ世代の先頭だった父は、戦争を経験し、焼け野原から復興した親たちの馬力とそれにともなう野心や暴力性に、違和感を少なからずもっていたと思う。「一家の大黒柱として家族を養い、国を支える」というような「男のあるべき姿」を引き受けるのは嫌だから浮草生活をしていたのに、気づいたら夫であり、父親であり、社長になっていた。ものすごく座りが悪かっただろう。なんとか自分のなかで整合性をとろうと、オルタナティブなスタンスを模索していたんだと思う。父親や社長というものにまつわる「あるある」への逆張り。可能なかぎり飄々と、執着せず、「そんなことはどうでもいい」と笑って酒を飲む。
父の骨を見る
葬儀の日は、まず火葬場に向かった。実家の仏間は2階にあって、そこから棺を運びだすのが大変だ。父は184cmあって(実際は縮んでいただろうけど)、標準サイズの棺には入らず、ひと回り大きいものを用意された。オプション料金を取られて、釈然としない。数人がかりで棺を傾けたり戻したりしながら階段から降ろすさまは、巨大な知恵の輪みたいだった。
この日は快晴で、小高い場所にある火葬場へのマイクロバスの車窓から海がきれいに見える。「こういう自然がある環境は、子育てにはいいんだろうね」と妻と話す。いやしかし、「子育てに向いている環境」というのはニアイコール「刺激的なものがない」ということで、小さい子どもをもつ親にとっては危険が少なくて安心だけども、数年たって思春期に突入した子ども本人にとってはめちゃくちゃ退屈でもある。子どもの成長のフェーズに合わせて住む場所も気軽に変えられたらいいんじゃないか。
到着して、簡単にお経をあげて、感傷に浸るすきもなく遺体は火葬炉へ。待合室で子のオムツを替えたり弁当を食べたりしていたら、あっという間に骨になった。思った以上に太い。焼けたらボロボロになってしまう骨もあるそうだが、しっかりと形が残っており、どの箇所も骨太。整形外科医をやっている伯父(父の兄)が「僕は股関節が専門なんだけど、これは立派な股関節だよ」と言いながら箸でつまんで骨壷に入れていた。弟も「こんなにちゃんとした骨なら、たぶん歩けたよね。リハビリをサボってただけだよ」と呆れ怒りしている。
たしかに弟の言うとおりだ。最晩年は肺癌を患っていたが、それまではとくに重篤な病名が診断されていたわけじゃない。ただただ生命力がなくなっていって、萎んでいくように寝たきりになり、母に介護されていた。少しでも気がまぎれればと、寝室のテレビで映画なんかが観られるようにFIRE STICK TVを贈ったら、「悪いけど、映画を観る気力も体力もない」とつき返されてしまった。もっとも、FIRE STICK TVはYouTubeにも接続できるので、陰謀論YouTuberの言うことを真に受けたりしていた可能性も考えると、これでよかったのかもしれない。ちなみに、ドナルド・トランプのことは「あんなやつは認めない」と言っていたので、最後まで「良いアメリカ」が好きだったんだなと思う。
せめて「マシな父親だった」と思われたい
斎場に移動し、葬儀がはじまる。喪主である母の隣に座って、お経を聞きながら祭壇を眺める。そういえば、葬儀の最前列に座るのは初めてだ。
父の体力・気力がガクッと下がったのは、ほとんど毎日いっしょに飲んでいた親友が急逝してしまったことがきっかけのひとつだったと母に聞いた。仕事は次代に引き継ぐ準備ができて、子どもたちも巣立ち、あとは人生が終わるまで毎日友だちと飲み歩いていればいいかと思っていたら、梯子が外れて宙吊りになった。執着せずに生きてきたことが、ある種のセルフネグレクトに転じてしまったんじゃないだろうか。
でも、だったら母といっしょに飲みにいったり、旅行したりすればよかったのに。一応書いておくと、家では毎晩いっしょに飲んでいて、寝たきりになるまではたまに外にも飲みにいっていたようだ。母もそれはそれで楽しかったと思う。しかし、あくまでもそれは父に合わせた行動であって、母の希望を叶えているわけではなかった。
結婚した当初に「俺は好きなようにやるから、あんたも好きにやりなさい」と父は母に常日ごろ言っていて、実際、部屋が散らかっていようが食事に何が出ようが、いっさい文句を言わなかったらしい。一見、女性の自由を尊重するフェミニスティックな言動にも思えるが、結局自分は家を空けて家事・育児を母と祖母に丸投げして、性別役割分業の構造に乗っかっているだけでもある。前世代の抑圧的な男性性から距離をとるために、地に足のつかない生き方を志向して、しかしそれは妻や母の支えがなくては成立せず、最終的には介護してもらっていた。新左翼の学生運動において、表立って活動する男子学生の陰で女子学生はおにぎりを握らされていた、という話を思い出した。
これはまったく他人事ではなく、自分が何かカウンターだと思ってやっていることがただのナイーブな責任回避だったり、差別的構造の再生産になっているという可能性はおおいにある。何をするにも、自分が立っている地点をよくよく理解しなければいけない。
もうひとつ思ったのは、もし父が家事の役割を少しでも担っていれば、晩年の生き方も変わっていたかもしれないということ。健全な家事は家族へのケアであるが、その家族には自分も含まれるので、結果的に自分のことも考えざるをえなくなる。
祖母(母の母)は「男の人が家事をするなんてもってのほか」という考えで、父には炊事も掃除も洗濯もいっさいさせなかったし、母もそれに従った。大正5年生まれの女性なのでそうするのは当然といえば当然だが、父はひとり暮らしも長く、学生時代は居酒屋でバイトしていたこともあるらしいから、それなりに料理の覚えがあったように思う。休日に珍しく家にいた父が「今日は俺が料理する」と言ってデパ地下に行き、ふだん使わないような食材を買い込んでビーフストロガノフか何かを作っていた記憶もある。これは「親父の気まぐれな趣味」としての料理で、家事としての炊事とは別物であるけれど、週に一度でも料理当番を拝命していれば、あんがい父は苦にせずこなしていた気もする。「父もまた性別役割の犠牲者で」と言う気はさらさらないが(飲んで寝てただけなので)、つくづく家父長制ってだれも幸せにしないよね。
葬儀の最中ずっとこういったことを考えていたら、気づいたらお経も終わり、遺族代表として私が挨拶する段になった。まとまらない頭でいっちょかましてやろうかと、神妙な面持ちで父の面白エピソードを紹介するというハイブロウなスピーチをしたところ、めちゃくちゃすべった。
思い返すといろいろあるが、それでも暴力を振るったり、家族をコントロールしようとするような父親に比べたら、何万倍もマシな父だった(少なくとも私にとっては。弟ふたりはまた違うかもしれない)。潜在的なミソジニーには無自覚だったろうから、ここで書かれていることを草葉の陰で知ったら「マジかよ」と思うことだろう。
私も将来、子どもに思いもよらない角度から断罪されることがあるかもしれない。それは避けるべく全力で行動したい一方、そうなったら子どもも含めて社会がいい方向に進んでいる証明であるだろうから、受け入れるほかないだろう。いやでも、やっぱりつらいよ。めちゃくちゃつらい。せめて私も「マシな父親だった」と思われたい。

張江浩司(はりえ・こうじ)
1985年、北海道函館生まれ。ライター、司会、バンドマン、オルタナティブミュージック史研究者など多岐にわたり活動中。レコードレーベル「ハリエンタル」主宰。
ポッドキャスト「映画雑談」、「オルナタティブミュージックヒストリカルパースペクティヴ」、「しんどいエブリデイのためのソングス」。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)