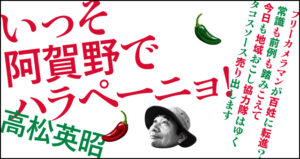お父さんはフェミニストだよ、と言える日のために|第12回|子どもに読まれる日がやがてはくるのだ|張江浩司
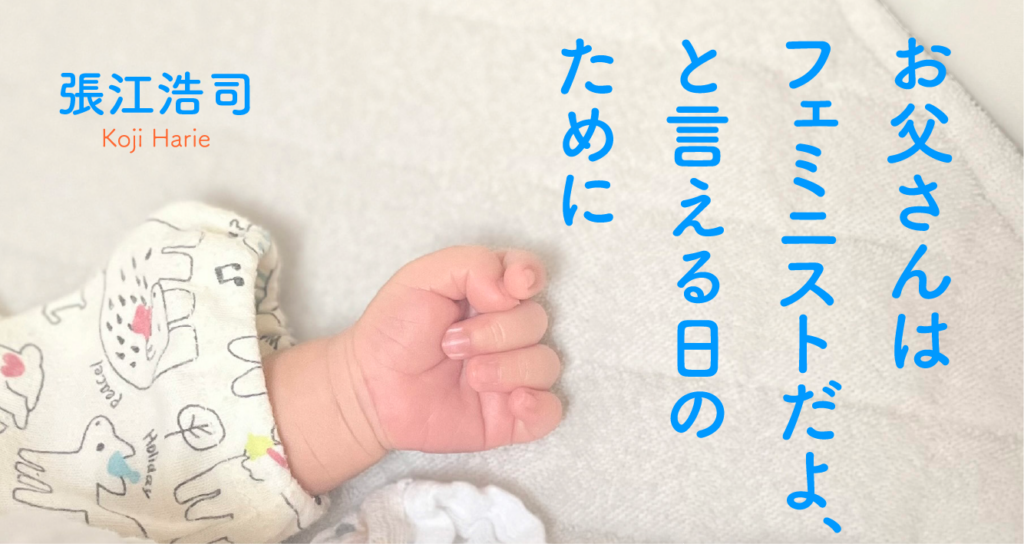
第12回
子どもに読まれる日がやがてはくるのだ
張江浩司
まもなく1歳、バグる成長の遠近感
この連載も、はや12回目。光陰矢の如しすぎる。写真を見返すと、当たりまえだがエッセイを書きはじめたころの子どもは見まごうことない赤ちゃん。ときおり「ふえー」と泣き、乳を飲むことしかできない赤ちゃん。それがいまや、白米をワシワシつかんで食べている。風呂では、ボディソープを手のひらにつけてあげると自らお腹や太ももに泡を塗ったりもする。まだどのボタンが何を意味しているかのルールは把握していないにせよ、教えてもいないのにテレビに向かってリモコンのボタンを押したりする。つかまり立ちしたと思ったら、流れている音楽に合わせ腰を動かしてダンスの萌芽のようなものを見せたりする。お気に入りのおもちゃを私がいじっていると、不服そうに所有権を主張しているような素振りを見せたりもする。どれもものすごい成長だ。飯を食って、身体を清潔にし、思うままに楽しんでいる。これこそ文化的な生活じゃないか。これはもう、どう考えても大人。
と思いながら2、3歩離れて見てみると、あまりにも小さい子どもがちんまりと座りながらリモコンをベロンベロンに舐めまわして「うー」とか言っている。どこからどう見ても赤ちゃんだ。成長の遠近感がバグって、わけがわからない。
そもそも、昨年のいまごろはまだ子どもがいなかったなんて信じられない。しかし、確かにまだ子は妻の子宮の中におり、ボコボコと内側から蹴りまくっていた。外から見ていてもはっきりわかるほどに、子が動くたび妻のお腹が盛り上がる。
リドリー・スコットの『エイリアン』のあの有名な、寄生された船員の胸部からチェストバスターが飛びだすシーンは、なるほどこの胎動のディフォルメだったんだなと感心して、映画好きな妊娠・出産経験のある知り合いに話すと「そんなに動きますか⋯⋯?」と怪訝な顔をされた。「あ、これが普通じゃないんだ」と思った、最初の出来事である。
第一子なこともあり、私と妻のなかには「乳児、かくあるべし」という基準があるわけではなく、自分たちの子どもが「普通」なのかどうかよくわからない。身長と体重に関しては発育曲線の目安があるからわかりやすい。体重は基準値のど真ん中、身長は基準の下限ギリギリで推移している。うちの子どもは小さめなんだなあ。もっとデカい、もしくはさらに小さい11か月児が世の中にはたくさんいるというのも、あまり想像ができない。ネットの映像では目にしているはずなのに、リアルな感覚として理解できるのはわが子だけだ。われながらものすごく閉じられた認識だが、これはしょうがない。自分の子どものことだけで手一杯なんだから。
保育園に通うようになってからは、もちろんクラスメイトとの比較はあるけれど、いまの時期は月齢によって発達速度がまったく違うので、同じ生年月日の人でもなければそれで一喜一憂する気にならない。
やはり小学校以降、なにかと数値化され平均がとられ偏差のなかに位置づけられるようになってくると、「普通」という物差しと対峙せざるをえなくなるのだろう。そう思うと、それまでのあと5年間はたいへん貴重な時間だ。
「おれ、ヤバいことしてないか?」
こうやって子の成長を描写するのが、われながら板についてきたと思う。と同時に、「おれ、ヤバいことしてないか?」という疑念がだんだん湧き上がってきた。
安易にジャンルを形容できないところがクールとしか言いようがないバンド「LOLOET」のベーシストであり、漫画を描いたりいろんなことをやってらっしゃる劔樹人さんが、先日SNSにこう書いていた。
「私は男性の育児に関わることで注目されたことが何度かあり、育児エッセイ的なマンガや執筆の仕事が増えかけた時期がありましたが、子どものプライバシーなどの問題を考え、結局全てやめて続けませんでした。それでよかったと思います」
劔さんが主夫生活や子育てについてさかんに発信していたのは2019〜2020年頃だろうか。子育ての「こ」の字もないのは当然として、結婚の「け」の字もパートナーの「パ」の字もなかった当時の私は、「いやーなんか大変ですね」とあからさまに他人事として楽しんでいた。しかし、いま読み返すと身もだえるほどに腹に落ちる。加えて「劔樹人の『育児は、遠い日の花火ではない』」からは、たった5、6年で男性の家事や育児を取り巻く環境がけっこう変化していることがわかる。お連れ合いであるエッセイストの犬山紙子さんがテレビ出演したさいに「犬山さんの旦那さん、働いてへんのでしょ?」とヒモ扱いされたエピソードがあるが、主夫という存在が目新しいものではなくなったことで、こういう類の笑いは成立しなくなった。お子さんと新幹線に乗っていたときには、泣きやまない子に対して「うるさい! デッキ行けよ!」とおっさんが怒鳴りつけてきて、それが女児誘拐騒動にまで発展するのだが、いまならこう叫ぶおっさんのほうが白い目で見られそうなものだし、そこまで大事にもならないだろう。そうであってほしい。
劔さんのような先行世代の実践と発信によって、私の子育てはやりやすくなっているんだなあと感謝しつつ、しかしそうであればなおさら劔さんが直面した「子どものプライバシー」にもよりいっそう真摯に向き合わなければならない。
子どもの身元が明らかにならないような配慮は安全上当然として、問題は将来テキストが読めるようになって、「どんなもんかな」とこのエッセイを読んだときにどう思うかだ。
会話できない乳児に、日々の様子をエッセイに掲載していいかどうかの許可を取ることはもちろん不可能だし、意思疎通がある程度できるようになった4、5歳の時点であらためて説明して、さかのぼって「いいよー」と言ってもらえた場合でも、それをしてオールOKというのも乱暴すぎる。何歳なら正当な判断ができるといえるのだろうか。10歳のときに「読んだけど、なんか面白かった」と言ってくれたとしても、15歳で「は? 最悪なんだけど」となる可能性もある。民法上は18歳から責任能力があるということになっているが、そこをクリアしたとて油断してはならない。史上もっとも有名なレコードジャケットのひとつであろうNirvanaの「Never Mind」に裸で写っている赤ちゃんが、30年後に性的搾取でバンドを訴えた例もある。
面白エピソードの公開とプライバシー
私自身に引き寄せて考えてみると、親から自分が子どものころのエピソードを聞くときに「赤ちゃんのときにどこそこでうんちを漏らした」みたいなものは問題なく笑っていられる。一方で母親から「5歳くらいのあんたは家の前のバス停に並ぶ女の人を指差して『あの人はおばさん、こっちの人はお姉さん』と選り好みしてた」と言われたときは心底頭を抱えた。自分が、学校に通うなりして女性蔑視的な社会規範にさらされる以前からそういった眼差しをもっている根源的家父長制内面化人間であることの、動かぬ証拠を突きつけられるようだ。勘弁してほしい。
もしこれがなんらかの面白おかしい文章として世に発表されていたら、それこそ5歳時点では何も感じず、10代でも「おれって、こんな小さいころからすけべだったらしい(笑)」とか言って仲間内の笑い話にし、30代になってようやく「なんとかこれを人の目に触れないようにできませんか⋯⋯?」と嘆願していたと思う。
赤子のうんこだのおしっこだのゲロだの、もしくは「リモコンをベロベロ舐める」のようなそれに準ずる(大人から見ての)奇行は自分の意志とは関係ないし、いくら笑ってもらってもかまわないが、現在の自分と地続きな自意識が顕れてくると途端に生々しいものになる。子育てエッセイで超えてはならない一線はこれなんじゃないだろうか。
いわゆるエッセイにおける「面白エピソード」というものはだれかの自意識に立脚していることがほとんどなわけで(育児エッセイなら子どもの)、誠実に「子どものプライバシー」を考慮するとだんだん立ちゆかなくなってくる。そこが止めるタイミングなんだと思う。
しかし、よくよく考えてみると、私のバス停の話。あれはおそらく親が笑ったりリアクションするからやっていたんだろうな。自分の経験から照らしあわせると、子どもは大人に囃されると期待に応えたくなってしまうものだし、自身の「子ども性」は重々承知していて、ギャップをねらったりもする。年端もいかない子どもが、急に「大人の男性のように」女性の年齢についてジャッジしはじめたら、その様子を80年代後半の大人たちは無邪気に楽しんだろう。これはこれで、なんともいたたまれない光景なので、やはり面白エピソードとして勝手に開帳されたくはない。
境界線を見失わぬよう、日々ジタバタする
大人の真似をして背伸びしている子どもは、とんでもなくかわいい。親の存在が子に影響を与えている証でもあるので、単純なかわいさを飛び越えて親自身が肯定されているような気持ちにもなるが、「背伸び」が加害性のある「イキリ」になった場合、逐一「それは面白いことじゃないんだよ」と訂正していかなくてはならない。「ああ、これは私の真似をした結果なんだな」と痛いところをつかれても、自分のことはいったん棚に置いて注意し、その後大急ぎで棚から戻してきて自分も改善する。子育てエッセイを書く/書かない以前に、30年後の子どもに頭を抱えさせたくないし、下手したら何歳になってもイキッたままの家父長制再生産人間に育ってしまうかもしれない。
子どものプライバシーを侵してまで面白おかしいエッセイを書くことと、親の真似をしてイキる子どもを無責任に愛でること。結局どちらも、子どもを一人の独立した人間とみなさず、親の所有物のように考えることが根本の原因だと思う。
自分と切り離して適切な距離を測る。言葉なしで通じあうことなんてありえないから、どんなことでも説明する。そのためにまず話を聞く。見ず知らずの他人であれば当たりまえのことなのに、子どもに対してだとすっ飛ばしてしまう。
先日観た「カーテンコールの灯」(ケリー・オサリバン、アレックス・トンプソン監督)という映画は、とある出来事によって大きな喪失を抱えた中年男性がひょんなことから市民劇団で「ロミオとジュリエット」を演じることになり、未経験ながらロミオ役に抜擢され、その経験をとおして妻と娘との関係を再構築するというあらすじで、正直、最近よくあるタイプの映画ではある。しかし、「アートで自己開示できてよかったね、おじさん」というだけではなく、だんだんと浮かび上がってくるのは「もうわかりあうことはできない絶対的な他者としての子ども」。それは絶望ではなく、かといって安易な希望でもない。ただそういうふうにある。その厳然たる事実を、緻密に優しく描きだしていた。
この映画を観終わったあと、「朝起きたら『子どもは私の思いどおりにならない』って3回唱えることにするわ」と妻はつぶやいていた。そうでもしないと、親と子どもの境界線はすぐに融解しそうになる。なんとか抗うために、毎日ジタバタしっぱなしだ。毎月書いているこのテキストは、子育てエッセイというよりも私のジタバタ報告である。何年か後にこれを読んだ子どもが「自分の話ばっかり書いてるじゃん」と苦笑いしてくれたら、それが一番いい。

張江浩司(はりえ・こうじ)
1985年、北海道函館生まれ。ライター、司会、バンドマン、オルタナティブミュージック史研究者など多岐にわたり活動中。レコードレーベル「ハリエンタル」主宰。
ポッドキャスト「映画雑談」、「オルナタティブミュージックヒストリカルパースペクティヴ」、「しんどいエブリデイのためのソングス」。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)