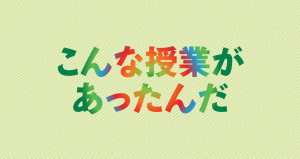お父さんはフェミニストだよ、と言える日のために|第13回|「将来の夢=仕事」って、なんか変じゃない?|張江浩司
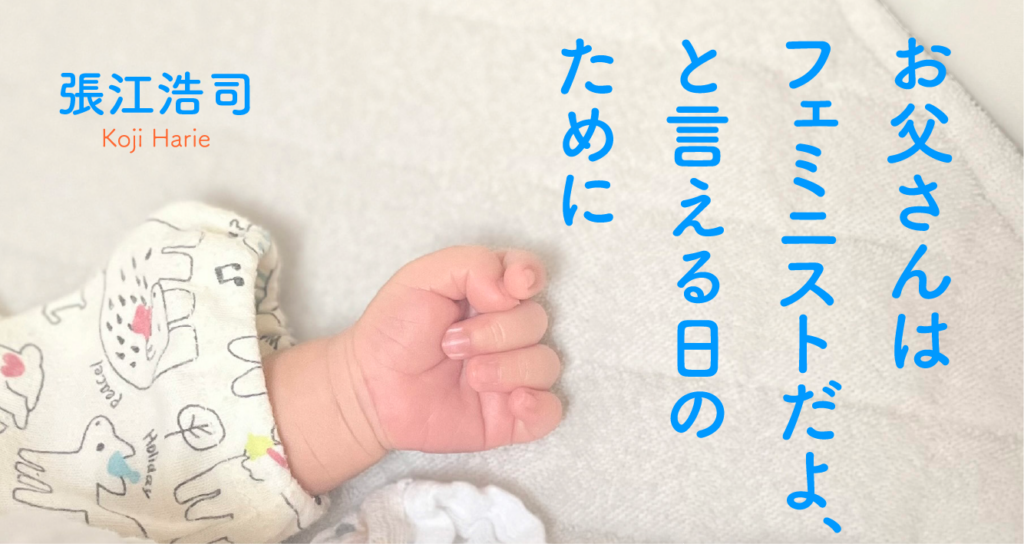
第13回
「将来の夢=仕事」って、なんか変じゃない?
張江浩司
兼業主夫生活をめぐる生産性の呪い
最近はありがたいことにちょいちょい仕事があって、少し忙しい。とはいえ、そのまえまではものすごく暇な時期があって白目をむいていたのでプラマイゼロ、むしろまだマイナス。独身のころは仕事がなければないで「サイゼで昼からお酒飲んじゃお」ってなもんでダラダラ気楽に生活していたが、働いている妻と保育園でいろいろやっている子どもを尻目に同じことをするのは忍びなさすぎる。新しい企画を考えたり、知り合いの編集者に御用うかがいのメールを書いたりするも、なかなか成果は出ず、パソコンの前でまんじりと時間が過ぎ、せめて今日という日に何かした証を残そうと、夕飯に手がかかるものを作って気をまぎらわせる。
炒め物ではすぐに終わってしまうから、なるべく煮込み料理がいい。シチューでもおでんでも参鶏湯でもいい。鍋の中で食材から出る出汁と調味料が折り重なって味が深くなる時間。火を止めて、冷めていくと同時に食材に味が染みていく時間。ただ鍋を眺めていたとしても、何か「生産性」を得られた気がして心が落ち着く。それでも、1円も生みだしていないことがつねに頭の片隅にあって、なかなか晴れない。
おかしい。私は「生産性」みたいな言葉が本当に、心の底から嫌いなのに、なんでそれを求めてしまうのか。私より収入が多い妻への後ろめたさはある。しかし、「もう少し収入があったら安心だよね」という話はするものの、不安定の極みであるフリーライターなんという職業でいることを咎められたことはいっさいない。なにより暇なときも忙しいときも、それなりの量の家事を担当している。もちろん妻と分担しながら、子の寝かしつけなんかはおまかせしながらだけど、てらいなく「私も家事はけっこうやってます」と言えるくらいではある。つげ義春の「無能の人」じゃないんだから、ちゃんとやることはやっています(読み返すと、つげ漫画には息子を叩いたあとに抱きしめるような描写がけっこうあって、いやーな気持ちになりますね)。
私とまったく同じ状況の友人がいるとして、「仕事がないと家族の役に立っていない気がしちゃう」と相談されたら、いや、家事も立派な労働だから! 家事分担してるからお連れ合いも仕事に出られてるわけだし、育児も順調なんじゃないの? そりゃ多くはないだろうけど、多少の収入はあるんだし。それを全部ギャンブルに溶かしてるわけでもないじゃない。『稼ぐことを第一に考えてほしい。給料がいい会社に就職してほしい』って言われてるんじゃないんでしょ? だったら何も思い悩むことないじゃん。そもそも、べつに役に立たないといけないなんてことないんだから。胸張ってればいいのよ!」とまくしたてると思う。
実際、暇でつらかったときの私は、私自身をこうやって励ましていた。わかっちゃいるけど、日常生活には支障がない程度の落ち込みは続いた。それが消えたのは、ドバッと仕事依頼のメールが届くようになってからである。
「男の本質」説はお話にならないが、「仕事=自己実現」観は?
もしかしてこれは、私の中に「男は稼いで家族を養ってなんぼ」という価値観が、私が思っているよりもずいぶん強固に居座っているからなのだろうか? そんなそんな、まさかまさか。こういう男性の経済的マッチョイズムは、男性のほうが職に就きやすい、働きつづけやすい、出世しやすい構造の上に築かれたもので、男性の本来持っている性質に基づいているわけでもなんでもないということは、百も千も万も承知している。
このあいだ中華料理店でご飯を食べてたら、瓶ビールをしたたかに飲んだと思われる男性が「男は狩りをしてたからさ、獲物とか怪我した仲間に共感してたら自分も危ないから、簡単には他人に共感しないようになってるんだよ。そのぶん、絶対に獲物を持って帰るぞ、っていう気持ちは持ってるのよ」と語っていた。ああいう根拠の薄弱な進化心理学もどきを得意気に話していると、阿呆に見えますな。なんで狩りの記憶だけが受け継がれるのか。「男は夜になると火の番をして、ひと晩じゅう火加減をコントロールする必要があったわけ、テレビの前に陣取ってリモコンをずっと握りしめてるのはその名残りなんだ」とか、「男は陰茎をぶら下げてるからね、バランス感覚に優れてるんだ」とか、なんだって言えるでしょうに(いや、これも言ってる人いるのか?⋯⋯と不安になり、念のため「陰茎 バランス感覚」で検索したところ目ぼしいものはヒットしなかったので胸をなでおろしました)。
こんな性別役割論みたいなもんは酒場の与太話にもならないことは、フェミニズムの言説に触れて早々にわかったことなのに、ある意味その恩恵で独り身のころはぬるーっと暮らしていけたのに、なんでここに来て苦しいのか。うんうん考えてみると、私は仕事を、生活費を稼ぐ手段としてだけでなく、自己実現をそこに見出しているからでは、ということに行き着いた。これは特別なことではなくて、だれしも学生時代に「将来の夢」を尋ねられると、職業名で答えていただろう。いままでなんの疑いもなかったけれど、「夢=仕事」と学校で刷り込まれるんだから、ザ・資本主義もはなはだしい。
とはいえ、私が進路というものを意識しはじめた2000年前後には、教師も「稼げる仕事に就け、そのためにいい大学に行け」というよりは、「本当にやりたいことを探してみよう、そのために選択肢が広がる進学先を選ぼう」と指導することが一応の建前になっていたように思う。これも搾取構造がマイルドに言い換えられているだけだし、いつぞやのYouTubeのキャッチコピーが「好きなことで、生きていく」だったことからも、昨今のアテンション・エコノミーの下地になったことは明らかではあるけど、当時の私はなんの疑いもなく「好きなこと」を探して、その結果、音楽をやったり文章を書いたり、人前でしゃべったりしている。
おもしろいと思ったことを仕事にしているから、当然、自分でもその成果物を見て「おもしろいなー」と思う。これに加えて、たいした仕事量でもないのでストレスもたまらない。したがって、仕事のストレスを解消するために余暇に散財する必要もない。仕事とプライベートのオンオフを分けることもない。こうやって、メリハリのないこぢんまりとした生活が形成されていく。東京の真ん中に住んでいるけども、やりがいと承認欲求の自給自足をしているようなもので、精神的な畑暮らしだ。
この生活は気に入っていたが、結婚して子どもを持ったとなれば、生活スタイルは変わって当然。それに、まだ慣れないことはこの連載の第8回でも書いたとおりで、私のささやかな畑のサイクルは途切れて、自給自足はままならなくなってしまった。それにとまどい、軽く気に病んだ。
妊娠・出産・育児と資本主義、相性悪すぎないか?
それにしても、私はべつに仕事を休んだわけでも辞めたわけでもなく、実際に依頼が来るようになったらあっさりと復調したけれども、妊娠・出産・育児によって否応なくビジネスキャリアを中断せざるをえない女性の被る喪失感は計り知れない。もちろん、育休によって子育てに専念できることに掛け値なしの幸せを感じる人も多いだろうが、そのことと、働くことで感じられる自己実現を奪われる不幸は両立する。働くことに関する性別役割の呪いは解かれつつあるが、「好きなことで、生きていく」はそれに替わって万人にかけられたつぎの呪いである。働きつづけられる男性はモチベーションに変換することもできる一方で、妊娠・出産・育児をする女性にとってはただただ呪いとしてしか機能しない。ここに圧倒的な格差がある。
育休が明けたからといって子どもが急にひとりで生活できるようになるはずもなく、時短勤務をしなければならないこともあるだろうし、落ち着いてきたころには「小1の壁」が立ちはだかる。「夫の稼ぎで十分生きていけるじゃん」という言葉は、ここではなんの意味もない。「お金以上に大切なものがありますよね」と経済が訳知り顔で近寄ってきたわりに、それを実現するシステムがまったくちゃんと整っていないことが問題なのだ。妊娠・出産・育児と資本主義、相性悪すぎないか?
そもそも、私のように素朴に「やりたいこと」を見つけてそれにまっすぐ向かっていけること自体が、男性の特権でもある。「女だから」という理由で親に大学進学を反対されたり、受験したら男子生徒だけに加点されたり、就職しても賃金格差があったりする。それに比べたら私のキャリアのなんとちょろいことか。イージーモードである。
「もう独りだと仕事がんばれない」に潜む男女差
社会人になって10年目くらいの人間が口にする、「もう独りだと仕事がんばれない」という言葉。これはほとんどクリシェ(決まり文句)で、みんなあんまりよく考えずに使っているように思う。かくいう私も、前職を辞める直前くらいに飲み会の席でちょくちょく言っていた覚えがある。
最近、この言葉をたて続けに聞いた。まずは久しぶりに会った、私と同じ年齢の男性の友人。サラリーマンをやっているが、ものすごい勢いで出世したらしい。「ちょっとこれ以上、会社でがんばるには、結婚とかしないと無理な気がするんだよなー」とこぼしていた。
つぎは、漫画家・冬野梅子さんが現在連載している「復讐が足りない」の第4話。冬野さんの作品は前作「スルーロマンス」、前々作「真面目な会社員」ともに、現代に生きる女性をとりまく不条理をこれでもかという解像度とハードボイルドなユーモアで描写する傑作だったが、今回もすごい。小さな会社に転職して3年、やっと正社員に登用された復田朱里(32歳)は、この職場で以前に男性社員から女性社員への性加害があったらしいことを知る。女性社員は退社し、男性社員は働きつづけている。それとなく事情を探るも、「合意だったって聞いたよ?」と矮小化する同僚、かたくなに中立を装ってかかわろうとしない同僚を目の当たりにして、辟易。「なんかもう辞めたいな」ととぼとぼ歩く家路の途中でペットショップに飾られるシベリアンハスキーの子犬を目撃。犬を飼う生活を妄想しながら「『自分のために頑張る』のは意外と難しい だからみんな結婚するのかな」「でも今の私じゃ 犬一匹だってままならない」と独りごちる。
一方は実在の人間、もう一方は漫画の登場人物であるけれど、この対比はたいへん象徴的だ。つまり「もう独りだと仕事がんばれない」を、男性友人は「それなりに順調にやってるけど、もう一段キャリアアップするためには『守るべきもの』がいたほうがいい」という意味で使っているのに対して、復田さんは「まじでこの職場で働くの無理すぎるんだが、辞めたら生活がヤバいし、思いとどまるためには『守るべきもの』がいたほうがいい」。言い換えれば「この世に自分をつなぎとめておくため」。
男性を働き手として想定している構造において、男性は当然のように「普通」に働ける。守るべきものを得て奮起するのは、つぎの段階の話だ。一方で女性はその構造に組み込まれていないので、まず「普通」に働くためにそれが必要になる。どちらが切実なのかは明白で、仕事をめぐる男女差がはっきり顕れている(「普通に働くことを当然視されるつらさ」も、もちろんあるけれど)。そして、両者とも「守るべきもの」が、会社に個人を縛りつけるために作用しているのも薄気味悪い。
*
うちの子どもが進路を考えるようになるころ、この男女差は解消されているだろうか。おおむね社会はその方向に動いているから、極端なバックラッシュがなければマシになっているんじゃないかと思う(極端なバックラッシュの可能性も、残念ながら高いけれど)。
それだけじゃなく、「夢=仕事」の呪いも解かなければならない。人間のすべての言動が経済に還元されてしまう根源がここにある気がするし、これがあるかぎり、たとえベーシックインカムが導入されて人間がいやいや働く必要がなくなったとしても、結婚や妊娠・出産・育児が経済に利用されつづけて、ジェンダー間の格差を温存しつづけるだろう。
最近、葉っぱを見かけると指をさして、まじまじと見て触っている。その様子を見ると、「将来は植物の研究者だろうか。少なくとも理系に進むかもしれない」なんて半ば自動的に考えてしまう。こりゃだめだ。
子どもが「将来の夢」という言葉をわかるようになったとき、「仕事じゃなくてもいいんだよ? 毎日寝てたいとか、週に3回ラーメンが食べたいとか、そういうのも夢でいいんだよ?」と伝えようと思う。いたって真面目に考えたメッセージだが、文字面の頼りなさよ。それでも、しつこく伝えようと思う。

張江浩司(はりえ・こうじ)
1985年、北海道函館生まれ。ライター、司会、バンドマン、オルタナティブミュージック史研究者など多岐にわたり活動中。レコードレーベル「ハリエンタル」主宰。
ポッドキャスト「映画雑談」、「オルナタティブミュージックヒストリカルパースペクティヴ」、「しんどいエブリデイのためのソングス」。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)