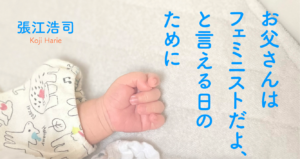こんな授業があったんだ|第57回|池を掘る〈前編〉|宮崎勇市
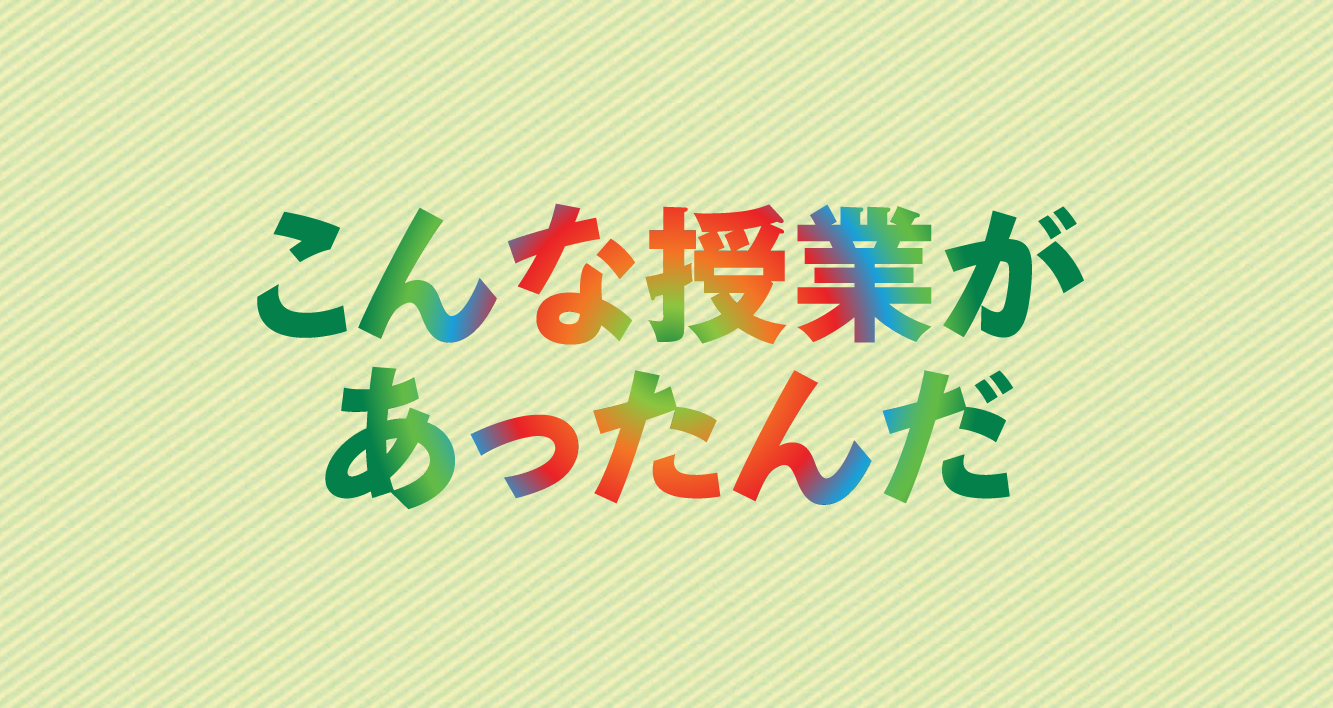
授業「池を掘る」
魚を飼おうと、まず池づくりから 〈前編〉
(小学1年生・1992年)
宮崎勇市
1年生の6月。校庭で生き物を飼おう。
どんなものがいいかな?
私は、92年4月に、神奈川県茅ヶ崎市の鶴が台団地という住宅公団のまんなかにある全校14クラスの小さな学校に転任してきて、1年生の担任になりました。1年生は2クラスです。
6月、1年生が学校に慣れてきたころ、
「生き物を飼おうよ。どんなものを飼いたいか考えて、連絡帳にメモしておいてください。おうちの人と相談してもいいからね。ただし、条件があります。いまから黒板に書くから、連絡帳に写してください」
①こうていでかう
②みんなでせわをする
という条件をつけて宿題にしておきました。
1週間後、子どもたちが考えてきたものを発表してもらいました。子どもたちの提案は20種類ぐらいにおよび、数が多すぎて、しぼりきれません。そこで、グループ分けして、いっしょに飼えそうなものをまとめてみました。リス、モルモット、ウサギなどの小動物、ニワトリ、インコ、ジュウシマツなどの鳥、コイ、フナ、ドジョウ、メダカなどの水の中の生き物の3グループに分けることができました。その3グループのうち、どれにするか、もう一度、考えてくるよう宿題にしました。
また1週間後、話しあいました。話しあいを始めたときの希望数は、小動物が8人、鳥が12人、水の中の生き物が16人でした。そのうち、希望を変える子がでてきて、水の中の生き物を飼いたいという子が25人ぐらいになりました。少数派の子たちもあきらめることになり、水の中の生き物を飼うことに決まりました。
それを聞いた隣のクラスでも、水の中の生き物を飼おうと決まり、1年生全員で取り組むことになりました。
「みんなで、水の中の生き物を飼おうと決めたけど、水の中の生き物を飼うにはなにが必要だと思う?」と問いかけました。
このころには、最初に提示した「校庭で飼う」という条件を忘れていたのでしょう。私の問いかけに、子どもたちは一瞬たじろぎました。しばらくして、池が必要だと気がついたようです。
「じゃあ、池づくりから始めよう」
職員の打ちあわせでは「1年生の生活科で水の中の生き物を飼うことになりました。そのうちに池を掘ります。どこに掘るかまだ決めていませんが、掘り始めたら、ご迷惑をかけるかもしれませんが、ご承知おきください」と言っておきました。
硬い部分があったり、針金やコンクリートがでてきたりして、
なかなか深く掘れない
7月6日、いよいよ掘り始めました。
小型のスコップ、くわ、とうぐわ、小型の手押し車、バケツなどで作業開始です。はじめてなので、道具の使い方の説明からです。おぼつかない手つきですが、ワイワイガヤガヤ楽しそうです。
3時間め・4時間めとやりました。子ども70人と教師2人で掘って、やっと5cmくらいの深さです。

翌日も2時間、掘りました。私はひたすら、つるはしを振るいます。前日よりも子どもたちの動きはいくらかスムーズです。
7月8日、三日め。「おとといも、きのうも掘ったけど、まだちょっとしか掘れてないね。みんな、どうする?」と聞きました。
「休み時間も掘る」
「日曜日もやる」
「土曜日と日曜日は休みたいよ」
「じゃあ、月曜日から金曜日まで毎日掘る」
「きょうもやるか?」
「やる」
「ようし、じゃあ、みんな外にでよう」
と、続行です。前日、前々日と私たちの作業を見ていた用務員さんが「先生、これ使ったらいいですよ」と、電動ドリルハンマーを貸してくださいました。
私がドリルハンマーで土を柔らかくします、子どもたちがスコップでその土をバケツに入れて運びます。しかし、田んぼを埋めたてて造られた学校の校庭は、やたらと硬い部分があったり、針金やコンクリートのかたまりなどが出てきたりで、なかなか深くは掘れません。
子どもたちは「がんばるう」といいます。子どもたちの発想には、お父さんやお母さんの力を借りようとか、機械力を導入しようという考えはないようです。子どもたちが「がんばる」というかぎり、私もつきあうしかありません。
最初から最後までを体験することで、
「この世界を知っている」という感情が生まれる
ここで、魚を飼うのになぜ池掘りから始めたかということに、ふれておきたいと思います。
以前、シュタイナー学校のことを書いた本(子安美知子さんの書かれた本)を読んでいたとき、つぎのようなことが書かれてありました。
シュタイナー学校では、3年生から生活科が教育課程に位置づけられていて、子どもたちがレンガを積んで家を造り、そして、最後に、それを壊すところまでやるそうです。こうした、さまざまなものづくりや体験が取りいれられている目的は、「子どもの心のなかに自分はこの世界を知っているのだという感情が生み出されることである。つまり、これは子どもの行動に確実性を与える。のちに自分を人間として世界に送り込むときの安定した感情を生み出す。それは人間の意志力と決断力にとって、非常に重要なことである。人間が自分の職業には属していない分野についても、このことに関して自分は以前、とても素朴なやりかたであったが、その原理、その出発点となる知識を体験的に身につけたことがあるのだという感情を持っていれば、何でも親しい思いで見ることができる」と書いてありました。
私は、生活科で体験的学習をやるのなら、「最初から最後まで」を体験できるようなものをやりたいと考えていました。TVの「ニュースステーション」が追っかけていた長野県の「やぎを飼う1年生」(タイトルは忘れましたが)を見たときも、やぎを飼うのに小屋づくりから始めていました。そのときも、私は「これだ」と思いました。
そんなわけで池掘りから始めたのですが、縦約7m、幅約3mの池を掘るのは、1年生70人と担任2人の力ではなかなかはかどりません。いつ完成するのか、見とおしさえつきません。それでも始めたからには途中で止めるわけにはいきません。
4日連続で掘ったあと、しばらく休んで、つぎの週に3~4時間やりました。深いところで30cmぐらい、浅いところで15cmぐらいになったところで、夏休みになってしまいました。
夏休み中に、だれかが水を溜めて遊んだらしく、また雨水も流れこんだのでしょう、まわりの土がはいりこんで、半分ぐらい埋まってしまいました。
(後編へつづく)
出典:別冊『ひと』3号、1993年7月、太郎次郎社
宮崎勇市(みやざき・ゆういち)
神奈川県、小学校教員。
退職後は熊本県に帰郷してきのこ園をひらき、キクラゲの栽培を手がけている。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)