こんな授業があったんだ|第46回|「まかぬたねははえぬ」の授業〈後編〉|平林浩

「まかぬたねははえぬ」の授業 〈後編〉
カビを使って「生物観」を追究する(小学4年生・1983年)
平林浩
平林浩
〈前編〉から読む子どもたちは「自然発生」を信じている?!
子どもたちがすでに、「生物は親がなければ生まれてこない。しぜんになにかから生まれてくることなどないのだ」ということがわかっているとすれば、こんな授業をわざわざやる必要はない。あるいは、とくに意図的な教育をしなくても、いつのまにか身についてしまうものであれば、これも学校でとくに教えることもないのだ。だから、子どもたちが自然発生観をもっているかどうか、授業書を作ろうとすれば、知っておかなければならない。
私が子どものころは、「ウジがわく」「虫がわく」ということばは日常にあった。魚の頭などはほうっておくと、いつのまにか、ウジが気持ちわるいほどにいっぱいになる。そんなとき、「ウジがわいた」と言ったものだ。そのころは、ほとんどの人がおなかのなかに寄生虫をもっていた。カイチュウとかジュウニシチョウチュウとかいう名の虫たちである。その寄生がふえると、「おなかに虫がわいた」と言った。髪の毛や衣類にシラミがつくと、「シラミがわいた」とも言った。
「わく」というのは、いかにもしぜんに出てきたという感じのことばだが、いまの子どもたちは、そんなことばはほとんど使わなくなってしまった。日常、そのような経験をしなくなったからである。
「ムシ(虫)」という日本語は、「ムス(蒸す)」ということばから生まれたものだそうである。ムシムシしたようなしめっぽいところからしぜんに生まれてくるという意味を、私たちの世代はごくしぜんにうけとめていたし、ものがくされば、ウジムシがしぜんにわいてくると思っていた。
科学の歴史のなかで「生物の自然発生説」に科学者パスツールが決定的な結論を出したのは、いまから100年ちょっとまえのことであって、そう古いことではない。それ以前は、アリストテレスもニュートンも、自然発生説を信じていたのだ。
それでは、いまの子どもたちはどうか。
すでに紹介した授業の討論のなかでも、「雑草は、たねがなくてもしぜんにはえてくる」とか、「かびはパンが古くなって、しめりけがあればはえてくる」とかいう考えが出てきている。これらはあきらかに、雑草やカビはひとりでに生じてくるという自然発生観である。
授業書を作るために、子どもたちの自然発生観を調査したことがある。1975年に、小学校3・4・5年生にむけてつぎのような質問をして、選択肢にマルをつけてもらった。この子どもたちには、「生物は自然発生しない」という授業はしていない。
<質問>
あき地や学校の庭などに、いつのまにかたくさんの草がはえてきます。あの草はどこからやってきたのでしょうか。つぎのなかから、あなたの考えにあうものを一つえらんで○をつけてください。
㋐ 草の根やたねがあるからはえてくる。
㋑ 草の根やたねからはえてくるものもあるが、土のなかのようぶんや水ぶんがもとになって、しぜんにはえる草もある。
㋒ 土やごみやようぶんがもとになって、たねや根がなくてもはえてくる。
㋓ そのほかの考え。
子どもたちの選んだ選択肢は、つぎのようになった。
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | |
| ㋐ | 9 | 9 | 16 |
| ㋑ | 14 | 22 | 16 |
| ㋒ | 5 | 4 | 6 |
| ㋓ | 4 | 7 | 1 |
そのほかの考えとして、
*たねなんかがとんできて、水分なんかではえる。
*たねが風でとばされて、くっついて芽がでる。
*雨や風にまざってとんでくる。
*ほかのところにある草のたねがとんでくる。(5人)
というのがあった。
この結果をみると、子どもたちのなかには、両方の考えがあることがわかる。たねや根がなければはえないと考えている子どもも、1/3ぐらいはいるのだ。
雑草についての自然発生観がこの程度だとすると、カビやコケのようなものになれば、もっと自然発生観があることはたしかだろう。
カビは臭気からやってくる?!
カビについては、つぎのような選択肢で○をつけてもらった。○は2つ以上つけてもよいことにした。この質問は、6年生と中学2年生にもやってもらった。
㋐ カビはたねのようなものがあって、それがくっつくからはえる。たねのようなものがつかなければ、ぜったいにはえない。
㋑ たねのようなものからもはえるが、食べものがもとになってできてくるのもある。
㋒ ごみやくさったものがもとになって、そこからしぜんにはえてくる。
㋓ 空気中のごみがかたまって、それがカビになる。
㋔ そのほかの考え。
結果はつぎのようだった。
| 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中2 | |
| ㋐ | 3 | 6 | 11 | 7 | 9 |
| ㋑ | 4 | 13 | 15 | 5 | 7 |
| ㋒ | 28 | 22 | 16 | 15 | 11 |
| ㋓ | 19 | 13 | 7 | 11 | 2 |
| ㋔ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
こうしてみると、カビについては、自然発生観は高学年になるにしたがって少し減るものの、はっきり自然発生を否定している者の数は、どの学年もたいした差はない。
もうひとつはっきりしたことは、雑草について、たねがなければはえてこないと考えている子どもは、カビについてもたね(胞子)がなければはえてこないと考える例が多いことである。このことは、親がなければ生まれてこないという自然観をもっている子どもは、カビも雑草も、たね(胞子)がなければはえてこないと考えられるのではないかということを示していると思う。
また、カビについての学習をしていない6年生に、カビはどうやってできるかを書いてもらったこともある。
*ごみがかたまってできたもの。 (沢田くん)
*パンとかしばらくたつとだんだん固くなってくる。すごく固くなって食べられなくなったら、カビははえてくると思う。どこからやってくるのかというのは、いろいろなものの原子がかたくなると、カビになると思う。 (中山くん)
*日光にあたらないと、その物にすいつくごみのような物だと思う。カビは空気中のごみが、そのものにすいついて、日光にあたらないため変色するのだと思う。 (葛西くん)
*雨が降っているとき、よごれた空気がかたまって、自然にできると思う。 (牧さん)
このように、たいへんおもしろい。なかには、「カビはしゅう気(臭気)からやってくる。(葛城くん)」というのもあった。
なんとなくアリストテレスの時代にもどったような気分で、たのしくなってきた。これなら授業はおもしろくなりそうだ、と思った。
「カビ」の授業書づくり
このような子どもたちの実態をみていると、「カビ」についての自然発生観が否定できれば、あとは比較的、すんなりといくのではないかと思った。そこで、「カビ」の部分だけをまず授業書にしようと思ったわけである。
いま、小学校の理科教科書からは、カビの教材が姿を消した。科学の教育にとって重要な教材が、あつかいにくいというような理由で、つぎつぎと姿を消していくのはおかしいなと思う。
「カビ」を教えるというだけでなく、自然発生説の否定という大きな目標をもった教材として位置づけようとしたのが、「まかぬたねははえぬ――カビ」の授業書である。
カビのようなものさえ、胞子がなければぜったいにはえてくることがないとわかれば、それに近い菌類も胞子(親)がなければ生まれてくることはないと考えるのは、わりあいにやさしいことだろう。細菌などについての部分は、まだ授業書としてはできていないので、このあと、つづけて作っていくつもりである。
授業書の構成は、つぎのようになっている。
この授業書はまだ作成途中のため、本印刷されていない。手書きのプリントを使っている。
★「まかぬたねははえぬ――カビ」の授業書★
<質問1>(1ページ)
① カビを見たことがあるか。
② カビはどんなものについていたか。
③ どんな場所にあったものについていたか。<問題1>(2ページ)
新しいパンをシャーレに入れてそのままにしておいたら、カビははえるか。<質問2>(3ページ)
パンやほかのものにつくカビは生きているか。<問題2>(4ページ)
カビをピンセットのさきでつまんで新しいパンにつけたら、そのカビはふえていくか。<観察1>(5ページ)
カビを顕微鏡で大きくして見たら、どんな様子をしているか。<お話>(6ページ)
カビのからだ。いろいろなカビを集める。<問題3>(7~8ページ)
カビのはえたパンと新しいパンをシャーレにいれ、蒸し器のなかで30分ぐらい蒸す。その熱したカビを熱したパンにつけたら、カビはふえていくか。<問題4>(9ページ)
蒸し器のなかで熱したパンにカビの胞子をふきつけたら、カビはふえていくか。<観察2>(10~11ページ)
胞子から芽がでるところを顕微鏡でみる。<お話>(12~14ページ)
カビの一生。種類をえらんでカビを育てる。<問題5>(15ページ)
新しいパンをシャーレに入れ、蒸し器のなかで30分ぐらい熱し、そのままふたをとらずにおいたら、カビがはえるか。<問題6>
きっちりふたのできるびんを2つ用意し、新しいパンをそれぞれにいれて、蒸し器のなかで30分ぐらい熱する。一方のびんⒶは、さめるまでふたをとっておいて、さめたらふたをしめ、すきまがないようビニールテープをはる。もう一方のびんⒷは、蒸し器から出すやいなや、ふたをきつくしめ、ビニールテープをまいて、すきまをなくす。こうしたら、ⒶⒷのパンにかびがはえるか。<お話>(16ページ)
シャーレのなかに胞子ははいらない。<お話>(19ページ)
胞子がなければ、カビははえない。<お話>(20~30ページ)
いろいろなカビの話
<問題4>
カビは、長い時間、蒸気をあてて、高い温度(100℃ぐらいになる)にすると、ふえなくなります。それは、高い温度のため、カビが死んでしまうからです。
それでは、今度はシャーレに入れた新しいパンに蒸気をあて、パンについているかもしれないカビを、ころしてしまうことにします。そのあと、シャーレのふたをしたまま、ふつうの温度になるまでひやしておきます。
そこへ、パンにはえたカビを近づけて、ひやしておいたシャーレのふたを少しあけ、息でカビの胞子をふきつけます。
そのあと、すぐにふたをして、あたたかく、うすぐらいところにおいたら、カビははえてくるでしょうか。

▶予想
㋐ カビはパン全体にはえる。
㋑ カビはパンの一部にはえる。
㋒ カビは、はえない。
▶討論
みんなの考えをだしあって討論しましょう。
▶実験の結果
<観察2>
胞子から芽がでるときは、どのように出ると思いますか。予想の絵をかいてから、観察してみましょう。
▶予想の絵
〝殺菌〟されたパンにははえない?!
蒸し器のなかに入れ、30分も蒸気をあてて熱したパンは、冷えてふつうの温度になってしまっても、カビははえないのだろうか。蒸気殺菌をしたパンには、カビをはやさないような性質ができてしまったのだろうか。あるいは、カビがそういうパンをきらってしまってはえないのだろうか。それとも、カビの胞子さえくっつけば、いくらでもはえるものだろうか。
こういう議論は、生物の自然発生論争のなかでもあったことだ。パスツールは、みごとな実験でそのような論争に結着をつけたのだ。
ところが、授業のなかには、このような歴史のなかに現われた考え方がたびたび登場してくる。私はそんな場面に出会うのが、わくわくするほどたのしい。1985年の4年生では、<問題4>でそんな討論をした。
いつものように子どもたちを教卓のまわりに集め、問題で問いかけられていることをていねいに説明する。すでに休み時間から蒸気をあげていた蒸し器の火をとめた。
「このなかには、シャーレにいれたパンがはいっています。いま、火をとめました。もうちょっとさめたら、外に出すからね」
そう言ってから、こんどはべつのシャーレをとりあげた。シャーレのなかはまっ黒になっている。パンにクロカビがびっしりはえているからだ。
「こちらは生きているカビ。この黒いのは胞子の色だね。もし、この胞子に息を吹きかけたら、どうなると思う?」
「やー、きもちわるい」
「胞子がとぶよ」
「ええ、胞子をすいこんじゃうの」
さわがしくなった子どもたちのまえで、シャーレのふたをとった。
「さあ、吹いてみるよ」
子どもたちはしんとして、私の口もとに視線を集めた。ふっと息をかけると、煙のようにクロカビの胞子が舞いあがった。
「わあ、すごい」
「煙みたいだ」
あわてて手で口をふさいだり、逃げだしたりする子もいる。
「胞子は集まっていると目に見えるけど、空気のなかに散ってしまうと、見えなくなるね」
「ええっ、それじゃ、ぼくたち胞子をすってるの?!」
「もちろん、口のなかにも鼻のなかにも、いっぱいはいっているんだ」
「やだなあ、体のなかがカビだらけになっちゃうよ」
「じゃあ、お弁当の上にもおちるわけね」
「ああ、そうだよ。いま、みんなの洋服にくっついた胞子が教室にいって、また舞いあがって、お弁当にくっつくことだってあるよ」
「オエー、おれ、きょうの弁当食えねえや」
またひとしきりさわがしくなってしまった。
「さあ、この胞子を蒸したパンに吹きつけるよ」
私は蒸し器からとりだしたシャーレのふたをあけ、そのなかの白いパンに、カビの胞子をふっと吹きつけた。白いパンの表面にはうっすらとクロカビの胞子がついた。すばやくシャーレのふたをした。
「ほら、少し黒くなるくらい胞子がくっついたよ。このシャーレを3~4日おいておいたら、なかのパンにカビがはえてくるかどうか……。なにか質問がありますか」
「わかった」
「ない」
「それじゃ、席にもどって予想をたてよう」
予想は、つぎのようになった。
㋐ カビはパン全体にはえる。……16人
㋑ カビはパンの一部にはえる。…… 9人
㋒ カビは、はえない。……14人
「それじゃ、いつものように、それぞれの予想をたてた人から、○をつけた理由をききます」
㋐の予想の代表として、奈緒子さんを指名。
「このまえやったとき(問題3)、カビはふえていかなかったけど、こんどは少しはふえると思う」
「それじゃ、㋒のひろ子さん」
「とにかく、カビははえないと思います」
「㋑は友くんにきこう」
「ぼくは、ただそう思ったから」
〝はえるパン〟から〝はえないパン〟に変身?!
それぞれの考えがでたところで、討論がはじまった。㋒の予想をたてていたたみさんが、口火をきった。
「わたしは㋒だけど、カビは100度ぐらいになると、死んじゃうんじゃないの。だから、もうはえてこない」
慶一くんがすぐそれに反論した。
「カビは、蒸し器のなかにいれて蒸気をあてたんだから、死んでしまう。でもね、胞子をとばしてくっつけるんだから、またはえてくるよ」
岳くんがいきおいよく手をあげた。㋒の予想だ。
「㋐の人に言いたいけど、蒸気をあててふかしたパンは、どんなにしたって、はえてこないと思う。胞子をふきつけたって、はえない」
ナナ子さんも㋒の予想。
「あのね、パンはね、もう殺菌されちゃったのだから、はえてこない」
殺菌ということばが、子どもたちの耳にピーンとひびいたようだった。大介くんがすぐつけたした。
「蒸気みたいのをつけると、パンは殺菌されて、もうはえてこないよ」
殺菌したものにはもうカビははえないのだという考えは、毎年、出てはくるのだが、ことしほど強い意見になったことはない。一博くんがそれに応じた。
「ぼくは㋐だけど、このまえの実験は、パンを蒸してカビを殺してやったからはえてこないけど、こんどは、カビの胞子は死んでないじゃないか」
「まえの<問題3>では、1週間たってもはえてこなかった。それは、殺菌されているからはえないんでしょう」と、たみさん。大介くんがすぐ受けついだ。
「そうだよ。ふつうのパンならはえてくると思うけど、殺菌したのだからはえてこない」
もう、ふつうのパンではなくなったというのだ。
ここで、㋐と㋑から㋒への予想がえが続出した(㋐→㋒6人、㋑→㋒7人)。ところが、裕くんは逆に㋒から㋐に予想をかえた。
「ぼくは、㋒から㋐にかわる。さっき、だれだったか、殺菌されたからはえないって言ったでしょう。それに言うけど、パンは焼いてつくるでしょう。それだったら、焼いたパンにだって、はえないはずじゃないか」
なかなかの理屈だ。一博くんもそれにいきおいを得たようだ。
「そうだよ。パンは焼いて作るんだから、焼けば菌が死ぬでしょう。それでもパンにカビがはえてくるのだから、それはパンに胞子がつくからでしょう」
この論理には、㋒の子どもたちも、ちょっと困ったようだが、「焼くのと蒸すのではちがうよ」「パンを焼いてもはえるっていうけど、それは蒸気でやるのとちがうんじゃないの」と、大介くんとたみさんがつづけて反論した。子どもは、理屈につまると、よくこのような手で反論する。〝それとこれとはちがう〟という論理だ。
討論はまだつづいていったが、あとははぶく。
じつは、この問題は、いま、子どもたちがやりあっているようなところが問題になるだろうと予想して作ったものである。パンならパンを熱して、外からなにもはいらないようにしておけば、パンにカビははえない。それは、ほんとうはカビの胞子がはいらないためだし、もともとパンについていた胞子は死んでしまったからである。
しかし、それだからといって、「胞子がなければ、カビははえない」ということにはならない。もしかしたら、パンが変質して、カビがはえないものになってしまった可能性もあるのだ。蒸気をあてて熱したパンも、けっして変質したわけではなく、生きている胞子をくっつければカビがはえることを知らせるための問題なのである。
あのパスツールも、自然発生説をとなえる人たちの反論をひとつひとつ破っていくために、いちど熱したスープでも、腐敗をおこす菌のもと(空気中にいくらでもとんでいる)を入れれば、菌がふえて腐敗することを証明する実験をしている。
実際に、胞子をふきつけたパンには、あたたかいところであれば、3日もするといっぱいカビがはえ、5日目には、もう一面にカビでおおわれてしまう。
シャーレのすきまから胞子がはいる?!
つぎの<問題5>は、冒頭に紹介した。1985年のこのクラスでは、シャーレのすきまから胞子がはいるかはいらないかが討論の焦点になった。この問題は、蒸気をあてて熱したパンには、外からカビの胞子がはいらないかぎりカビがはえてこないことを証明する問題として作ったものである。
だから、熱したパンもふつうの温度まで冷えれば、またしぜんにカビがはえてくると考える子どもと、胞子が外からはいらないかぎり、カビははえてこないと考える子どもとの討論になる。大げさにいうと、自然発生説と、それを否定する説とがぶつかりあうわけである。
たいへん長い討論だったので、全部を紹介しきれないから、後半の討論が煮つまってきたところをちょっと紹介しよう。
亜月さんは「カビははえない」の予想だ。
「シャーレに入れて蒸気をあててあるのだから、もうカビははえてこない」
「ふたがしてあるのだから、カビがはいらないよ。だから、カビははえないよ」と大介くん。この二人は、カビがはいらないから、もうはえないと言っている。それに対し、「いちばん最初のときだってふたがしてあったのに、はえたじゃないか」と一博くん。実験条件のちがいを見落としている。
「大介くんに言いたい。シャーレのふたのあいだにはすきまがあるでしょう。だから、青虫だって飼えるじゃない。そのすきまからカビがはいるかもしれないじゃない」
たみさんは、シャーレの身とふたのすきまに着目したのだ。おなじはえるとは言っても、一博くんは自然発生説だし、たみさんは、胞子がなければはえないという説なのだ。
「蒸気でむしたって、蒸気がなくなれば、ふつうのパンにもどるのだから」
一博くんは、ふつうのパンにもどればはえてくるという。大介くんはたみさんの意見で、少々ぐらついた。
「だって、すきまがあるということはたしかだけど……」
口ごもったところへ、たみさんがたたみかける。
「カビの胞子は、目に見えないでしょう。そんなに小さいものだから、空気がはいればいっしょにはいる」
この意見をきいていた一博くんは、「そうだ、わかった」と大声をあげ、発言を求めた。私が指名すると、黒板に出て、つぎのような絵を描き、「蒸気が出ていったら、ふつうのパンになる。そのすきまから胞子がはいってきて、カビがはえるんだ」と説明した。
おなじ予想だが、一博くんはここで自然発生説をすてたのだ。
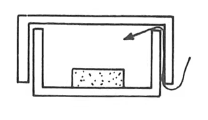
慈世さんはそれを聞いていて、「いまのに言いたい。蒸気はカビを殺してしまうし、そのままなにもはいらないのだから、カビははえない」と反論した。裕くんは、カビははえるという理由として、「トウモロコシを蒸し器でむして、あまったのを蒸し器のすみのほうにおいておいたら、蒸し器のなかにあったトウモロコシにカビがはえてた。だから、ふたがあっても、蒸気があたってもカビははえる」という考えを言った。胞子がどうのこうのというのではない、自分の経験をもとにした自然発生的な考えのようだ。
大介くんも黒板にでた。
「いくらすきまがあったって、このすきまからヒューなんてカビがはいっていくことはない。引き出しのなかに入れておくのだから」
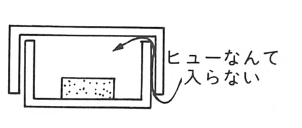
一博くんがまた、「そうか!」と声をだした。
「ぼくは㋐から㋑にかえる。引き出しのなかは、風なんかぜったいふかないから、胞子はシャーレのなかにははいらないよ」
たみさんが反論する。
「大介くんのに言いたい。空気がはいるからカビもはいると思う。蒸気で殺菌されたって、カビがはいればはえるのだから」
たみさんはまえの問題では、殺菌されたパンにはもうカビがはえないと主張していたのだが、実験の結果を知って、はっきり考えをかえることができたのだ。大介くんもたみさんも、もう自然発生観はすててしまった。胞子がはいるかはいらないかの論争になっているのだ。
まだ何人かは胞子のことを考えず、長くおくからはえるという考えをもっていた。しかし、この問題で、パンにはカビがはえず、1週間たっても2週間たってもパンはきれいで、いいにおいがしていることを知り、つぎの問題では、考えを変えていく。
最後の<問題6>では、びんづめの原理を知ることになる。さすがに、このクラスでは討論のすえ、全員がⒶにはカビがはえるが、Ⓑははえないと予想することができた。Ⓐは冷えるまでふたをとっておくので、そのあいだに胞子がはいってしまう。Ⓑは、殺菌されたあと、なにもはいりこまないのだから、カビははえてこない。
まかぬたねははえぬ
「カビ」の授業が終わったところで、子どもたちに、こんな質問をしてみた。
「この授業の題は、『まかぬたねははえぬ――かび』となっています。ここまで勉強してきて、なぜ『まかぬたねははえぬ』という題名がつけられたか、わかりますか。あなたの考えを書いてみてください」
子どもたちは、みんな考えを書いてくれた。
「まかぬたねははえぬ、というのは、まかぬ胞子ははえぬ、つまり、まかないたねは花がはえないということ。胞子がなければ、カビははえないといういみで~す」(直子さん)
こんなふうに書かれたものが多かった。もちろん「まかぬたねははえぬ」という格言のもっている意味はべつの意味であろう。しかし、この授業書の題名として使った意図を、子どもたちはちゃんととらえていた。
「やさいなどをはえさせるにはタネがいる。タネがなければ、やさいなどははえてこない。それと同じに、もし空中に胞子がういていないとする。だいたいそんなことはおこらないけど。そしたら、胞子がないからカビはきっとはえない。だから、胞子がなければ、カビははえないという意味だ。
それに、まかないというのは、はじめ胞子があってもとちゅうからなくなったら、そのカビはほろびてしまうということもある」(恵以子さん)
この文をみると、生物がずっと世代をかさねていくことへの視野の広がりまでみられて、私も感心させられた。
「カビは胞子をいっぱいとばして、どんどんいでんしていってふえる。だから、その子である胞子をまいてなければ、いくらなんでもふえていかないから。それに、カビは胞子をとばしたら、そのおやが死んでも、とばした胞子がかわりとなり、だんだんふえていく。先生が〝まかぬたねははえぬ〟とかいた。はたけにたねをまかないで、やさいはできないから、それと同じという意味だよ」(将雄くん)
子どもたちは、まだ細菌などについては学んでない。腐敗が細菌によることも知らない。しかし、ここまで見わたせるようになっていれば、細菌についてもこのような見方ができるようになるのは、そうむずかしいことではないだろう。ただ、どのような問題を設定し、どういう実験でたしかめていくか、それが授業書を完成させるためのこれからの課題である。
さらに、この授業を「あま酒づくり」「キノコ栽培」などへ発展させることもやってみたい。
(おわり)
出典:『ひと』1986年5月号、太郎次郎社
平林 浩(ひらばやし・ひろし)
1934年、長野県生まれ。1988年まで東京都で小学校教諭。退職後は「出前教師」として、科学を楽しむ教室を各地で開く。仮説実験授業研究会、障害者の教育権を実現する会会員。著書に『仮説実験授業と障害児統合教育』(現代ジャーナリズム出版会)、『平林さん、自然を観る』『作って遊んで大発見! 不思議おもちゃ工作』『キミにも作れる! 伝承おもちゃ&おしゃれ手工芸』『しのぶちゃん日記』(以上、太郎次郎社エディタス)など。津田道夫との共著に『イメージと科学教育』(績文堂)がある。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)



