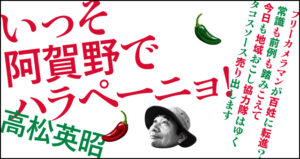こんな授業があったんだ|第50回|詩「初恋」(島崎藤村)を書きかえる〈後編〉|近藤真
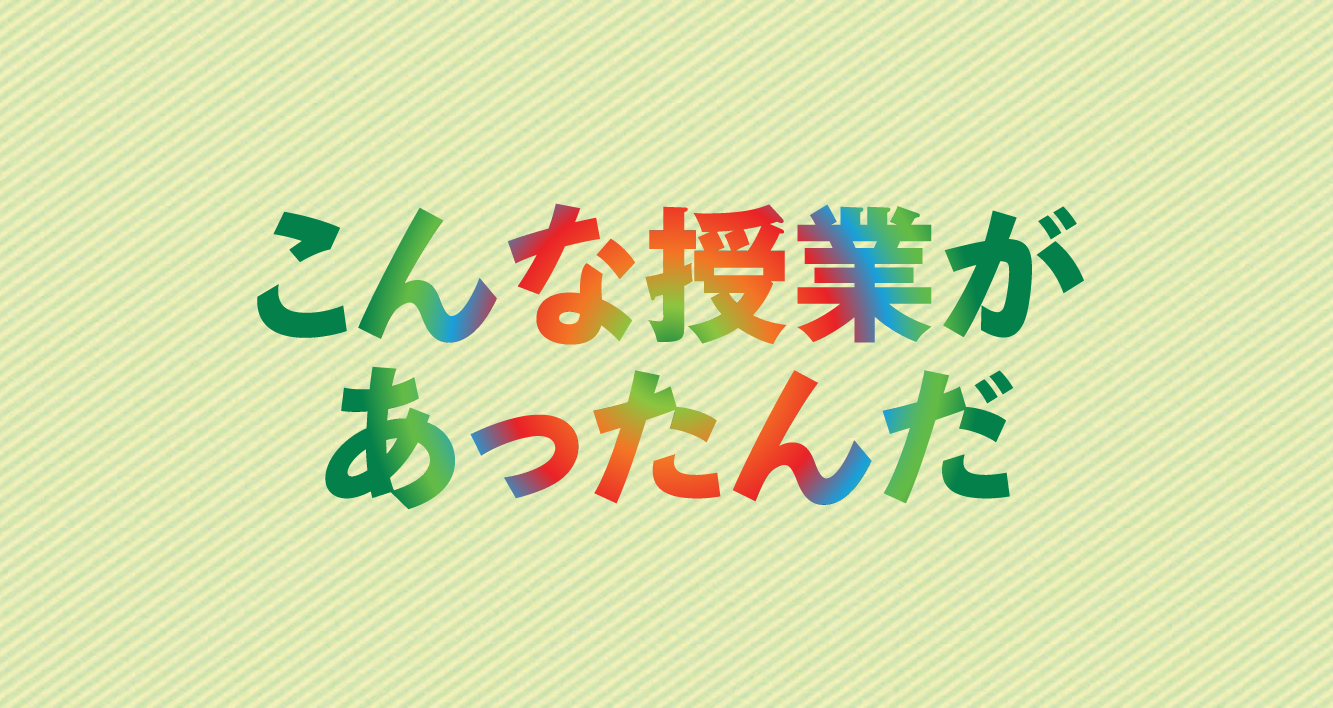
詩「初恋」(島崎藤村)を書きかえる 〈後編〉
(中学3年生・2009年)
近藤真
近藤真
初恋 島崎藤村
まだあげ初めし前髪の
林檎のもとに見えしとき
前にさしたる花櫛の
花ある君と思ひけりやさしく白き手をのべて
林檎をわれにあたへしは
薄紅の秋の実に
人こひ初めしはじめなりわがこころなきためいきの
その髪の毛にかかるとき
たのしき恋の盃を
君が情に酌みしかな林檎畠の樹の下に
おのづからなる細道は
誰が踏みそめしかたみぞと
問ひたまふこそこひしけれ(『日本の詩歌』1〈中央公論社〉から)
「薄紅の秋の実」を教室に持ち込んで
授業の日、私は紙袋に入れたグループの数だけの林檎を携えて教室に入った。品種は紅玉。スーパーや果物店を回り、市内でいちばん大きなデパートでやっと見つけた。小ぶりでかりっとした歯ごたえ、そしてこの香り。甘くておいしい林檎に慣れたわれわれの舌には、酸っぱすぎるかもしれない。しかしこれが子どものころに食べていた林檎の味だった。この酸っぱさが「初恋」の味であり香りなのだ。
「きょうの課題です。──詩『初恋』を書きかえる」。生徒はきょとんとしている。
「詩『初恋』を、“君”の立場から書きかえよう」。ますます、きょとんとしている。「鳩が豆鉄砲を食ったよう」とはこのときの生徒を表す形容である。
詩「初恋」を、“君”の立場から書きかえよう。
・“君”の目には“われ”はどのように映っているか、想像しよう。
・“われ”からの呼びかけに、あなたが“君”になって応答しよう。
・七・五調の定型で書いてみよう。
「『初恋』は、少年・男性の“われ”の視点で書かれている。あくまでも“われ”の目に映った“君”が描かれている。この詩において、世界の中心にいるのは“われ”なんだ。今度は“君”の視点にたち、少女を主人公にこの詩を書きかえてほしい。だから、いっそきみたちが“われ”の恋人になって思いきり『恋の詩』を作ってみよう!」
「教科書(S社)の学習課題は『“われ”の目には“君”はどのような姿に映っているか、想像しよう』だった。この問いを転回させた課題がこうだ。すなわち、『“君”の目には“われ”はどのような姿に映っているか、想像しよう』と。“われ”からの呼びかけに、あなたが“君”になって応答しよう。この女性にいかに変身できるか。ひょっとしたら、男子のなかには、女子以上に女性らしく変身する人がいるかもしれないよ」
「むずかしい。そんなことできないよ、先生」。課題を提示するなり、ひとりの男子生徒が声を上げた。
ここで、より具体的に生徒に問うた。
第一連は「あなた(少年)と出会った私」
少女の美しさに心を動かされた少年の、この呼びかけに対する返事を書く。
林檎の木の下に立っている少女は、少年の視線を感じて何を語ったのか。第二連は「あなたに林檎を渡した私」
はじめて恋心を抱いた少年の呼びかけに対する返事を書く。
林檎を少年に渡しながら、少女は何を語ったのか。第三連は「あなたの告白を受けた私」
恋の喜びに酔いしれ、少女に夢中になっている少年の呼びかけに対する返事を書く。
自分の髪の毛にかかる少年のため息を感じながら、少女は何を少年にささやいたのか。第四連は「あなたとの恋をいたずらっぽく問いかけた私」
少女への愛しさを募らせる少年の呼びかけに対する返事を書く。
自分の問いかけに、いっそう深い恋心の吐露で応答する少年に、少女は何を語ったのか。
林檎を手に“君”になりきって書く
書くにあたっての指示は、つぎのことがらである。
「これから書く詩は、自分を離れて書きます。固有名詞『近藤真』を離れ、少女に変身して書くのです。だから、それにふさわしいペンネームを考えてください。作品は、各自のペンネームで発表します。だから照れずに思いきり書けます」
「いちばん書きやすい連、書いてみたい連から書いてごらん」
「書き方の極意をひとつだけ伝授しよう。それは『ちょっと気取って書け』(丸谷才一『文章読本』)だ」
「どんな詩がいい詩なのか? キーワードは、『想像力』です。『思いやり』と言いかえてもいい。どこまで当事者の身になって感じ、考えることができるか。私はきみたちの作品を、『想像力』の一点で評価します」
「詩『初恋』の詩の種類は何だった?」
「文語定型詩。七・五調」
「だから、きょうあなたがたが書く詩は、七・五調の口語定型詩です。この形式で詩『初恋』を書きかえます」
「たしかに課題はそれほど容易ではない。徹底的に思考し、想像してほしい。そこで、ここに思考と想像を手助けし、創作を促進する『道具』を準備してきた」と紅玉を取りだした。
「林檎は、初恋の象徴だったね。林檎と少女が重なっている。“林檎”“薄紅の秋の実”“君”は、一体なのだ。この林檎は、“君”を具体的にイメージするためのよすが。林檎を“君”に重ね、リアルに“君”になりかわるための装置だ。あなたがた苦しむ表現者への応援団。考えあぐね、ことばに詰まったときの相談相手」
生徒は、ワークシートに向かって鉛筆を握った。なかには、シートをじっと見つめたままの生徒もいる。
「ことばに詰まったら、林檎に逃げなさい。問いかけなさい。林檎の声を聞きなさい」
「食べちゃいけないんですか?」
「グループにひとつだけだからね。食感や味わいはそれぞれに想像してほしい」
食べて味わうことはできないものの、色あいを視覚で、香りを嗅覚で、重さ・肌ざわり・温度を触覚でとらえることができる。耳を当てれば林檎の声を聞くことだってできる。筆が止まると生徒は、林檎に手を伸ばす。握って、嗅いで、眺めて、そして机に置いてふたたび筆をとる。置かれた林檎を、隣の子が握っている。
やがてトミコがいちばんに第一連を書きあげた。
「さっそく、書けた人が出たよ」。私がゆっくり読んでやる。
前髪上げて誇らしげ/私の頬は赤かった
それは遠くのかなたから/あなたが私を見てるから
生徒は筆を止めてじっと聞いている。聞きおわったとたんに、「だれ?」。それからシートに向かう生徒の筆が勢いづく。同じ表現者としてのライバル意識が生まれるのだろうか。
「第二連を書いた人が出たよ」
林檎にかけたこの思い/あなたはちゃんと気づいたか
よくわからないこの想い/甘くて酸っぱい恋の味
30分も経てば、生徒の多くは四連まで書きすすめることができた。こうしてできあがった作品は男女混合の四人グループで読みあう。
「トミコさん。出てきて」。自分の作品を持って黒板のまえに出た彼女に、私が向きあう。
「“われ”が私、“君”がトミコさんです」
「まず私が、原詩の第一連を読みます。それに続けてトミコさんが自分の作品を読みます。こうやって連ごとに“われ”と“君”が対話するのです。自分の連を読みおわったら、相手を見て、自分に応える相手のことばを促すのだよ。聞くほうは、相手を見ながら聞くんだよ」
まだあげ初めし前髪の/林檎のもとに見えしとき
前にさしたる花櫛の/花ある君と思ひけり
前髪上げて誇らしげ/私の頬は赤かった
それは遠くのかなたから/あなたが私を見てるから
やさしく白き手をのべて/林檎をわれにあたへしは
薄紅の秋の実に/人こひ初めしはじめなり
林檎を使って近づいて/あなたに林檎を渡したわ
林檎は私のキューピッド/あなたと私の恋の形
わがこころなきためいきの/その髪の毛にかかるとき
たのしき恋の盃を/君が情に酌みしかな
あなたの気持ち聞く私/ふと空を見て顔かくす
あなたの口から出る言葉/一つ一つに顔ゆがむ
林檎畠の樹の下に/おのづからなる細道は
誰が踏みそめしかたみぞと/問ひたまふこそこひしけれ
私の問い聞き赤くなる/その顔ずっと見る私
そんなあなたが大好きです/あなたに逢えてホントによかった
こうして読むと、原詩の文語と生徒作品の口語の響きが交差して、たがいのよさがくっきりと見えてくる。
グループで向きあって座ったふたりが読み、ほかのふたりが聞く。ひとりの読み手Aが原詩を読み、いっぽうの読み手Bが自作を読む。Aが原詩の第一連を朗読したあと、Bが続けて自作の第一連を朗読する。これを第四連まで続けてゆく。これを読み手を交代して4回くり返す。“われ”と“君”との4通りの応答を生徒は聞くことができる。
グループは、男女混合で構成しているから、照れているのはやはり男子のほう。それに対して女子は、つかのまの恋の疑似体験を楽しんでいるかのようだ。そこではさまざまな仕方の音読が生まれている。コウサクはおずおずと、ノリコはやさしく、ユキオは情熱をこめて、トモコは淡々と⋯⋯。音読によっても、たがいの作品の差異に気づかせ、そのよさを味わうことができる。
このように、同じ原詩のことばに立ち止まりながら詩を書いても、そこに多様な作品が生まれる。読みの複数性の積極的承認とそこに生じた差異の吟味に、教室で文学を読み・書くことの楽しさがある。最後は、学級のみんなに聞いてほしい一編をそれぞれのグループから選んで、その作者に発表してもらった。
モノが触発した表現──生徒が書いた5つの「初恋」
フランスの現象学者メルロ・ポンティに倣えば、詩「初恋」を読んでしまった者にとって、林檎はもはやいままでの「林檎」ではなく、詩的な奥行きをともなった「薄紅の秋の実」として見える、といえよう。創作の場所に置かれた一顆の林檎は、生徒の想像力を無限に触発する。これも〈ことばに立ち止まる〉ための作法であり、じっくりと感じ考え想像してことばを紡ぎだすための補助装置となる。思考がよどみ筆の勢いが衰えたとき、林檎を掌に載せ、その色や形、その重さ、その肌ざわり、その匂いを身体にくぐらせる。やがてそれらはことばに姿を変えて鉛筆の先からほとばしる。
林檎というごくありふれた日常のなかのモノも、ひとたび教室に持ち込まれ授業のなかに置かれるや、テキストと関係づけられ、劇的な光のなかでがぜん非日常の輝きをまとって生徒の学びを促進する道具に変身する。個人の思考を紡ぎ表現を促進する触媒として、また、協同の学びを成立させるための生徒どうしをつなぐ媒介物として。とくに国語のような座学、しかもテキスト依存型の教科の場合は、モノにそくして思考し想像し発想するという学習活動がきわめて限られている。とりわけ短歌や俳句の短詩型文学では、モノや出来事にそくして創作する態度が基本である。「寄物陳思 」という万葉以来の表現様式の伝統を、情報リテラシーを育てる21世紀の国語教室において蘇生させたい。
生徒作品1
あげたばかりの前髪に
きれいな花櫛さしました
あなたの私を見るその目
林檎のようにきれいですあなたのためにとったのよ
赤くて小さな恋の実を
あなたはそっと口にした
いったいどんな味がした?あなたのついたため息が
私の髪にふれたとき
うれしはずかしとまどって
私もあなたが好きです困るあなたのその顔が
とても愛しく思えます
はにかむ君のその笑顔
とても愛しく思えます
生徒作品2
あげたばかりの前髪を
誰かが見てる気がしたの
はっと気づくと君がいる
赤い顔した男の子あなたに似てる林檎の実
だからあなたにあげたいな
あなたにあげるそのときに
触れあう指が恥ずかしいいつもと違う君がいる
林檎のようにまっかっか
あなたが口を開いたら
二人の顔が赤くなる君に聞きたいことがある
何で私を好きなのか
いつもの道を歩いても
あなたはいつも答えない
生徒作品3
誰かの視線気になって
林檎の下を見ていると
学生服の君がいて
心ときめくなぜだろう林檎を見てた君を見て
愛がつまったこの林檎
そっと渡した私です
なぜか心がドッキドキこれで逢うのは何回目
君がそわそわどうしたの
君の言葉で一変し
林檎みたいに真っ赤っか君と出会ったあの日から
ずっといっしょに歩いてた
この道誰が作ったの
この一言に悩む君
生徒作品4
あげたばかりの前髪を
あなたに気に入ってほしくって
きれいな花櫛かざったの
もっと近くで見てほしい心と同じ赤色の
林檎をあなたにプレゼント
あなたの心はどんな色
同じ色だとうれしいななんでため息ついてるの
私の気持ちは同じだよ
あなたのそばにずっといたい
今日が二人の記念日ね甘いにおいのこの場所で
あなたに何度会ったかな
これから何度会うのかな
数えきれなくなるのかな
生徒作品5
ふと立ち止まった木の下で
視線感じて顔上げる
あなたと目が合うそのときに
私の頬は熱を持つ林檎片手に近づいて
ためらいつつも差しだすと
あなたは少し驚いて
二人真っ赤な林檎かな夢中なあなた幼くて
思わず見入る私への
言葉すべてがうれしくて
そっと答えるあなたへの想い私の問いにあなたまた
うつむきながら頬染める
そんなあなたが愛しいと
私の心も騒ぎだす
「他者」の発見──情報リテラシーを支える力
「愛の喜びは愛することにある。そして人は、相手に抱かせる情熱によってよりも、自分の抱く情熱によって幸福になるのである」「恋人どうしがいっしょにいて少しも飽きないのは、ずっと自分のことばかり話しているからである」(『ラ・ロシュフコー箴言集』、二宮フサ訳、岩波書店)。フランスの思想家ラ・ロシュフコーのことばである。恋愛において、人は情熱的になればなるほど他者感覚を喪失していくという逆接的現象がしばしば生じる。そこでは当事者さえも気づかぬうちに、届ける相手を見失なった恋のことばは、他者の存在の空白を埋めあわせるかのように限りなくモノローグへと傾斜していくのである。このことを、詩「初恋」の読者は了解しておく必要があるのかもしれない。思えば、20代の私のひっかかりもここにあったのだ。
生徒は、原詩の第二人称「君」を第一人称「私」に、さらに原詩の第一人称「われ」を第二人称「あなた」に転回させる言語作業をつうじて、ふたりの若い男女のときめきやアンビバレントな心の揺らぎを、その時間をも共有しながら理解しようと試み、原詩のことばたちにやわらかくレスポンスしながら、対話のことばを紡いでいった。この授業で発見した「君」という他者と、ささやかながらも身につけた他者の身になってわがこととして感じ考え、さらには悩み苦しむ精神態度が、ダイアローグのことばを準備し情報リテラシーの基底をかたちづくるものだと考える。
「ことば」は相手に届けるものである。そうであるならば、詩「初恋」のことばは、はたして「君」に届いたのだろうか。──今度は、この問いで生徒を挑発してみたい。
[補記]
本記録の初出は、『情報リテラシー──言葉に立ち止まる国語の授業』(2009年11月・明治図書)である。このなかで、編者の髙木まさき氏は「情報リテラシー」についてつぎのように書かれている。
「『情報リテラシー(information literacy)』とは『情報活用能力』と言い表されることもあるように、コンピュータなどの情報機器の活用に限らず、文字や映像等を含む様々な情報を批判的に受容し、効果的・創造的に活用する能力ほどの意味合いで用いられる。本書では、その中核となる力を『言葉に立ち止まる力』であると考え」た。
また「ここでは問題提起の意味も込め、あえて『情報リテラシー』の一般的な意味合いからは対象となりにくい、詩歌や物語、古典の学習なども含めて考えた。それは、詩歌や物語、古典などが紛れもなく『情報』そのものであるということの他に、それらに『情報』という角度から光を当てることで、従来とはやや違った学習材としての価値やその扱い方が見えてくるのではないか」。(ともに「まえがき」より。)
本記録は、髙木氏の考え方をふまえ「従来とはやや違った学習材としての価値やその扱い方」を、詩「初恋」について試みたものである。
(おわり)
出典:『中学生のことばの授業』所収、2010年、太郎次郎社エディタス
近藤 真(こんどう・まこと)
1957年、山口県宇部市に生まれ、長崎県北松浦郡で育つ。国語教師として、文学作品の深い読みと創作をとおし生徒がみずからのことばを紡ぐ授業をつくりつづけてきた。著書に『大人のための恋歌の授業』『中学生のことばの授業』『コンピューター綴り方教室』、共著書に『文学作品の読み方・詩の読み方』(以上、小社刊)がある。ほか、『中学校新国語科の授業モデル〈4〉』『情報リテラシー――言葉に立ち止まる国語の授業』(ともに明治図書出版)、『地域で障害者と共生五十年』(小社)などに執筆。〈NHK10min.ボックス 現代文/古文・漢文〉番組委員。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)