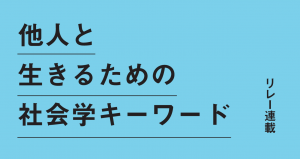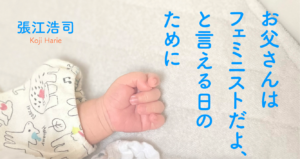お父さんはフェミニストだよ、と言える日のために|第14回|子どもは政治の人質でも経済の言い訳でもないのよ|張江浩司
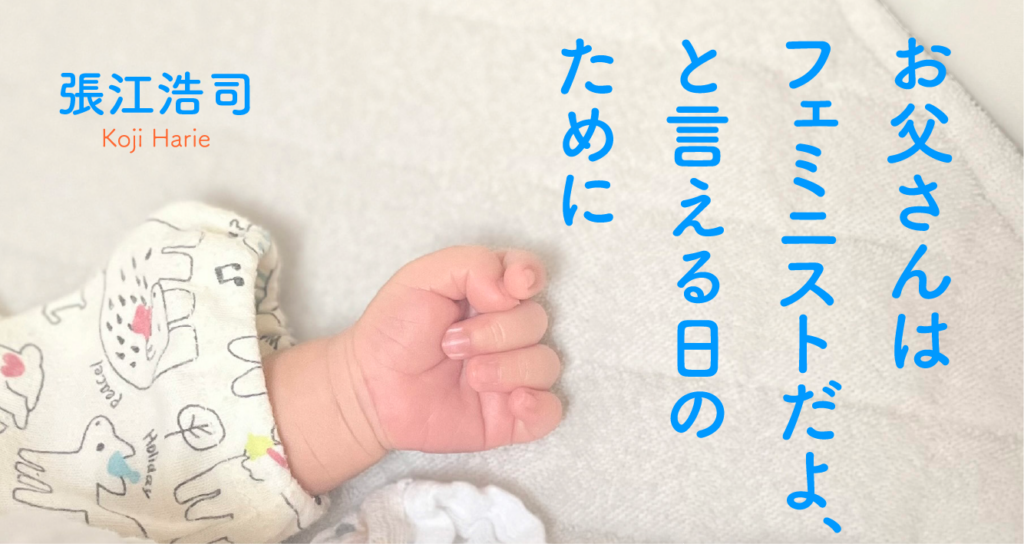
第14回
子どもは政治の人質でも経済の言い訳でもないのよ
張江浩司
視界に入っていたのに見えなかったもの
子どもができて、街の見え方が変わった。
まず、公園に目がいく。それまでは天気がいい日にひとりでベンチに座ってアイス食べたりビール飲んだりするスポットとしか認識していなかったが、いまでは「ほう、なかなかきれいでいい公園ですね。遊具の整備もしっかりしているし、なによりこの大きな滑り台はなんとも楽しそうだ。アスレチックもいい仕事してますね」と、中島誠之助みたいな審美眼を発揮してしまう。うちの子どもはまだひとりで歩く段階にないので、遊具で遊ぶのは先のことなんだけども、公園の前を通るたびにシミュレーション。「歩けるようになったらここに来よう」と脳内のマップにピンを立てている。
保育園にしてもそうで、見学に回っていたときはもちろん、いまでも園児たちの活気のある声が聞こえてくる園を見かけると、「あら、いいですね」と心のグッドボタンを押す。一方で、なんだかどんよりした雰囲気を感じる園もあって、いたずらに不安になったりもする。完全に目が肥えてきている。
そもそも、以前はこんなに公園や保育園が存在していることに気づいていなかった。散歩していても目に入ってくるのは、こだわりが感じられる外観の書店、名盤で埋め尽くされた中古レコード店、歴史を感じさせる寄席演芸場、通い慣れたライブハウス、いい感じの赤提灯をぶら下げた大衆居酒屋、「今なら瓶ビール100円引き!」という松屋のポスターなどで、ふり返ってみると私はひじょうに狭義な「カルチャー」(と飲酒)にしか興味がなかったんだなと思う。
とある俳優さんが「舞台で視覚障害者の役をやったとき、街中に点字ブロックとか音響信号があることを初めて意識した。同時に、ぜんぜんバリアフリーじゃない場所がいっぱいあることもわかった」と言っていた。何不自由なく街を歩いているつもりでも、というか、だからこそ自分に関係ないと思っている部分への解像度がめちゃくちゃに低いままで生活している。
ファミレスとマックの腹立たしい便利さ
最近わかってきたのは、大きな道路沿いにある駐車場完備の和食系ファミレスチェーンのこと。具体的にいうと、和食さと、藍屋、華屋与兵衛、味の民芸。正直、もっと値段の安いファミレスはほかにもあるし、たとえばとんかつ食べるなら専門店に行ったほうが美味しいし、まったく外食の選択肢に入ってこなかった。「こういう店って、だれがいつ行くんだろう? 法事のとき?」くらいに思っていた。
それが先日、私の母が実家の北海道から遊びにくることがあり、どこかで昼食をとろうということになった。母は足腰が悪いので、歩き回るのは厳しい。自然と車で行ける店を探すことになり、候補に上がったのが先述の店。「そういえば、うちの近所にあるけど行ったことないよね」ということで向かうと、繁盛しているけど激混みではない店内、狭すぎない席間隔、70代の母から1歳までの嗜好を網羅するメニュー、子が食べやすいように食材を切れるハサミやエプロンといった無料サービス、など、まさにいまの私たち家族のストライクゾーンに堂々と直球を投げ込まれた。ここは文字どおり、ファミリーが来るところだったのか。
サイゼリヤやバーミヤンだとけっこうな時間待たされる可能性があるし、日高屋にはもっと修羅の空気が漂っている。いつだったか、珍しく朝イチで用事があり、それを済ませて何か食べようとあたりを調べたら日高屋が。ちょうど開店時間の10:30ちょっとまえに店頭に着くと、先客のおじいさんがひとり。開店と同時に入店すると、そのおじいさんはメニューも見ずに生ビールとそら豆をオーダーして、午前中からめちゃくちゃ飲んでいた。日高屋にはそういう玄人がちょくちょくいるから、ファミリーとの相性は悪い(でも、そんな日高屋も大好き。ホッピーあるし)。
もうひとつ、マクドナルドのハッピーセットというやつも、いままでまったくわからなかった。私の幼少期、地元にはマクドナルドがなく、転売目的におまけのおもちゃを買い漁ったこともないので、本当に一度もハッピーセットを注文したことがなかった。しかし、家族で出かけるまえに朝食を準備するのがおっくうになったわれわれは、近所の駐車場があるマクドナルドに寄って朝マックすることにして、子のぶんをハッピーセットにしたところ、これもまた1歳児でも手づかみで食べやすいプチパンケーキを選択可能、栄養価が高くてファストフードの罪悪感を多少やわらげるえだまめコーンを選択可能、同じく牛乳も選択可能と、かゆいところに手が届く布陣。
うちの子どもは1歳児なのでこのチョイスになるが、成長するにつれてハンバーガーになったりポテトになったりオレンジジュースになったり、この選択可能性こそがハッピーセットのバリューだということに思い至った。これに加えて大人が食べるものももちろんあって、すぐ出てきてそれなりに安価。マクドナルドって便利。飲食店に関して「美味しいか否か」が基本的な判断基準だったが、「便利かどうか」というベンチマークもある。
このマクドナルドはとても広々としてゆったりした造りになっており、2階席にはエレベーターでも行けるようになっている。車椅子の人でも問題なく利用できそうだ。とても居心地がいい。
とはいえ、モヤモヤもするんです。こういった便利さは言うまでもなく資本力によって成立してるわけで、個人経営の飲食店はこんなに豊富な選択肢を用意するのは難しいし、ましてやどかんと大きい店舗を構えて、駐車場やエレベーターを設置することなんてできない。
資本に支えられたバリアフリーの理不尽
アーティストで美術史家の近藤銀河さんは、ME/CFS(筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群)という難病を患っていて、車椅子で生活している。近藤さんのSNSに、こういったポストがあった。
「東京の素晴らしい文化には金がなくバリアフリーには金が必要で、そしてバリアフリーは勝手に再開発とセットにされ私を含めて再開発に抗う人はバリアフリーから遠くなる。そういう理不尽の中で私たちは生きている。その理不尽と手を切ることは数十年では難しい。だからその理不尽をちゃんと考えたいよね」(参照URL)
「バリアフリーのない場所で何かをやるしかない人も、バリアフリーがない場所に行けない人も、同じ理不尽に押しつぶされているんだよ。そしてそれは一朝一夕には変わらない。途方もなく長い時間が変わるのにかかる。その変わらなさ、変わらなさの中で生きるしかないことこそを考えたいんだよ」(参照URL)
子どもを連れているとアクセスしづらい場所は無数にある。私が先ほど挙げたような、「カルチャー」な場所のほとんどはそれで、トイレにオムツ交換台が設置されているライブハウスはほとんどないし(2022年まで新木場にあったSTUDIO COASTのトイレにはコンドームの自動販売機はあった)、「子ども連れのお客様は入店ご遠慮ください」と張り出されている居酒屋も多い。社会通念上「普通のこと」とされている子連れですらそうなのだから、いわんや障害をはじめとしたあまねくマイノリティーをや。
スノッブな排他性も理由のひとつではある。かくいう私も、20代のころは子連れや障害をもった人が「こういう場所」に来ることはほとんど想定していなかったし、なんならたまに見かけると「ちょっと非常識だな」くらいの感想を素朴に抱いていたように思う。ステージ上でだれよりも非常識であろうとがんばって振る舞ったり、泥酔して非常識な武勇伝を大声で喚いたりしていたのに。いま思うと、大変恥ずかしいダブルスタンダードだ。
子育てしてようがなんだろうが、ライブは観たいし酒は飲みたい。「子ども最高にかわいい、ずっといっしょにいたい」という気持ちとこれらの欲望は並列に存在する。考えてみれば当たりまえだよ。違う人間になったわけじゃないんだから。
それを「女性は母になると本能的に子ども第一になるんです。この点、男はかないませんな」みたいなぼんやりとした印象操作で蓋をしてきた。若いうちは性別問わずいろんな人が集まっていたのに、結果的に「カルチャー」な場所は、ある年齢以上になるとおっさんが大勢を占めるようになる(もちろん、女性はゼロではない。こういった環境にもかかわらず大人の女性たちがつくり上げて守ってきた居場所は「カルチャー」のなかにも少なからずあって、それなしでは存在しなかったものもおおいにある)。
2025年になって、私を含めて社会全体の意識は変わってきたが、ひと昔前に比べても文化的なものを取り巻く経済状況は悪い。コロナ禍もあって、大企業以外はどこも、資金も人手も足りない。「そこにコストをかける余裕がない」というのが本音だと思う。
じゃあ、やっぱり子連れや障害をもった人たちは、再開発された小ぎれいな街をブラブラするしかないのか。もしくは、パートナーに家事と子育てを押しつけてジェンダーギャップを再生産し、ここに来られない人のことを無視しながらヘラヘラと「カルチャー」を楽しむしかないのか。
子どもは「スペ3」でもない
そんなもん、両方NOですよ。原則的に人間はどこに行ってもいいし、何をしてもいいわけで、それができないなら社会構造に問題があるのは当然。それを「子どもがいるから」という理由で資本主義のうわずみのような場所にしか行けないのは、ひじょうにファックオフです。極端にいえば、資本主義に子どもを人質に取られているような気さえする。巨大な企業が社会的な責任として、バリアフリーな環境を整えることはもちろん悪いことではないが、それによって構造的な搾取が帳消しになるわけではない。清潔なベビー休憩室や多目的トイレは、ジェントリフィケーション(社会的排除を含んだ都市再編)の免罪符ではない。
そもそも、マクドナルドは「BDS運動が支持する草の根ボイコット対象」だから、できるだけ行きたくないのよ。それでも行かざるをえない便利さに振りまわされる自分も腹立たしいし、そもそもこんなこと気にしないといけないイスラエルの蛮行も最悪。ほとんどマッチポンプな停戦の絵図を描いてノーベル平和賞を獲ろうとしてるトランプも最悪(考えうるかぎりの金と権力を手中に収めた老人が、後世の人びとの記憶には「いい人」として残りたいと願った結果、思いついたのが「ノーベル平和賞を獲ろう!」だった、とするとペーソスが効きすぎている。そんな悲喜劇に世界中を巻き込むんじゃない)。
日本維新の会の吉村洋文代表は、自民党との連立政権合意書に調印した会見の冒頭で「これからですね、難題課題、ひじょうに多くあると思います。でも日本に生まれた子どもたちが、この国に生まれてよかったなと、この国に住んでよかったなと、日出る国日本に住んでよかったなと思ってもらえるような国づくりをしっかりとやっていきたいと思います」と語っていた。急に「子ども」というワードが出てきて、その唐突さにギョッとした。
いくらなんでも雑じゃないか。「子どものために」と言われて「そんなことやめろ!」と怒る人はまずいないし、無条件でいい感じに話を終わらせられる言葉というだけの「子ども」。大富豪ゲームにおけるスペードの3。
私たちの目の前にいる子どもは、そんなふわっとした使い勝手のいい概念ではなく、寝てるときと食べてるとき以外はマジでほとんど活発に暴れており、行きたい方向に指をさし、葉っぱや犬を見かけると目を輝かせる自我を持った人間である。それを育てている親も人間である。たとえば政治家が「子どもたちの未来のために痛みを伴う改革が必要です」と言うとき、私はその痛みを拒否する。子どもが政治の人質になることも、経済の言い訳になることも許さない。子どもに限らず、すべてのマイノリティー性がそのように利用されることを認めない。
企業は公平にバリアフリーを拡充しろ。国と自治体は、企業にはできない部分に金をじゃんじゃん使え。演劇では助成金を活用した託児サービスなんかが普及してきてて、めちゃくちゃいいことだから他のジャンルにも適用していけ(とはいえいろいろ課題があるようで、演劇ユニット「宝宝」の鼎談でそのあたりがひじょうに詳しく話されていて勉強になりました→「宝宝の『私たち(えんげき)の現在地』【育児と演劇】どうだね編」)。都知事は現状の子育て支援でドヤ顔してないで、もっと充実させて、いいかげん関東大震災のさいに虐殺された朝鮮人をはじめとする方々を悼む式典へ追悼文を送りなさいよ。
私も妻も子も、それぞれがひとりの人間として、いっさい我慢することなく、行きたい場所に行ってやりたいことをやって、めちゃくちゃ面白楽しく毎日を過ごすことに注力し、隣人たちとも協働する。
もう毎日、勘弁してほしいニュースが続くので、逆にバッキバキになってきました。マジで楽しく生活してやるからな、うちの家族は。見とけよこの野郎。

背中で語っています
張江浩司(はりえ・こうじ)
1985年、北海道函館生まれ。ライター、司会、バンドマン、オルタナティブミュージック史研究者など多岐にわたり活動中。レコードレーベル「ハリエンタル」主宰。
ポッドキャスト「映画雑談」、「オルナタティブミュージックヒストリカルパースペクティヴ」、「しんどいエブリデイのためのソングス」。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)