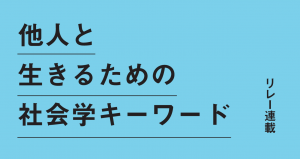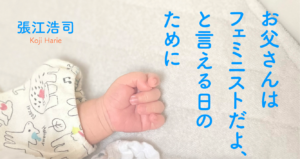いっそ阿賀野でハラペーニョ!|第12回|ハラペーニョよ、無事に発芽してくれ|高松英昭
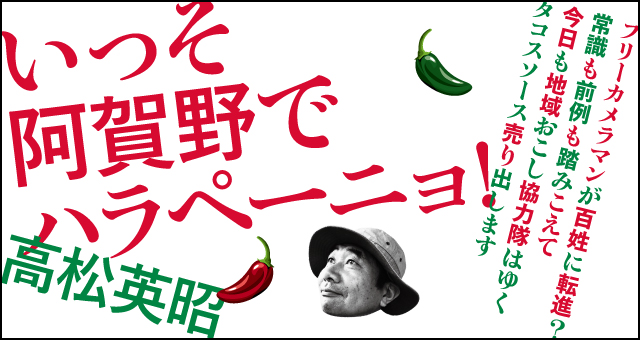
第12回
ハラペーニョよ、無事に発芽してくれ
寒い阿賀野でどう発芽させるか
阿賀野市でハラペーニョを栽培するには、育苗が最大の課題だった。5月初旬ごろには苗を畑に定植したいので、逆算すると3月下旬までには種まきを終わらせたかった。発芽させるには20度以上の温度が必要だが、新潟の冬は長い。3月に入っても残雪があるくらいで、平均気温は10度を下回る。どこかに「春」をつくる必要があった。
知り合った苗農家の音田淳さん(前回参照)は農業用ハウスのなかにビニール状のトンネルを作り、そこに農業用電熱シートを敷き、発芽させるための「春」を人工的につくっている。ベテラン農家の音田さんは長年、農家から注文のあった苗や直売所などで販売する苗などを40種類ほど育てているので、ハラペーニョの育苗を音田さんの農業用ハウスでできないか、ダメもとでお願いしたみたところ「べつにかまわないけど」と、苦笑いをちょっぴり浮かべてこころよく引き受けてくれた。
音田さんの指導を受けながら自分で育苗するつもりだが、温情に無償で甘えるわけにもいかないので、農作業のお手伝いをできるだけさせてもらうことを条件にお願いした。受注した苗を決められた時期に順々に出荷していく育苗農家は、早春から農繁期に入る。息子の寛貴さんとほぼふたりで作業しているので、私でも猫の手くらいには役立つはずだ。
育苗は保育器に入った赤子が中学生くらいになるまで育児するようなものなので、発育状況を注意深く観察しながら、温度管理などまめに面倒をみる必要がある。とくに、音田さんは丈夫な苗にするために接ぎ木をしているので多忙に拍車がかかっていた。接ぎ木は2種類の植物を茎の部分でつなぎあわせる技術で、病害虫に強い植物を台木としてつなぎ合わせれば、丈夫な苗を作ることができる。
接ぎ木はハラペーニョ栽培でも役に立つ技術だ。ハラペーニョは同じ畑で毎年育てると連作障害を起こし、病気が発生しやすくなる。そこで、3年ほど違う作物を栽培する必要があるが、ハラペーニョと同じナス科に属するナス、ピーマン、トマト、ジャガイモなども栽培することができない。ローテーションするための畑を確保しなければいけないし、休ませているあいだにナス科の植物は栽培できないという制約もあるので、将来、接ぎ木したハラペーニョ苗を定植できるようになれば、リスクや負担もかなり軽減できそうだった。
とはいえ、忙しいさなかに「私も接ぎ木を手伝います」というのは愚の骨頂である。「やったことあるの?」と音田さんに聞かれて、「やったことはありませんが、教えていただければできると思います」と呑気なことを言ってる場合ではないのだ。接ぎ木はカミソリで茎を切り、切断面を上手に組み合わせなければ結合せず、見よう見まねでできるものではない。私に接ぎ木を教える時間や失敗するリスクを考えれば、休憩時間にお茶の用意をするだけでもまだ役に立つ。

苗農家の音田さんのところに通う日々
私はビニールハウスのなかで、ホウレンソウをひたすら抜いていた。冬のあいだ、音田さんは農業用ハウス内でホウレンソウを栽培しているので、その残渣を整理して、夏野菜を栽培する準備が必要だった。午前中は市役所で情報発信の仕事をして、午後から農作業着に着替えて、音田さんのところで作業するようにしていた。ホウレンソウはすこっと簡単に抜けることもあるし、しっかりと根を張ってなかなか抜けないこともあった。スマートフォンでヨルシカの「春泥棒」を聴きながらリズムに合わせてすこっ、すこっと連続して抜けると爽快感があって気持ちいい。習うより慣れろで、なかなか抜けないホウレンソウも微妙な角度とひねりを加えると、すこっと抜けるようになっていった。体を動かしていると汗ばんでくる。外気は10度以下だが、ビニールハウス内は陽が射すと暖かくなり、Tシャツでちょうどよいくらいだ。
いつも15時30分くらいなると「お茶にしましょう」と音田さんが声をかけてくれる。休憩時に音田さんはインスタントコーヒーを作る。暑いときでもインスタントコーヒーだから、休憩時のお茶はインスタントコーヒーと決めているようだった。私は自宅ではインスタントコーヒーは飲まないが、メキシコの食堂で食後にコーヒーを注文すると、インスタントコーヒーの粉とお湯が無造作にテーブルの上に置かれることが多かったので、なんだか懐かしい香りと味がした。コーヒーをすすりながら、苗づくりのことなどを質問できる休憩時間が私の勉強時間になった。
「そろそろ種まきをしようと思うのですが。必要な材料は持ってきますので、やり方を教えてもらってもいいでしょうか」
音田さんのところに通うになったのは3月上旬で、すでに2週間ほど経っていた。そろそろ種まきをしなければ、ゴールデンウィークごろの定植に間にあわなさそうだ。
「そうだね。そろそろやらんとだね。少し遅いぐらいかも」
「種をまく育苗箱もお借りしたいのですが、よろしいでしょうか」
音田さんが種まきに使っている育苗箱は、ホームセンターに売っていなかったのだ。とくに特別な工夫がしてある育苗箱ではないが、できるだけ音田さんと同じように育苗したかったので、ぶしつけだと思ったがお願いしてみた。
「空いてる箱があるから使えばいいわね」
「ありがとうございます。近日中に種と育苗培土を持ってきますので、よろしくお願いいたします。まずは作業に戻りますね」
コーヒーを飲み終えた紙コップを机がわりにしている収穫コンテナに置くと、「抜いたホウレンソウは好きなだけ持っていっていいよ。残ったもので、どうせ廃棄するものだから」と音田さんが言った。
「ありがとうございます。ホウレンソウの胡麻あえが大好きなんですよ。どんぶりいっぱい作りたいので、たくさんもらって行きますね」と私は遠慮せずにお礼を言った。砂糖と胡麻をたっぷり入れた胡麻団子みたいなホウレンソウの胡麻あえならいくらでも食べられる。
いよいよ、ハラペーニョの種をまく
音田さんから手ほどきを受けながらハラペーニョの種まきをするので、農業分野で活動する同僚の荒木美和子さんも誘っていた。苗農家の手ほどきを受けられるよい機会だったし、250粒をまくのにどれだけ時間がかかるか見当もつかないので、荒木さんの手助けもほしかった。だが、その作業は想像以上にスムーズだった。
種と育苗培土を持参すると、音田さんがシートを敷いてくれた。その上に育苗箱を置き、育苗培土を詰めていく。地面の上に直接置かないのは育苗箱を病原菌から守るためで、育苗中は病原菌耐性が弱く、育苗培土は殺菌処理されている。土壌にはさまざまな菌がいるので、できるだけ地面に直接触れないようにする必要があった。
育苗培土を詰めおわると、音田さんが育苗箱にふたをするように板を押しつけた。板を持ち上げると、育苗培土に1センチほどの深さの筋が10列ほどできている。あとは、筋に種を落としていくだけだ。種の間隔も、メモリが付いた定規があるので、メモリに合わせるだけで機械的に種を落としていけばよかった。やはり、音田さんの育苗箱を借りて正解だった。すべての道具が育苗箱にぴったり合うように作られていた。
苗農家では何千粒と種をまくから、効率よく作業がはかどるように工夫されている。おそらく、音田さんにとって250粒はそれほど大きな数字ではないのだろう。プロとアマチュアの差は経験や知識だけではなく、効率よく作業を進めるための工夫も重要な要素になっている。その延長線上に「事業と趣味」の違いがあるのだろう。趣味なら時間や量、収益などの数字を気にしなくていい。10分ほどの作業時間の違いでも、同じ作業が1週間続けば1時間以上の差が生まれる。その1時間で別の作業ができる。それほど、農繁期はやることが多くて忙しいのだ。
音田さんは農業用ハウスで夜明け前から休日もなく作業していた。阿賀野市の会計年度任用職員という公務員である私は週休2日で、労働時間も就業規則で決まっている。育苗中は温度管理や水管理を毎日しなければいけないので、規則どおりに勤務したら育苗などできない。日々の管理は音田さんにお願いすることになる。そう考えると、音田さんの協力がなかったら、事業自体どうなっていたかわからなかった。それなりになんとかなったかもしれないが、これほどスムーズにはいかなかっただろう。
育苗箱にまいたハラペーニョの種に覆土すると、音田さんが農業用ハウス内にある井戸水の蛇口をひねり、散水ノズルで水まきして、加温しているビニール状のトンネルに育苗箱を並べてくれた。あとは発芽を待つだけである。10日ほどで発芽するはずで、それまで、できるだけ音田さんの役に立ちたいので、すこっすこっと効率よくホウレンソウや雑草を抜くことに専念することにした。

吹けば飛ぶような種なので、そこそこ神経を使う
種は条件がそろって初めて芽を出す
阿賀野市に移住するまえにもハラペーニョを栽培していたが、その当時も発芽させるのに苦労した。ヒーターが付いた小型の育苗器を部屋に置いて、そのなかで発芽させていたのだが、何度か失敗をくり返した。種には発芽スイッチがあるらしく、温度、水分、酸素がスロットマシーンのように適切に3つそろうと、大当たりのスイッチオンで発芽する。仕事ではギャンブルというわけにはいかないので、農家は「大当たり」する確率を上げるためにさまざまな工夫と知恵を凝らす。パチプロ集団「梁山泊」みたいなもんである。ベテラン苗農家の音田さんでも「発芽するまでは気が気でない」らしい。
音田さんのところに農作業に行くたびに、発芽しているかどうか気になって確認したくなるが、育苗箱はビニールトンネルのなかで、結露して白く曇っているので外から様子はわからなかった。音田さんが天候や気温に応じてビニールを開閉して温度管理しているので、ビニールを勝手に開けるわけにもいかないので、気をもみながら「大当たり」を待った。
しばらくして、いつものように顔を出すと、「発芽したみたいだね」と、音田さんがいつもと同じ小さな声で教えてくれた。ビニールが持ち上がったトンネルから育苗箱をのぞくと、筋に沿ってまいた種と同じ間隔で、ぴょこん、ぴょこんと芽吹いている。空に向かって合掌するように伸びた双葉は閉じていて、葉先にまだ殻がついている。夜に発芽したばかりのようだった。葉先の殻がはずれると、両手を広げるように双葉が開く。なんだかヨガのポーズみたいである。ところどころ発芽してない箇所があるが、「電熱シートのあたりぐあいで部分的に温度が違うから、そのうち芽が出てくると思うよ」と音田さんが言いながら、育苗箱の向きを変えて電熱シートに置きなおした。
「ありがとうございます。芽が出てよかったです」とお礼を言うと、音田さんは安堵した表情を浮かべて微笑んだ。音田さんも気をもんでいたのかもしれないと思うと、なんだか申し訳なく思い、雑草抜きをできるだけ効率よくできるように、無駄のない所作をさらに工夫するようにした。
山場をひとつ越えたが育苗は山あり谷で、まだまだ気をもむことはある。日照不足になると徒長しやすくなるのだ。茎がひょろひょろと細長く伸びて生長することを徒長といい、害虫や病気への抵抗力が弱まり、収穫にも大きく影響する。日照が足りないと、発芽した芽はイカロスのように太陽を求めてぐんぐんひょろひょろと伸びていくのだ。ちなみに、暗所でわざとひょろひょろと徒長させたのが、もやしになる。
部屋に置いた育苗器を使っていたときは、ちょうど県外に出張しているときに発芽したらしく、帰宅して育苗器をのぞいたら、茎が絹糸のように伸びてスプラウトになっていたことがあった。農業用ハウスといえども曇天が続き日照不足になれば、徒長する心配があった。いつの時代もお天道様に逆らえない。
さいわい、徒長することなく苗はすくすくと育ち、あとは鉢上げである。苗をひとつずつポットに植え替える作業で、成長につれて手狭になった子ども部屋から、それぞれ個室にしてあげるようなもので、ポットで病気や害虫に抵抗できるまで育てて、畑に定植する。植物を育てるのと人間を育てるのは、やることや考え方がほぼいっしょで、生き物を育てることには普遍的ななにかがあるのだと、農業をするようになって感じることが多い。ただ、私にとって農業は経済活動の側面が強く、自分に都合がよいように育てているので、いつも、どこか後ろめたい気持ちになっている。

(つづく)
高松英昭(たかまつ・ひであき)
1970年生まれ。日本農業新聞を経て、2000年からフリーの写真家として活動を始める。食糧援助をテーマに内戦下のアンゴラ、インドでカースト制度に反対する不可触賤民の抗議運動、ホームレスの人々などを取材。2018年に新潟市にUターン。2023年から新潟県阿賀野市で移住者促進のための情報発信を担当する地域おこし協力隊員として活動中。
著書(写真集)に『STREET PEOPLE』(太郎次郎社エディタス)、『Documentary 写真』(共著)などがある。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)