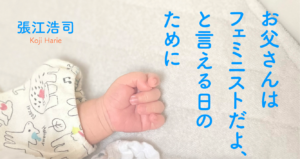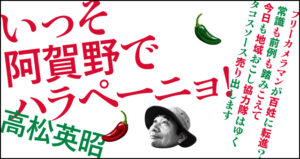他人と生きるための社会学キーワード|第14回(第4期)|ニーズ──どうしたら満たされるか|小山田建太
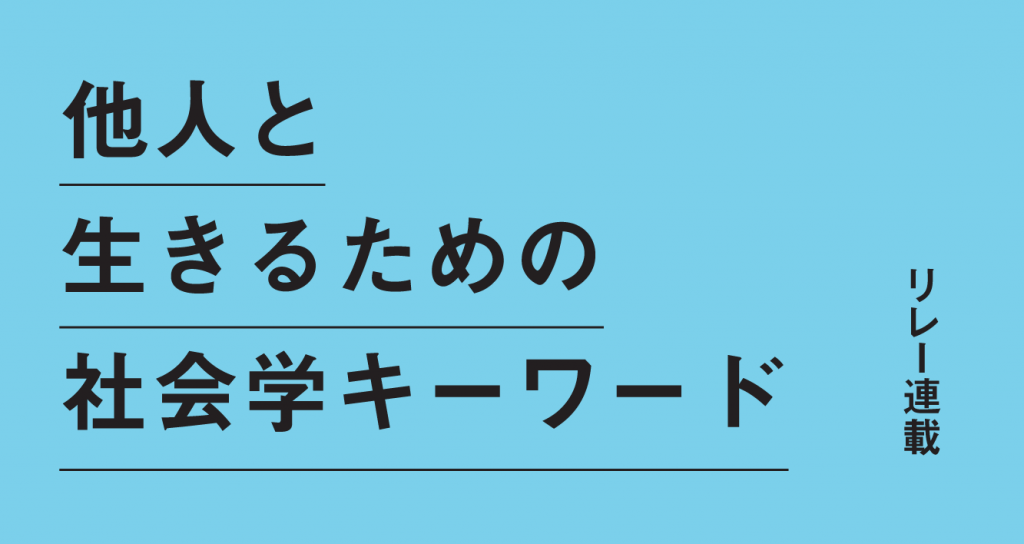
ニーズ
どうしたら満たされるか
小山田建太
2023年4月に「こども家庭庁」が発足し、あわせて「こども基本法」が施行された。こども家庭庁は「こどもまんなか社会」の実現を目指す行政機関であり、こども基本法はこども施策を社会全体で総合的に推進していくための包括的な基本法である。なぜこのような行政機関や法律が成立する必要があるのかといえば、それは日本社会での子どもや若者の「ニーズ」が十分に満たされていないためである。そこで本稿では、はじめに日本の子ども・若者をめぐる実態や課題を整理し、つぎに「ニーズ」とはどのようなものであるか、そして最後に子ども・若者の「ニーズ」はどうしたら満たされるのかについて、それぞれ考えてみたい。
はじめに、昨今の日本の子ども・若者をめぐっては、自己肯定感や自信の低さなどが指摘されている。たとえば自己肯定感について、国立青少年教育振興機構が4か国の高校生を対象として2017年に実施した「高校生の心と体の健康に関する意識調査」の結果によれば、「私は価値のある人間だと思う」と回答した日本の高校生の割合は44.9%であり、アメリカ・中国・韓国の高校生の回答がいずれも80%以上であったことと比較して大きな差が見られた。
加えて彼らの社会観については、いくぶん冷めた見方が示されている。内閣府が13~29歳の7か国の子ども・若者を対象として2018年に実施した「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」の結果によれば、「私の参加により、変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない」と思う日本の子ども・若者の割合は32.5%に留まり、他国に14ポイント以上の差をつけて最低となった。同様の傾向はNHK放送文化研究所の国内調査の結果からも確認され、とくに高年層(60歳以上)と比較したさいの若年層(20~29歳)による「政治的有効性感覚」は明確に低い(NHK放送文化研究所編『現代日本人の意識構造[第九版]』NHK出版、2020年)。ここで「政治的有効性感覚」とは、「政治的、社会的決定に対して、自分個人または他の人々との共同の行動や努力が効果があるという感覚・信念のこと」を指すが、上記のいずれの調査においても、現代の子ども・若者が不安定な自己像や社会観などを持つことが憂慮される結果となっている(公平愼策「政治的有効性感覚」大学教育社編『現代政治学事典』ブレーン出版、1991年)。
そしてこのような子ども・若者をめぐる社会指標の不安定性とは、その現状をふまえても看過することはできない。具体的には、2023年度の不登校児童生徒数や児童相談所における児童虐待相談対応件数、2024年中の小中高生の自殺者数などはいずれも過去最大となり、今日の子ども・若者が安心して社会生活を営むことができていない可能性が考えられる。このような現状は、さまざまな支援や対応によって直ちに改善される必要がある。
つぎに、このような子ども・若者をめぐる状況を、「ニーズ」という言葉から考えたい。「ニーズ」とは、「人間が社会生活を営むために欠かすことのできない基本的要件を欠く状態」として定義されるものであり、「ニード」や「必要」などとも呼ばれる(小林良二「社会福祉対象の認識方法」仲村優一ほか監修『エンサイクロペディア社会福祉学』中央法規出版、2007年)。したがって一定数の日本の子ども・若者には、社会生活を安心して営むためのなんらかのニーズがあり、またそれらが満たされる必要があるのだと表現することができる。
重ねてこのニーズとは、さらに2つの側面から大別される(上野千鶴子・中西正司編『ニーズ中心の福祉社会へ』医学書院、2008年)。1つには、「客観的ニーズ」がある。これは、おもに専門家や行政官などの第三者が当人に対して客観的に見出すニーズを指す。ここで病院や学校を舞台に例を挙げれば、医者が患者に、または教師が児童生徒に、「あなたには○○が必要である」などと診断したり判断したりして浮かび上がるニーズである。
そしてもう1つには、「主観的ニーズ」がある。これは、第三者でなく当人が自ら主観的に見出すニーズを指す。これも同じく例を挙げれば、医者や教師などが気づかず本人だけが持つ思いや自覚が主観的ニーズであり、加えてその思いや自覚、主訴を他者にも伝わるように表明したり、またなんらかのサービス利用を申請したりするときのニーズなどもこのうちに含まれる。すなわち私たちにとってのニーズとは、第三者が客観的に満たしてくれることもあれば、私たちが自ら主観的に満たすことも考えられるのだ。
このように大別されるニーズだが、それでは現代の子ども・若者のニーズをよりよく説明してくれるのは、客観的ニーズであろうか、それとも主観的ニーズであろうか? 言い換えれば、現代の子ども・若者のニーズとは第三者が代弁することでより満たされるのだろうか、それとも彼ら自身が自己表明することでより満たされるのだろうか?
このとき子ども・若者の客観的ニーズの導出や充足にかかわっては、今日の社会政策がその大きな役割を担っている。2021年の「子供・若者育成支援推進大綱」は、「子供・若者育成支援の基本的な方針」として5本の柱を設定するとともに、その総合的な推進に向けた多数の施策の具体を提示している。
ただ最後に、今日のこども家庭庁やこども基本法が子ども・若者の主観的ニーズを捕捉することを重要視している点に、あえて言及したい。こども基本法は「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)にのっとった法律であるが、同法および同条約の要点は子どもの「意見表明権」を規定している点にある。この「意見表明権」とは、「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」(こども基本法第三条第三項)を指す。すなわちこれは、彼らの主観的ニーズを社会全体で受けとめるということにほかならない。
また近年では学校においても、子どもたちによる意見交換や対話を通じた校則の見直し(ルールメイキング)が推奨されるなど、子ども・若者が主観的ニーズを表明することの重要性を認める活動が広がりつつある。そしてなによりこのような活動のプロセスとは、彼らの自信や自己有用感などを醸成する点でも大きな意義を有する。子ども・若者が積極的に主観的ニーズを表明できるようになること、ひいては彼らが主観的ニーズを表明しやすい環境を整備することこそが、彼らのニーズをよりよく説明するのかもしれない。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
苫野一徳監修、古田雄一・認定NPO法人カタリバ編『校則が変わる、生徒が変わる、学校が変わる──みんなのルールメイキングプロジェクト』学事出版、2022年
富永京子『みんなの「わがまま」入門』左右社、2019年
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
小山田建太(おやまだ・けんた)
立正大学社会福祉学部講師。筑波大学大学院博士課程人間総合科学研究科教育基礎学専攻単位取得満期退学。専門分野:教育社会学、共生社会学、福祉社会学、若者支援。
主要著作:
『多様性〈いろいろ〉と凝集性〈まとまり〉の社会学』(共著)、太郎次郎社エディタス
「準市場における事業評価の影響の検討」(『日本教育政策学会年報』第26巻、2019年)
「公的若者支援施策における支援の意義に関する考察」(『社会政策』第14巻第3号、2023年)
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)