他人と生きるための社会学キーワード|第12回(第3期)|「ぼやき」──それは社会をかえる糸口になるかも|西村大志
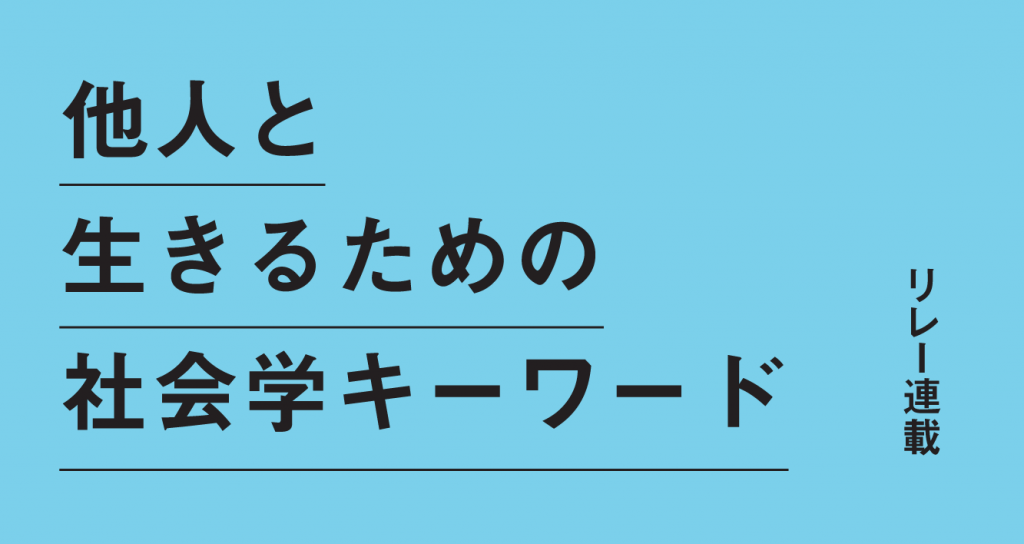
「ぼやき」
それは社会をかえる糸口になるかも
西村大志
「責任者でてこいッ!」。かつてよく知られた上方のぼやき漫才師、人生幸朗の名セリフである。「ぼやく」とは、辞書的にはぶつぶつと不平をいうくらいの意味である。ぼやき漫才では、一方がぼやきつづけ、相方があいづちをうったり、たしなめたりする。ぼやく側は、相方の話にあまり反応しないまま、ぼやきつづける。掛け合い漫才が中心の現代では異質なスタイルともいえる。2022年のM1で優勝したウエストランドもぼやき漫才の系譜に属するかもしれない。
ただ、ぼやきと、悪口とは違う。現実に違和感をもったとき、ぼやきは、さまざまな対象にぶつぶつと違和感を表明するところから始まる。なので、攻撃的な批判とは違う。上から目線でもない。ちょっと無責任で弱気なところも含みながら、現実世界の事象への個人的な違和感を語る。
古くは「てなもんや三度笠」「花王名人劇場」などのテレビ番組を手がけ、1980年代初頭の漫才ブームの仕掛け人ともされるプロデューサー、澤田隆治は「ぼやき」について、『上方芸能列伝』(文藝春秋・1993年)のなかでつぎのように書いている。
ぼやき漫才の“ぼやき”はビートたけしの世相の切り口とは違うのだ。諷刺であっても攻撃を伴わない。ニガイ笑いをとったのでは失敗なのだ。ぼやきに“責任”はない。ビートたけしは激しく対象に迫り過ぎて逃げられなくなり、しばしば責任をとらされる。
「赤信号 みんなで渡れば こわくない」で知られるようなビートたけしの切り口は、鋭く対象をとらえる。対象をとらえる側の漫才師も、しっかりと覚醒している。鍛えられ研ぎ澄まされた刀で、スパッと斬りかかる。攻撃の対象も明瞭で、攻撃した対象から反撃されることもある。
これに対し、人生幸朗の漫才は、一部分だけ切りとれば、言葉ははげしく聞こえるかもしれないが、思考はもっとゆっくりで呑気なのである。刀は刃こぼれして鈍い。振り回しているが、何を攻撃しているのかよくわからない。振り回している本人も頼りないおじさんなのである。いい意味でキレがなく、不平不満を温かい笑いへとつなげる。澤田は、人生幸朗・生恵幸子の漫才のなかのつぎのようなやりとりをとりあげている。
幸朗 なめとったら承知せんぞ、バカヤロー、責任者、出てこい!
幸子 どないです、責任者出てこいやて、えらそうに。出てきはったらどないするんや
幸朗 あやまったらええんや
幸子 アホか、えらそうなことぬかすな、ボケ!
幸朗 ゴメンチャイ
このかわいらしさに、“ぼやき”の本質があると澤田はいう。
「責任者でてこいッ!」は、ぶつぶつ言っている間に感情が高まって出る。だがじつは、本人はいたって弱気なのだ。本当に責任者が出てきたりしたらこわい。調子が出はじめるとつい強気になってしまうが、最後までそれを貫徹するほど本人はしっかりしていない。
漫才から落語まで幅広い著書のある演芸評論家・相羽秋夫の『上方漫才入門』(弘文出版・1995年)によると、ぼやき漫才の創始者として目されるのは、都家文雄である。文雄は人生幸朗の師匠であり、幸朗はかつて都家文蔵の名で活動していた。師匠の文雄は社会や政治をネタとしたため、第二次世界大戦ごろは、幾度も警察に逮捕、拘留されたという。それもあってか、戦後には文雄はある意味で立派な人になってしまった。のちには関西演芸協会会長にもなっている。
師匠の文雄のほうが、幸朗よりも漫才にキレがあったとされる。しかし、技術と観客に響くこととのあいだにはずれがある。漫才には、技術をこえて、観客をひきつける要素があるのだ。幸朗のよさは、ぼやきつつも、その鈍さと滑稽さゆえに、社会批評にはならないところである。さらに、幸朗は、気楽にぼやく、無責任にぼやくことの価値を示してくれる。これは、社会をある方向に押し流さないための、すぐれた知恵のひとつである。
沈黙を強いられるわりに、沈黙は承認を意味してしまう状況が世間には多々ある。そんなときに激しい抵抗を示すような都家文雄的批評はハードルが高い。そこで、人生幸朗のように、とりあえずなんでもいいからぼやいてみる。だれに向けてかもわからないまま、ぼやいてみるという方法がある。
理不尽さに対して、ぼやくな、ただ黙って、もしくは、むしろかえって明るくおこなえというような雰囲気は、戦時中を思わせる。1942年11月15日の朝日新聞の朝刊をみると、大政翼賛会・読売新聞・東京日日新聞・朝日新聞の主催で、「国民決意の標語」が募集されている。太平洋戦争1周年を機に募集された「戦争完遂の挙国的決意を力強く表現し、戦場精神昂揚と生産増強と戦争生活の実践(一字不明)行を促すべき寸鉄的標語」だという。
1942年11月27日の朝日新聞の朝刊には、入選作10点が掲載されている。入選作10点のなかには、有名な「欲しがりません勝つまでは」もある。作品群には、その精神構造が現代の日本社会に残っているものも多い。「理屈言う間に一仕事」「その手ゆるめば戦力にぶる」「すべてを戦争へ」などがその代表であろう。戦争を仕事に置き換えれば、現代でも多くの職場が要求していることにつながる。つべこべ言うな、気をゆるめるな、全力で働け。仕事内容が戦争でないだけのことである。
「さようなら」のかわりに「お疲れさま」が使われるようになったのはいつからだろうか。別れの言葉でなくて、職場での慰労の言葉にいつの間にか置き換わっている。われわれは、ほかにも「コスパ」「タイパ」に代表されるような効率化にかかわる言葉、言いかえれば「現代版・国民決意の標語」を無意識に用いている。「仕事」とその効率化の言葉が、さまざまな場所に流れ込んでいる。なぜポジティブに、愚痴もいわずに、「よろこんで」もしくは、「スマイル0円」なのだろうか。よろこべないこともあるし、スマイルは0円ではないのである。人の魂にかかわるようなスマイルが0円である、という感覚には注意を要する。感情を一定の範囲でコントロールすることが求められるサービス業にみられがちな「感情労働」に、しかるべき対価を払わない主因のひとつがここには見いだされる。
そんな現状へ強い抵抗を示すことは、普通の人には困難である。真面目に考え、まっすぐに抵抗して、上位者や周囲からの苛烈な圧力にへとへとになる。だれもが歩める道ではない。これに対し、幸朗的ぼやきから得るものは大きい。とりあえず何か余計なことを言ってみる。しかも、無責任に言う。理屈にならない屁理屈でもよい。まとはずれでもよい。それが、私たちが現状に違和感を感じたときに参考になる姿勢である。「混ぜ返すな」と怒る上位者もいるだろう。しかし、場を、状況を、社会を、ときどき混ぜ返さなかったために、さまざまな構造が固定化し、流動性を失い、閉塞感に満ちた状況が続いてしまうことが多いことを、私たちは経験してきている。
人生幸朗はなかなか売れず歳を重ね、50歳近くでやっと人気を得た。次第に大舞台でのトリも任されるようになった。人生幸朗の妻で相方の生恵幸子に『帰ってきた“ぼやき”漫才──人生幸朗のうらおもて』(ヒューマガジン・1988年)という作品がある。人生幸朗の紆余曲折の一代記である。
「人生幸朗」とは、「幸せを求めて、朗らかに人生を送ろう」と人生幸朗が自身でつけた名前であるという。「生恵幸子」は、「亭主に死に別れた女が、生まれ変わって幸せになるように」と、幸朗が妻につけたという。ともに逆境にあり、ふたりで再出発した芸人夫婦の祈るような気持ちの込められた名前であった。
歳をえるにつれ、幸朗は次第に歌謡曲についてぼやくことが増えていった。時事ネタから遠ざかったのは、ふたりがネタ覚えが遅く時事ネタをすぐに盛り込めない、幸朗の極度の近眼のためラジオやテレビでの終わりの指示が見えないなどの理由があった。ネタのなかで幸子が「いつまでしゃべってるねん、この泥亀」というのはツッコミの意味だけでなく、あまり遠くの見えない幸朗に舞台の下で出されている終了1分前の合図を伝えるためでもあった。さまざまなハンディキャップにもめげず、老いて心身が思いどおりにならないなかでも、ふたりはがんばりつづけたのである。
幸朗、幸子の舞台にもどろう。
幸朗 私も「ぼやき、ぼやき」と言われながら、このぼやきの姿勢は崩すことなく、政治、経済、スポーツ、文化、広範囲にわたって長年、ぼやき続けてやっと今日の地位を築きあげました
幸子 たいそうにいいなや、なんの地位やそれは
幸朗 けどね皆さん、私もね、何もないことをぼやくのやおまへん、
これ聞いとくなはれや、今の世の中が私に舞台でぼやかしとる (澤田・前掲)
世の中のせいでぼやきがでる。無理なこと、理不尽なことがあれば、ついぼやいてしまうのである。ぼやきはネガティブで、社会を、日々を、暗くするように思う人も多いかもしれない。しかし、表面をとりつくろって明るいことにし、裏にはいると暗い沈鬱な世界が広がっている世界のほうがよいのだろうか。
幸朗の無責任で論理性を欠くぼやきは、社会の流動性を高め、閉塞感を打開するためのひとつの糸口だと思える。ただ、そこにかわいらしさと愛嬌をまぜ、人びとを笑わせるためにはかなりの修業が必要そうである。その道の第一人者・人生幸朗ですら50年以上かかったのである。まずは、志ある者で、コスパもタイパも無視して、ぼやくところからはじめよう。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
鶴見俊輔『限界芸術論』ちくま学芸文庫、1999年.
三田純市『昭和上方笑芸史』學藝書林、1993年.
柳田國男『不幸なる芸術・笑の本願』岩波文庫、1979年.
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
西村大志(にしむら・ひろし)
広島大学大学院人間社会科学研究科准教授。京都大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学、博士(文学)。専門分野:文化社会学、歴史社会学。
主要著作:
『小学校で椅子に座ること』国際日本文化研究センター、2005年
『夜食の文化誌』編著、青弓社、2010年
『映画は社会学する』共編著、法律文化社、2016年
『夜更かしの社会史』共著(近森高明・右田裕規編)、吉川弘文館、2024年
『昭和史講義【戦後文化篇】(下)』共著(筒井清忠編)、筑摩書房、2022年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)


