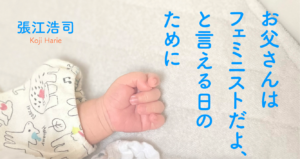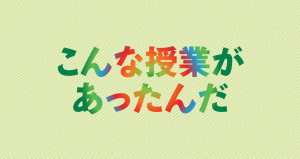他人と生きるための社会学キーワード|第12回(第4期)|少子化社会対策──リプロダクティブ・ヘルス/ライツという、もうひとつの観点|笹野悦子
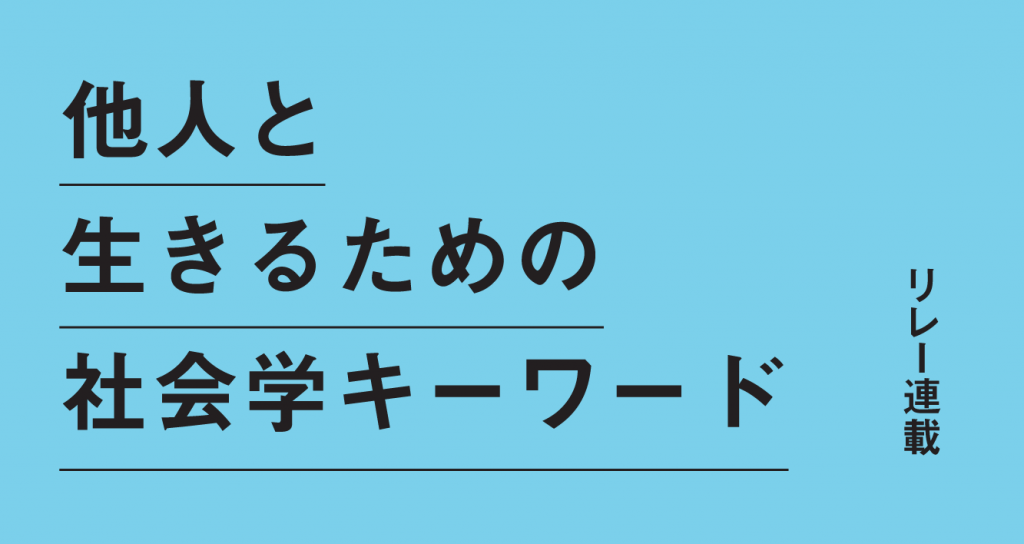
少子化社会対策
リプロダクティブ・ヘルス/ライツという、もうひとつの観点
笹野悦子
担当している授業のなかで、学生たちが模擬調査を実施した。「現在の日本社会において社会問題と呼ぶ問題があるとすれば、まず何をあげますか」という質問に、「少子化」「少子高齢化」など少子化に関連する回答が集中し、37パーセントにのぼった。回答者は社会学を専攻する大学生200名あまりときわめて偏ったデータではあるが、若い人びとに少子化が社会問題として強く意識されている一端がうかがわれる。労働力の不足、高齢化とあいまって、青壮年層の税・社会保障費負担の増大は、これから社会人となる若い世代にはとりわけ喫緊の課題と感じとられている。
ここでは少子化社会対策の問題を少し別の観点から考えてみたい。
日本では、人口問題の解決のために出生数増加と人的資本の充実に志向した施策がなされている。「少子化社会対策基本法」(2003年、以下「基本法」)にもとづいて策定された「少子化社会対策大綱」では、若者の就業による自立奨励と、女性の両立支援も重点課題として力点が置かれた。新自由主義的な人的資本の育成、産業社会への貢献と、保守主義的なジェンダー役割を担った異性婚と結婚、妊娠、出産、子育てがパッケージ化された生殖を前提とした出生数の増加が諮られている。
学校教育では、2010年代に、「社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度を育てる」キャリア教育と、ライフプラン教育が始まる。ライフプラン教育では、定型的なライフプランをイラストで示しながら、女性の身体の過程を妊娠・出産に関連づけて、少子化対策への啓発を謳う副読本を使用する自治体もあった。推奨された過程のなかでの出産がうながされる。この文章を読んでいる読者も、「( )歳で結婚、( )歳で第一子、第二子⋯⋯」とワークシートに書き込みながら自分のキャリアプランやライフプランを考える授業を受けた経験があるかもしれない。だが、シングルで、または同性カップルで、子どもを産んだり養子縁組で家族を形成するあり方もある。また、子どもをもたなくても、少子化社会をどんなかたちで支えられるかを考えるきっかけとなる授業もありえるだろう。しかしそれらは、推奨されたライフプランには現れない。どのように産むかを選択するのではなく、どんな選択をしても社会を支える一員として生きるという多様な生き方の尊重が必要なのではないだろうか。
また、2000年代初めのバックラッシュの影響で、性教育でのリプロダクティブ・ヘルス/ライツの教育も後退した。中等教育ではジェンダー教育よりも「柔軟な性役割の獲得」(「生徒指導提要」)を目指す男女平等が目標づけられ、包括的性教育は遅滞した。教育課程をつうじて、人的資本としての産業社会への貢献と、結婚・妊娠・出産(そして育児)という定型的なコースでの女性の出産がうながされたのである。
だが、少子化社会対策は当初から新自由主義的な産業社会の維持と、保守主義による家族形成を前提とした出生数増加を目指していたわけではなかった。「基本法」制定の準備段階、1990年代に目を転じて、もうひとつの観点を確認したい。
日本で少子化社会が社会問題化しはじめていたころ、国連人口基金では人権問題への国際的な関心の高まりを反映して、人口問題対策のパラダイムを大きく転換した。従来の人口管理から、開発途上国や経済移行諸国への人口関連の支援、女性の健康問題やジェンダー平等などの取り組みに力点を移したのである。1994年の第1回国際人口開発会議(カイロ会議)ではリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(Sexual and Reproductive Health and Rights=日本語では「性と生殖の健康と権利」)の保障が盛り込まれた。生殖をめぐる健康と、どのように産むか産まないかを女性が決定する権利の保障である。
この時期は国内で少子化が課題となり、国会でも少子化社会対策の審議が重ねられた。「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」概念が紹介され、少子化社会対策と関連づけて、女性やカップルがいつ、何人産むか(産まないか)を決める権利の保障をめぐる議論が継続的にくり返された記録が会議録には残っている。2000年の「第一次男女共同参画基本計画」には、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツの視点から女性の生涯を通じた健康を支援するための総合的な対策の推進を図る」必要性が謳われた。「性教育」においてもリプロダクティブ・ヘルス/ライツを含む性に関する学習内容を取り上げるよううながしている。男女平等政策のなかでも、個人が決定する主体として尊重され、育まれる方向が示されていた。しかしリプロダクティブ・ヘルス/ライツをめぐっては、この概念の浸透を見るまえに、2000年代前半のバックラッシュの波に飲み込まれて雲散してしまう。2003年に成立した「基本法」には「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」の観点は盛り込まれなかった。
こんにち、リプロダクティブ・ヘルス/ライツは、遠い開発途上社会のこと、現代の自分たちの社会にはあまり関係のないことと思われるかもしれない。だがここで、2022年に邦訳出版された『母親になって後悔してる』を紹介しながら、それが現代日本社会の問題でもあることを再考してみたい。著者であるイスラエルの社会学者オルナ・ドーナトは、「もう一度やり直すとしても母にはならない」と答えた母親23人に、母親になった「後悔」について詳細なインタビュー調査をおこなった。それによると、社会の側は、女性に対して母になることを期待している一方で、彼女たちが母になった時点では自らの自由意志によって母になることを選択決定したとみなしている。母になった女性の実際の戸惑いや悩みは座視し、むしろそれを忘れるようにうながす。社会規範は、母親役割を生きる母としての成長と安心のルールに沿ったハッピーエンドに導く。だからこそ、母になったことへの後悔の念は、逸脱として不信の念をもって迎えられ罰せられるというのだ。それゆえに、その後悔は口にしてはならなかったし、著書のタイトルに人はたじろぐ。リプロダクティブ・ヘルス/ライツが一定程度保障されていると考えられている西洋社会での事象である。日本社会でも同様であろう。妊娠や出産をめぐる女性たちの口にされない逡巡や悩みがあり、周囲はそれを見ようとしない。
著者ドーナトは、「母親役割を生きる」母たちは、ひとりの人間として生きる主体というよりも、他者のために存在する客体であると分析する。そしてそんな女性たちに、硬直化した母性の役割から、動的な関係性として母性をとらえ直すよう勧める。個人がおこなう選択や決定は、いつも躊躇や後悔と隣り合わせなのだ。その躊躇や後悔に寄り添い支える社会が求められる。著作内で引用される母親の幸福度調査によると、経済的福祉は重要だが、母の健康と福祉を政治的措置の優先事項としている国において、母親の幸福度は高いことが示される。いつ、どのように子どもを産むか産まないか、リプロダクティブ・ヘルス/ライツは確かに個人の権利であり、個人の選択に委ねられるべきではある。だが、同時にその選択と決定はときとしてためらい揺らぐものでもある。そのような選択の結果は自己責任として本人が引き受けざるをえないものではなく、調査結果が示すように、社会制度のなかで個人的選択と決定への支援の準備が求められる。それなくしては、個人の選択と権利は自己責任の陥穽をまえにすくんでしまう。
少子化社会の問題を議論するさいに、こうした当事者の声が聞かれにくいのではないだろうか。先に挙げた国連人口基金の『世界人口白書2023』では「子どもを産む人々の主体性がほとんど認識されないまま、出生率が問題として、そして解決策としてみなされるという状況が繰り返されている」として、問いの立て方を問い質す。
人が多過ぎるのか、少な過ぎるのかを問うのではなく、人々、特に女性や少女、そして最も疎外された人々が、生殖に関する自己決定権を行使できているのかを問うべきです。人々は出生に関する目標を実現できているのか。そうでない場合、それはなぜか。人々の生殖に関する権利は守られ、尊厳をもって平等な暮らしができているのか。こうした問いは政策立案者にとって、人が多いか少ないかという大きな概念よりもはるかに有用です。(出典:『世界人口白書2023』130頁)
持続可能な福祉制度や経済力のためにもっと人口を増やすべきだという抽象的な議論ではなく、具体的に出生数を抑制しているものは何かについて議論すべきである。少子化が進行する国の特徴としてしばしば指摘される、「職場でのジェンダー不平等、家庭でのジェンダー不平等、勤労者世帯への構造的支援の欠如という三重の足かせ」(『世界人口白書2023』145頁)がなぜ解消できずにいるのかを議論するほうが、喫緊の課題をまえにしてはるかに現実的である。また、人口増加に的を絞った議論は、女性の身体を理想的な人口を管理するための道具と考えることを容易に可能にする。福祉制度や経済力や社会システムは、人口を構成する人びとのためにあるのであり、人びとが制度のためにあるのではない。自分たちの生きていく社会をどのような社会にしたいのかを構想することも必要であろう。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
西山千恵子・柘植あづみ編著『文科省/高校「妊活」教材の嘘』論創社、2017年
オルナ・ドーナト著、鹿田昌美訳『母親になって後悔してる』新潮社、2022年
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
笹野悦子(ささの・えつこ)
武蔵大学・都留文科大学ほか非常勤講師。早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士後期課程単位取得退学。専門分野:社会学、ジェンダー研究、家族研究。
主要著作:
『共生と希望の教育学』共著、筑波大学出版会、2011年
『ジェンダーが拓く共生社会』共著、論創社、2013年
『共生の社会学』共著、太郎次郎社エディタス、2016年
『教育社会学』共著、ミネルヴァ書房、2018年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)