他人と生きるための社会学キーワード|第6回(第3期)|学校群制度──入学者選抜と格差への問い直し|池本紗良
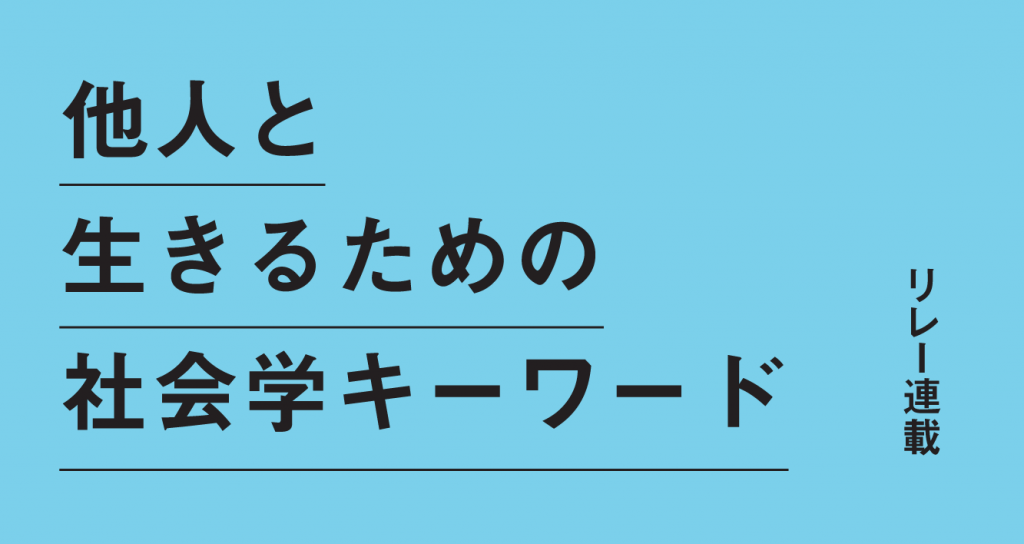
学校群制度
入学者選抜と格差への問い直し
池本紗良
2023年度の東京都立高等学校入学者選抜には英語のスピーキングテストが導入され、波紋を呼んだ。「ほかの人の声が聞こえた」や「前半の受験生の声が後半組に聞こえた」という実施方法への疑義、不受験者が有利になると噂される配点方法への疑義が呈され、はたして公正といえるのかが問われている。
選抜方法が変わるたびにこうした議論はくり返されている。かつて東京都の都立高校入試には「学校群制度」という方法が採られていた。このしくみは1967年度入試から導入され、1981年度まで敷かれていた。同一学区内の高校が2~4校の「群」に編成され、受験生はその「群」を志願する。あとはその群でおこなわれる入学試験に合格した者が、学力が均等になるよう機械的に群内の高校に振り分けられるというしくみである。たとえばA高校に行きたいと願う受験生がいても、直接そのA高校に志願書は出せない。A高校が含まれる学校群に志望するしかなく、たとえその群に合格したとしても、他の受験生の成績とのかねあいからB高校やC高校に振り分けられることもある。その意味では、A高校に入れるかは「運」に委ねられるのである。
いまの感覚でいうところの公正からは、ほど遠い選抜方法であろう。ゆえにこの制度はかなり批判的に語られる。生徒の学校選択を認めなかったために、生徒自身も愛校心を抱けず、都立高校がそれぞれ受け継いできた学校文化を破壊した、そればかりか学校選択の自由を失った成績優秀な生徒は私立高校へと流れ、都立のレベルダウンにつながった、という語り口である。現に新聞や雑誌でも、「都立離れ」や「都立凋落」が話題となり、4年制大学進学率の指標をもって、かつての都立有名校が低迷し、代わって私立高校が台頭している傾向が報道された(『朝日新聞』1988年5月24日朝刊)。
また東京都の議会においても、この制度が都立高校の凋落を引き起こしたという指摘がなされている。たとえば、1996年の都教育委員会定例会では、黒須隆一都議会議員がつぎのような発言をしている。
「大学進学という面で見ますと、都立高校の現況にじくじたる思いを感じるのは、私ばかりではないと思います。現在の都立高校たらしめた最大の原因は、昭和42年の学校群制度の導入であります。この制度を導入する前の都立の進学実績は、私立や他府県の公立高校をはるかに凌駕していたと認識しております……都立高校全体のレベルダウンと都立高校離れを招くという結果しか得られなかったことは、ご承知のとおりであります。私立の存在を無視して、都立の形式的な平等化をねらっても、進学校が都立から私立へ移動しただけであり、あわせて、学校選択の自由を失った生徒がさらに私立へと向かう状況となり、その結果、都立は私立の後塵を拝し、軒並み地盤沈下したわけであります」(『都教育委員会第3回定例会議事録』1996年9月12日)。
こうした批判は、学校選択が可能になり、かつ大学進学実績を気にすることが通常化したいまだからこそ、理にかなった語り口のように感じられる。このように多くの人びとにとって学校群制度は、「都立凋落」を招いた「元凶」として記憶に刻まれている。
では、そもそもなぜ学校群制度は導入されたのか。このころの東京都において問題になっていたのが受験偏重教育であった。居住地が含まれない他学区に入学する「越境入学」や、補習授業や試験勉強に必死に取り組む「詰め込み教育」が横行していた。
この状況を当時の都教育長・小尾乕雄が問題視した。彼はこうした受験偏重教育を生じさせている原因が「学校間格差」にあるとみた。「学校間格差」があるからこそ、少しでも進学・就職に有利な高校に入ろうと、学区を越境する手立てがとられ、睡眠や遊びを削ってでも知識を詰め込む勉強がなされると判断したのである(小尾乕雄『教育の新しい姿勢』1967年、読売新聞社)。
そこで「学校間格差」を是正するために選抜制度が見直されることになった。もともと1965年3月時点では、6校の高校増設と学区の小規模化を軸にした「14学区による総合選抜」案が進められていた。これはなるべく多くの子どもが高校に入学する土台を整えようという案であった。しかし学区の再編成をめぐって意見がまとまらず、この案は頓挫するに至った。そこで新たに見出されたのが、学区編成はそのままにしながら、群を設けて「学校間格差」に対処する学校群制度であった。
この構想は都立高校選抜制度改善審議会にて練り上げられていった。当初の審議では、①「学校群」は、主として地域並びに交通事情を考慮して組み合わせ、有名校が一つの「学校群」に偏在しないようにする、②「学校群」間の各高校の教員、施設を同じ水準にそろえる、③父兄の中に誤った有名校尊重の考え方が根強いが、これを改めていくことが前提だとされた(『朝日新聞』1966年5月31日朝刊)。
このとき前提として、通学区重視で群編成が志されたこと、そして施設の充実と教員の補充・異動といった教育条件の整備が不可欠であるとされたことは刮目に値する。この前提がしだいになし崩されていく。
まず、学校群制度に対する強い反対の声が沸き起こった。とくに有名校OBやPTAは猛反対し、学校群反対連盟が結成された。この学校群制度の導入で、学力が水準に満たない者も入学してくることになり、学校の「レベルダウン」につながると懸念されたのが大きな理由であった。
都立高校が反対の姿勢を強めたこともあって、都教育庁は「急激な改革は避ける」と弁明を出した。そして都教育庁学校群委員会から、「①従来の学力差を無視して、ただ地域的に近いという理由から、有名校とレベルの低い高校をいっしょの群にするような『均一化』は考えない。②群編成の第一の重点は、『地域・交通』だが、これには各高校の現在の生徒の通学区域のもようを重視していく。③いわゆる有名校は散在させるが、これと組み合わせる学校は、有名校とあまり学力差のないものにしていく」(『朝日新聞』1966年7月3日朝刊)という旨が公表された。「地域・交通」が「第一の重点」とは押さえながらも、「学力差」がかなり考慮されるようになっていったことがわかる。さらにどのように群編成をするかという議論が熱く交わされる一方で、教員・施設といった教育条件の整備は後回しにされてしまった。現行学区はそのまま、高校増設や教員異動もさほど念頭におかれずに、学校群制度が運用されていったのである。
ただこの学校群制度は、導入直後においては「学校間格差」の是正にたしかに寄与していた。当時の群志望状況をみると、有名校を含む群には集中せず、通学しやすい自宅近くの群を選ぶ傾向があったという(『朝日新聞』1967年1月26日朝刊)。また伊藤純によると、かつて二流校とされていた高校が「準一流校」として大学進学実績を引き上げるなどの「同じ群内の高校の平均化」が見出されたという(『東京都立高校における学校群方式入試制度の考察』1971年)。学校群制度は「有名校集中」や「学校間格差」に対して一定の効力をもっていたといえる。
しかし、その効力は長くは続かなかった。都立高校の受験を辞退する者が年々増加し、私立高校へ流れる「都立離れ」が顕著になっていった。さらに同じ学校内において生徒の学力差が広がったために、各学校内で能力別学級編成が設けられることにもなった。学校群制度の導入直後には是正されたかのようにみえた「学校間格差」が、都立─私立の公私間格差や、能力別学級編成の学校内格差という新たな格差に変形していったといえる。
では、こうした「都立凋落」や新たな格差の原因は、「学校間格差」をなくそうという学校群制度の目的そのものに埋め込まれていたのだろうか。そうではなく、学校群制度が運用されていく過程での「おから工事」にその原因があった。群編成の段階で結局は「学力差」も重視され、かつ教育条件の整備も後回しにされたため、本来の目的をかなえることができなくなってしまったのだ。
そもそも「都立凋落」や新たな格差という事態は結果論にすぎない。この結果論だけで、学校群制度が「愚策」として片付けられるのは尚早であろう。あらためて振り返ると、格差是正より学力水準の問題に論点をずらす姿勢や、高校教育費用が十分に割かれなかった事態こそが「元凶」だったのかもしれない。
そして学校群制度を再考するにあたって、こうした発想があり、制度として実現したこと自体の意味も最後に押さえておきたい。当時は「学校間格差」を問題視し、それへの対応をすることがなによりも優先された、ということである。選抜を経たあとに生じうる「格差」を問題視するこの立場は、選抜方法の公平性にばかり焦点化される議論に対しても、また新たな視点をもたらしてくれるだろう。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
天野郁夫『教育と選抜の社会史』ちくま学芸文庫、2006年.
マイケル・サンデル『実力も運のうち――能力主義は正義か?』鬼澤忍訳、早川書房、2021年.
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
池本紗良(いけもと・さら)
早稲田大学文学部社会学コース助手・同大学院文学研究科社会学コース博士後期課程在学中。専門分野:教育社会学、共生社会学、ジェンダー論。
主要著作:
「国民統合装置としての『教育する母親』像の歴史的検討──バーンスティンのコード理論を手掛かりに」単著、『共生教育学研究』第6号、2019年
「『教育ママ』言説における母親像の変容──1962-1980年の『読売新聞』を事例に」単著、『ソシオロジカル・ペーパーズ』第30号、2021年
「高度経済成長期における女性の公共性の様相──高校全員入学運動に活用された『母親』カテゴリーに注目して」単著、『社会学年誌』第62号、2021年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)

