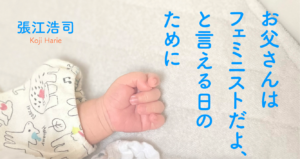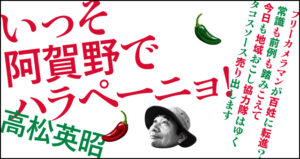他人と生きるための社会学キーワード|第10回(第4期)|なぜ高校受験はあるのか?──適格者主義のしくみ|池本紗良
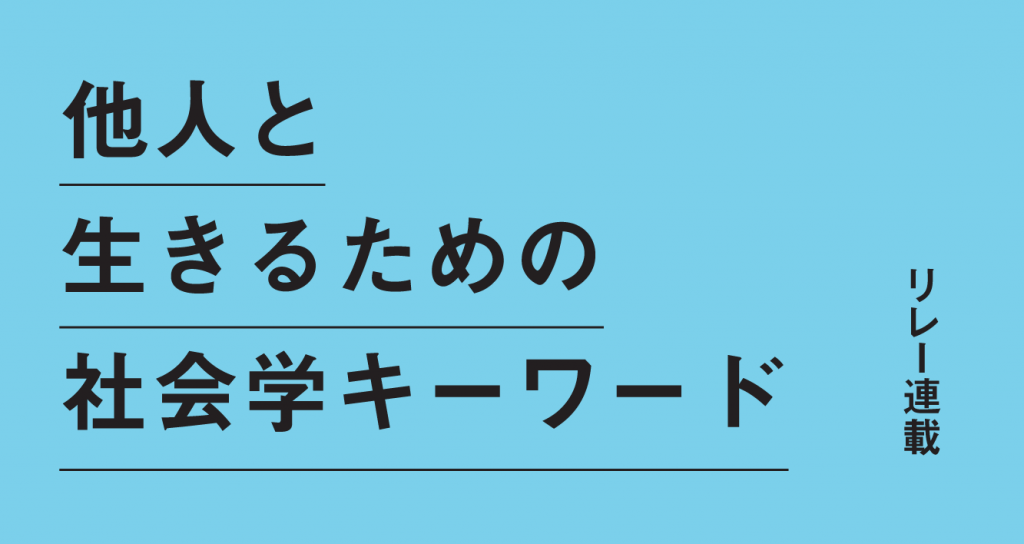
なぜ高校受験はあるのか ?
適格者主義のしくみ
池本紗良
2023年現在、高校進学率は98%を超え、中学校を卒業した生徒ほぼすべてが、高校に進学する時代、いわゆる「高校全入時代」になっている。この「高校全入」の背景にあるのが、少子化による生徒数の減少である。ここ5年ほど、中学校卒業者数は毎年2~3万人ほどずつ減少している。
そうした生徒減少期にあって、もはやほぼすべての者が高校に入れるようになっている。それはすなわち、ほぼすべての者が高校進学までに、なんらかの入学試験を受験することを意味する。それでは、なぜ、ほぼすべての生徒が高校に入れるようになったにもかかわらず、高校受験というしくみがあるのだろうか。
高校教育の原型は、戦後直後に発足した新制高校に見出せる。新制高校は、戦前の限られたエリートのみが進学する旧制高校を見直し、希望する者すべてに開かれた高校教育を保障する制度として構想された。じつは、その発足時には、高校受験=入学者選抜は「志望者数が、入学定員を超過した場合」にのみおこなう「やむをえない害悪」と規定されていた(文部省『新制中学校・新制高等学校 望ましい運営の指針』、1949年)。すなわち、高校受験は実施するのが当たりまえといったものではなく、むしろ廃止するべきものとみなされていた。
それが1963年、文部省から各都道府県教育委員会に向けて通知された「公立高等学校における入学者選抜について」によって、入学者選抜は「原則実施」するように転換が図られた。その通知の一部を、以下に抜粋する(傍線は引用者による)。
高等学校の目的に照らして、心身に異常があり、修学に堪えないと認められる者その他高等学校の教育課程を履修できる見込みのない者をも入学させることは適当ではない[省略]。
高等学校の入学者の選抜は、[省略]高等学校教育を受けるに足る資質と能力を判定して行なうものとする。
この年の高校進学率は66.8%、第1次ベビーブーマーの影響により、急増した進学者を受け入れるだけの高校数・学級数は整備されておらず、だれでも好きなように入ってしまうと、席が足りなくなる問題があった。そこで、高校教育は条件を満たした者のみが受けられる段階だという考え=「適格者主義」を打ち出し、入学に制限をかけるようになった。ここで重要なのが、「高等学校教育を受けるに足る資質と能力を判定」するための方法として、「入学者の選抜」が設けられたことである。この「入学者の選抜」は、個人の「資質と能力」そのものを絶対的基準から測るものではなく、他の受験生との相対的な成績順位により、合否が決まるものであった。すなわち、選抜試験の合格者を「高等学校教育を受けるに足る資質と能力」を有する者とみなし、不合格者を振り落とす手続きを当たりまえとする社会が形成されていった。この、限られた合格者の枠を受験生同士が取りあい、あぶれた者は振り落とされる論理を〈選抜の適格者主義〉と名づけたい。
その後、中学校卒業者数が減っていき、高校進学率も上昇していった。高校進学率が94.1%に到達した1984年、文部省は「公立高等学校の入学者選抜について」を出し、以下のような文言で入学者選抜を定めた。
高等学校の入学者選抜は、各高等学校、学科等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を判定して行う。
63年通知の文言と比べてみると、さほど大きな違いがないようにみえる。だが、「能力」の判定基準が、63年通知では「高等学校教育」に定められていたのに対し、84年通知は「その教育」=「各高等学校、学科等」に変化している。じつは、この小さな変更には、大きな意図が込められていた。文部科学省は、この変更について、「高等学校の入学者選抜は、飽くまで設置者及び学校の責任と判断で行うものであることを明確にし、一律に高等学校教育を受けるに足る能力・適性を有することを前提とする考え方を採らないことを明らかにした」ものだと表明している(文部科学省HP「高等学校教育の現状」:2023年8月1日閲覧)。すなわち、能力の判定は一律におこなうものではなく、各高等学校の判断でおこなうものだと位置づけなおすことで、「いわゆる適格者主義」の立場を明確には採らないと主張したかったのだと汲みとれる。
ただし、この主張は、「適格者主義」の立場を完全否定したわけではない。つまり、公式にはその立場を明示することはせず、「各高等学校」の責任と判断に任せたのである。背景には、多様なニーズに即した高校教育を提供していくうえで、入学者選抜も多様な方法で施すことが妥当だとする考えがあった。そうして、推薦入試や自校作成問題の試験など、さまざまな入学者選抜の方法が、各高等学校単位で採られていくことになった。こうした事態は、それぞれの高校が入学者を決め、受験生がなんらかの教育機関に振り分けられていくという意味で、〈選別の適格者主義〉と名指せる。
以上みてきたように、「適格者主義」は、〈選抜の適格者主義〉から〈選別の適格者主義〉へと形相を変えた。しかしそれは、入学者選抜の方法が多様化しただけで、その実質は受験生どうしの順位づけであることに変わりはなかった。 たとえば、東京都立高校の入学者選抜実施要綱(令和7年)には、「当該都立高校の募集人員(推薦にもとづく選抜の入学手続者数を除く。以下同じ)に相当する人員を総合成績の順により決定し、これをその都立高校の合格候補者とする」(東京都教育委員会HP:2025年5月1日閲覧)とある。いわば、その学校の教育を受けるに足るかどうかは、総合成績順に並べられ、募集人員枠内に入ること意味しており、枠内に入れたら「能力・適性等」があるとみなされる。
高校受験実施の建前としては、高校教育を受けるだけの「能力の有無」を確認するためだと説明される。しかし、実際に受験でおこなわれているのは、他の受験生との順位争いのなかで「能力の優劣」をつけることである。ここに、高校全入時代だといわれながら、高校受験が実施されつづけている便法がある。たとえ少子化によって進学希望者の数が少なくなっても、能力の優劣を競って順位をつけることが自明視されていれば、高校受験はひき続きおこなわれることになるだろう。高校受験が、他者との「優劣」をつけるためにおこなわれ、その順位によって「能力」が判断されるかぎりは。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
門脇厚司・飯田浩之編『高等学校の社会史――新制高校の〈予期せぬ帰結〉』東信堂、1992年.
門脇厚司・陣内靖彦編『高校教育の社会学――教育を蝕む〈見えざるメカニズム〉の解明』東信堂、1992年.
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
池本紗良(いけもと・さら)
早稲田大学文学部社会学コース助手。専門分野:教育社会学、共生社会学、ジェンダー論。
主要著作:
「高度経済成長期における女性の公共性の様相──高校全員入学運動に活用された『母親』カテゴリーに注目して」単著、『社会学年誌』第62号、2021年
「学校群制度の語り口の変容──都立高校の『格差是正』から『都立凋落』へ」単著、『早稲田大学文学研究科紀要』第69号、2024年
「教育の大衆化における『高校全入』の意味変容──高校全員入学運動が抱えた葛藤の分析」単著、『社会学年誌』第65号、2024年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)