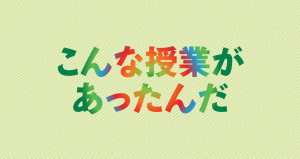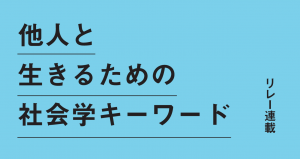いっそ阿賀野でハラペーニョ!|第13回|土壌をつくり、竹を切りだす|高松英昭
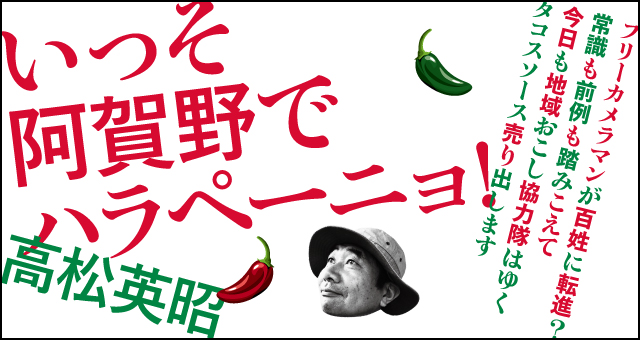
第13回
土壌をつくり、竹を切りだす
まずは地元の堆肥で土づくり
農業用ハウスでハラペーニョの苗を育てながら、畑作業も始まった。阿賀野市が管理する「うららの森農園」の畑を利用することになっていた。面積は半反ほどで、バスケットコートくらいの大きさである。市民にサツマイモ栽培体験を提供する畑だったが、「サツマイモ畑は別の場所に移動するから、そこでハラペーニョを栽培したらいいよ」と、農林課がこころよく畑を貸してくれたのだ。サツマイモはヒルガオ科でハラペーニョはナス科なので、連作障害の心配もない。前年まで「現役の畑」だったのできっちりと耕されていて、作業負担も軽減できそうでありがたかった。
まずは有機物を畑に投入して、土づくりである。微生物が有機物を分解しながら活性化して土壌を豊かにするので作物がすくすく育ち、病害虫の被害も抑制できる。阿賀野市は新潟県の酪農発祥の地で、酪農家も多く、そこから排出される糞尿を活用して堆肥を製造していた。「畑に堆肥をまくなら連絡しておくから」と農林課が手配してくれた堆肥が、ハラペーニョ畑に運ばれてきていた。
完熟した堆肥は臭いもなく、さらさらしている。春になると市内のあちこちで、水田に堆肥をまく風景が広がる。米づくりも土づくりからである。春先に東京から来た友人が鼻をクンクンさせながら、「なんだか醤油せんべいを焼いている香りがする」と言っていた。私は慣れてしまって感じないが、あたりは水田が広がっていたので、おそらく堆肥の香りのことだろう。外国人旅行者が「日本の空港は醤油の香りがする」というのと同じで、慣れ親しんで意識することがない「風土の香り」があるのかもしれない。私は果物が発酵した甘くすえた香りを嗅ぐとメキシコのメルカード(市場)を思い出すし、移住してからは化粧品の香りがすると都会を感じてしまうようになった。
畑のわきにズドンと置かれた約300キロのフレコンパックから堆肥を一輪車に移し替えて、できるだけ均等になるようにスコップを使って畑にまき、耕耘機で耕しながら、堆肥を土中にすき込んだ。家庭菜園で使うような小型の手押し耕耘機で耕すので、半反ぐらいの面積でも、そこそこ時間がかかる。トラクターで耕せば30分もかからない面積だが、50センチ幅くらいずつしか耕せないので、何度も往復することになった。
この手押し耕耘機は土をかく爪も小さいので、できるだけ深く耕すために、地面に押しつけるようにして前進する。なかなかの重労働だった。それでも1回耕しただけでは不十分な気がして、もう1度同じことをくり返すことにした。細かく耕耘することで土中に空気を送り込み、微生物を活性化させ、保水性を高めることができる。それに、植物の根も酸素が必要なのだ。
Tシャツが汗で湿ってきたが、春の農作業は心地よい。ふかふかに耕された土の感触は達成感を増幅させるし、掘り返された土といっしょに出てくるミミズや虫をついばもうと、ハクセキレイがぴょこんぴょこんとあたまを振りながら、耕耘機を押す私のあとをついてきた。たまにふり返ってハクセキレイを観察すると、「すいません。勝手にご相伴にあずからせてもらっています」みたいな感じで、バツが悪そうに顔を横に向けるのがなんとも愛くるしいのだ。土を耕す行為が自分と自然を一体化させているような気がして、肉体労働が崇高な使命にさえ思えてくる。
3時間ほどで作業を終え、少し痛くなった腰をさすりながら耕した畑を眺めていると甘い炭酸飲料が飲みたくなったので、自分へのご褒美にと、割高なのでふだんは利用することがない自動販売機に向かうことにした。

苗の支柱はホームセンターではなく、竹林から調達
つぎは竹を切る必要があった。畑は山麓にあり、山から吹き下ろしの強風が吹き抜けて苗が倒伏することがあるし、実の重さで茎が折れることもあるので、支柱は不可欠だった。
ホームセンターでイボ竹と呼ばれる支柱が1本100円くらいで買えるが、250本ほどの苗分となると高額になる。限られた予算のなかで購入するのは厳しいので、竹を切って支柱にしようと考えていた。畑がある笹神地区は名のとおり竹林が多く、繁殖力が旺盛な竹の維持管理も地域の課題になっていた。放っておくと、まさに破竹の勢いで竹林が広がっていくのだ。竹を切れば課題解決にもささやかながら役立ち、無料で支柱を手に入れられるので一石二鳥になる。事業計画を練っているときから、支柱には竹を利用するつもりでいたので、イボ竹の購入費用は予算計上していなかった。
ただ、笹神地区には直径が10センチ以上になる真竹や孟宗竹の竹林が多く、支柱に適した直径3センチほどの篠竹の竹林を見つけるのに苦労した。篠竹は河川敷に群生していることが多いので、当初は、畑の近くに篠竹が群生する河川敷を見つけて目星をつけていた。基本的に行政が河川敷を管理しているので農林課に相談にすると、「確認したら県が管理している河川敷なので、県のほうに許可申請を提出する必要があるけど、どうする?」という返事だった。市が管理しているなら話が早いと思っていたが、県に許可申請を出すとなるとなんだか手続きが煩雑そうなので、別の場所を探すことにした。

車で移動中も、篠竹の竹林を意識して探すようにしていると、育苗している農業用ハウスに向かう道中でたまたま見つけることができた。よく通る道でいままで気がつかなかったのが不思議なくらいで、「求めよ、さらば与えられん」である。
車を停めて篠竹を観察すると、支柱に手ごろな太さで背丈も2メートル以上あり、1本刈れば支柱が2本取れそうである。150本ほど切ったところで竹林の見た目はあまり変わらないくらい、広範囲に群生している。あとは、地主を探して許可を得るだけだ。
竹林から少し離れた場所に集落があるので、そこで地主のことを聞こうと思ったが、手当たりしだいに家を訪ねて「あそこにある篠竹を切りたいのですが、地主の方をご存じですか」と聞くのもなんだか怪しい。竹林のわきをたまたま通りかかった人に「この篠竹を切らせていただきたいのですが、持ち主をご存じですか」と世間話をするように話しかけるほうが自然だが、なんせ歩行者は皆無である。
「その集落って、農林課のE課長が住んでいるところだと思うけど」
地域おこし協力隊の同僚と雑談しているときに篠竹の話をすると、地主の許可を得られる最短ルートにつながるヒントをくれたのだ。同じ集落に住む住民の口添えは、プラチナチケットを手に入れたようなものだ。さっそくE課長のところに相談にいくと、「こんど集落の集まりがあるから、そのときに聞いてみるよ」と約束してくれた。
翌週にはE課長が私の席までやってきて、「どうぞ好きなだけ切ってください、ということだったよ。それから、うちの近くにも篠竹の竹林があるから、そこも切っていいよ。そこは道路に面してないから、竹を搬出しやすいように車を入れられる敷地の地主にも許可をもらったから、作業するときに連絡すれば、竹林の近くまで車で行けるようにしてくれるから」と言って、地主の連絡先を書いたメモを渡してくれた。
「ありがとうございます。さっそく切りにいこうと思います」とお礼を伝えると、「竹林は放っておくわけにもいかないから、切ってもらえると助かるんさ。ぜんぶ切ってもいいからね」とE課長は言って、笑いながら去った。竹林を整備しておかないと、イノシシが潜んだりすることもあるらしかった。
竹を切る作業に、地域おこし協力隊の荒木美和子さんにも声をかけることにした。荒木さんは農業分野で活動していて、竹を農業に活用することを考えていた。竹炭を畑に散布すると土壌改良にもなり、保水性が高まるという。100本以上の竹を切らないといけないから、人手は多いほうが助かる。竹を切る専用のこぎりがあることも、荒木さんが教えてくれた。木工用のこぎりと違い、竹の繊維を効率よく切るために、刃が細かく並んでいるらしい。それから保護メガネも必要らしく、竹の枝がぴょんと跳ねて目に刺さることがあるという。想像するだけでおぞましいので、ホームセンターで購入することにした。
支柱160本分の篠竹を1日で切りだす
篠竹切りは順調だった。太さが3センチほどなので、3、4回くらいのこぎりをひけば切ることができた。慣れると稲刈りの要領で何本かまとめて切ることができるようになった。同じ篠竹でもぐにゃりと曲がる軟弱なものがあったり、芯がしっかりして支柱として最適なものがあったり、不思議である。最初は手で触れて確かめていたが、しだいに見た目で硬派か軟派かを見分けられるようになった。
大学時代、体格がよかった私は応援団のスカウトを受けたことがあった。まずは話だけも聞いてほしいと、指定された居酒屋に行くと、4人全員が漫画「嗚呼!!花の応援団」の主人公・青田赤道が着ていたような学ランを着て、私を待っていた。あきらかに外見からして硬派である。軟派な私は応援団のスカウトを断り、三三七拍子をすることもなく、学園祭に来たアイドルの歌声に合わせて手拍子を打つ道を選んだ。だから、軟派な篠竹にも親近感を抱きつつ、支柱にはなれない自分をメタ認知したりもするのである。
私は肉体労働しながら考えごとをしたり、想像をめぐらしたりすることが大好きで、じっとして考えごとをするよりも、いいアイデアが浮かぶことが多い。くだらないことを想像して、ニヤニヤしながら作業することもあるので、ほかの人から気味悪がられることもある。

竹林の近くに池があり、そのほとりには桜が咲いていた。竹林のなかから空を見上げると、青空に1羽の鷺が大きな白い羽を広げて飛んでいる。「桜舞う 空に白鷺 竹を漕ぐ」などと竹を刈りながら1句ひねる余裕まであったのだが、なんだか腕にかゆみを感じるようになった。腕を見ると、じんましんができて赤くなっている。露出した腕が竹の葉とこすれてアレルギー反応を起こしたようだった。肌が弱いことをすっかり忘れていた。
「かゆい、かゆい」と騒いでいると、「Tシャツで作業してるからだよ」と荒木さんが笑っている。荒木さんの恰好をみると、長袖で首にはタオルを巻いて、肌の露出を最低限に抑えている。私もヤッケを着て作業することにした。ヤッケは防風性が高く、竹の葉からもしっかり守ってくれるが、こんどはあせもに悩まされることになった。
1日の作業で80本ほどの篠竹を切ることができた。1本で支柱を2本分くらい取れるから、160本ほどの支柱になるはずだ。ホームセンターで支柱が1本100円だから、1万6000円分の支柱を手に入れたことになる。ただ、薬局でじんましん用の軟膏が1500円した。

(つづく)
高松英昭(たかまつ・ひであき)
1970年生まれ。日本農業新聞を経て、2000年からフリーの写真家として活動を始める。食糧援助をテーマに内戦下のアンゴラ、インドでカースト制度に反対する不可触賤民の抗議運動、ホームレスの人々などを取材。2018年に新潟市にUターン。2023年から新潟県阿賀野市で移住者促進のための情報発信を担当する地域おこし協力隊員として活動中。
著書(写真集)に『STREET PEOPLE』(太郎次郎社エディタス)、『Documentary 写真』(共著)などがある。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)