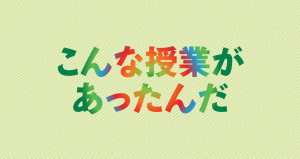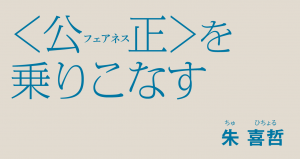きらわれ虫の真実│第2回│蚊——時差出勤のドラキュラ│谷本雄治

※冒頭以外の写真は小さくしてあります。写真をクリックすると拡大されますので、抵抗のない方はどうぞごらんください
第2回
蚊——時差出勤のドラキュラ (公開終了)
【虫の履歴書】双翅目カ科の昆虫。双翅目はハエ目とも呼ぶので、蚊なのにハエの一員ということになる。世界に三千数百種、日本だけで100種を超す蚊が知られる。人間の血を求めるのは、そのうちの約20種。病原体を媒介する蚊もいることから、衛生害虫として警戒される。
■この連載が本になりました(2022年8月5日発売、定価1800円+税)
2021年7月から全17回にわたって、じっくりと“きらわれ虫”の世界を観察してきた本連載「きらわれ虫の真実」が、本日、書籍として発売されました。大幅に書き下ろしを加えて、おなじみの「きらわれ虫」30種を紹介、楽しいコラムも盛りだくさんです。さらに、イラストレーターのコハラアキコさんによるユーモラスな虫イラストがウジャウジャ。虫だらけのこの季節、招かれざるヤツらに悩まされている人も、虫マニアも、大人も子どもも楽しめる一冊です。
谷本雄治(たにもと・ゆうじ)
プチ生物研究家・作家。1953年、名古屋市生まれ。田畑や雑木林の周辺に出没し、虫をはじめとする、てのひらサイズの身近な生きものとの対話を試みている。肩書きの「プチ」は、対象の大きさと、研究もどきをたしなむという意味から。家庭菜園ではミニトマト、ナスなどに加えて「悪魔の爪」ツノゴマの栽培に挑戦し、趣味的な〝養蚕ごっこ〟も楽しむ。おもな著書に『週末ナチュラリストのすすめ』(岩波科学ライブラリー)、『土をつくる生きものたち』(岩崎書店)、『ケンさん、イチゴの虫をこらしめる』(フレーベル館)などがある。自由研究っぽい飼育・観察をもとにした、児童向け作品も多い。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)