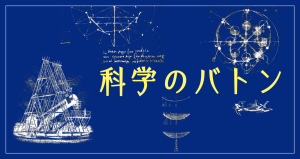他人と生きるための社会学キーワード|第12回(第2期)|子育てをめぐる「神話」──「3歳までは母の手で」?|丹治恭子
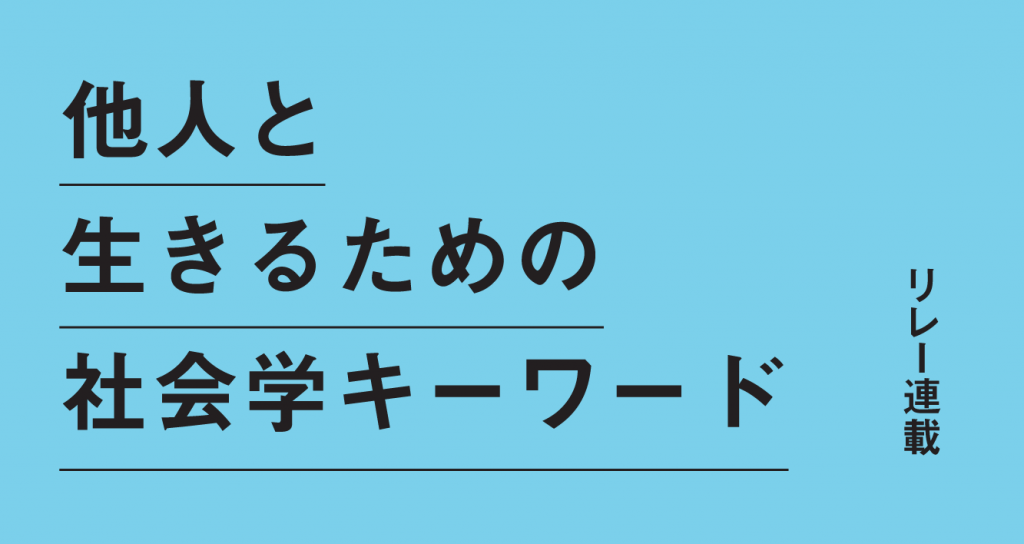
子育てをめぐる「神話」
「3歳までは母の手で」?
丹治恭子
子育てにはたくさんの「神話」が存在している。神話といっても、特定の宗教にかかわる話ではない。ある社会において「正しい」「望ましい」ものとされた子育てのあり方が、あたかも神話のように受け入れられ、広く信じられてきたのである。
その代表的なものが、女性には生まれつき母性が備わるとする母性神話、ならびに、「3歳までは母の手で」というフレーズで知られる3歳児神話である。
なお、母性とは、妊娠・出産・哺乳といった生理学的特質をもつ女性に宿るとされる、子どもを愛し、育てることのできる能力・特性のことである。母性を先天的・本能的で「自然」なものと位置づけることにより、女性が子育てを担うことを当然視する見方を基礎づけてきた。
子育てを母親のものとするこうした考え方は、サラリーマンの父親と専業主婦の母親という性別役割分業をおこなう夫婦と子どもからなる家族像(近代家族)に顕著にみられる。男性を仕事の場へ女性を私的なケアの場へと性別によってその役割を振り分ける近代家族のあり方は、産業社会を維持・発展させていくための合理的な体制とされ、日本が高度成長期を迎えた1950年代から1970年代にかけて、広く流布され定着していった。
そのなかでも、母親たちを「正しい」子育てへと追いたてていったのが、「乳幼児期の子どもには血のつながった母親の愛情が不可欠であり、母親が育児に専念しないと、子どもにとりかえしのつかない傷を残す」とする物語(のちの3歳児神話)である。この物語は、高度経済成長期に、欧米でのホスピタリズム(施設病)研究の知見とともに、「望ましい」子育てのあり方として日本に紹介された。ホスピタリズムとは、20世紀の初頭に発見された、乳児院や孤児院等の施設で暮らす子どもたちにみられる知的発達の遅れや精神発達上の問題のことである。イギリスの精神医学者ボウルビィはこのホスピタリズムの原因として、施設入所によって母親または母親代理者との継続的な愛着関係が絶たれることを挙げた。心理学や医学の研究にもとづく科学的・学術的な裏づけによって正当化された物語は、子育ての規範を示すのみならず、それを怠ると子どもに悪影響を及ぼすという脅し文句をともなう点で、母親たちをみずから進んで育児に専念する道へと進ませるものとなっていった。
しかしその後、1970年代後半に入ると、フェミニズム運動ならびにそこから生じた女性学・ジェンダー研究が、子育ての「正しい」姿のイデオロギー性を指摘し、「神話」と名づけて解体を試みていくようになる。生得的とされる性別にもとづくジェンダー構造からの解放をめざしたフェミニズムにとって、女性を母親役割に縛りつける母性規範や3歳までは産みの母親が子育てを担うべきとする物語の存在は、行く手を阻む最大の障壁のひとつであった。そのため、母性や子育てをめぐる物語のイデオロギー性を暴き、神話として説きおこす研究がさかんに取り組まれた。
たとえば、先に挙げたホスピタリズム研究においては当初、子どもが愛着関係を形成する対象として、産みの母親に限らない多様な他者が想定されていた。しかし、日本に紹介される段階では、母親不在が乳幼児の発達を阻害するという一面のみが強調されたことが、のちの検証によって詳らかにされている。また、3歳児神話の普及の過程では、「保育園に預けると子どもが自閉症になる」などの誤った説が、ホスピタリズム研究を参照して流布されたこともあったという。こうした知見からは、母性や「3歳までは母の手で」という物語が科学的な根拠の乏しい、イデオロギー性を帯びた神話であることが確認できる。そして、1998年にはこれらの見解をふまえたかたちで、厚生省(当時)が、かつて政府や行政が主体となって広めた3歳児神話について、「少なくとも合理的な根拠は認められない」との見解を『厚生白書』内で示すこととなった。
ただその一方で、2000年代以降、ジェンダー論や家族のあり方をめぐって、「バックラッシュ(揺り戻し)」と呼ばれる、懐古的な動きもみられるようになっている。その過程では、「3歳までは母の手で」という物語を再評価し、従来の性別役割分業や母親による育児にプラスの効果を見出そうとする科学的知見も散見される状況となっている。いったんは公的に「神話」として否定された子育てのあり方に回帰し、その「正しさ」を科学的に示そうとする試みからは、強いイデオロギー性を読みとることができる。
また、他国に目を向けると、スウェーデンには、子どもは1歳になるまでのあいだ、家庭内で家族によって育てられるべきとする「1歳児神話」ともいえる考え方が存在している。事実、スウェーデンは育児休業制度が充実しており、さらに育休の取得率も男女問わず高いことから、0歳児保育自体がほとんど実施されていない状況がある。0歳児保育施設の運営にかかる人件費や設備費を考慮すると、育児休業制度を整えるほうが合理的という社会政策上の判断もあるようであるが、少なくともここからは、スウェーデンにおける「望ましい」子育てのあり方が広く社会に浸透しており、そうした神話をもとにした社会制度が整えられている様子が確認できるであろう。
ここまで見てきたように、子育てをめぐる神話はさまざまなかたちで存在しており、その時代や地域の社会構造によって支えられている。したがって、私たちが子育てについて語ろうとするさいに、イデオロギーから完全に離れることは実質的には不可能である。世間に溢れるさまざまな子育て論、育児科学は多かれ少なかれイデオロギー性を帯びていると言わざるをえない。以前、本連載においてとりあげた 「子育ての社会化」もまた当然のことながら、「正しい」あり方を示すものではなく、子育てをめぐるイデオロギーのひとつである。
そうであるとすれば、私たちができるのは、「『正しい』子育ては何か」を追い求めるのではなく、そこで語られている子育て論において「『正しい』とされているものは何か」、あるいは「何を『正しい』ものと考えたがっているのか」を見極めることである。
私たちが生きる世界には、社会の違いや時代の違いはもちろん、人の数だけ子育てのやり方があるといっても過言ではない。ただその一方で子育て当事者には、さまざまな立場からくり返し「望ましい」子育てが要求される。暴力や虐待といった人権を損なうようなあり方は否定しつつも、子育てにはさまざまなやり方があるという事実を受けとめること、「望ましい」「正しい」とされた方法と異なるあり方を容易に否定しないこと。そうした姿勢こそが私たちを「正しい」子育ての呪縛から解き放ち、一人ひとりの違いにあった環境づくりを可能とするのではないだろうか。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
天野正子ほか編『新編 日本のフェミニズム5 母性』岩波書店、2009年
山口慎太郎『「家族の幸せ」の経済学──データ分析でわかった結婚、出産、子育ての真実』光文社、2019年
アンジェラ・サイニー著、東郷えりか訳『科学の女性差別とたたかう──脳科学から人類の進化史まで』作品社、2019年
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
丹治恭子(たんじ・きょうこ)
立正大学仏教学部教授。筑波大学大学院博士課程人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻修了。博士(ヒューマン・ケア科学)。専門分野:教育社会学、幼児教育・保育学、ジェンダー論。
主要著作:
『共生と希望の教育学』共著、筑波大学出版会、2011年
『ケアの始まる場所』共著、ナカニシヤ出版、2015年
『共生の社会学』共編著、太郎次郎社エディタス、2016年
『教育社会学』共著、ミネルヴァ書房、2018年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)