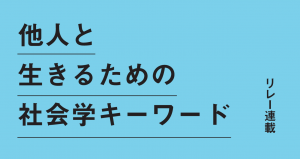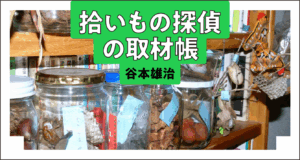保護者の疑問にヤナギサワ事務主幹が答えます。|第5回|集めた遠足代、あまったらどうするの?|栁澤靖明
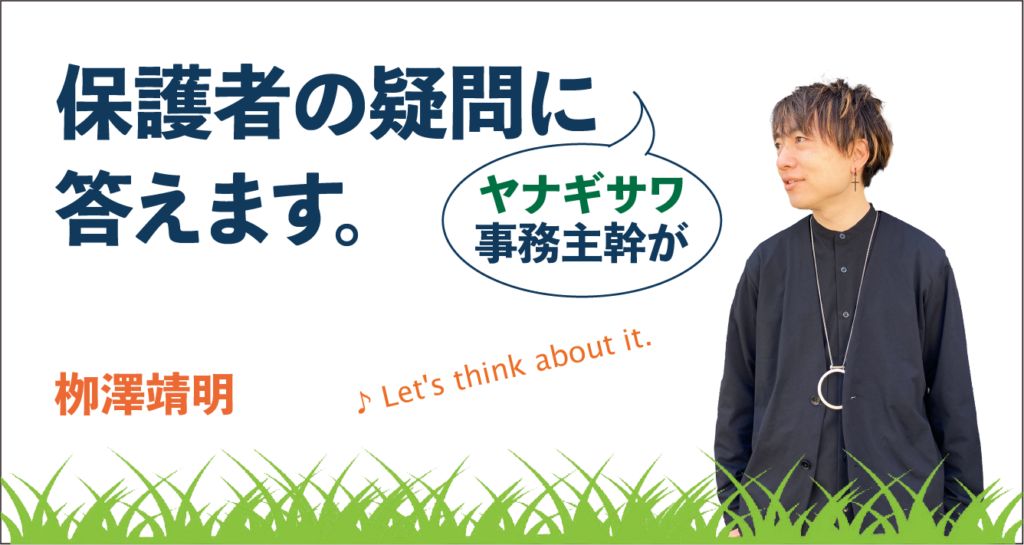
第5回
集めた遠足代、あまったらどうするの?
栁澤靖明
さぁ~明日は、たのしい遠足です。帰って準備を終わらせたら、早く寝ましょうね。あまりワクワクしすぎると眠れなくなることもあるから注意しましょう。あ、だいじなことを忘れていました。おやつは300円までですよ。バナナはおやつに含みません。では、遅れないように登校してください。さようなら~。──担任の先生みたいな導入にしてみました(笑)。
今月は遠足です。主査エディションから通算して53回目⋯⋯あ、50回記念をスルーしていたことにいまさらながら気がつきました、残念無念。それはそれで、50個超もよくネタを思いつくなぁーと自分自身に感心していますが、それだけ学校のお金って、〝不思議〟にあふれているんでしょうね。ボクの場合、寝る直前(消灯して目をつぶったあと)にネタを考えることが多いです。そのタイミングだと、思いついてもメモれないこと多く、朝になると忘れちゃいます。がんばってメモると原稿を書きたくなって目がさえちゃうことも多いので、遠足の前日にはやっちゃダメですね。
今回は、「遠足代○○円」という徴収の裏側にあるドラマ(疑問・問題・課題)を紹介していきます。
♪ Together──Let’s think about it. ♪
まず、「遠足」を定義しましょうか。コトバンクによる説明では、「学校で、運動や見学を目的として、教師の引率で行う日帰りの小旅行」「遠い所まで出かけること」とされています。まぁ、あえて検索する必要もなかったかもしれませんね。では、ルーツを確認しておきましょう。該当部分を『隠れ教育費』から転載します(太字は引用者)。
修学旅行の原点は、明治期に学制が敷かれた時期にまでさかのぼる。当時の文部大臣・森有礼は軍事教育の一環として「行軍」を推奨したのだった。この「行軍」の定義はあいまいであるが、軍装をし、背嚢・鉄砲を担いで長距離を歩き、目的地で軍事演習などをおこなうことを指し、当時はおおむね「遠足」という言葉と同様の意味とされた。泊まりの場合は「行軍」、日帰りの場合は「遠足」であったともいわれている。これが転じて、複数校で共同開催される運動会の会場へ向かうための長距離の徒歩移動のことを「遠足」と呼ぶようにもなった。すなわち、当時において、軍事演習と「運動会」、そしてそこへ向かう「行軍」あるいは「遠足」は一体的であったのだといえる。(p.211、福嶋尚子)
意外と奥深くなってきましたね。もういっちょ、学習指導要領もみておきましょう。「遠足」は、特別活動のなかに学校行事(遠足・集団宿泊的行事)として発見できます。そのねらいは「自然の中での集団宿泊活動などの平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、よりよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積むことができるようにすること」です(小学校学習指導要領)。ちなみに、中学校学習指導要領では「遠足」が「旅行」となっています(ねらいについての説明は「自然の中での集団宿泊活動などの」がなくなっているだけ)。
遠足のことがわかってきたところで、そろそろ費用面の話をしましょうか。学習指導要領は、「教育課程の基準」(学校教育法施行規則第52条:小学校)であるため、費用について定めていません。そのため、その解説【特別活動編】小学校学習指導要領解説を検索してみると「遠足」で18件ヒットしましたが、やはり直接の定めはありません。しかし、なぜか中学校のそれにだけ、「経済的な負担(⋯)などに十分配慮」(p.102)という文字がみつかります。また、1968年の文部省通知「小学校、中学校、高等学校等の遠足・修学旅行について」(10月2日:文初中第450号)という文書が紹介され、そこには「できるだけ簡素で実質的な計画をたて、実施に必要な経費をなるべく低廉にすること」と指示されています。
少し長くなりました。以上が、遠足とその費用について定めている内容です。むかしはいろいろあったけどいまは授業の一環であること、費用負担も抑えていくべき必要性がわかりました。さきの文部省通知では、「児童生徒の所持金、服装、携行品などについても保護者の負担の軽減に努め(⋯)保護者の協力を得る」とあり、「実施に必要な経費」の一部として保護者負担が想定されているようにも読めます。「携行品などについて『も』[『』:引用者]」とあるため、「実施に必要な経費」のすべてが「保護者の負担」であり、「保護者の協力を得る」とも読めます。解釈はいろいろできますが、今回は遠足の費用を保護者負担と想定し、その問題や課題に迫ります。⋯⋯と大きく出ましたが、問題や課題ってそれなりに多いので、今回は「端数問題」を扱います。

かんたんに説明すれば、遠足の総費用が100万円だったとします。参加者は、子ども190人+引率教員10人(引率者分は公費で事後精算)=200人だとすれば、ひとり5,000円ですよね。これなら端数問題は起こらず、キレイに清算できますが、そんなことはほとんどありえません。また、借り上げバスや高速代、駐車料金などといった費用は、ひとりあたり○○円という計算ではなく、参加人数で頭割りをします。
たとえば、総費用が100万円で参加者は190人の場合、5,263.157⋯⋯円となり、徴収額を5,264円に設定します。その結果、100万円に加えて「160円」という余剰が生じてしまいます。その160円(端数)をどのように扱うかという問題があります。
読者のみなさんだったらどうしますか?
160円だし、だれかがもらっちゃえばいい──さすがにそれはないですよね。
引率者10人に16円ずつ配る──それも業務上横領や信用失墜行為になりそうです。
じゃあ、子どもに還元するとして紙でも買いましょうか、「しおり印刷代」として学校がもらっちゃいましょうか、などといろいろな案が浮かびます。
前半は違法行為だし、後半も倫理的な問題になりそうです。
そこで思いついたのが、寄付ですね。慈善団体に寄付すれば、みんな納得してくれるでしょう。それが、この報道「ユニセフに27円寄付はルール違反? 練馬区教委が小学校を指導」(毎日新聞2025年5月4日)です。記事では、「区教委が定めたルールでは、余剰金は保護者に返金することになっている」とあり、それは肯定できます。続く説明に「割り切れない場合は寄付も想定されている」と書かれています。もちろん、出てしまった端数は、なんらかの対応が必要です。しかし、端数をどうするかという対症療法ではなく、あとで述べるとおり端数を出さないという原因療法が重要になります。このことについて受けた取材が、記事「識者に聞く 学校徴収金の今後は」(日本教育新聞2025年6月23日)にもなっています。
お察しのとおり、この問題は遠足以外でも起こります。人数分の色画用紙ではなくグループで数枚必要というケースや、そのグループにカラーペンを1セット用意するというケースでも端数は生じます。その解決策としては、私費ではなく公費で購入すればいいのです。公費のサイフはひとつですが、私費は子どもの人数分、(保護者の)サイフから徴収することになります。こういった端数問題からも、私費負担ではなく公費負担を増やしていくことが求められますね。
しかし、遠足ともなると莫大な総費用がかかります。そのすべてを公費負担するのが難しい自治体も多く、どうしても私費負担による遠足となってしまいます。
それでは、どう解決させるべきでしょうか。そのひとつとして、見積もり徴収方法の工夫があります。前述したように、高速代や駐車料金などは頭割りするしかありませんが、見積もりの段階から人数で割りきれる額に調整してもらうことは可能でしょう。もちろん、業者と学校ともに損得をしないボーダーラインは必要です。それは、200人規模でしたら金額にして1円~199円の範囲になります。学校から「あと199円もうけていいから端数がでない金額にしてください」というのはちがうため、あらかじめ見積りの段階で端数について相談しておくといいかなと思います。じっさいに、端数調整をした金額で請求してくる業者もあります。あとは、端数分だけ公費で支払うという方法もなくはありません。若干ですが、私費負担の軽減にもつながるでしょう。
Let’s think about it.
この問題、保護者にはどうすることもできませんよね。でも、こういった問題が生じていることはわかっていただけたと思います。この連載では、よく聞かれる保護者の疑問だけではなく、「学校にあふれる〝それ、どうなの?〟」についても、みなさまとシェアリングしていきたいと思います。
遠足だけにとどまらず、学校にあふれる端数問題は、安易な寄付に走るのではなく、公費保障の拡大に向けたひとつのきっかけととらえ、考えていくことが必要です。秋の遠足が始まる時期ですね。もし、端数処理に困っている学校がありましたら記事を活用してみてください。
栁澤靖明(やなぎさわ・やすあき)
「隠れ教育費」研究室・チーフディレクター。埼玉県の小学校と中学校に事務職員として勤務。「事務職員の仕事を事務室の外へ開き、教育社会問題の解決に教育事務領域から寄与する」をモットーに、教職員・保護者・子ども・地域、そして現代社会へ情報を発信。研究関心は、家庭の教育費負担・修学支援制度。具体的には、「教育の機会均等と無償性」「子どもの権利」「PTA活動」などを研究している。
おもな著書に『学校事務職員の実務マニュアル』(明治図書)、『学校徴収金は絶対に減らせます。』『事務だよりの教科書』(ともに学事出版)、『本当の学校事務の話をしよう』(太郎次郎社エディタス、日本教育事務学会「学術研究賞」)、共著に『隠れ教育費』(太郎次郎社エディタス、日本教育事務学会「研究奨励賞」)、『教師の自腹』(東洋館出版社)、編著に『学校事務職員の仕事大全』『学校財務がよくわかる本』(ともに学事出版)など。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)