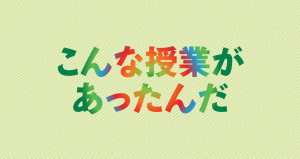拾いもの探偵の取材帳|第1回|天界からの紙巻きたばこ|谷本雄治

※一部、刺激の強い写真は小さくしてあります。写真をクリックすると拡大されるので、好奇心旺盛な方はどうぞごらんください
第1回
天界からの紙巻きたばこ
少年時代からの
拾いものグセ
子どものころはたびたび、おまわりさんの世話になった。
悪事を働いたわけではない。むしろ逆だ。大人より背が低くて顔が地面に近いぶん、落としものに目がいく。それで硬貨を拾うことが多く、学校で教わったとおり、交番に届けた。
「お金がそこに落ちていました!」
「やあ。えらいなあ」
そこまではいいのだが、手に握られた10円玉に気づくと、やさしいおまわりさんの顔はとたんに、困惑した表情に変わる。
それでも書類を出して日付や落ちていた場所などを書きこみ、控えをくれた。そのあとどうなったのか記憶にないが、おまわりさんを困らせた理由がわかるのは、ずっとあとのことである。
少年時代に身につけた硬貨拾いの技は、年をとってからも役立つ。自然界には驚くほど多くの落としものがあるが、気づくためにはちょっとしたコツが必要だからである。
夏目漱石は『草枕』に「智に働けば角が立つ」と記したが、地に目をやれば落としものに出くわす。「情に棹させば流される」とはいうものの、海に行けば浜に流れついたものが堆積している。
家を出てすぐの道端には、タマムシのはねがよく落ちている。有名な「玉虫厨子」に使われたくらい美しい拾得物ではあるが、たいていはいちどに前ばね1枚しか見つからない。それなのにもう、何枚か手元にある。
雑木林に入ってカブトムシでもいないかと目を凝らすと、たいして太くもない木の下に黒っぽいものが見えた。近づくとそれは、クワガタムシの死骸だった。
その数が、尋常ではない。木を中心にして半径1メートルほどの範囲に、大小さまざまの30匹を超すクワガタムシの頭部だけが散乱していた。
言ってみれば、バラバラ死体だ。
「なんじゃ、こりゃ!」
ほかのことばは思いつかない。
するとその謎が解きたくなり、プチ生物研究家の内なる「拾いもの探偵ゴコロ」が覚醒する。
犯人は現場にいる!
ドラマでよく聞くせりふが浮かぶ。だが、さて、どうだろう……。
頭だけ残して虫のからだを持ち去るなんて、なんとも不可解だ。1匹、2匹ならまだしも、2桁の頭部が現場にはある。犯人はまだどこかに隠れていて、つぎの獲物をねらっているかもしれない。
きょろきょろと、あたりを見まわした。
何もいない。
少し先の木の根元に、不自然に動く黒い物体が見えた。
――なんだろう?
バラバラ事件の現場を一時的に離れ、その木に近づく。
そこにいたのは、カブトムシだった。
だが、何かが欠けている。
ほんらいあるべきはずの腹の部分だ。からだはちぎれ、頭部と硬い上ばねだけが何ごともなかったかのようにそこにあり、胸部から伸びるあしが、宙をつかむようにぎこちなく動いていた。
野生の猛獣はまず、捕えた獲物の腹にかみつく。カブトムシやクワガタムシのように堅牢仕様の甲虫類の腹を同じように食べるとしたら……それはきっと、鳥だ。
いつか読んだ本には、フクロウがカブトムシを襲うと記されていた。そうはいっても現場付近でフクロウを見たことはない。声も聞かない。となると、あやしいのはカラスだ。
カラスなら何羽も見た。くちばしが細いから、ハシボソガラスが加害者である可能性が高い。その場に居合わせないかぎり断言はできないが、とりあえずの〝犯人〟が判明し、拾いもの探偵は胸をなでおろす。
そんなことのくり返しで、いろいろな落とし主を割りだしてきた。しかし、正体不明の落としものに出くわすと、答えを見つけるまでに時間のかかることも多い。
指のような、葉巻のような物体
あれは、秋のことだった。
犬でも連れて散歩をしていればサマになるのだが、あいにく、犬はきらいである。ついでに言えば、猫も好かない。そのときは近所の公園にいて、家族もいっしょだった。
「ヘンなものが落ちてるよ」
「どこ?」
「そこ」
秋といってもまだ入り口で、落ち葉が積もるほどではない。それでもあたり一帯の地面は茶色い葉に覆われ、秋はまじめに務めを果たしているようだった。
まずは、しっかり見ることだ。
得体の知れぬ物体は円筒形で、両端は半球に近い丸みを帯びていた。真ん中がふくらんだ感じだから、紡錘形といってもいいかもしれない。
「なんだか気味が悪いよ」
そのひと言が、拾いもの探偵の直感につながった。
――もしかして、ゴリラのような動物の指?
そんなことはまず、ありえない。切りおとされたゴリラの指だったら、ワイドショーの取材陣が押しよせる大事件だ。
では、ナニモノか。
頭のなかには、生きもの関係のデータバンクがある。ちょっとばかりポンコツなのが玉にきずだが、大急ぎで検索すると、何かの繭とみるのがよさそうだとの結論に至った。
とはいうものの、はじめて見る。
手にとると、かさかさ感がある。油紙の包み、沖縄で食べた丸い棒状のかりんとうを思わせる。
いやいや、太めの紙巻きたばこのようでもあるぞ、葉脈のようなものが見えるから、もしかしたら新種のミノムシかもしれない……などという推理もした。
つまり、決定打はない。
そうした場合は、とりあえず拾っておく。それも少年時代に身につけた技のひとつである。
数年後の出会い
時間は過ぎる。
そしてわが常なる習慣ではあるのだが、そのうちそんなものがあったことさえ忘れてしまった。新たな不思議ものに出会うと、それ以外はすっかり頭から消える。リセット、リセットの連続だ。
そんなある日のことだった。
といっても、ゴリラの指もどき発見から数年もたっているのだが、玄関のカナメモチの木に、巨大なイモムシが数匹現れた。数日前から地面に丸い塊があるのには気づいていたが、忙しいこともあって知らんぷりを決めこんでいた。
かりにもプチ生物研究家を自称し、虫が好きだと公言している。それなのに虫を無視するなんて、洒落にもならない。というのもイモムシ類がどうにも苦手だからだ。子どもでも平気で手にする蚕でさえ、指でつまむときにはそうとうの覚悟が求められる。
そんなぼくの前に、太さも長さも人差し指ぐらいある大きなイモムシの出現だ。イモムシというだけでオソロシイのに、三角錐をいくつも張りつけたような背中で、それぞれのてっぺんから長い毛が生えている。
こいつはイモムシなのか、それともケムシとよぶべきか。なんとも悩ましいが、全身が毛で覆われているわけではないので、イモムシの一種とみることにした。有毒種も少なくないケムシにくらべれば、安心できる。
透明感のある緑色で、側面にはオレンジ色の模様が入る。見ているうちに嫌悪感は薄らぎ、蚕よりはかわいく高級な幼虫であるかのように思えてきた。つまり、ぼくにとってはワングレード上のイモムシだ。だからといって、手でつかめるわけではない。
手元のハンドブックを開くと、正体はすぐにわかった。ヤママユガ科のオオミズアオだ。成虫なら、何度か見たことがある。
「玄関のイモムシなんだけど、オオミズアオの幼虫らしいよ」
「オオミズアオなの? もういちど、見たかったんだ」
どこでいつ見たのか、家族はその名を知っていた。
そういうことなら、カナメモチの葉ぐらい、腹いっぱい食べさせてやろう。おそらくあと数日で繭をつくり、そのなかでさなぎになる。
結びついた記憶
オオミズアオは大型の蛾で、はねを広げると10センチはある。
はねの色は、エメラルドグリーン。人間でいえば肩の部分がえんじ色で縁どりされていて、なかなかおしゃれである。後ろばねには、しっぽのような尾状突起がつく。
白い毛に覆われたからだは、もふもふ感たっぷり。大きな複眼は黒く輝き、オスの触角は、みごとなまでの櫛状だ。そんなことから、蛾なのにファンも多い。
数日後。幼虫は予想どおり、繭になった。葉の裏に茶色のかたまりがあり、それだとわかった。
家族を呼んだ。
「へえ。茶色い紙で包んだみたいだね」
「なんかさあ、葉巻に似てない?」
な、なんと!
そのひと言は、いつか見たゴリラの指もどきを思い出させた。
なんということはない。あのとき拾ったのはオオミズアオの繭の殻だったのだ。にわか探偵の実力といえば、このていどなのである。
オオミズアオは、その美しい姿から「月の女神」と称される。かつての学名にギリシャ神話の月の女神「アルテミス」の名前が使われていたからだ。
英語では「月の蛾」。月明かりの下で優雅に舞うところは、天女の羽衣のイメージにつながる。
繭を確認してしばらくしたある晩。門灯のまわりに天女が現れた。そこだけが、昼間の空の忘れもののように明るかった。
谷本雄治(たにもと・ゆうじ)
プチ生物研究家・作家。1953年、名古屋市生まれ。田畑や雑木林の周辺に出没し、虫をはじめとする、てのひらサイズの身近な生きものとの対話を試みている。肩書きの「プチ」は、対象の大きさと、研究もどきをたしなむという意味から。家庭菜園ではミニトマト、ナスなどに加えて「悪魔の爪」ツノゴマの栽培に挑戦し、趣味的な“養蚕ごっこ”も楽しむ。著書に、『雑草を攻略するための13の方法 悩み多きプチ菜園家の日々』(山と溪谷社)、『地味にスゴい! 農業をささえる生きもの図鑑』(小峰書店)、『きらわれ虫の真実 なぜ、ヤツらはやってくるのか』(太郎次郎社エディタス)など多数。自由研究っぽい飼育・観察をもとにした、児童向け作品も多い。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)