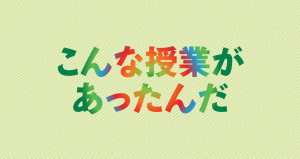アイドルとのつきあいかた│特別編│コロナ禍があぶりだしたオタクの業│ロマン優光
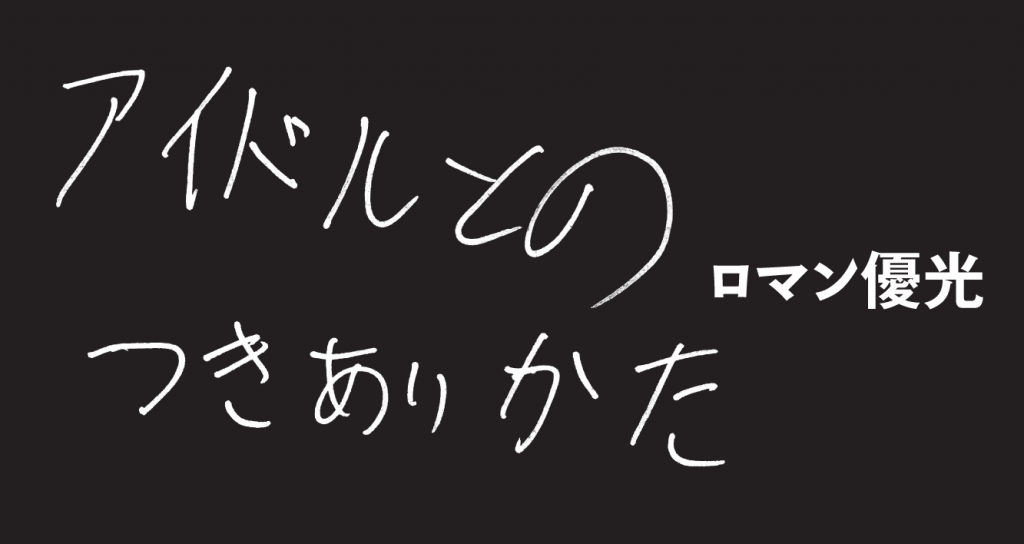
特別編
コロナ禍があぶりだしたオタクの業 (公開終了)
現場から
オタクが減った
2020年からの新型コロナの蔓延はアイドル現場の様相を大きく変えた。いや、変えたというか、第一回目の緊急事態宣言の影響で、観客を入れたライブというものが約2か月半~3か月ものあいだ、完全に失われてしまった。
・・・・・・・・・・
■この連載が本になります(2023年3月31日発売、定価1800円+税)
2021年1月から全12回にわたって、著者がアイドルオタクとして10年以上にわたり地下アイドル現場で体感してきたアイドルとオタクの悲喜こもごもを通して、地下アイドルとオタクの関係を考察してきた本連載が、2023年3月、『地下アイドルとのつきあいかた』とタイトルを変え、書籍として発売されます。大幅に書き下ろしを加えて、ちょっとマニアックな用語集も収録。これまでありそうでなかった当事者研究的「地下アイドルオタク」論にして新時代の「人間関係論」です。
ロマン優光(ろまん・ゆうこう)
1972年高知県生まれ。ソロパンクユニット「プンクボイ」で音楽デビューしたのち、友人であった掟ポルシェとともに、ニューウェイヴバンド「ロマンポルシェ。」を結成。ディレイ担当。WEBサイト「ブッチNEWS」でコラム「ロマン優光のさよなら、くまさん」を隔週連載中。
著書に『90年代サブカルの呪い』『SNSは権力に忠実なバカだらけ』『間違ったサブカルで「マウンティング」してくるすべてのクズどもに』『日本人の99.9%はバカ』(いずれもコア新書)、『音楽家残酷物語』(ひよこ書房)。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)