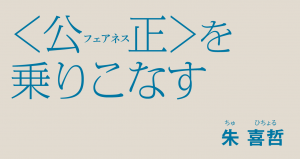他人と生きるための社会学キーワード|第7回|パーソナル・アシスタンス──『最強のふたり』から『道草』へ|麦倉泰子
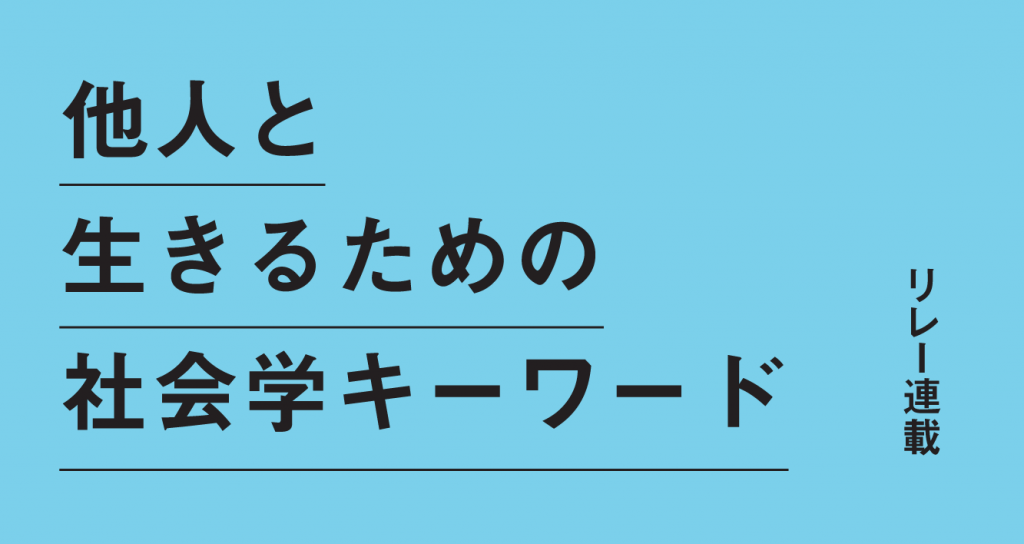
パーソナル・アシスタンス
『最強のふたり』から『道草』へ
麦倉泰子
『最強のふたり』(原題:Intouchables、2011年、フランス)という映画がある。移民の貧困層に属する若者と、頸髄損傷によって身体に重い障害のある裕福な白人の男性とが、 介助を通じて友情を育んでいくというストーリーであり、実話にもとづいて作られている。
介助者として雇われた若者は移民であり、失業中である。求人に応募したのは失業手当を得るためであるから、そもそも雇われる気がない。一方、雇用主はきわめて富裕な白人であり、専門的な知識や技術をもつ介助者を雇うことも可能だが、そうした人びとの話すタテマエ(「人に興味があるからこの仕事に応募しました」といったような)にウンザリしている。応募してきた若者の飾り気のない人柄に興味を抱き、周囲の心配をよそに自分の介助者として雇うこととする。
経済的にも、文化的にも、また社会階層の面からもまったく異なる背景をもつふたりが、 介助という行為を通じておたがいに理解を深めていく過程は、「障害者を介助する/障害者が介助される」という行為のもつイメージをことごとく覆すものであり、痛快である。
オープニングは象徴的だ。じつは物語の終盤でもあるこのシーンで、ある場所へ急ぐふたりは警察によるスピード違反の取り締まりを逃れるために「共謀」する。車の窓から声をかける警察官に対して、車いすの男性は発作を起こしたふりをし、介助者の男性は、彼が死んだらどうするのだ、と警察官を詰問するのである。責任を問われることに恐れをなした警察官は、スピード違反を見逃すどころか、パトカーで病院まで先導しようとする。おおげさな大名行列のなかから、ふたりは隙をついて逃げおおせてしまう。自由になったふたりは、カーオーディオでアース・ウインド&ファイアを大音量で流し、笑いあいながらパリの夜の街を疾走していく。
この場面が愉快であるのは、ふたりに向けられるまなざしに「障害者は弱いもの」というイメージや、「身なりのよくない移民の若者」と「裕福そうな白人の男性」という組み合わせを不審なものとしてみるというステレオタイプがあからさまに見てとれるからである。 さらに公務員の事なかれ主義が拍車をかける。ふたりはそうした既成の役割イメージの裏をかいて逃げおおせてゆく。既存の鈍重なシステムから軽やかに抜けだすさまは、さまざまな脱出劇で描かれる「バディ=相棒関係」そのものである。
この愉快さ、痛快さは、ふたりの関係性が、個別的な支援関係にもとづくものであることに由来するだろう。『最強のふたり』がもとにしているのは、富裕な個人が個別の介助者を雇用する私的な雇用関係であるが、これを公的な制度にもとづいてだれでも利用できるように制度化したものが、「パーソナル・アシスタンス」である。
パーソナル・アシスタンスとは、障害者運動のなかから生みだされてきた理念である。 個別化された支援を実現することによって、障害のある人の参加を阻むさまざまな障壁を除去し、上で述べてきたような無力化された状況を覆すことを目指すものである。スウェーデンで当事者の管理にもとづく個別支援のあり方を実践してきたアドルフ・D・ラツカはパーソナル・アシスタンスについて、援助の内容と、援助がおこなわれる関係性という2つの条件によって定義している。
援助の内容については、範囲を限定しないところにパーソナル・アシスタンスの特性があり、援助がおこなわれる関係性については、当事者による決定と管理という原則が確保されていることが必要になる。範囲を限定せず、当事者が決定する内容について、当事者の管理のもとにアシスタンス(援助)がおこなわれることによってはじめて、そこでおこなわれる実践が「パーソナル・アシスタンス」となりうる。
このようなラツカの言うパーソナル・アシスタンスという概念によって示される当事者主導の支援のあり方は、障害者運動が目指してきた目標であったといえるだろう。これらの運動の成果は、各国における差別禁止法の成立や、欧米において障害のある人がサービスの代わりに現金を受けとり、自らの介助者を雇用することを可能にするダイレクト・ペイメントの制度化として、じょじょに結実してきた。
当事者の決定という原則を敷衍して考えるならば、生活のどの領域に支援が必要か、どの領域には必要でないかという決定それ自体も、当事者によっておこなわれるべき必要があるという考えにつながるだろう。この決定が国家や公的な立場にある専門家を含む他者によっておこなわれ、本人の意思を反映しないかたちでおこなわれるならば、それは個人の幸福追求に対する不当な干渉となる。多様な意思決定を認めない意識のあり方は容易にパターナリズムとなって、個人の生活を制限する。これはパーソナルな関係性が目指すものの対極にある。
ところで、ラツカが論じるような当事者の自己決定にもとづくパーソナル・アシスタンスとは、身体に障害のある人による自己の生活の管理が想定されている。『最強のふたり』でも、介助者を雇用していた男性は頸髄損傷を負った人であった。ここで想定されている自律とは、判断能力には支障がないとみなされている人であった。この部分にも変化の兆しが見えてきている。
最近日本で公開された映画『道草』(2019年、日本)には、その変化の萌芽を読みとることができる。『道草』は知的障害のある人たちが、介助者たちと地域で自立生活を送るさまを描いたドキュメンタリーである。この自立生活がベースにしているのは、障害者総合支援法における重度訪問介護と呼ばれるサービスの類型である。
『最強のふたり』では、パーソナル・アシスタンスはいわば富裕層に限られた特権として享受されていたが、『道草』では公的なサービスの範囲内で支援がおこなわれている。支援を受けながら、緩やかに自分の意思を実現していく。こうした生活が制度として可能になってきているという点では、支援をめぐる社会意識にも「柔らかさ」を許容する幅が生まれてきていると考えることもできるのではないだろうか。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
アドルフ・D・ラツカ『スウェーデンにおける自立生活とパーソナル・アシスタンス(改訂版)』河東田博・古関ダール瑞穂訳、現代書館、1997年
寺本晃久・岡部耕典・末永弘・岩橋誠治『ズレてる支援!』生活書院、2015年
深田耕一郎『福祉と贈与──全身性障害者・新田勲と介護者たち』生活書院、2013年
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
麦倉泰子(むぎくら・やすこ)
関東学院大学社会学部教授。早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。専門分野:障害学、障害者福祉、福祉社会学。
主要著作:
『施設とは何か』生活書院、2019年
『支援の障害学に向けて』共著、現代書館、2007年
『共生と希望の教育学』共著、筑波大学出版会、2011年
『共生の社会学』共著、太郎次郎社エディタス、2016年
『パーソナルアシスタンス』共著、生活書院、2017年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)