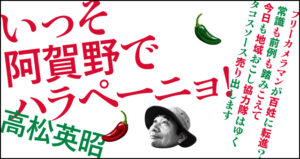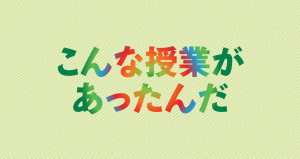他人と生きるための社会学キーワード|第13回(第4期)|見識ある市民──「自分の頭で考える」ということ|三津田悠
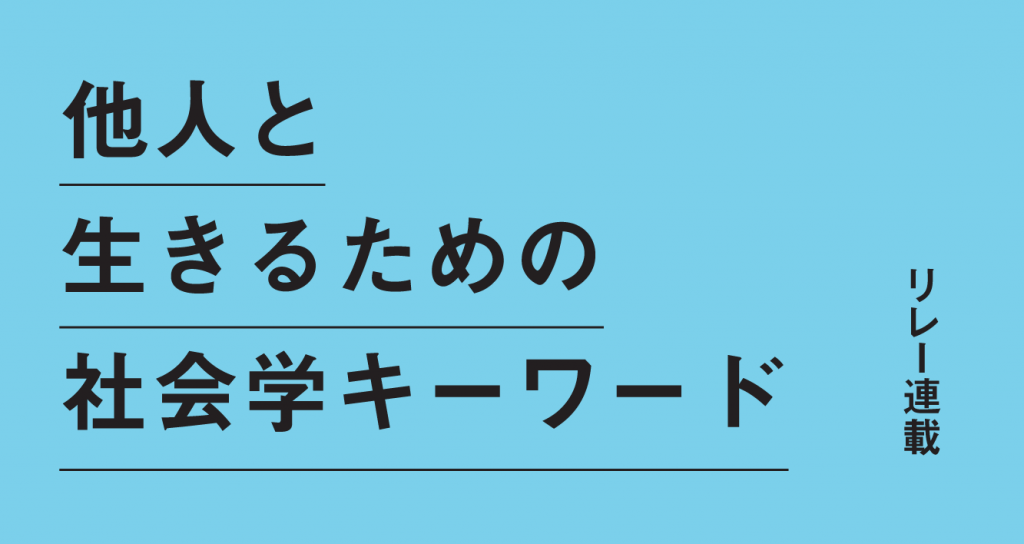
見識ある市民
「自分の頭で考える」ということ
三津田 悠
価値観が多様化し、また情報が氾濫し、何が正しく何が間違っているのかを簡単には見通せなくなった現代社会において「自分の頭で考える」ことの重要性が叫ばれることがある。社会の変化を見すえたうえで、既存の権威や伝統によって「当たりまえ」であるとされてきたことがらを批判的にとらえ、よりよい社会生活を求めて認識や実践を改めていくことは、社会のなかで素朴に生きているのみならず社会を形成する担い手でもあるわれわれにとって、ひとつの義務であるとさえ言ってよいかもしれない。
しかし他方で厄介なのは、この「自分の頭で考える」というスローガンが、よりよい社会生活を求めるための共通の基盤を根底から破壊しかねない言説──いわゆる「陰謀論」や「フェイクニュース」と呼ばれる、科学的な真理や民主主義の制度を骨抜きにしかねない言説──を産みだし、それを正当化してもいる、という事実である。政治家が言っていること、科学者が言っていること、その他の「権威」や「既得権益」をもつ連中が言っていることは、現実を把握できていないか、あるいは「真実」を覆い隠している。だからこそわれわれは目を覚まさなければならないし、そのためには「自分の頭で考える」必要がある、と。この文脈での「自分の頭で考える」ということは、既存の知識体系──とりわけ、科学の専門家が積み上げてきた知識体系──を疑い、それとは別の知識体系に依拠して世界を説明しようとすることを指すのだろう。
このような、これまで自明であるとされてきた知のありようが根底から掘り崩されていく現象は、ある意味で現代社会の宿命であるといえるかもしれない。現代社会を「リスク社会」として論じたドイツの社会学者ウルリッヒ・ベックによれば、われわれが生きている社会は「近代」という時代に特有の原理が徹底された先にある「後期近代(第二の近代)」の社会である。後期近代では、専門家がその他の人びとに対して特権的な地位を占めていた時代は終わりを迎え、どの科学技術を選択するのか、そしてその選択によって人間はどのような「リスク」に直面することになるのかがつねに問われている。近代社会において当たりまえとされてきた、科学が人びとにとって安全で確実な未来をもたらすという信念はもはや揺らいでいるのである。
しかし他方で、われわれは、日常を生きていくなかでその都度の問題解決に追われているため、つねにあらゆる知識を疑いつづけるわけにはいかない。高度に複雑に分化した現代社会では、あらゆる分野において専門的知識を身につけようとすることは不可能である。それゆえ、自分だけでは手に負えない問題を解決するためには、その問題に関連する分野の専門家に頼らざるをえない。ようするに、現代社会では、一方では専門家に対する依存が、他方で同時に専門家に対する不信が昂進しているのである。
それでは、このような時代状況のなかで「自分の頭で考える」ということは、いかなる営為でありうるのだろうか。先に整理したように、専門家がとり扱ってきた既存の知識体系を疑い、否定すること、そして、各人が納得できる、いずれかの知識体系に寄りかかることが「自分の頭で考える」ということなのだろうか。
仮にそうだとすれば、われわれは多元的で調停不可能な無数の「真実」について論じざるをえず──つまり「ポスト・トゥルース」的状況は不可避であり──したがって、よりよい社会をともに実現しようとするための共通基盤を構想することは不可能であるということになるだろう。他者との差異をもたらしている知識体系は固定化されたまま残りつづけ、したがって他者との「共生」について語ることもまた空虚な営みになってしまうだろう。
こうした見方はあまりにも悲観的であるかもしれないが、筆者はここで、知識とそれをめぐる経験について詳細に検討することをとおして「自分の頭で考える」ということの意味をとらえ直すことによって、他者との共生を模索するためのひとつの道筋を示すことを試みたい。その作業は、専門的知識に対して、それを素朴に受け容れるのとも、たんに切り捨てるのとも異なる、別様の向き合い方がありうるということを示唆することにもなるだろう。
このさいに手がかりとなるのが、現象学的社会学と呼ばれる視座から知識について論じたアルフレッド・シュッツの議論であり、とりわけ彼の「見識ある市民 well-informed citizen」という論考である。シュッツが言う「知識」とは、具体的な内容をともなった情報のことではなく、シュッツが「レリヴァンス」という概念によってとらえている知の体系のことを指している。「レリヴァンス」とは──単純化の誹りを恐れずにあえて要約してみると──世界のどの側面がどのように関連がある、重要なものとして選びだされ、そしてどのような行為を導くのかという、人びとの認識と実践とにかかわる概念である。どの対象のどの側面がレリヴァントである(関連があり、重要である)のかは、解決すべき当面の問題によって決まる(たとえば、ある物体を「赤くておいしそうなリンゴ」としてとらえるのか、あるいは「バラ科の植物」としてとらえるのかは、探究の目的次第である)。
ここではシュッツにしたがって知識を、問題とその解決の仕方、および対象の選びだし方が連なった「レリヴァンス体系」として整理しておこう。シュッツによれば、レリヴァンス体系には、個々人が自主的に選びだした結果として形成される体系がある一方で、自由裁量による選択からは生じてこない、あるがままに、前提として受けとらねばならない体系がある。われわれには後者のレリヴァンス体系それ自体を変化させる術はなく、その体系を自ら選択し、受容しながら実践を進めていくほかない。
後者のレリヴァンス体系は、他者とのやりとりのなかで、あるいは制度的な営みのなかで、認識や実践の前提として、それらの準拠枠として、手がかりとして機能している。とくに複雑化した現代社会においては、前提として受け容れねばならないレリヴァンス体系もまた高度に分化しており、その経験の仕方もまた多様化している。シュッツが「見識ある市民」の論考において試みているのは、前提として課されるレリヴァンス体系をどのように受け容れるのか、その態度を区別することであった。
高度に分化した(分業の進んだ)社会においては、成員が一様に同じ知識を備えているわけではなく、ある限られた領域に関して明晰で判明な知識をもっている「専門家」と、その領域には馴染んでおらず、明晰・判明な知識をもたない「市井の人」とを区別することができる。市井の人は、一連の思い込みや明晰でない見解をつくりあげ、素朴にそれらに頼っており、知識が当面の実践的目的にとって有用であれば十分である。また、専門的知識の詳細についても関心をもたず、当面の目的を達成するために助言が必要になったときにどの専門家に相談すればよいかを知ってさえいれば十分であると考えている。
こうした専門家と市井の人との区別は、専門家と非専門家との区別としてわれわれが馴染んでいる議論からもそう遠くないものであろう。特定の知の領域において明晰で判明な知識を身につけている度合いという観点からすれば、つねに専門家が優位であり、素人である市井の人は劣っていることになる。
ただし、シュッツの議論が興味深いのは、知のありようを自明視する心構えのあり方という観点からすれば、両者は自らがもつ知のありようを自明のものとして受け容れている点で共通していると示唆している点である。
市井の人は、知識が当面の問題解決にとって有用であるか否かが重要であるため、自分自身の認識や実践の枠組みとなっている知のありようを疑うことはない。他方で、専門家もまた、自分の分野内ですでに確立している、当該分野にとって何がレリヴァントであるのかを規定する知識の体系を自明のものとして受け容れている(がゆえに、専門家集団のなかで認められる議論を展開し、知見を積み上げていくことができる)のであり、やはり市井の人と同様に、自らに前提として課されている知識体系を疑っていないのである。
これらに対して、シュッツが第三の類型として挙げているのが「見識ある市民」である(ここで、シュッツが精確には「見識をもつことを目指している市民」のことを指すと注釈を加えている点にも注意しておきたい)。見識ある市民は、特定の分野での専門的知識をもっているわけではないし、それを目指しているわけでもない。他方で、たんなる問題解決のための知識や、明晰でない、非合理的な情念や感情に受動的に従っているわけでもない。ここで「見識がある」とは「当面の自分の目的には関わりがないけれども、少なくとも自分には間接的には関わりがあると知っているような領野において、理に適った形で基づけられた意見に到達すること」を意味しているのである。
見識ある市民は、自分の目の前には無数の準拠枠が存在することを見出し、自分の関心を選びだすことによって準拠枠を選択しなければならない。見識ある市民にとっては、あらかじめ与えられている目的もなければ、安定した避難所も存在しないのであり、自分自身が前提としている知のありようがどのような起源と源泉をもつのかについて、可能なかぎり知識を収集しなければならない。そして当面のあいだレリヴァントでないことがらでも、明日はレリヴァントなものとして考慮に入れざるをえなくなるかもしれないことを念頭に置かなければならない。つまり、市井の人びととも専門家とも異なる、自らが依ってたつ知のありようそれ自体に関心をもつ心構えこそが、見識ある市民の態度なのである。
以上で示した見識ある市民の知のあり方は、後期近代の社会において「自分の頭で考える」ことの可能性と困難とを論じる手がかりになりうるだろう。見識ある市民とはまさしく、既存の知のありようを自明視することなく、自分の知識として納得して受け容れることができるまでその知を疑いつづける態度として特徴づけられるからである。実際シュッツ自身もまた述べているように、見識ある市民にとっては、有能な専門家がだれであるのかを決定するのは自分自身であり、対立している専門家同士の意見を聞いてから自分の意見を決定するのもまた自分自身なのである。
このことを確認するだけでは「見識ある市民」の態度は結局のところ、自分自身が納得できる、すっきりとした見通しを与えてくれる知の体系に無批判にしがみつく態度と区別できないだろう。注目すべきは、この態度は、自らが前提として受け容れている、自らのレリヴァンス体系それ自体に対する関心によって特徴づけられている、という点である。この態度は、ある権威や伝統を疑うために別の権威や伝統をもちだそうとすること、あるいは、ある知識体系を否定するために別の知識体系に寄りかかろうとすること、これらの態度と等価ではない。見識ある市民の態度は、そのレリヴァンス体系があくまでも暫定的なものである──いまレリヴァントなことがらであっても、明日にはレリヴァントでなくなるかもしれない、あるいは、別のことがらがレリヴァントになるかもしれない──ということ、したがって自分の知識もまた可変的なものであるということに自覚的であること、これらのことを含意しているのである。すなわち、仮にすっきりと見通しのよい説明を与えてくれる知識体系が目の前にあったとしても、それをそのまま受け容れるのではなく、その知識体系と既存の知識体系とでは何がどのように異なるのか、その知識に依拠することによって何がレリヴァントなものとして浮かび上がってくるのか、あるいは何が切り捨てられることになるのか、これらのことをつねに吟味しようとする心構えこそが、見識ある市民の態度なのである。
われわれは、専門的知識を受け容れる場合でも、それに懐疑を向ける場合でも、あるいは別の知の体系を取り入れようとする場合でも、いずれの場合であってもなんらかのレリヴァンス体系のなかで思考し、行動している。自分自身がレリヴァンス体系という枠組みのなかで思考し、行動しているという事情に自覚的になること、そして、そのレリヴァンス体系はつねに相対的、暫定的なものであり、それ自体を反省的にとらえうること、これらのことを念頭に置いて──つまり、自らの知識をつねに反省へと開いておきながら──思考・行動することこそが「自分の頭で考える」ということである、と言えるのではないだろうか。
とはいえ、このように述べたからといって、見識ある市民であろうとすることが、自分にとって納得がいく知の体系を見つけだし、それに依拠することで満足してしまうリスクとつねに隣り合わせであることに変わりはない。しかし、次のように言えるかもしれない。仮に現代社会において多元的な知識体系を前提としたポスト・トゥルース的状況が避けがたいとしても、そしてわれわれがなんらかの知の体系を準拠枠として選択せざるをえないのだとしても、自らが依拠しているその知のありようを対象化し、改良しうる可能性がわれわれには残されているのである、と。
安定的で確固たる枠組みを求め、それに寄りかかろうとしがちなわれわれにとって、そうした反省の作業はつねに困難な課題でありつづける。しかしながら、その困難な課題のなかにこそ、他者とともに生きるための共通基盤を模索する道筋を見出しうるのである。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
アルフレッド・シュッツ『社会理論の研究』アルフレッド・シュッツ著作集第3巻、渡部光・那須壽・西原和久訳、マルジュ社、1991年
上田薫『知られざる教育──抽象への抵抗』上田薫著作集第1巻、黎明書房、1992年
岡本智周・丹治恭子編『共生の社会学──ナショナリズム、ケア、世代、社会意識』太郎次郎社エディタス、2016年
栗原亘・関水徹平・大黒屋貴稔編『知の社会学の可能性』学文社、2019年
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
三津田 悠(みつだ・ゆう)
高千穂大学人間科学部助教。専門分野:理論社会学、知識社会学、道徳の社会学、共生社会学。
主要著作:
「道徳経験と対自的批判──T. ルックマンの道徳論を手がかりに」『年報社会学論集』第37号、2024年
「日常生活批判と『道徳経験』──アルフレッド・シュッツおよび中井久夫の所論を手がかりに」『現代社会学理論研究』第17号、2023年
「日常生活世界の構造と『道徳的抵抗』──バウマン道徳論からの展開」『理論と動態』第15号、2022年
「2020年度のコロナ禍における大学での対面授業推進政策の論理と倫理──『社会問題の構築主義』の視角から」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第67輯、2022年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)