他人と生きるための社会学キーワード|第11回|高齢社会における世代間共生──生きがい観の共有による共生の可能性|和田修一
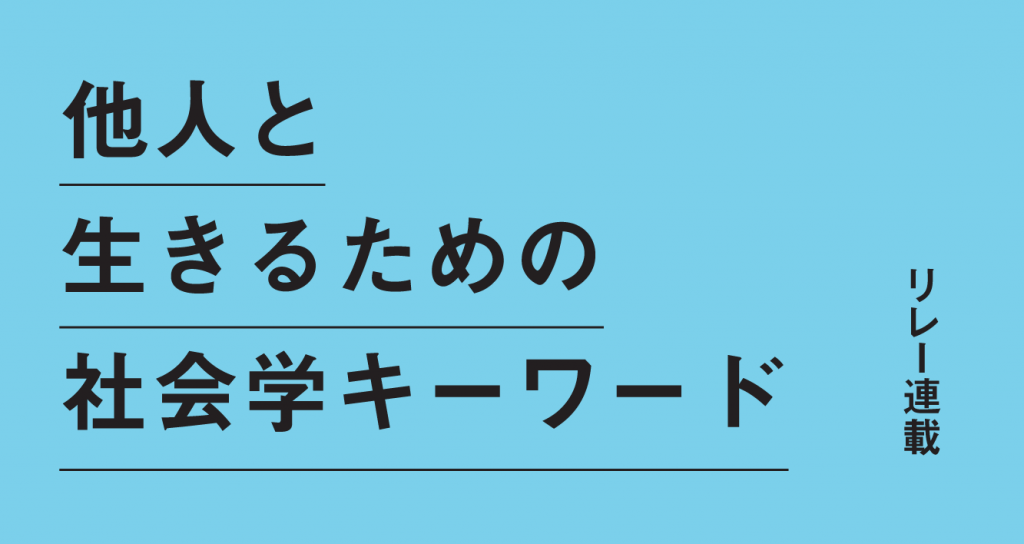
高齢社会における世代間共生
生きがい観の共有による共生の可能性
和田修一
人口構造の変化と老齢年金
わが国はいま、世界的にも前例のない規模と速度で少子高齢化という大きな人口構造の変動に直面している。こうした問題を抱えるわが国において、社会保障制度を安定的に維持していくためには、財政上の収支の健全なバランスを図ることが重要である。またそのためには、一定程度の国庫収入の拡大が必須要件である。その問題に対応する目的で諸施策が提示されている。しかし、その施策を組み立てるうえでの背景となっている考え方には問題点がないわけではない。
たとえば公的年金制度の財政的安定化を例にあげれば、個人個人が年金保険をもつことを推奨する自己責任論や勤め先の組織ごとに企業年金等の設置を求める共助論への傾斜を見てとれるのだが、こうした施策の実施に関しては国民の経済生活に一定の負担増を求めることが不可避となるであろうことは否定できない。
賦課方式による老齢年金の維持
将来にわたって国民に課せられるかもしれないこうした負担増の是非について考えるとき、わが国の年金制度では景気変動の影響を受けにくいとされる「賦課方式」が用いられていることにまず留意する必要がある。この仕組みは、政府の年金財政運営と税金による財政支援によって成り立つ仕組みであり、社会文化的な観点からすると、一種の集合主義的共助原理に則るものだともいえる。つまり、わが国の賦課方式の考え方からすれば、人びとは一定の年齢で仕事から引退したうえで、いわゆる「年金世代」の仲間入りをし、「(勤労)現役世代」の納める年金保険料を原資とした老齢年金の給付を受けることとなる、という仕組みである。この制度の下では、勤労世代の勤労所得が納税や年金保険料の納付という政府管掌の機構をとおして、その生活を支える資金として老齢世代に移転されていく仕組みとなるわけである。
年金を支える勤労世代と年金を受けとる高齢世代
この制度の下では、制度を支えるために所得の一部を提供する責務を負う側としての勤労世代とその制度によって生活が支えられる受益者側としての(高齢)年金世代のあいだには、対立した利害関係が存在する可能性がつねに存在するのだが、老後生活の経済的維持に関する自己責任論への傾斜は、利害意識の対立をより強める危険性も生みだすと思われる。
たとえば、マクロ経済スライドのような係数を用いて年金受給額の調整をおこない、現役世代への過重な負担を回避するとされているのであるが、高齢者が受けとる年金の額と現役世代が納める保険料のあいだでバランスがとれているか否かを客観的に(あるいは、社会正義に準じて)判定する基準はかならずしも存在しない。とくに、所得(フロー)に関する調整は仮に妥当であったとしても、資産(ストック)に関しては高齢者のほうがより大きな額を所有する傾向にあることは変えようがないであろうから、現在時点での生活水準の視点で両者の経済環境を均衡化しようとするならば、両者に不満の残ることはおおいにありうるだろう。
客観的な判定基準が存在しない場合には、政治的判断から両者の生活水準を均衡化すると想定される施策が決定されることになるが、大きな人口を占めるようになった高齢世代により有利な方向で決まりやすい可能性があるとする主張も(「シルバー民主主義」)、看過することはできないだろう。
勤労世代と高齢世代の相互依存性は経済原理だけでは完結しない
仮に将来の経済事情がより厳しくなるとすると、わが国の年金制度に対する将来の現役世代の眼差しはより冷ややかになるかもしれないが、しかし一方で、勤労現役世代がその中壮年期から自らの努力で老年期の経済生活について備えるという自己責任の考え方もけっして容易なものではないだろう。しかも、勤労世代と高齢世代の関係性は経済原理だけでわりきれるという性格のものではないという事情も存在する。年金世代と現役世代の関係は(家族メタファーからすれば)親あるいは祖父母にあたる世代と子どもあるいは孫の世代の関係でもあり、高齢者の生活は、子や孫の世代である現役世代が(直接的にしろ、間接的にしろ)支えざるをえないという現実が存在するのである。そしてまた、今日の現役世代もまた明日の年金世代となる運命にある。
両世代の扶養関係性はかつて、家族制度の下での血縁関係的互酬関係のなかで完結していたのであるが、今日の福祉社会の理念下では、その関係性を世代間の心理的親和性ならびに規範的互酬性という理念という、より抽象的な文脈のなかで実現していかざるをえないのである。ということは、両世代のあいだで形成される関係性を共生関係論の視点から考察するためには、所得移転の供給側とその受けとり側という経済的利害関係の次元と、親・子あるいは祖父母・孫関係という家族メタファーに起原を有する理念的・規範的家族関係の次元の、両者が織りなすアンビバレントな二元的認識構造を有する関係性であるとの前提から出発し、その二元的認識構造のあいだにいかに調和性を醸すかという議論とならざるをえないのである。
経済制度の外で生じる経済財の移転
以上のことからすれば、福祉社会における年金制度の下での世代関係を共生社会論の視点から論じるさいには、制度を支える側と受益者側のあいだの経済的利害関係としてだけでとらえることも、また家族メタファーからする心情的・理念的関係がすべてに優越する関係として強調することも、それぞれを単独に論じることからは世代間の共生条件を導くうえでは不十分なのである。
ということは、「理念と利害」という社会関係の二元的構造理解の視点からとらえることが必須となる、ということである。ということは、世代間の共生要件を求めることは、年金制度における受益世代とその制度を支える勤労世代のあいだの経済的利害関係を互酬的な利害関係であると認識させる非経済的理念を導出する、ということである。こうした社会関係の二元的構造がもたらす二元的アンビバランスをあらたな視点で再解釈せざるをえない状況の発生することは、年金制度をめぐる世代関係以外にも、現代社会ではけっして稀なことでないのである。
経済財を非経済的理念によって動かす
たとえば、経済的互酬性規範が強く働くわれわれの市民社会においても、経済財の移転をうながす要因が(たとえば、金銭のような)同価値の反対給付を前提とするばかりではなく、ある特定の関係性形成が起因となって経済財が移転する場合のあることをわれわれは知っている。
すなわち、主体Aが主体Bとある特定の関係性(社会的互酬関係)が形成されたとき、その関係性が水路となって(Bからの直接的な経済的反対給付はなくとも)AからBへの経済財の移転が成立する場合がしばしば存在する──ただしここでは、暴力的力による経済財の移転は視野の外にある。経済財の一方向的移転と見えるこの現象をうながす要因は、あたかも社会関係が経済資本のような働きをすることから、「社会関係資本」と呼ばれている。この観点からすると、現役世代の獲得した所得を非就労世代の生活を支える年金資金にあてる賦課方式は、勤労世代から年金世代への経済財の移転をうながすある種の社会関係資本を背景にしているといえるだろう。そして、わが国の年金制度を成り立たせる社会関係資本を導く価値理念としては、勤労世代と年金世代の関係性を子と親あるいは孫と祖父母のあいだの関係性によって象徴化する家族メタファーが用いられてきたことも周知である。
生きがい追求理念が世代間共生を促進する理念となる
ただし、経済的な互酬性が大きなウェイトを占めていた世代間関係の認識様式は、戦後の社会保障制度の進展と家族観の歴史的変容のなかで、その影響力を失いつつあるといってよいだろう。たとえば、個人主義化という社会的価値の一般化という近代の成熟という文脈のなかで、従来わが国の家族に期待されてきた伝統的社会的機能と家族関係のあるべき姿というものも変容しつつあるといえるだろう。わが国の社会は今、伝統的な家族関係意識の歴史的変容のなかで、高齢者世代と現役勤労世代のあいだの関係性を損得勘定が中性化された共生関係として安定化させる理念を構築すべき状況に直面しているのではないだろうか。
この問題を考えるうえでのヒントのひとつは、社会関係資本による経済財の移転というアイデアを適用することだと考えるのである。たとえば、勤労世代の生活スタイルを多様化するという趣旨で今日喧伝されている「働き方改革」の理念がひとつの手がかりを与えてくれるのではないだろうか。というのは、現役世代の仕事を「生きがい追求の道」という次元で考えることがその理念の本質であるならば、高齢者がその追求をするうえでの社会関係資本となることによって、ふたつの世代のあいだに互酬的関係性が成立しうると想定されるからである。従来の社会で家族関係のなかで高齢者が提供してきた若者世代の生活を支えるサービスを、新たに社会関係資本としての高齢者役割に負ってもらうということである。
ただし、この認識転換が成立するためには、高齢者の側に社会関係資本役割を主体的に遂行してもらうことが必須となるが、そのためのひとつの手立てとして、その役割遂行が高齢期の生きがいとなることがポイントなのである。この点に関しては、わが国の文化に根づいてきた生きがいという価値概念においては、その概念がたんに個人の満足感の充足を強調するばかりではなく、「生きてある甲斐[かい:効験ということ]」という側面からも認識されてきたという特性を強調しておきたいのである。そこでは公益への貢献が人生における達成感と重なりあうことによって人生への充足感が実現されると主張されてきたのである。その結果、個人の生きがい追求が他者の生きがい追求と重なり、社会のなかで生きがい追求への共感を共有できる状況が生まれると想定されるのである。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
神谷美恵子『生きがいについて』みすず書房、2004年
和田修一「世代間経済格差と世代間共生」岡本智周・丹治恭子編著『共生の社会学』、太郎次郎社エディタス、2016年
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
和田修一(わだ・しゅういち)
早稲田大学名誉教授。早稲田大学文学部卒業、東京教育大学大学院文学研究科博士課程中退。国立精神衛生研究所研究員・主任研究官・室長をへて早稲田大学文学部助教授・教授(改組により文学学術院教授)。2018年定年退職。専門分野:老年社会学、文化的近代化論。
主要著作:
“The Status and Images of the Elderly in Japan: Understanding the Paternalistic Ideology” in M. Featherstone and A. Wernick (eds.) Images of Aging: Cultural Presentation of Later Life. 1995, Routledge, London.
『生きがいの社会学――高齢社会における幸福とは何か』共編著、弘文堂、2001年
「映画『生きる』から考える老年期の生きがい」『新鐘』11、早稲田大学、2008年
『共生の社会学』共著、太郎次郎社エディタス、2016年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)


