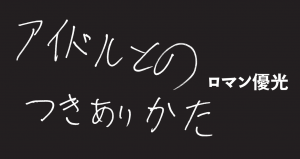こんな授業があったんだ│第8回│ヒロシマへの修学旅行〈前編〉│ 小島靖子+小福田文男

ヒロシマへの修学旅行
被爆の街・ヒロシマを学ぶ〈前編〉
小島靖子+小福田史男
(1984年・八王子養護学校の実践から)
被爆の街・ヒロシマを学ぶ〈前編〉
小島靖子+小福田史男
(1984年・八王子養護学校の実践から)
ヒロシマを問い返しながら
高等部の生徒がはじめてヒロシマに修学旅行に行ったのは1977年の10月だから、ヒロシマ行きはことし(1984年)で8年目になる。このとき以来、高等部の修学旅行は従来の観光を主とした旅行から、人間の生き方を深く学ぶ原爆学習を中心とした旅行に変わった。
当時、高等部3年生の修学旅行の候補地は、父母や生徒たちの希望を聞きながら選定していたが、阿蘇を中心とする九州地方が最有力候補地として残った。「修学旅行だからできるだけ遠くへ行ってみたい、行かせたい。阿蘇の雄大な大自然にふれさせたい」というのが、そのおもな理由であった。しかし、いざ実施計画をたててみると、飛行機を使わなければ修学旅行の規定時間数を超えてしまうとか、出張旅費もたりないとかの理由で、その計画は流れてしまった。
そこで、第二の候補地としてヒロシマを中心とする瀬戸内地方が浮かびあがった。ヒロシマに修学旅行にいった都内の中学校の実践は聞き知ってはいたが、養護学校での実践は聞いたことがなかったので、生徒たちがどれほど原爆問題に関心を示すかは未知で、取り組むのに不安だった。しかも、修学旅行にはお楽しみ旅行としての性格があっただけに、そこに原爆のような深刻な問題を持ちこむことはややためらわれた。しかし、第二次世界大戦後、大きく生まれ変わった日本の社会に生きる生徒たちに、戦争のこと、とりわけ第二次世界大戦を特徴づける原爆投下という歴史的事実を学ばせることなく、社会に送りだしてよいものだろうかとも思いはじめた。まして、核問題は、こんごの人類の生存にもかかわる重要な現代の課題として新聞やテレビでもしばしば報道されている。それを高等部の生徒に教えて卒業させたい。そう思うようになった。むしろヒロシマに目的地を定めるまで戦争や核の問題をすどおりしてきたことを反省させられた。当初は学習半分、観光半分の気持ちが教師側にもあったが、こうしてヒロシマ被爆という重大な歴史的事実をまえにして、しだいにその学習に焦点を定めていった。
この学習は、まず歴史の学習からという従来のやり方ではなく、いきなり被爆のようすを具象化した「原爆の図」や記録写真に出会わせることからはじまった。ことばでうまく表現できない生徒たちも、それらを熱心に凝視したり、ショックの叫び声をあげて目をそむけたりした。それらをとおして「ひどい」「かわいそう」「どうしておかあさんや赤ちゃんまで殺すのか」などと感情のこもった声もあがってきた。しかし、なかには絵や写真を見ただけでは「人間がそんなに恐ろしいことをするなんて信じられない」というものも出てきた。そこで実際にヒロシマに行って、原爆ドームやさまざまな展示物を見たり、心身に傷を負った被爆者に話を聞いたりして、それらが事実であることを確かめあった。
『原爆の子』の手記、峠三吉の詩、中国侵略に参加させられた日本兵士の手記「放火」などの読みきかせは国語の時間に、「原爆の図」の制作は美術の時間に行なった。
そうした学習をつづけるなかで、生徒たちは「原爆とはなんだったのか」「なぜ戦争をしなければならなかったのか。どうすれば防げるのか」「その後、被爆者はどのように生きてきたのか」ということをもっと知りたい、もっとよく考えなければならないと思うようになっていった。また、自分たちが学んだことを後輩や家族にも伝えるために、文化祭で発表したり、卒業制作に被爆についての共同画を制作したいと申しでたりする生徒たちもでてきた。
こうして、当初、教師が計画した総合的学習の内容を生徒たちははるかに超えて発展させていった。生徒たちは、戦争・被爆という過酷な歴史的事実を突きつけられてたじたじとなったり、極限状況のなかでも、なお人間として生きぬこうとする姿に感動したり、「被爆者差別」に「障害者差別」を重ねあわせ、「障害者」として生きる自分の問題としてとらえたりする生徒も生まれてきた。
これまでの実践をふりかえってみると、教師自身がヒロシマを問いかえすことによって生徒も問いかえし、また、さらに生徒が鋭く考えることによって、逆に教師が触発される。このくりかえしのなかで、あらためてこの学習がもつテーマの重要性に気づかされ、年々、学習が深まってきているように思える。
こうして総合的学習として取り組むということは、たんに第二次世界大戦にかんする歴史上の知識や原爆の性能にかんする科学的知識を寄せ集めればよいというのではない。また、教科ごとに分担を決めて各分野の学習をただ進めればよいということでもない。むしろ、「自分たちは、この社会のなかでどう生きていったらよいか」という課題に集約されるかたちで学習が展開されなくてはならないのではないだろうか。学んだことが響きあい、影響しあい、深められあって、ひとつの世界観として形成されていったように思われる。
そうした意味で、この総合的学習は、生き方を学びあう授業といえるかもしれない。遠山啓さんのことばを借りれば、教科を「学」の授業だとしたら、これは「観」の授業とでもよんだらいいのだろうか。また、どんな子どもでも参加でき、内容をどこまでも深め、発展させることができるという点でも、子どもたちを能力差で分断している現在の学校教育全体に、重要な示唆を与えるものではないだろうか、と私たちは考えている。(中略)
被爆の記録に衝撃を受ける
1984年9月18日、いよいよヒロシマに向かう。ヒロシマへの8度目の修学旅行である。この日のヒロシマは、前日までの曇天とはうって変わって、39年まえの8月6日の朝と同様、澄んだ青空だった。広島駅から路面電車に乗って平和公園へ。爆心地の相生橋に近づくと、「何橋かな」という問いに、「おいのり橋」と言って手をあわせる由里枝ちゃん。心さわぐ胸をおさえながら原爆ドームのまえに立つ。目に見えて風化していくドームを永久保存するのはなぜか。こうして平和公園での第一歩がはじまった。
相生橋のたもとから、「39年まえは、ここは死体でいっぱいだったんだよ」と、生徒たちと元安川を見おろすと、川辺にカニが動いている。あのカニが死体を食ったという。「39年まえの8月6日のいまごろ(午前10時をまわったころ)、このあたりは生きている人はだあれもいない焼け野原だったんだよ」と話しながら川岸を歩く。公園のなかは、何千羽というハト、ハト、ハト。観光バスでドッと来ては、バスガイドさんに案内されて歩く高校生たち。引率の教師は、生徒たちがはみださないかと、そんなことばかり気にしているようす……。
◉―資料館を見学して
4、5人ずつわかれて資料館にはいる。やはり強烈な印象は、赤あかと燃えあがる火を背景に、被爆直後の姿を表わしたろう人形だった。生徒たちのほとんどがこのコーナーにいちばんショックを受けたようで、いつまでもいつまでも見いっていた。
「あちいよー」「いたいよー」と思わずつぶやいていた麻里さん。その晩の発表会のときにも「あの人、あちいよー、言ってたの」と言っていた。人形であったにもかかわらず語りかけているように思えたのだろう。栗原君は、焼けた手をまえにたらし、ぼうぜんと歩いている姿を「おばあさんになった」と表現し、腰を曲げて歩きながら「水、水」と言う。「ゆうれい、おばけ」という生徒がいて、「あれは人間が原爆にやられて、ああなったの」と一生懸命に説得する生徒が出てくる一幕もあった。髪の毛が、熱と爆風によって舞いあがったホコリでモジャモジャに逆立ったようになっていたり、手の皮がむけてたれさがり、全身が赤むけて血が出ていたりする。コトバで表現することのむずかしい八木さんなどは、これらのようすを手真似でやってみせる。
アッちゃん、俊哉くんは、資料館の入り口まできげんよく歩いていたのに、資料館の雰囲気に圧倒されてか、なかにはいりたがらず、アッちゃんはついに廊下に出てしまった。むりやり見させられた俊哉くんは、ところどころにある明かりとりの窓にへばりついて、ハトの飛んでいる明るい外をながめていた。それは、自分の気持ちを表現することのむずかしいふたりが、「原爆はいやだよ。平和がいいよ」ということを、こういうかたちで表現したのだろうと思わせる場面であった。
また、資料館の中央あたりに展示されている焼けこげた子どもたちの洋服やはきものなどを見て、だまって涙を流している子どももいた。
廃墟と化し、どこまでも平らになってしまったように思わせる街の写真。越沼くんは、そのまえでジッと見入っていた。修学旅行まえ、ヒロシマはいまでも当時のままだろうという思いで恐くなってしまい、「オレ、ヒロシマ行かねえよ」と言っていた彼には、「街がなくなった」ことが、やはりいちばん気になるところだったのだろう。こわれてしまった街を見ている彼に、「街がなくなったんだね」と声をかけると、彼は「はやく戦争がなくなんないかなあ」とつぶやいた。となりでそれを聞いていた何人かから、すかさず「そうだよ」「なあ」と声があがる。自分たちがうまく表現できなかったことを、越沼くんが代弁してくれたという感じである。
◉―記念館と原爆碑の見学
つづいて、資料館のとなりにある記念館にはいった。記念館では記録映画「ヒロシマ」をみた。瀕死の子どもが治療を受けながら「おかあさん、おかあさん」と呼びつづける姿に生徒も私たちも涙した。自分では涙を流さない和夫くんも、みんなが涙を流しているような場面では、まわりを見まわしている。「あの先生、泣くだろう。あの人も泣くだろう」と思うのだろうか。それが彼の感動の表現なのだ。
記念館には、広島市民が当時のようすを描いた原爆の絵がたくさん飾られていた。その1枚1枚の絵にさまざまな怒りや思いや願いがこめられていた。絵のすきな野山くんは、「ああ、これはやけどをした人が、あついあついって川にはいったところだ」「みんなあつかったろうね」といいながら、ていねいに見つづけていた。
倒れた家の柱にはさまれて助けだせない赤ん坊が焼け死ぬのを、目のまえで見ていなくてはならなかった母親の姿を描いた絵に、何人もの生徒が涙していた。資料館・記念館の資料や記録の与えた衝撃は想像以上のものであったように思う。
そのあと、公園のなかにあるたくさんの原爆碑を見てまわった。〝嵐のなかの母子像〟のまえで、「おかあさん、あかちゃんおもたいよ。ふたり。よいしょって、がんばったよ」と富士子はつぶやいた。ひとりの子を胸にだき、もうひとりの子どもを背中に背負おうとしている母親をみて感動したのだろう。この母子像のまえで、和子さんは教師の説明にあわせるように「原爆許すまじ」を口ずさみはじめた。それにあわせてみんなも歌いだす。〝原爆の子の像〟のまえでは、みんなで折った千羽鶴を「原爆許すまじ」を歌いながらささげた。
明美さんや洋子さんは感激のあまり声をだして泣きだした。それをみていた友だちも、もらい泣きしたようである。また、宏之くんは、みんなが泣いているのをみて、佐々木貞子さんが原爆病で入院しながら死んだという話を思いだし、「くやしいよ。病院の先生をなぐりたいよ」という。その当時もいまも、医者もどう治してよいかわからないという話をすると、「ぼくは、アメリカの兵隊さんをなぐりたい」と言いだした。
峠三吉の詩碑では、みんな、その詩を口ずさみはじめた。
ちちをかえせ ははをかえせ
としよりをかえせ こどもをかえせ
わたしをかえせ わたしにつながるにんげんをかえせ
にんげんの にんげんのよのあるかぎり
くずれぬへいわを
へいわをかえせ
いつもあまり話さない石川さんが、ほかの友だちや私たち教師が「ちちを」というと、続きをすぐに口ずさむ。おぼえたい一心で、宿舎に帰ってから部屋でくり返し練習している生徒もいた。ほとんどの生徒がその晩のうちに口ずさめるようになってしまった。「わたしは生きているのに、わたしをかえせって、どういうことかなあー」「わたしにつながる人間って、だれのことかなあー」とつぶやいていたのは実くん。(学校にもどってから、ゆっくりこの詩の学習をすることにした。)
学徒動員中に亡くなった人たちの名まえがきざまれている碑もほうぼうにあった。少し離れた川むこうに、韓国人原爆犠牲者慰霊碑がある。そこにいってみた。「どうして、ひとつだけ、こっちにあるの? みんな公園のなかにあるのに」と不思議そうにたずねていた生徒たち。
夕やみせまるころ、心さわぐ胸をおさえて、ふたたび原爆ドームのまえに立つ。「どうしてこんなこわれた建物を残しておくんだろうね」と問うてみた。きょう一日の衝撃と疲れにみんな押し黙っていたが、木下くんがぽつんと「あれば、みんながみる!」といった。
はじめて語った被差別の悩み
◉―被爆者の体験に触発されて
1978年、「被爆の街・ヒロシマ」に取り組みはじめてまもない2年目のヒロシマへの修学旅行のときのことだ。資料館・記念館の見学を終えたその日の夕方、私たちは宿泊していたホテルの部屋で、被爆体験者である下原さん(被爆当時、中学生で、学徒動員中であった。いまは広島の小学校で教師をしている)の話を聞いた。この下原さんとの話しあいのなかで、生徒たちはそれまで私たちにも語ってくれなかった「被差別」の思いをはじめて表わしたのだ。
下原さんが、「被爆者は、自分が原爆を受けたことをかくそうとする。就職させてもらえない。結婚させてもらえない。差別されるからかくしておきたい。私にもそういう気持ちがある。でも、原爆がどうして落とされたかを考えたら、日本が戦争をおこしたからで、日本にむりやり連れてこられて被爆した朝鮮人もいる。だまっていたら、また日本がこのような戦争をするかもしれない。二度とこういう戦争をおこさないように、私は原爆のことを話す」といった内容の話をしたときのことである。
その場の司会をやっていた担任が、「なぜ話したくないのに話してくれたんだろうか」という質問につづけて、〝話したくない〟という気持ちの重さに気づいてほしいと思ったのであろうか、思いきったようすで、「ちょっと話がちがうんだけどさ。みんなは八王子養護学校にきているよね。八王子養護学校にきていることをだれにでも言える人?」と質問をかさねた。
養護学校に通っていることを知られたくないために、毎日、遅刻してくる生徒や、「養護学校に通っている」とすぐわかってしまうので、「重度」の友だちの家に行くことをいやがったりする生徒もいる。推測するに、被差別の思いに悩んでいる生徒は多くいる。
差別の問題は、ホーム・ルームでもたびたび取りあげてきたのだが、だれも自分の思いをすなおに、率直には語らない。遅刻をする生徒も、けっしてそのほんとうの理由を語ろうとしない。「おかあさんが寝坊した」とか、「朝飯ができてなかった」とかとべつのささいな理由を語るだけだった。
いままで、そんなときのホーム・ルームは、私たちにも、この課題をどう受けとめ、生徒たちと、どう追求していったらよいのかわからず、あるいはふれないほうが……といった迷いや不安もあり、そうした教師の気持ちと生徒たちの語れない思いとが共鳴しあうのか、沈黙のなかで、いつも的を射ないまま終わってしまっていた。
しかし、このときは、この「養護学校に通っていることを語れるかどうか」という質問に、生徒たちがまた沈黙するのではないかといった私たちの不安をよそに、生徒たちの何人かが「言えない。恥ずかしい」と声をあげた。その声にひきつづき、宏くんが「新幹線のなかで、どこの学校に行っているんですかって食堂の女の人がきいたわけ。だから、八王子高校っていった。そうすると、そうですか、ということに……。養護というと、そういう〝身体障害者〟は身体がこうなったり……。むこうにバカだなと思われてしまう。だから、いいづらいわけ。バカにされるからいわないわけ。ほかの人もそういう気持ちになることある?」と語ると、「おなじ」と呼応する声があがった。「ぼくもいやだ。学校のバッジをつけるような洋服は着たくない」と、敏浩が発言した。
◉―被爆者も障害者もおなじ「被差別者」だ
下原さんが、そういうみんなの気持ちにこたえて、「おなじというか、原爆を受けた人と似ているでしょ。言ったら差別される、きらわれる。きらわれるけど、黙っておったらだめなのでしょ。原爆を受けていることは何も悪いことじゃない。みんなの話をきいていると、ほんとうに自分に似ているように思う。絶対にはずかしいことじゃないと思う。わかってもらうためには時間がかかるけど、がんばろうね」と語りかけると、生徒たちも「似ているような気がする」とすぐに共鳴する。
それを機に、司会が「どんなところが似ているのかな」ともう一歩ふみこんでいこうとするが、生徒たちはまだつぎつぎに「養護学校」と言えない気持ちを語りつづける。いつも明るく楽天的で、そんなこと考えたこともないのでは、と私たちが考えていた茂子や智美までもが「言えない」という。
いっしょに話しあいを聞いていた被爆二世である山田さんが、せつせつとつぎのような話をしてくれた。
「みんなに言いたいんですけど、被爆二世は〝結婚してはならない〟というようなね、そんなことが一部でいわれている。じゃあ、しないほうがいいかといったら、そんなことはないと思うんですね。やっぱり、人間はみんな平等なんだし、それぞれ自分の生き方を自分で決める必要があるし。私たちは、そういう〝結婚しないほうがいい〟とか〝子どもを生まないほうがいい〟とかいう差別ね。人間がほんとうにだれでもおなじように生きるんじゃなくて、何か生きていてはいけないようなね。ぼくたちが生きて存在すること、世の中に生きていることが、何か悪いように思われている社会はまちがっていると思うし。
で、ほんとうは、そういう社会じゃなくて、みんなおなじように生きるためには、〝自分たちの親は被爆している。放射能の影響があるかもしれない〟──そういうことを隠して黙っているんじゃなくて……、そんなのはまちがっている。自分たちは被爆した親をもつけれど、やっぱり人間としてうしろ指さされることはひとつもない。だから、〝結婚しないほうがいい〟〝子どもは生まないほうがいい〟というような、人間を人間としてあつかわない社会だったら、そういう社会に負けないで、立派に生きていこうと思うわけ。そういう点で、みんなと共通した点があると思うし、そういうことについて、みんなもがんばってもらいたいわけ」
司会のほうで、「山田さんも、山田さんの気持ちときみたちの気持ちとは似ているというふうにいったし、さっき、下原先生も自分のことときみたちとは似ているといったけど、きみたちもなんとなく似ているかもしれないと感じだしたね。なにが似ているのかな。これからもう少し考えてみようね」とまとめて、話しあいを終えた。
このとき、生徒たちが発した被差別の思いは、これからもずっとひきつづく大きな課題として残された。
◉―つきつけられた課題
この修学旅行のときの生徒たちの姿は、私たちにいろいろな問いを投げかけた。そのひとつは、「被爆の街・ヒロシマ」を学習することは、「障害者」としてどう生きるのかという課題に真正面から取り組むことになっていくのだということである。こんご、この単元を組むとき、このことをもっとも重要な点として考えなければならないと思った。
もうひとつは、私たち教師にとっての課題である。差別の悩みを、生徒たちは被爆者である下原さんとの関係のなかではじめて表現しはじめた。3年間もつきあってきている私たちにも語ってくれなかった心の内側を、下原さんには語った。それは、下原さんが自分たちと近い存在であることを生徒たちは、直観的に感じたからではないだろうか。私たちは、この差別の問題を、重要な課題であると感じてきていたにもかかわらず、私たちの存在が、まだまだ生徒たちとのあいだに溝をつくっていることに気づかされた。
また、差別の課題を追求しなければと考えつつも、「差別」の実態をみつめさせ、それへの考えを表現させたうえで、私たちに何ができるのだろうか、といった不安もあり、気づくまでそっとしておいたほうがよいのでは、といった思いもないわけではなかった。が、このときの生徒たちの姿は、自分たちの悩みにふれ、共感して語りあえる関係を望んでいたかのように思われた。私たちが変わっていくことによって、日常的にも生徒たちが自分の心を解放し、被差別の思いを表現してくれるような、そんな生徒との関係を創りだし、この課題を追求しつづけなければならないことをつくづく感じさせられた。(後編に続く)
出典:小島靖子・小福田史男(編著)『ものづくりとヒロシマの授業』1985年、太郎次郎社
八王子養護学校の実践を伝える本
◎ 遠山啓 編『歩きはじめの算数』国土社、1972年
◎ 小島靖子・ 小福田史男 編『八王子養護学校の思想と実践』明治図書出版、1984年
◎ 鈴木瑞穂『子ども美術館17:絵がかけたよ 養護学校の子どもたち』ポプラ社、1983年
◎ 加藤茂男『子ども美術館18:ぼくらは生きたい 原爆の絵をかく』同前
◎ 小島靖子・ 小福田史男 編著『ものづくりとヒロシマの授業』太郎次郎社、1985年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)