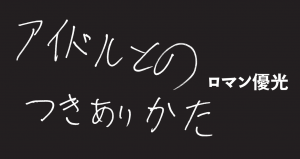他人と生きるための社会学キーワード|第5回|和解のための道程──歴史をふり返ることの意味|坂口真康
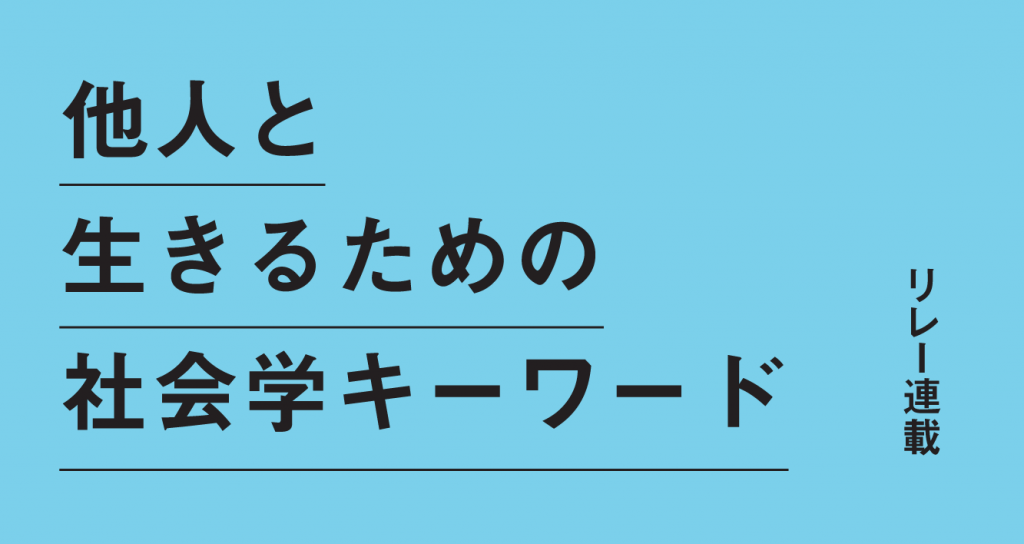
和解のための道程
歴史をふり返ることの意味
坂口真康
われわれは、自分たちが直接経験したわけではない過去の出来事については、まったく関係がないのであろうか。過去の戦争や紛争がひき起こした出来事に関する議論に、それらを直接経験したことがない世代は、いっさい関わる必要がないのであろうか。
とくに若い世代においては、自分たちが直接的に関わったわけではない出来事に対して責任を問われるすじあいはないと思われるかもしれない。しかし、はたして過去に起きた出来事は、その時代に生きた人びとのみが解決すべきこと、あるいはできることであり、その時代を生きていなかった人びとにはいっさい関係のないことなのであろうか。
ここでは歴史のふり返りと和解という観点から、先進的とされてきた事例をもとに両者について考えてみたい。具体的には、南アフリカ共和国(以下、南ア)において取り組まれた、過去のアパルトヘイト(人種隔離政策)を通じて何が起きたのかを探究するとともに、被害者と加害者との和解をめざした、真実和解委員会(1996年~1998年)の活動をとりあげながら考える(その詳細については下記ブックガイドの①と②を参照されたい)。
南アの真実和解委員会では、アパルトヘイト体制下に起きた事件の真実をあきらかにすることで被害者を救済すると同時に加害者には恩赦を付与することで、新生南アを生きる人びとの和解を達成することがめざされた。その活動の特徴のひとつとして挙げられているのが、歴史をふり返るさいに、たんに「黒人対白人」という枠組みで過去の出来事を切りとらなかった点である。すなわち、どちらの「人種」集団にも被害者と加害者がいたという真実を描きだすことで、過去の出来事を特定の「人種」集団の問題とはしなかったのである。
さらに、同委員会の活動で、歴史のふり返りと和解という観点から着目できるのが、人びとの証言に重きをおいていたことである。そして、そのような人びとの対話を重んじるという同委員会の姿勢の根底にあるものとして挙げられてきたのが、「ウブントゥ」と呼ばれるアフリカ哲学である。
「人は人を通じて人となる」という意味をもつとされる同哲学では、人びとの対話が重視され、そこでは多数決によらない「民主主義」の精神が基盤となっているとされる。同委員会では、「ウブントゥ」の概念にもとづき、白黒をつけるための議論ではなく、人びとが対話すること自体に重きがおかれたのである。戦争や紛争のあとには、敗戦側が資料を破棄することなどから、文書による証拠をふまえた出来事の検証が困難であることが指摘されてきたが(下記ブックガイドの④にくわしい)、南アでは被害者と加害者の実際の声を拾いあげることで、人間がひき起こしたアパルトヘイトという過去の出来事の真実を探究しようとしたのである。
何千ページにもおよぶ報告書が書かれて南アの真実和解委員会の活動はひとつの終わりを迎えたが、その後の同国では、同委員会の活動で和解が達成されたというよりもむしろ、和解には終わりがないという認識が共有されたといわれている。和解には終わりがない、ということが意味するのは、被害者と加害者間の和解が簡単には成立しえないというだけではない。そこには、被害者あるいは加害者という存在自体が、歴史をふり返るなかで更新されうるものであるという点も含まれているのである。
そのような点を象徴する出来事としては、たとえば、南アにおいて2008年に中国人の人びとが、みずからもいわゆる「黒人」であるとして最高裁判所にその承認のための訴訟を起こし、それが認められた出来事が挙げられる(下記ブックガイドの③にくわしい)。過去の不平等の清算のために南ア憲法により認められている積極的差別是正措置の対象となるという観点から、いわゆる「黒人」として認められることには意味があったわけであるが、この出来事はそれと同時に、過去の体制による被害者の範囲――「被害者」カテゴリや「人種」カテゴリ――が更新されたという重要な意味をもっていたといえる。
さらに、ポスト・アパルトヘイト時代の南アでは、被害者と加害者を生みだした「人種」カテゴリ自体を考えなおそうとする動きもみられる。たとえば、象徴的な出来事としては、1996年から南アで実施されてきた国勢調査において、2011年の調査より、「人種」を答える欄に「その他」という項目が設けられたことが挙げられる。「その他」の箇所には、「人種」を書きこむかわりに「人間」と書きこむこともあるとされるなど、過去の被害者と加害者を生みだした「人種」カテゴリ自体を別のものに置き換えようとする動きもみられるのである(南アの「共生」の事例についてくわしくは拙著『「共生社会」と教育』を参照されたい)。
歴史をふり返るとき、語り手によって真実そのものが異なる内容となりえることは言うまでもないが、語り手の存在自体も更新されうるものであるということを、南アの事例からは学ぶことができる。それはすなわち、歴史のなかにいた時点と現在(あるいは未来)とでは、同じ人間であっても異なる存在になることが可能であることを意味しているといえる。そして、歴史をふり返る視点や存在がつねに更新されうるという点をふまえると、最終的な合意も一地点の一時的なものとしかなりえないことを示唆しているといえ、現在(そして未来)にも関わるという点において、歴史をふり返るという行為が、過去を生きていなかった人びとにも関係するものであるといえるのである。
ところで、以上のような点をふまえて日本の社会を概観したとき、歴史のふり返りという観点からたびたび話題にあげられる大韓民国(以下、韓国)の社会との関わりも、別なる角度から見ることができるのではないだろうか。
たとえば、近年、メディアを通じて報道された出来事としては(『朝日新聞』2018年11月22日朝刊・12月29日朝刊など)、2018年11月に韓国政府が、「元慰安婦」の人びとに支援事業を展開してきた「和解・癒し財団」の解散を発表したことがとりあげられよう。日本政府の合意なしに同財団が解散されたことなどが批判されるなか、その1か月後には、韓国の「元慰安婦」支援団体が、2015年の日韓合意の破棄と日本政府が拠出した10億円の返還を韓国政府に求めたという報道にみられるように、日韓の政府間でなされた和解への合意が当事者の側から拒否されたのである。
「和解・癒し財団」の解散の決定、あるいはその存在自体の否定という一連の出来事は、「最終的かつ不可逆的」という強い言葉で合意された事項であったとしても、その解釈は、歴史をふり返るなかで見直されうるものであることを示したという点で象徴的な出来事であったといえよう。そしてそれは、人間社会においては、めまぐるしく進行する現在という地点から歴史をふり返るという営みが絶えずおこなわれるものであることを示しており、人間社会における過去の出来事に対する和解が、到達できる場所ではなく終わりのない道程として位置づけられることを示しているという点で象徴的だったといえるだろう。
過去の出来事は、現在にも未来にも終わりなく関わりつづける。歴史をふり返る作業にも和解にも終わりがないという前提のもとで、他者と共に社会を生きていく――築いていく――ことは、けっして容易なことではない。しかしそのような前提は、過去の出来事の直接的な当事者間、そして直接的な関わりをもたない者も含むより広範な集団間において、過去の人間社会の「非人道性」と向きあい、現在そして未来の人間社会の「人道性」を探究するうえで、ひいては「共生社会」について模索するうえで不可欠なことではないだろうか。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
① 阿部利洋『紛争後社会と向き合う』京都大学学術出版会、2007年
② アレックス・ボレイン(下村則夫訳)『国家の仮面が剥がされるとき』第三書館、2008年
③ 峯陽一編『南アフリカを知るための60章』明石書店、2010年
④ 上野千鶴子『ナショナリズムとジェンダー』岩波書店、2012年
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
坂口真康(さかぐち・まさやす)
兵庫教育大学講師。筑波大学大学院3年制博士課程人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻修了。博士(教育学)。専門分野:教育社会学、比較教育学、共生社会論、南アフリカ共和国の教育研究。
主要著作:
『「共生社会」と教育』春風社、2021年
『共生の社会学』共著、太郎次郎社エディタス、2016年
『教育社会学』共著、ミネルヴァ書房、2018年
「南アフリカ共和国における『共生』のための教育に関する一考察」『比較教育学研究』第50号、2015年
「「ナショナルな基準」と多様な実践の間で揺れる社会的な「共生」を志向する教育」『教育社会学研究』 第106集、2020年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)