他人と生きるための社会学キーワード|第4回(第2期)|歴史修正主義──わがままな自画像|岡本智周
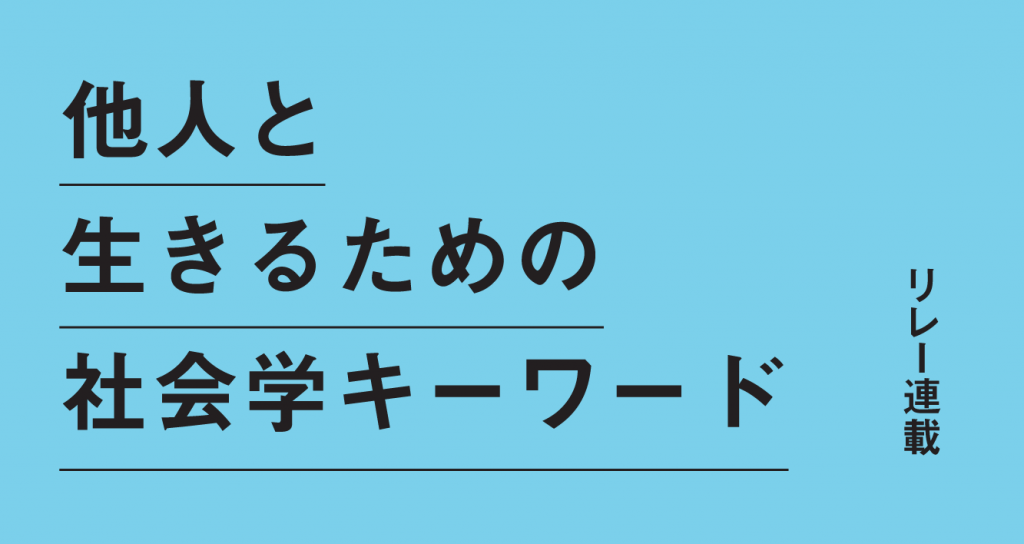
歴史修正主義
わがままな自画像
岡本智周
1986年9月、時の文部大臣が総理大臣によって罷免された。理由は、総合雑誌のインタビューにて日韓併合について、「形式的にも事実の上でも両国の合意の上に成立している。韓国側にもいくらかの責任がある」との歴史認識を発表し、内外の批判を呼んだからである。
罷免に値する由々しき事態だと社会的にも政治的にも強く認知されたわけだが、その後も1980年代後半から90年代にかけて、大臣を務める政治家の歴史認識が社会で問題視され、辞任に至るという出来事は続いた。
「白色人種がアジアを植民地にしていたのであり、だれが侵略者かと言えば白色人種だ。それが、日本だけが悪いということにされてしまった」(1988年4月、国土庁長官)
「私は南京事件というのは、あれ、でっち上げだと思う」「慰安婦は程度の差はあるが、米、英軍などでも同じようなことをやっている。慰安婦は当時の公娼であって、それを今の目から女性べっ視とか、韓国人差別とかは言えない」(1994年5月、法務大臣)
といった具合である。
こうした認識が、実証的な手続きを経た歴史学的知見とは相容れないものであることは明らかだが、ここで着目しておきたいのは、これらの問題発言が1980年代からひんぱんに起こりはじめたこと、そして現在では、この手の認識を公人が表明しても誤謬を追及されることがめっきり減ってしまったという事実である。
公言することで社会からの批判が生じるが、同様の発言がくり返されることで「またか」と常態化してしまい、認識に問題があることが受けとめられ難くなってしまう──とくに1990年代末からその傾向が強まることとなった。20世紀から21世紀に移り変わる時期から、いわゆる歴史修正主義が日本社会に浸透しはじめたのである。
* * *
歴史修正主義とは、多面的な学術的検証によって確定され一般的なものとなった歴史の理解を、特定の立場からの異議申し立てによって相対化し、誇張や捏造を含んだ別なる像で上書きしようとする立場のことである。第二次世界大戦時に生じたナチスドイツによるホロコーストを否定する言説などが、その代表例である。
日本においても20世紀前半の戦争状況に関して、1950年代の半ばから、同様の「歴史の見直し」が折々に議論されるようになってはいた。第二次世界大戦の敗戦に至るまでの軍国主義を肯定的にとらえなおそうとする動きが生じていたのである。ただし、それが社会のなかであえて公然と表明されることは少なかった。表明されたとしても、真っ当な現実認識にもとづく批判が機能していたからだ。
状況が変わったのは1980年代からである。なぜか。
大塚英志氏は『メディアミックス化する日本』(イースト・プレス)において、サブカルチャーの領域で蓄積された架空の大きな物語が、1980年代から現実に越境しはじめたことに注目している。オウム真理教がおたく的な世界理解の妄想を現実化させようとしたのがこの時期であり、それと同様に、諸外国の圧力で戦後の日本は歴史を書き換えさせられたという被害者意識が歴史観の形をまとって台頭した、と説明する。それは、「架空の歴史と本当の歴史を交換しようとするテロ」とも呼べる現象であった。そしてそれを可能にしたのが、多様なメディアを同時的に活用して物語を消費する「メディアミックス化」した社会の成立であった。
実際、1995年に組織された「自由主義史観研究会」は複数の新聞社・雑誌社の後押しを得て、多くの文化人を動員し、日本における歴史認識の現状に向けた問題提起を盛り上げた。1996年には保守系言論人によって「新しい歴史教科書をつくる会」が発足し、やはりマンガを含めた多様な表現媒体がその活動の展開を支えた。その目的は、「“戦後平和主義者” たちの過剰な自責感情・贖罪感・自虐史観」を批判し(「天下不穏」『産経新聞』1996年8月26日夕刊1面)、明治期日本の活気を称揚し、極東裁判を否定し、「南京事件」「従軍慰安婦制度」に関する認識を改めさせることに据えられた。
* * *
しかし考えてみれば、歴史の通説を再検討し改訂を加えること自体は、正統な歴史学のなかでおこなわれていることでもある。歴史を分析する人間は、利用可能な情報を資源として根拠を固め、ひとつの像を提示していくのである。イタリアの著名な歴史学者ベネディット・クローチェは、「歴史とは、そこに描かれている時代以上にそれを描いている時代の諸問題を、より十全に指し示すものだ」という言葉を残したが、それは観察し語る人間の立場、すなわち現在その書き手をとりまいている環境が、生みだされる歴史叙述に影響を与えていることに目を向けさせるものであった。
ではそのうえで、正統な歴史学と、歴史修正主義とを分かつものは何なのだろうか。
それは、歴史像を構成する思考のそもそもの出発点が、対象となる事象に据えられているか、それとも現在の自分自身に据えられているか、という違いである。
歴史学の研究では、まず出来事にかかわる情報を可能なかぎり多く検討し、そこにいわば無数の因果連関の可能性を想定する。原因-結果の連なりは多様に想定することができ、だからこそ史資料の収集・批判・読解がたえず積み重ねられるのである。そうして吟味された因果の連なりの束から、より妥当性の高いものが抽出され、歴史の理解に供される。したがって新たな情報が発見されれば、因果連関には新たな可能性がつけ加わることになり、吟味は再開される。このような手法によれば、現在に至る歴史の連なりは、ありえたさまざまな解釈のうちでも、もっとも妥当性を主張しつづけられた一つとして示されるのである。
対して歴史修正主義による作業では、歴史の連なりを考える起点はつねに現在に据えられている。現在の状況を説明するために適合的であるか否かが情報を取捨する基準となり、したがって、過去と現在を結ぶ因果連関は一つであることをあらかじめ設定した思考をしていることになる。現在から過去へさかのぼる叙述──「倒叙」という──が語り手自身を正当化しがちになるのは、対象となる事象をとりまいていた無数の因果の連なりの可能性を顧みることなく、ただ一直線に現在と過去とを結ぶからである。そうして生みだされる歴史像は、現在の自分たち自身が見て満足するために、過剰に装飾された自画像のようになる。
「歴史とは何か」についてのこのような考え方を言葉にしたのが、ドイツの社会学者マックス・ウェーバーであった。歴史研究の領域でも模範となる方法論に裏打ちされた業績を数多く残した彼の作業を支えたのは、事象の存在を支える根拠(実在根拠)と、事象の解釈を成立させる根拠(認識根拠)とを、厳格に峻別する思考であった。
歴史を知ること、描くこととは、そもそもどういうことなのかを考えるために、そうした先人たちの古典的著作に学んでみることは重要だろう。そこに展開されている思考を実際に活用しながら生きていくことが、現在の私たちにはできるはずなのである。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
エドワルト・マイヤー、マックス・ウェーバー『歴史は科学か』森岡弘通訳、みすず書房、1965年.
マックス・ウェーバー『歴史学の方法』祇園寺信彦・祇園寺則夫訳、講談社、1998年.
岡本智周「歴史教育内容の現状と、伝統の学び方のこれから」岡本智周・丹治恭子編『共生の社会学──ナショナリズム、ケア、世代、社会意識』太郎次郎社エディタス、2016年.
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
岡本智周(おかもと・ともちか)
早稲田大学文学学術院教授。専門分野:教育社会学、共生社会学、ナショナリズム研究、社会意識研究。
主要著作:
『共生社会とナショナルヒストリー』勁草書房、2013年
『「ゆとり」批判はどうつくられたのか』共著、太郎次郎社エディタス、2014年
『共生の社会学』共編著、太郎次郎社エディタス、2016年
『教育と社会』共著、学文社、2021年
「歴史教育の高大接続の現状と課題──社会科教育と社会科学教育の接続として考える」『共生教育学研究』第10巻、2022年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)


