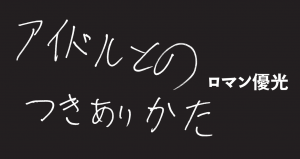こんな授業があったんだ│第5回│にわとりを殺して食べる〈後編〉│鳥山敏子

にわとりを殺して食べる 〈後編〉
(小学4年生・1981年)
鳥山敏子
(小学4年生・1981年)
鳥山敏子
前編から読む
自分のなかにある差別を見つめる
──田島征三『土の絵本』をめぐって
画家の田島征三さんの書いた『土の絵本』(すばる書房刊)を使って授業をした。この本はもう何年もまえに読み、強く印象に残っていた。自分の幼いころ目にしたにわとりの料理のシーンとダブり、共感するところが多かった。自分の育ててきたにわとりが、ある日、野犬におそわれた。怒った彼は、その野犬をとらえて、肉はもちろん、その血までのんでしまおうとした話である。
わたしはこの田島さんの考えを子どもたちにぶつけて、ただ、「かわいそうだ」ということでとどまっている子や、「どうせ生きものを殺さなけりゃ生きていけないんだよ」と割りきることによって自分のからだのなかに動いていたものをみつめようとしない子に、ゆさぶりをかけたかった。さらに一歩つっこんで、被差別部落ということや、自分のなかにある差別ということにもふれさせてみようと思った。少し長くなるが、「庵で犬を」の部分を引用する。
「庵で犬を」
──一部引用
◉─野犬
野犬が、鶏を二羽も噛み殺した。
二羽とも、よく卵を生んでくれる奴だったが、こうなっては鳥鍋にするよりほかはない。晩めしの支度に羽根を毟ってから、まず一羽をばらしにかかった。夢中で内臓などを取り出して並べていたら、件の犬が洗面器の中に入れてあったもう一羽の方を咥えていった。僕は、気違いのように出刃包丁を振りまわして追いかけたが、逃げられてしまった。多分、野犬は、あの鶏を山の中でゆっくり食ったに違いない。
夕餉の食卓を賑わした鶏は、腹いっぱい明日からの卵を抱えていた。殺されなければ、腹の中の小さな卵が毎日一つずつ生まれてきたことだろう。このことを考えるとこの鶏を殺した野犬に憤りがむらむらと沸いてきた。それにしても、その夜一家の栄養源になってくれた一羽は、まだいいが、もう一羽はまるごと紛失してしまったのだ。
次の夜、けたたましく鶏が騒ぐので、「又、殺られたのでは」と心配して見たら、例の野犬が鳥小屋の戸を壊しかけていた。もし手遅れだと、又、僕の鶏たちを死なせるところだった。「もう許せない」僕は、山羊を繋ぐ鉄製の棒を握り闇の中を走った。しかし、敵も命がけ、又逃がしてしまった。
「そんなやり方では犬はつかまりませんよ」丁度泊っていた農大出身の男が、私に任せなさい、朝までには捕えてみせる、というので、僕は寝てしまった。翌朝起きてみると、憎き野犬は、首と後足を荒縄で縛られ、それぞれ別の方向から引っぱられてくさむらに転がされていた。悪辣な猛犬も完全に自由を奪われて、我が手中に落ちてしまうと憐れである。(中略)
◉─土の思想
「たべちゃいますか」農大卒がうれしそうに言う。保健所に連れて行けば、注射で殺されてゴミとして捨てられるだけだが、僕達で料理して食ってしまえば、動物性タンパクを無駄にしないですむ。というのが農大の言い分である。賛成である。僕は食物を捨てる人をみると「この人は悪い人だ!」と思ってしまう。逆に、なんでも食べる人は好きだし、僕も川や山から採ってきたものは、草でも魚でも全て食う。そのかわり、食べないものは採ってこない。自分が食べないのに魚を釣りに行く人をいやな人だと僕は思っている。
「食べよう」と決心した。
ところで農大はどうやって彼女を捕えたか。彼は、一晩かかって彼女を餌付けしたのである。徐々に、餌を手から食べさせるようにし、頭をなでさせる所までなつかせ、朝方には、ついに首輪をつかまえたのだそうだ。
「まず講和を結んで、それからつかまえるのでなければ、野性の動物は生け捕りには出来ませんよ」
「それは、まるで、アメリカのやり方ではないか」
僕は急に不機嫌になってしまった。
ベトナムでもそうだったが、アメリカインディアンを亡滅させて行く過程で、いつも、手を結んでは手中に引き込んで殺すというやり方を使っている。(中略)
◉─犬料理
僕たちはまず彼女の動脈を切った。血が五センチだけ舞い上がり、その血のさっきまでの持主は低く長く鳴いた。
白土三平の漫画の中に、馬の血をよく洗った腸に詰め、所々草でしばってサラミソーセージを作る所があったので、僕は農大にサラミをつくろうよといった。流れる血が不憫でしょうがなかったのだ。
農大は、おどおどしながらいろいろのことをしゃべりつづける僕を無視して、ゴリゴリと音をたてて首を切断してしまった。最後の血が泡をともなってゴボッと草の根にすいこまれていった。二人は二つになった彼女の体を飼料袋にいれて仕事場まで運んだ。(中略)
その山頭火の庵のような小屋に彼女を運んでいって料理を始めた。まず皮をはがすと庵の中に動物の匂いがひろがった。この匂いはその後二週間も僕の身体にしみついてしまった匂いだが、この匂いは十年前、僕が貧乏で食うものも食わずにやたらと絵ばかり描きなぐっていたころ、ある日突然栄養失調で起きられなくなって死ぬかと思いながら何週間か寝こんでしまった時に自分の身体からにおった匂いである。その時に僕が「あっ」と思ったのは、小学校の時の貧乏な友達から共通してにおってきたあの匂いなのだと気がついたからである。これは、貧乏の匂いなのだとわかって、ああ僕は貧乏で死ぬのだと思うと、僕の絵を認めてくれない世間を恨んで蒲団の中でやたらと涙が流れてしかたがなかった。
その後、岩手県の前森山集団農場へいった時、裾野の村の小学校から山麓の農場まで帰るスクールバスの中にたちこめていた匂いも同じ匂いだった。バスの中で可愛い顔をした女の子がそっと僕のそばに来て小さな袋を僕の鼻先におしあてて、いたずらっぽく笑った。なんだろう、隠すのを無理に引っぱると、それはその子の首からひもで下げた匂い袋だった。「お母ちゃんがつけてくれた」という匂い袋の意味するものが心を暗くさせるのは、僕が小学生だった時、この匂いのする友達を皆でのけものにしていじめたことを思い出すからだ。指を四本その子の顔のすぐ前につきつけることがどんなにその子の心を鋭く深く切りさいていたか、僕は知らなかった。しかし、僕が意識しようとすまいとその子の体の内側には今でも、深い傷が残っているに違いないのだ。その傷は、古傷ではなく今も血を流しつづける生傷なのだ。あれから、二十数年たって、多少は差別に対する大人の世界の状況も変ったし、未開放部落ではない前森の子らに、麓の村の子らがかつての僕らのようなひどいことをするとは考えられない。だが「におう」ということに対する人間の感性は前森の子らにも、鋭い刃となっておそいかかっているのではないだろうか。
農場では牛が数十頭、豚が二百頭と二十七年前の切り株だけの荒地からは、想像もつかぬ豊かさを築き上げていた。しかし人々は、質素で家畜の匂いにすっぽりおおわれて生きていた。家畜の匂い。そうか、この匂いは動物の身体の匂いだったのか。そのことが農場の次の朝、ちちしぼりを見学した時わかった。これは、家畜の匂いであり、獣の匂いであり、屠殺の匂いであったのだ。数週間体をふきもせず寝ていた僕は動物の匂いがしたのだなあ。(以下省略)
子どもたちからの手紙
──田島征三さんへ
◎梶圭子
私たちは、このまえにわとりをころして食べました。先生は、犬とにわとりを食べたそうですね。先生の考えは、人間は他の生き物を殺して食べるのはあたりまえだと思ってるみたいです。ころしたときのにわとりと、ころしたあとのにわとりがちがうみたいなんです。ころしたときのにわとり――とってもかわいそう。でも、肉に変わってしまえば、なんでもないのです。ふしぎです。
生きものを食べるのがかわいそうだからって食べなくちゃ死んじゃうから、やっぱり食べてもいいと思います。犬はおいしかったですか? みんな気持ちわるがっているけど、私はいいと思います。
◎後藤有理子
田島先生の『土の絵本』、先生がよんでくださいました。犬がにわとりをもっていってしまう話、その犬を、田島先生が食べてしまう話、聞いていて、にわとりがりのにわとりもたべられないのに、いっしゅん、犬をたべてみたくなりました。
◎坪井研一
いくら野犬が鶏を食べたからって野犬をたべるのは残こくだ。ぼくは野犬なんて食べたことがない。食べてだいじょうぶなんだろうか。生きている犬を殺して食べるなんて気もちわるい。肉屋みたいになっていればいいけど。生きたままじゃ気もちわるい。
考えてみれば、ぼくたちは、つみのないものを殺して食べるほうが残こくだ。だが生物を食べないと生きていけない。だから、しようがない。
◎岡本みちえ
わたしは、田島先生がなぜこんなはなしをつくったのかがしりたいし、どんな人かもしりたい。こういうはなしをきいていると、なんだか、むかついてくるようです。でもほんとに、ふしぎな人だな。
わたしは、鶏をころすのはざんこくだとかんじるけど、人はどう物やしょく物をたべていかなければいきていけないということがはっきりした。
それにしても、田島先生は、いぬをころして、「ち」までのこさないでたべるなんて、なんだかかわってるな。
◎檜谷さつき
牛やぶたの肉を食べてもさべつされないのに、犬の肉を食べると、どうしてさべつされるのだろう。肉屋では犬の肉は、うっていないからかもしれない。きっとそうだ。でも、これから生活がまずしくなっていったら、犬でもなんでも食べると思う。そのことを考えたら、犬の肉なんて気持ち悪くない。私は、そう思う。みんなの考えは、きっとちがうだろう。
私とみんなの考えは、やっぱりちがった。気持ちが悪いということばかりだ。私は少しかわりものかもしれない。今までは、人の話をきくと、すぐに考えがかわったけど、今度はまったくかわらない。
田島先生は、すごくかわったことをして、そのことにたいしてすごく考える人だ。それと、さべつのキライなやさしい人だ。
イメージの世界へ
──にわとりになる
これまで、殺すことをとおして、「いのちとは」「人間とは」「差別とは」を追求しつづけてきた子どもたちをみて、わたしは子どもたちを理屈で考えさせすぎたように思えてきた。そこで、からだを使って、「にわとりになる」イメージの世界にはいることにした。にわとりの側から、にわとりと人間をみることをしたくなった。
机を後ろに運び、にわとりを殺す人間と、にわとりと、子どもたちを半分ずつにわけた。にわとりになった子には、「いま、卵!」といって、卵になってもらった。人間になった子は、卵から離れてもらった。
「いま、卵です。お母さんのあたたかい胸のなか。あったかーい! 卵のなかで少しずつおーきく、少しずつ大きくなっていく。血管には、血も流れている。小さな心臓は休みなく血を送っている。ああ、大きくなってきたからだ。羽もはえている。カラいっぱいにふくれあがってきたからだ。もうすぐ外へ出られそう。出られそうな人は出てみてください。
さあ、外へ出た。
ひよこだよ。羽はぬれているけど、少しずつ、少しずつかわいてきた。
お母さんどりといっしょに草原へ。
草を食べよう。
ミミズも……。
だんだん暗くなってきた。
さあ、ねよう」
夜のシーンでは、ときどき、野犬(子ども)を登場させた。早く大きく成長する子もいれば、なかなか卵からかえらない子、ヒヨコから大きくならない子もいて、おもしろい。野犬がなくたびに、かたまってふるえている。少しずつヒヨコを成長させてにわとりにした。
「さあ、にわとりをつかまえて、殺してたべよう!」
机の上下、いすの上下、ロッカーのかげにかくれていたにわとりも、全部ひきずりだされて殺された。殺し方は、まえに実際に殺したのとおなじ。
「首をひねって!」
「首の毛をむしって!」
「さあ、するどい包丁でぐさりと!」
バタバタあばれるにわとりをおさえこんで料理する。ぐたりとするにわとり、まだあばれつづけているにわとり。
「さあ、さかさまにつるして!」
足をもってさかさづり。まだ、あきらめられないのがいて、もがいている。
「あつい湯のなかへ。全部つけて、もっと湯のなかへ、そう!」
「さあ、毛をむしろう!」
湯から出してねかされ、毛をむしっていく。
「きれいにむしったかな」
もう、ここでは、みんな観念したようだ。あばれる子はいない。
「バラバラにばらそう」
包丁をふたたびもち、バラバラにしていく。
「それをくしにさして、火にあぶろう」
「やけたら、食べて!」
殺されるにわとりになる
──子どもたちの感想文
◎木原久仁子
卵からはじまった。先生が、
「お母さんのおなかで、あたためられている」
と、言ったとき、ほんとうにせなかのあたりが自然にあったかくなってきた。3週間くらい卵のなかにはいっていた。だんだんと卵のなかにいて、きゅうくつになったとき、私は、外に出ました。外にいて、いちばんこわかったこと、というと、犬が来たことです。
大人になって、何日かたってから、人間におそわれた。つかまえられたら、すぐにナイフで切られ、そして、つるされました。血が全部出てしまったら、こんどは、手や足を切られ、それにあぶらをぬられて、火をつけて、やかれました。私は、すごいやき方をするなあと、思いました。
◎岡本佳子
たまごからうまれて、だんだんおおきくなって、鶏となった。ある日のよる、犬がおそってきた。私たちは同じ場にあつまり、ちぢまっていた。何分かして帰っていった。ある日、おそろしい人間がきて、私たちをつかまえた。私はいっしょうけんめいにげたら、みんなおなじところにあつまってしまった。友達のせなかでふるえていた。私は、つかまり、どきっとした。毛をむしられ、私はあばれていた。いたいっと思うと、ころされていて、血がどくどくとでていた。
◎梶圭子
たまごのなかは、とってもあったかい。体が大きくなりすぎて、からにはいっていられないので、からの外へ出ました。はねは、ぬれています。おなかがすいてきました。草をつっついて虫をたべます。
すこししたら、犬がやってきました。犬におそわれたらたいへんです。みんなのなかにもぐりこみました。でも犬は、私をひっかいて、いってしまいました。けがをしたのもかまわず、また、虫をたべました。
ひよこは、とっても犬がこわいとわかりました。
◎山縣慈子
私達は犬がこわい。
私はははおや、たまごもち。ころされたとき、たまごさえ生きればと思った。さむけが私をおそう。みんな元気でいますように。神様おねがいいたします。この食物がほうふなあれのはらに⋯⋯。
◎川崎隆之
たまごのなか。まわりは、かたいものでおおわれている。きゅうくつで、はやくでたい。くちばしで、とんとんたたく。ひびがはいってきた。出口を見つけた。すぽっと頭を出すと、大きな大きな大草原が見えた。ハイジャンプして、外に出ると、もう太陽がしずみかけている。そのとき、地面にミミズがはっていた。まだなにを食べていいか、わからない。そのミミズを口に入れてみた。ステーキのようにおいしい。
夜になると、野性の犬があたりをうろついた。そしておそいかかりもした。でもぼくは、なんとか食べられなかった。
ある日、エサを食べていると、生き残りの原始人が、木のナイフをもっておそいかかってきた。む中になってにげていると、行き止まりにきてしまった。どうしよう、と、思っても、あとは飛んでにげるしかない。バサバサバサと音を立てて、大空へまいあがった。一しゅん、やったと思ったが、原始人のなかでいちばん白いのと黒いのが、ナイフをぼくめがけてなげた。プスンと、ぼくのくびにささった。ドバーッと血が出てきた。もうだめだ、力がない。目をまわして、地面に落ちていく。ドッスーン。とうとう殺されるうんめいがきた。原始人がくる。ナイフを首にあてた。グサリ、と首にナイフがくいこんだ。まだがんばっている。さかさにして、血をだした。毛をぬかれて、とうとう死んでしまった。
殺す人間になる
──子どもたちの感想文
つぎは、交替だ。にわとりのほうは人間に、人間のほうは今度はにわとりに。もう、にわとりになって殺され、食べられてしまった子の相手に対する目つきがちがう。「ようし、しかえしをするぞ」といきまいている子もいる。最初の人間よりも、もっとはげしく、にわとりを殺して食べる人間になっていた。
◎牟田賢一
反対になった。しかえしに白井君のにわとりにまっさきにとびかかった。児玉君といっしょに白井君のにわとりをいためつけた。みんなにわとりはキャーキャーキャーキャーいっていた。なかなか血がでないので、ぶらさげようと思った。が、おもすぎてもちあがらなかった。どんどんおした。血が落ちてきた。しんでいるはずのにわとりがうごいているので、児玉君が、
「やめろよ」
といいました。ぼくはおこって首を切って切ってきりまくりました。白井君のにわとりはわらっていた。ナイフでもものところをちぎってたべた。まずいのは、どんどん投げすててしまった。けれどたいしておいしい肉はなかった。だけど、さっきのうらみだと思い、ほねになるまで肉をとっていった。もう白井君は死んだ。まだうごいているが、もうやめてしまった。
◎伊藤ふじ美
にわとりの大群がいる。一わのよわそうなにわとりが、にげまわっていた。
私は、走ってにわとりをひっつかんだ。とても弱そうなにわとりで、あまりおいしそうではなかった。だから、向こうのほうにいる小さなにわとりをつかまえた。そして首にナイフをたてた。血がたれた。そしてにわとりをさかさにつるした。血が全部なくなったようだ。そして、火であぶった。とてもおいしそうにやけた。
でも、不思議なことに、かわいそうになってきた。まるで、やいたにわとりが、ふるえてないているように思えた。
◎木原久仁子
鶏が大人になったころ、私たちは、鶏を殺しにいった。小さな鶏をつかまえて、坂内さんと切ったりした。首のところを切るとき、私はほんとうに殺すみたいで、切るまねをするだけでも、いやだった。体のなかのものを取りだした。全部に血がついていた。やこうと思ったころには、手が血でよごれていた。なんだか気持ち悪かった。
生きものとしての自分を見つめる
──この豊かな生活の背後にあるもの
にわとりを殺すという授業は、戦争とか原爆とかをもっと深く考えさせたいというところから出発したものである。一見、戦争や原爆は個人の努力、個人の考え、個人の善意ではどうしようもないものであるかのようにみえるが、しかし、出発はあくまでもひとりひとりの同意から始まっている。それなのに、過去の戦争はいつも犠牲だけが強調されて、ひとりひとりの責任は回避されたように思えてならない。これは、いいすぎだといわれるのを覚悟のうえで、どうしてもそれを強調したいのだ。
犠牲が強調されればされるほど、戦争へ追いやった為政者への追及は強くなったが、為政者を支えたおのれ自身の責任はいつも回避され、弱められてきた。「戦争に反対しなかったのは、反対すると非国民だといわれるから反対できなかったのだ」と、もしいうのであれば、戦争はけっしてなくならないだろう。都合のいいときは自分のおかげであり、都合の悪いときは為政者や体制のせいにする大衆が社会をつくっているかぎり、戦争はけっしてなくならないだろう。
この資源の少ない日本の毎日のぜいたくな生活、世界のなかでも進んでいるといわれるこの生活は、戦争のおかげではなかったか。あの朝鮮戦争の特需で、経済的に立ちなおることができたのではなかったか。もう戦争で殺しあうのはこりごりだったはずの日本人が、もうけるために戦争に参加したのではなかったか。
自分の欲望を満たしてくれているもの、これは、他国の人たちのいのちを奪うという行為のうえに成りたっているのだ。この豊かな生活のなかに、殺されていった、半殺しにされ、“かたわ”にされていった人の魂が、うらみをはたせぬまま、ふわりふわりとさまよっているのだ。
犠牲だけを強調する戦争はもうたくさんだ。あの第二次大戦のときも、男だけでなく、女だって手をかし、参加し、おし進めたのだ。泣いたのは自分だが、泣くようなことをしたのも自分なのだ。その事実を直視しなければ。人間なんて、そうりっぱなものではないのだ。戦争などというくだらないことを平気でやってしまうおそろしい生きものなのだ。生きものとしての自分をみつめることから戦争をとらえなおしてみたい。そのことが自分を相手をも理解する第一歩になるのではないだろうか。
いま、自分のからだが食べたがっているものや、食べたい量をいっさい無視して行なわれている給食という「教育」が、どんなに生命を軽視し、からだ感覚をにぶくしてしまう子を大量生産していることか。これは、たいへんな生命蔑視の思想教育だと歯ぎしりしているのだが、どうにもならない。あいかわらず、パンもおかずも捨てられているのだ。多くの無駄になったいのちは、いつかきっと人間に報復するだろう。
* * *
[付記]これを書いて四年後、わたしのつとめる桃園第二小に新しく原田さんという栄養士さんがはいった。彼女は、子どもたちのからだと心のことを考えて献立をつくり、有機農法の野菜やくだものを仕入れるなどの努力をし、親たちを啓発するために、通信も出した。桃二小の給食は一変した。
しかし、いっそう残念なことに、残飯はやはり出るのだ。しかも、子どもたちのからだにいいと思って作る献立に残飯がたくさんでるということも起きている。冷凍食品やインスタント食品、そして、ハンバーグなどのやわらかい食品に慣れた子どもの舌は、素材がしっかりし、手をかけて作る食品を好むようには、かならずしもなっていないのだ。むしろ、その傾向が強くなっているといってもいいだろう。外食産業からおかずを買う母親が多くなった現在、ある意味では、この給食ほど子どものからだにいいものはないのだが⋯⋯。
わたしたちは、そういった時代を生きている。
出典:鳥山敏子『いのちに触れる』太郎次郎社、1985年
鳥山敏子(とりやま・としこ)
1941年、広島県生まれ。1964年、東京都で小学校教師に。60年代の教育科学運動のなかで実践を深め、先駆的な授業を生みだす。70年代、竹内敏晴らの「『からだ』と『ことば』の会」に参加。80年代をとおして「いのちの授業」を実践。また、教師としての宮沢賢治を研究する。94年に公立学校を退職し、ほどなく「賢治の学校」(現「東京賢治シュタイナー学校」)を立ち上げる。著書多数。『いのちに触れる』『イメージをさぐる』(ともに太郎次郎社)、『親のしごと 教師のしごと』(法蔵館)、『生きる力をからだで学ぶ』(トランスビュー)など。2013年死去。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)