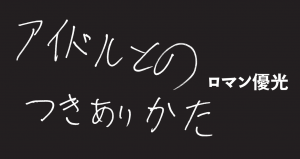こんな授業があったんだ│第2回│授業「木になる」PART1│近藤真

授業「木になる」 PART1
詩 「き」 (谷川俊太郎) を読む(中学2年生・1997年)
近藤 真
詩 「き」 (谷川俊太郎) を読む(中学2年生・1997年)
近藤 真
校舎の裏には原生林が続く
N中学校は森の学校である。標高四百四十五メートルのS岳の麓に学校はあり、校舎の裏に原生林が迫る。新緑の季節には、さまざまのニュアンスの緑の塊がむくむくと沸きたって、クリーム色の四角な校舎を包んでいる。
敷地を区切るフェンスもなく、理科室裏の側溝を飛びこえると、容易に森に入ることができる。一歩足を踏みいれると、そこは完全な別世界である。倒木を乗りこえけもの道をのぼっていくと、やがて木立のあいだにうち捨てられた墓石がいくつも立っている。なかには元禄二年の銘が読めるものもある。かつてここには寺院があり墓地があった。
また墓石のつぎ目に落ちた種が根を張り、実生の大木となって墓石を抱きかかえているすごい光景にも出会える。やがて墓石は木の胎内に蔵されていくことだろう。森がこの先もずっと存在すればの話であるが。
私がN中に赴任した五年前は、生徒の荒れが濃厚で、落ち葉の上にはたばこの吸い殻やジュースの空き缶が散乱していた。おまけに木の枝から枝へと張りわたしたターザンロープまでこしらえてあって、森はツッパリ生徒たちの格好の息抜きと遊びの空間であった。
昼休みに私はときどき校舎をぶらつく。すると、私の姿をめざとく見つけたヒロミやテルコたち数名が駆けよってくる。
「ねえねえ、先生。森へ連れてってよ」
私がよく森に入るのを彼女たちは知っているのだ。冬に入って食後の散歩を数日やめたら、彼女たちは職員室に押しかけて、私を戸外へ引っぱりだす。
「裏山に入るべからず」と学級担任からきびしいお達しを受けているから、森に入るためには私の同伴が必要なのである。すなわち私は彼女たちの保護者というわけだ。私の手を引くようにして彼女たちはずんずん森のなかに入っていく。やがて栗の大木がある。この下に数人が腰を下ろせる空間があるのだ。地面にはたくさんの毬が落ちている。
森に入ると不思議に心が落ち着く。なつかしさがこみ上げる。自分がほんとうに帰ってきたかった場所、それがここなんだ。──そんな気がしてくるから不思議だ。
それは、少年時代に友人や父といっしょに森に入って遊んだ記憶に、三十年の時空を超えて、まっすぐにつながるからだろう。……春は、つくし、うど、わらびなどの山菜とり。夏はクワガタ、カブトムシ、セミなどの虫とり。十歳の夏休みに、六つの弟を連れて半日森に入ってとったカブトムシを、父の車で、S市の港の朝市に売りにいったことがある。おばさんが三十数匹まとめて千円で買ってくれた。私の人生ではじめての「労働」(?)による現金収入であった。秋の森はほんとうに楽しい。栗拾い、山芋掘り(父はこれが好きだった)、うべ、あけび、柿、野生の梨、キノコとり……。戦争ごっこ、やぐらづくり、穴堀り、木登り……。
ただじっとして森の気に包まれるのが心地よい。木立の向こうから聞こえてくる運動場の喚声が、なんだか遠い世界の出来事のように思えてくる。教室ではめったに口を開かない(とくに授業になると)彼女たちは、森のなかだとびっくりするほど饒舌になる。いろんな話題がめまぐるしく飛びかう。友だちのこと、家族のこと、将来のこと……。森のなかだからできる秘めやかな語らいがある。
話に夢中になっていると、やがて昼休み終わりのチャイムが聞こえてくる。とたんにわれわれは現実に引きもどされる。「早く、早く」。掃除の始まりに遅れる。掃除点検係のチェックが入る! 生徒も先生も自分の受けもちの区域に急ぐ。──われながらのんきな話である。
こんな森の学校だから、校庭にはタヌキがうろつくことがある。側溝に落ちてはい上がれなくなっている野ウサギの子を、生徒が見つけたことがある。
人のいない校庭、休日の学校は森の動物たちの天国だ。だから、休み明けの運動場にはウサギたちの糞がいたるところに散らばっている。
鳥の声が授業中の教室に届く。夏になるとオニヤンマやアゲハチョウが迷い込んでくる。スズメバチもやってきて、そのたびに教室は大騒ぎとなる。
谷川俊太郎「き」の詩をなぜとりあげたか
こんなときに私は、谷川俊太郎の詩「き」に出会ったのである。
『三省堂国語教育』(第三十六号・一九九六年二月号)の見返しにこの詩はあった。この号に掲載されている論文「対話的他者としての教師」で、筆者の佐藤学氏が、この詩を授業した考察を書かれている。そこで佐藤氏が言われるように、「生々しい変身の言葉、拒絶の言葉、一人で生きる意志の言葉を謳った」詩「き」に、私はひどく惹かれた。
き 谷川俊太郎
ぼくはもうすぐきになる
なかゆびのさきっぽがくすぐったくなると
そこからみどりいろのはっぱがはえてくる
くすりゆびにもひとさしゆびにも
いつのまにかはっぱがいっぱいしげってきて
りょううではしなやかなえだになり
からだはしゃつのしたで
ごつごつしたみきにかわっている
あしのゆびがしめったどろにとけていって
したはらになまぬるいみずがしみこんでくる
そうしてぼくはもうがっこうへいかない
やきゅうにもつりにもいかない
ぼくはうごかずによるもそこにたっている
あめがふりだすととてもきもちがいい
だれもぼくがそこにいることにきづかずに
いそぎあしでみちをとおりすぎていく
ぼくはもうかれるまでどこにもいかない
いつまでもかぜにそよいでたっている
(『はだか』〈筑摩書房〉から)
くり返し読むうちに、やがてこの詩の力は、四回使われている係助詞の「は」にあることに気づいた。
ぼくはもうすぐきになる
……略……
そうしてぼくはもうがっこうへいかない
やきゅうにもつりにもいかない
ぼくはうごかずによるもそこにたっている
……略……
ぼくはもうかれるまでどこにもいかない
いつまでもかぜにそよいでたっている
係助詞「は」は、「*主体や対象、行為・作用・状態などを特に取り立てて述べるときに用いる。*ハ文型の判断文は、題目に対する解説部分、質問の回答部分に当たる『何だ/どんなだ/何する』の述語部分に表現意図があるのは当然のことである。しかも、題目と解説との連合は話し手の判断によって行われ、それが真か否かは話し手の主観の責任となる。*否定文は『は』の判断文となりやすい。否定判断『……ではない/……しない』は、既定の題目があって初めて成立する判断である。*ハ文型が非現場における判断の主題を共通の題目として取り上げる意識から、〝他はどうか知らないが、これは……〟〝他はそうではないが、これは……〟という対比意識が伴ってくる」(森田良行『基礎日本語』角川書店)。
いま、われわれは、自分を主題にすえた、一人称ハ文型の判断文(とくに否定文)を、日常のなかで、どれだけ自己の責任において使えているのだろうか。主体意識を欠いた受身形の文章ばかりを書いてはいないだろうか。
子どもが、先生に、友だちに、親に気兼ねして使いたくても使えない一人称ハ文型の判断文(とくに否定文)。そのジレンマはやがて自己へのあきらめとなる。これは反対に、匿名ならばなんでも言える精神態度、匿名で日ごろのうっぷんを晴らそうとする無責任な言動につながってゆく。他人のうわさ話、誹謗中傷、デマ、何でもあり、だ。加害者の特定できない巧妙ないじめのやり方そのものだ。これはそのまま、いまの大人たちの精神状況でもある。
自分の意志と判断において何かをすること、否、むしろしないことの自覚の大切さを、この詩から読みとってほしい。周囲と隔絶し孤立することの恐怖におびえているかれらである。仲間はずしにあわずに、いかにして日々を大過なく過ごしてゆくのか。だから寄らば大樹の陰、長いものには巻かれろだ。率直に自分の思いは語れない。──これがいまの子ども(大人も)の行動の基準ではないのか。こんなかれらの意識に、「き」を読むことでちょっとした揺さぶりをかけたい。そしてかれらのなかに隠されている、願いや怒りや拒絶やあこがれ、希望、嫌悪、批判……にことばのかたちを与えたい。
きみは変身して、何になりたいか
まずこう聞いてみた。
「きみがいま、何かに変身できるとするなら、何に変身したい? それは、なぜ?」
さまざまな変身願望が出た。鳥になりたいと答えた者がいちばん多かった。「誰にも生活を束縛されることもなく、いつまでも自由に大空を駆けめぐることができるから。いろんな人の喜びや悲しみを、その人に気づかれることなく空の上から見ていられるから。──カオリ」。
空や雲になりたい者も何人もいた。空になりたいアキコ。「いつでも世界中を見ていられるから。機嫌がいいときには海の色を思いっきり反射させて、機嫌が悪いときには雨雲でも呼んで雨を降らせて、みんなを困らせて、その困った顔を見て笑う。のんびりしたいときには、雲でも浮かべておしゃべりをして、そんで暑い日に、たまには風でも吹かせてやろう。寒い日には雪と風を降らせてもっと寒くしてやる。そういうふうに、いつでものんびりとやさしいから」。
雲になりたいケンタとジロウ。「雲になって下界をながめてみたい。雲になって風に流されてみたい。何もしないでただ浮かんでいるだけでいいから」。
ほかにもいくつか。「ドラエモンになりたい。なぜなら今を精いっぱい遊びたいから。──ミキオ」「うちの犬になりたい。いつも昼寝をしているから、うらやましい。──ミエ」「僕はかわらです。ひなたぼっこをしたいから。──タダシ」。
この変身願望はすなわち、他者に束縛されたくない、自由でありたい、気ままに暮らしたい、のんびりしたい、いっそ何もしたくないという願望であるのだ。しかし、このことは、かれらがじっさいにおいて無精で怠惰であるということではない。むしろ無為は罪悪であるという意識のもと、勤勉さと不断の努力を大人たちに要求され、つねに何かにガンバっていなければならない生活、つねに何かに追いたてられて、とらわれの意識に苦しんでいる証左ではないのか。カオリもアキコもケンタもジロウも、みんなまじめながんばりやなのだ。ケンタとジロウは生徒会役員で、教師に劣らず多忙な毎日である。
女になりたいと書いた男の子が三人いた。「男を誘惑してみたい。──タケル」「女の気持ちを知りたい。──セイイチ」。
反対に男になりたいと書いた女の子がひとり。「何でもできるから。──ノリコ」。
彼女は女であるがゆえに自由ではないことを感じているのだろうか。一見のびのびと「自由に」ふるまっているように、私には見えるのだが……。
たとえば、飛行機、車、校長先生、ブルース・リー、しろながすくじら……さまざまな変身願望が出た。しかし、自分が木になりたいと思う者はひとりもいない。
生徒は詩「き」をどう読んだか
こうやって詩「き」を生徒に与えた。まず私が朗読しよう。
「ぼくはもうすぐきになる」──いきなり自分の強い意志の表明である。だからここは大きく息を吸って、決然たる響きで読む。生徒はびっくりしたような顔をしている。読みおえたあとに、簡単な感想を書いてもらった。
★谷川さんよ。木はそんなにいいもんじゃないぜ。だってよ、木は言葉も話せなければ、友人もいないんだぜ。病気になってもしらんふりされて。君はそれでもいいというのか。俺はイヤだね。まあ、孤独でよければいいんだけど……。──マサオ
★『き』って少しさびしいかもしれない。ずっと同じ所に何百年もたたずんで、誰ともしゃべらないし、何もできない。それに最近は森林伐採や酸性雨などで大変だと思う。でも一番さびしいのは人間だろう。自分がよりよく暮らすためには少々の犠牲をともなっても何も感じない。「ぼく」の選択は正しかったのかもしれない。──ユリ
★この少年はなぜ木になってしまうのだろう? 人間のままならばたくさんのいろんなことができるのに……。かぜにそよいで立っているだけなら、自分のしたいこともできないのに。この少年は木になることを悔やんではいないのだろうか。人間から木になることに抵抗しないのだろうか。──サチコ
★何となく悲しい詩だな。現実を遠ざけたいという気持ちが伝わってきたような気がしました。 ──ミズエ
★自分の道を持っていて、なんだかとてもうらやましいです。私も木になりたい! そう思う時があります。──ナナコ
動けないこと、何もできないことへの拒否の姿勢をあらわにした感想がほとんどだった。おそらくナナコだけが「いつまでもかぜにそよいでたっている」だけの木になる「ぼく」への共感を表明した生徒であった。
さあ、これからどう読みすすめようか。そこで、はっと思いついたのだ。そうだ、森がある。生徒を森へ連れていこう。森を教室にして、森のなかで詩を読もう。森の気に包まれること、木々のにおいをかぐこと、木に触れること、じっと止まっているような冬の森の時間に浸ること。ほんものの「き」とじかに触れあうこと。生徒の身体を森の空間と時間のなかにおくことによって、このテキストとかれらのあいだに思いがけないドラマが生まれるかもしれない。──そう思ったのだ。ありていに言えば、気楽に、束縛されない緩やかな時間と空間のなかに身をおいて、「き」を媒介に、のびやかな、意味深い時間を子どもと共有したい、ということなのだ。
冬の森で一本の木に詩をよびかける
翌日の授業は、詩「き」のプリントを携えて森へ行く。森にはじめて足を踏みいれた生徒も多く、目のまえの神秘の空間に待ちうけているものを期待しながら奥へと分けいった。
二月の朝の森はひんやりして薄暗く、鳥の声もまだ聞こえない。枯れ葉を踏みしめながら奥へ奥へ。森の精や元禄の人骨、タヌキやウサギや鳥たちが、突然の闖入者の群れにびっくりしていることだろう。大きな沼、苔むした石垣、墓石、倒木、梢から垂れ下がった太いかずら──学校のすぐそばに、われわれの日常とは異質の空間があり時間が流れている。
木々は息をころして立っているが、やがて来る春の祭典の準備を着実に進めている。試みにひと枝手折ってみるがいい。ぷんとかぐわしいにおいが立つ。私はそこで蕪村の「斧入れて香におどろくや冬こだち」の句を紹介する。
「幹に耳を当てると、木のなかを水の流れる音が聞こえるというよ。やってごらん」
それを聞いた生徒は、てんでに木に頬ずりをしながらせせらぎの音を聴きとろうとする。「これぞと思う木によりそって、その木に向かって『き』を声に出して読みなさい。その木に呼びかけるつもりで大きな声で何度も読みなさい。それから簡単な感想を書きなさい。そしてこの詩の続きを書いてみなさい」と言って、森に放った。
「ただし、あまり遠くに行かないように。私の声が届くところまでだよ」
虚構と変身の詩である「き」の学習こそ、『第三の書く』(青木幹勇)で示された方法、すなわち虚構の作文、理解と表現の連動という方法がぴったりなのではないか。そこで、書きたしという方法を使って、生徒と「き」との〈和解〉を試みた。森のなかに入って自分が見つけた一本の木によりそって、詩の続きを書くのだ。
生徒は二、三人で組んで森の奥へ散っていく。やがて自分の木を見つけたのだ。あちこちから声が聞こえてくる。私はかれらのあいだをまわって朗読を聞く。
「ぼくはもうすぐきになる……」。シンゴは栗の木の下で。
「なかゆびのさきっぽがくすぐったくなると……」。ハルミは斜面に生える大木のそばの細い木のそばで。
「あしのゆびがしめったどろにとけていって……」。あれ、ユウゾウは墓を包んでいる榎になっているぞ。
ミチルとノリコは高い木の梢を見上げて読んでいる。梢のあいだからちらちら冬の青空がのぞく。きょうは暖かくなりそうだ。くり返し読むうちに、遠くの声がよく届いてくる。教室のなかだったらこんなに通る声は出まい。それが薄暗い森のあちこちから交錯しあう。木漏れ日が当たった生徒の横顔には、はっとするような存在感がある。
やがてさざめきはやみ、森には静寂が戻った。かれらはつぎの課題に入ったのである。
こうやって「き」を読み、書きたしの詩を作って、かれらは森のなかから出ていった。
森のなかの「き」、140の「書きたし」
森に入るといままでの自分とは少し違った自分になれる。それは森の生物の一員としての自分だ。森の気に抱かれて、教室の自分とは異質な自分が生まれる。
百四十人の「ぼく」の〈つぶやき〉が聞こえてきた。これをたがいに紹介しあう。そのなかから。
★木はうごけない。木はしゃべれない。木はなにもできない。でも何だか木はいいなあ。何十年も何百年も生きられる。だまっているけど何でも知っている。木は人間よりえらい。──キミコ
★木ってつらい。動けないし、話せないし何もできない。ときどき吹く風に体がゆれて、生きていることを確かめる。いつもは立つだけ。でも、木は生きている。静かな命を持っている。──ジュンコ
★みんな木にはあまり気づいていないからかわいそうだ。木はほんとうに影が薄い。──チエ
★僕は木になったら、見えるものをすべて見ながらのんびりくらします。──コウイチ
★森というのは、とても落ち着ける大事な場所だな。──シンジ
★木になるためには時間がかかる。長い間じっとして木になったこの人はすばらしい。──ジュンヤ
★大きくなるためには相手を蹴落とさなくてはならない。自然は厳しい。──マサオ
★木は日の光に向かって伸びていて、いろんな形をしていた。曲がっているものがあった。石の間から生えている木が不思議だった。──ススム
★太陽の光とどかぬやみの中、一人孤独に暮らしてみたい。──ヨウゾウ
★でも僕は一人ではない。家族も友だちもたくさんいる。だから、ぼくは大丈夫。──タケシ
★木は同じ種類のものでも一本一本形が違う。この人は自分だけがやりたいことをしたかったのか。──ヒロトシ
★僕はあらためておもう。森にはやさしさがあふれていると。──ミキオ
さらに、生徒たちは、詩「き」につぎのような〈書きたし〉を続けていった。
◉そしてまたはるがきて、ぼくはきれいなはなを、たくさんたくさんさかすんだ、けどにんげんはぼくのことをほめてはくれない。──ナオコ
◉何の規制にもしばられず、ここを通る人をそっと見守る。──キョウコ
◉光さえも届かぬ、神さえも気づかぬこの空間で、一人空しく生きていく。だれも気づかない孤独な空間で。──コウタ
◉ぼくの友だちは枝に止まる鳥たち
風、太陽、そしてかわるがわるめぐってくる四季
友だちはみんな動いているのに
ぼくは動かずに今日もまた
そこに立っている──フミ
◉太陽の光が葉に当たり、あおあおとしげっている。
風が吹くと他の木たちがさわいでいる。
僕にはたくさんの仲間たちがいる。
いっしょに歌う鳥たち、たくさんしゃべる風。
春には花が咲く。
四季が移り変わるごとにたくさんの色の花になる。
僕は木でよかった。──マサミ
◉ぼくのところに鳥がやってきた
春というおみやげをたずさえて
ぼくの体のあちこちで
いろんな動物の人生が展開される
あたらしい命の誕生
別れ
死
でもぼくはなにもできない
いつまでもそこに立っているだけ──マチコ
教室で一行ごと、一語ごとの訓詁注釈的授業をしなかった。けれど、森に入り、木によりそうことで、木になった「ぼく」との〈和解〉をそれぞれの仕方で果たしたのではないだろうか。(後編につづく)
出典:近藤真『中学生のことばの授業』太郎次郎社エディタス、2010年
近藤 真(こんどう・まこと)
1957年、山口県宇部市生まれ。長崎県北松浦郡佐々町に育つ。1981年より長崎県中学校教員。のち、長崎県の公立中学校校長。著書に、上に紹介した『中学生のことばの授業』のほか、『コンピューター綴り方教室』『大人のための恋歌の授業』、共著書に『文学作品の読み方・詩の読み方』などがある。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)