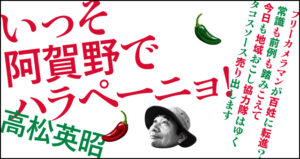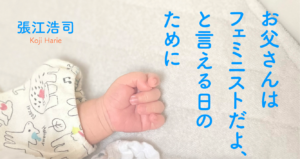他人と生きるための社会学キーワード|第16回(第4期)|排外主義──わからないことへの不安や恐怖|坂口真康
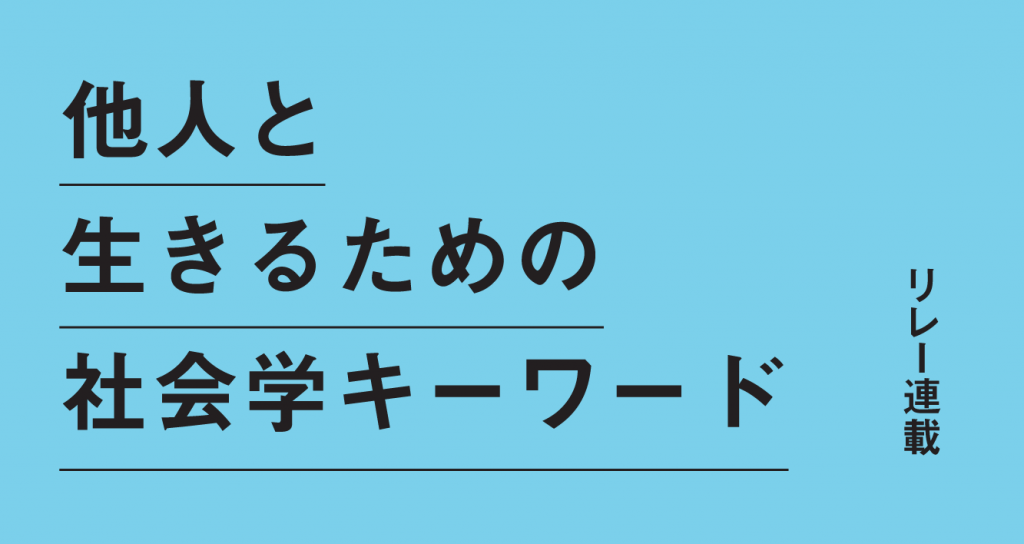
排外主義
わからないことへの不安や恐怖
坂口真康
昨今、実際には身の周りでは起きていない出来事に対して、さまざまな想像をふくらませながら不安や恐怖をあおる言説が飛び交っている。それらはときに攻撃性をともない、その矛先はとくに集団の外側から来たとカテゴリ化される人びとに対して向けられるきらいがある。日本社会において、そのような現象を象徴するものとして挙げられるのが、2025年8月に日本で開催された第9回アフリカ開発会議において、国際協力機構(Japan International Cooperation Agency: JICA)が「ホームタウン」という名前のついた計画を発表してからの一連の出来事である。本稿では、おもに新聞報道(とくに『朝日新聞』の2025年8月27日から9月17日までの記事)をもとに、この出来事について整理してみたい。
一連の出来事に関して、「きっかけは一部の国で発信された誤情報」であったとされる(8月27日朝刊)。もともと、「ホームタウン」という名で流布した計画は、千葉県木更津市とナイジェリア連邦共和国、山形県長井市とタンザニア連合共和国、新潟県三条市とガーナ共和国、愛媛県今治市とモザンビーク共和国が、おのおのペアとなって実施する人びとの交流などのイベントをJICAが支援するために、4市をそれぞれの「ホームタウン」と認定することで国際交流を促進することが目的であった(同上)。
それが、後述するような一部の地域の政府や現地報道等を通じて伝えられた誤情報により、ソーシャル・メディアなどで「移民が押し寄せる」といった投稿が拡散され、日本の外務省や長井市が対応にあたるなどして誤情報は削除・訂正されたにもかかわらず、その後も同市に抗議のメールや電話が寄せられたのである(8月28日朝刊、8月29日朝刊山形県版)。さらに、メールや電話やソーシャル・メディアのみならず、今治市の市役所のトイレで「移民反対」と複数回書かれる出来事が起きるなど、物理的なかたちでも抗議がなされたことが報じられた(9月15日朝刊)。これらの出来事が象徴するのは、誤情報で、しかも削除・訂正されたにもかかわらず、情報の真偽とはかけ離れたところで不安や恐怖があおられながら飛散する排外主義の堅固さである。
ここで強調しておかなければならないことは、上記の一連の出来事では、誤情報が削除・訂正されてからも排外主義的言動が継続的に拡散した点である。情報の真偽はなおざりにされ、信条や感情などにまかせて排他主義的言動がとられたと捉えられる点については、論理的かつ冷静に見直す必要があるだろう。とくに、さまざまな情報が飛び交う現代社会で他者と共生するさいには、ある出来事に対する言動を反射的かつ矢継ぎ早にとるのではなく、落ち着いて、時間をかけて冷静に考え、論理的に判断することが肝要になるといえる。
たしかに、わからないことへの不安や恐怖は簡単にぬぐい去れるものではない。「ホームタウン」をめぐる一連の出来事について、慶應義塾大学の塩原良和教授は、その背後に「外国人に対する排外主義や福祉排外主義があるのではないか」としつつ、急激に変化する現代社会において「あらゆる人々は根拠のない漠然とした不安」を抱いており、「脅威を設定し、攻撃することで安心感を得ようとするのが排外主義」だと述べている(9月15日朝刊)。それでは、外側に攻撃対象(スケープゴート)をつくらないかたちで排外主義を乗り越えるために参照できる視点や考え方としてはどのようなものがあるだろうか。
実際には身の周りで起きていない出来事を想定して不安や恐怖を抱くという想像力は、よりポジティブな別の出来事を想像する方向にも向かわせることができるはずである。言い換えると、不安や恐怖ではなく、わからないからこそ生まれる別の何かに注目することもできると思われる。
そのひとつとして、ここでは問いへの探究心を挙げたい。かつてマックス・ウェーバーは、著書『職業としての学問』(1936[1980]、尾高邦雄訳、岩波書店)のなかで、「学問上の『達成』はつねに新しい『問題提起』を意味する。それは他の仕事によって『打ち破られ』、時代遅れとなることをみずから欲するのである」(30頁、傍点原文)と論じていた。あらゆる事象の答えを導きだすことではなく、それらを問いつづけることはもどかしさや葛藤をともないうることではあるが、ウェーバーの議論をふまえると、学問では答えよりも問い──わからないこと──を出しつづけることが肝要になるということになる。そしてそれは、人間社会を対象とする学問である人文・社会科学ではいっそう重要になるということができる。
本リレー連載の第1期「「科学」と「技術」──大事なのはゴールか、プロセスか」(岡本智周著)では、「自然科学がもたらす技術にはゴールの実現を可能にする『目覚ましい成果』があり得るのに対して、人文・社会科学においては科学の営みと人間社会のあり様がお互いに影響を与えあって進展するプロセス自体に価値がある」と論じられていた。そのことをふまえると、自然科学と人文・社会科学を比較したさいに、前者は探究の結果として出される答えが重視される一方で、後者は答えそのものというよりも答えを導きだすための相互作用のなかでの探究プロセス自体に価値がおかれると捉えることができる。
後者の視点に関しては、「何を悠長なことを⋯⋯」と思われるかもしれない。しかしながら、時間をかけて人間社会におけるわからないことも含めた物事を冷静に判断することの重要性は、上述の「ホームタウン」にかかわる誤情報の拡散から始まった一連の出来事からも学ぶことができるだろう。
先に示した「ホームタウン」をめぐる一連の出来事の最中に、長井市が位置する山形県の吉村美栄子知事は定例会見において、誤情報が拡散されていることを「大変遺憾」として外務省やJICAに適切な発信を求めるとともに、国際交流自体への異議に対しては、「一時的な感情ではなく、落ち着いて、長い目で考えていただきたい」と訴えた(8月30日朝刊山形県版)。さらに、「長井市をはじめ県内には国際交流に熱心に取り組む自治体が多く、県も多文化共生社会を構築しようとしている。山形の発展のため、(外国人を含めた)皆さんのウェルビーイングにしっかり取り組んでいきたい」と発言したことが報道された(同上)。
誤情報が「ホームタウン」にかかわる一連の排外主義的な出来事の始まりであったなか、それを経てもなお、国際的な視点からの、地域における外国人とカテゴリ化される人びともそうではない人びとも共生できるような手立て──特定の個人や集団ではなく、あらゆる人びとのウェルビーイングの向上──に取り組むことが山形県知事により宣言されたのである。そして、その取り組みを「落ち着いて、長い目」で捉えることの重要性も述べられているわけであるが、それは、日々のなかで時間をかけて試行錯誤をしながら、社会における他者との共生を考え、取り組むことと言い換えることもできると思われる。
くり返しになるが、2025年の「ホームタウン」に関わる一連の出来事のきっかけは誤情報であった。そのことに関して、日本の外務省のウェブサイトでは、「「JICAアフリカ・ホームタウン」に関して」(8月25日)や「「JICAアフリカ・ホームタウン」に関するナイジェリア連邦共和国大統領府のプレス・リリースに関して」(8月26日)といったかたちで、またJICAのウェブサイトでも、「「JICAアフリカ・ホームタウン」に関する報道について」(8月25日)や「「JICAアフリカ・ホームタウン」に関する報道内容の更新について」(8月29日)といったかたちで記事が掲載されている。そこでは、「ホームタウン」に関わる事実関係や、ナイジェリア連邦共和国大統領府、The Tanzania Times(タンザニア共和国)やPremium Times(ナイジェリア連邦共和国)等による誤情報の発信や、その後の同大統領府やBBC News Pidgin(ナイジェリア連邦共和国)による報道の削除や訂正の状況に関する説明がなされているのである。
今回の「ホームタウン」にかかわる誤情報の発信と削除・訂正という一連の出来事からは、グローバル化時代においては、一国のなかだけに留まらないより大きな文脈も想定した対応が求められるということがあらためて確認されたといえよう。
さまざまな動きのなか、2025年9月25日に「ホームタウン」をめぐる出来事は急展開することになる。同日、JICAは記者会見を開き、「外務省や自治体と検討を進めた結果、依然として誤った情報が広がっており、自治体に抗議の電話やメールが相次ぎ、過度な負担が続いているとして、事業を撤回する方針を明らかに」したのである(NHKウェブサイト「JICA「ホームタウン」認定交流事業 撤回方針を明らかに」)。さらに、同日中にJICAのウェブサイトで、「「JICAアフリカ・ホームタウン」構想について」と題した記事が公開されるとともに、記者会見の動画のリンクが「「JICAアフリカ・ホームタウン」構想にかかるJICA理事長記者会見の動画公開について」として掲載された(翌日の9月26日には、「「JICAアフリカ・ホームタウン」構想にかかるJICA理事長記者会見要旨の掲載について」も公表された)。1か月で目まぐるしく事態が展開し、「ホームタウン」事業は撤回されたのである。
そのようななか、それらのJICAの記事や記者会見においては、今回の撤回は国際交流の後退ではないことが表明されていることを特筆することができる。上記の記事では、JICAとしては「『アフリカ・ホームタウン』構想を撤回した上で、今後も国際交流を促進する取組を支援していく考え」が表明されている。「ホームタウン」をめぐる一連の出来事のあとでも、ひきつづき国際交流を積極的に推進していく方向性がJICAから発せられたのである。言い換えると、排外主義に抗うことにつながる取り組みへの支援の継続が表明されたといえる。
最後に、わからないことに対する不安や恐怖から排外主義的言動につながる経路を避けるための方策のひとつとして、一人ひとりの人間の現実の日常的な関係性の積み重ねのなかに人間社会の可能性を見出す視点を示したい。それはすなわち、想像上の他者とではなく、実際に存在する他者を想定して、現実の社会にねざして共生を考えることにほかならない(上述の人文・社会科学のうち、とくに社会学の観点から、現実の社会におけるプロセスとしての他者との共生〈“living together”〉について議論した書籍として『多様性と凝集性の社会学』〈とくに第3章〉も参照されたい)。グローバル化時代においてそのような視点をもつことは、日本社会だけの議論に留まらずに──かつ排外主義に陥らずに──、他の社会の文脈における共生を考えることにも展開する可能性を秘めていることからも重要であると思われる。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
岡本智周編著『多様性と凝集性の社会学──共生社会の考え方』太郎次郎社エディタス、2025年.
塩原良和『共に生きる──多民族・多文化社会における対話』(現代社会学ライブラリー3)、弘文堂、2012年.
マックス・ウェーバー著、尾高邦雄訳『職業としての学問』岩波書店、1936[1980]年.
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
坂口真康(さかぐち・まさやす)
大阪大学大学院人間科学研究科准教授。筑波大学大学院3年制博士課程人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻修了。博士(教育学)。専門分野:教育社会学、比較教育学、共生社会論、共生教育論。
主要著作:
『「共生社会」と教育』春風社、2021年
『共生の社会学』共著、太郎次郎社エディタス、2016年
『SDGs時代にみる教育の普遍化と格差』共著、明石書店、2023年
『「途上国」から問う教育のかたち』共著、左右社、2025年
『多様性と凝集性の社会学』共著、太郎次郎社エディタス、2025年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)