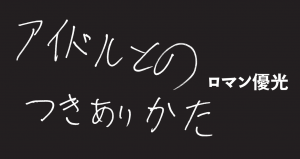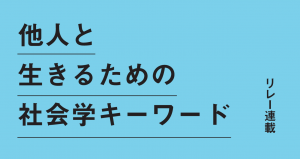〈公正(フェアネス)〉を乗りこなす│第2回│「正義」の模範運転とジョン・ロールズ│朱喜哲
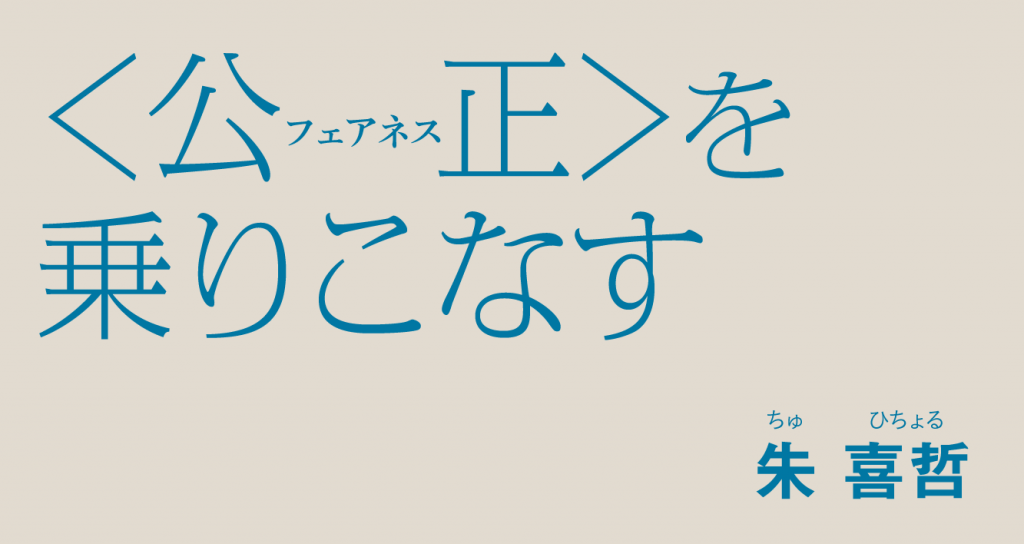
そのことばの使いこなし方をプラグマティズム言語哲学からさぐります。
第2回
「正義」の模範運転とジョン・ロールズ(公開終了)
アメリカ大統領選挙をとりまくことば
・・・・・・・・・・
■この連載が本になります(2023年8月29日発売、定価2200円+税)
2020年12月から全12回にわたって、著者が「公正」とはなにか、「正義」とはなにか、そのことばの使いこなし方をプラグマティズム言語哲学からさぐってきた本連載を、2023年8月、『〈公正〉を乗りこなす──正義の反対は別の正義か』として、書籍化しました。全編にわたり大幅に加筆修正を加え、「正しさ」とはなにかを考えるうえで、わたしたち自身の〝ことばづかい〞を通して「正しいことば」をとらえなおす画期的論考となっています。ぜひご一読ください。
朱喜哲(ちゅ・ひちょる)
1985年大阪生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。大阪大学社会技術共創研究センター招へい教員ほか。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。前者ではヘイトスピーチやデータを用いた推論を研究対象として扱っている。共著に『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』(さくら舎)、『世界最先端の研究が教える すごい哲学』(総合法令出版)、『在野研究ビギナーズ』(明石書店)、『信頼を考える』(勁草書房)など。共訳に『プラグマティズムはどこから来て、どこへ行くのか』(ブランダム著、勁草書房)などがある。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)