科学のバトン│第11回│生活のなかで学び、自然のなかで研究する│平林浩(出前教師)
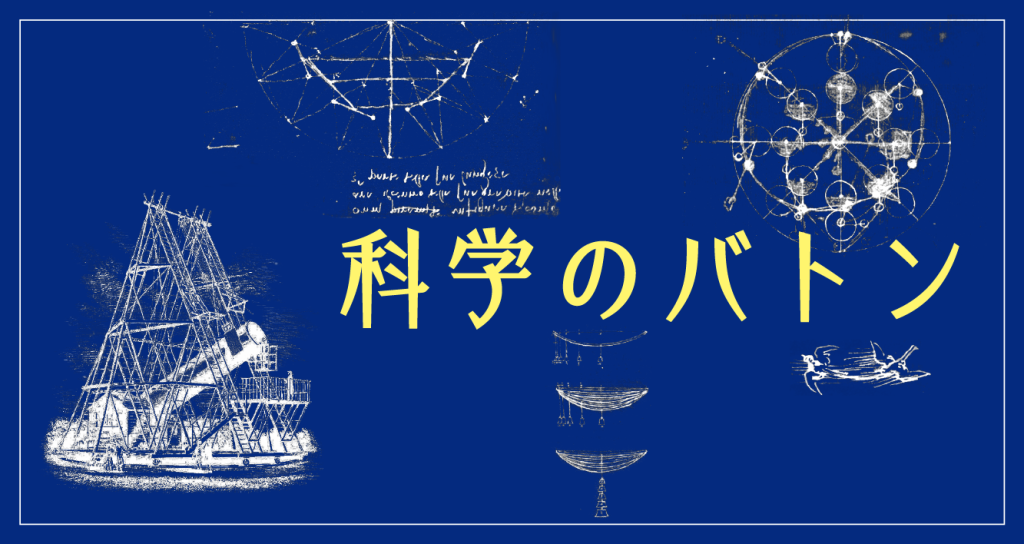
生活のなかで学び、自然のなかで研究する
体験から科学研究へ
平林浩(出前教師)
恩師略歴●清水三雄(しみず・みつお/1910-1967):
茨城師範学校、東京文理科大学生物科卒業。厚生省から小児衛生に関する研究を嘱託される。理学博士(東京大学)、信州大学教授。人間の成長、各種の動物の相対生長の研究で医学博士(新潟大学)。著書に『動物の生長』(北隆館)など多数。
恩師略歴●羽田健三(はねだ・けんぞう/1921-1994):
長野師範学校、東京師範学校卒業。鳥類を中心に生態学を研究する。理学博士(京都大学)、信州大学教育学部教授。長野県の鳥類・哺乳類の生態研究、保護活動を進める。そのもとで山岸哲、中村浩志などの鳥類研究者が育った。著書に『信州の鳥』(白馬書房)など。
・・・・・・・・・・
5歳のころの原風景
8月末、田んぼの稲の穂の先の実がふくらみはじめ、穂先が傾いてくる。そのころになると、田んぼのあちこちで、突然「パアーン」と大きくはじけるような音が響きわたる。
その年巣立ったスズメたちが何十羽も群れになって、傾きはじめた稲穂の実を食べにやってくる。実の中身はまだ固まっていなくて、くちばしではさむと白い乳のような汁が出てくる。スズメたちは、この汁をつぎつぎとついばむ。何十羽ものスズメがやってきて、米粒になるまえの実をかたはしからついばんでいく。米を育てる農家にとっては大きな被害を受けることになる。
「パアーン」と音が響くと、田んぼからスズメが群れて飛び立ち、遠くまで飛び去っていった。「スズメおどし」とよばれていた、大きな音を出す装置があった。
わたしの父親は小学校の教員で、転勤によって長野県諏訪郡永明村に住むようになった。わたしが5歳のときだった。遠く東に八ヶ岳の連峰を望み、その広大な裾野の末端に位置する村で、現在は茅野市となっている。
借家には小さな庭があり、幅3メートルほどの小路と、粗末な板塀で仕切られていた。小路の向こう側は田んぼが2枚あり、その先に人家があった。5月、田んぼに水が入ると、アマガエルとトノサマガエルの合唱がはじまり、その音はみごとなものであった。
スズメおどしのやり方を教わる
わたしの家の前に広がる田んぼは、竹村さんという農家の田んぼだった。竹村さんはほかにもたくさんの田んぼを持っていた。わたしは小学校5年生(当時は国民学校)のころから、竹村さんの家の稲刈りや田植えを手伝うようになった。竹村さんの家のおじさんは、わたしにいろいろなことを教えてくれた。稲の借り方、稲苗の植え方、蚕の飼い方などなど、ていねいに教えてくれた。おかげで、農業の仕事を身につけ、中学生のころにはじゅうぶんな働き手になった。
5年生のときだったと思う。スズメおどしの使い方を説明され、使ってみることをすすめられた。スズメおどしはかんたんなつくりだった。直径6〜7センチぐらいだったろうか。長さ1メートルほどのブリキの筒がある。その筒の下方には木のくいが差しこんである。くいは筒の穴をふさぐと同時に、田のあぜなどのやわらかい土に差しこむことができるように先がとがらせてあった。
木のくいが筒をふさいでいるあたりより少し上のブリキ筒には、直径5ミリぐらいの穴があけてあった。そこからさらに10センチほど上に、同じぐらいの大きさの穴がある。おじさんは、筒の上の口から灰色の小石のようなかたまりを落としこんだ。灰色のものは、独特なにおいがあった。学校へ行く途中にある鍛冶屋のところでも同じようなにおいがしていた。
「これはカーバイトというものだよ。これに水をかけると、どうなるか」
おじさんは、土の上に置いたカーバイトのかたまりに、少し水をかけた。カーバイトからブジュブジュと泡が出て、かたまりがくずれていった。においはさらに強くなった。
「いま出ている泡は、アセチレンガスというガスで、よく燃えるんだ」
おじさんは、筒の下の穴から水を注ぎこんだ。
「こうやって、ちょっとのあいだ待つ。アセチレンガスが筒のなかにたまってきたら⋯⋯」
おじさんは、マッチに火をつけ、上の穴に近づけた。
「パカーン」
目の前の筒の先端から薄い煙のようなものが出ると同時に、乾いた大きな音が鳴り響いた。
「アセチレンガスと空気がまじったところに火を近づけると、爆発するんだ。筒の先に顔を近づけたりしちゃあぶないから、ぜったいにするなよ」
「やってみな」
ジュブジュブとカーバイトから泡が出ている音が弱くなったころ、わたしはマッチに火をつけ、上方の小穴に炎を近づけた。マッチの炎が穴にすっと吸いこまれたように見えた瞬間、「パカーン」とも「ドカーン」とも表される音が筒の全体を振動させ、広い田んぼの上を響きわたった。
その後、何回かわたしは、そのスズメおどしを鳴らせる役目をはたした。
石灰石と火打石
ものの変化といえば、竹村さんに教わったことで、はっきりと心に残っていることがまだある。
ひとつは、生石灰に水をかけ、消石灰にして田んぼに入れるときの変化である。石灰を田畑にまいて、酸性の土壌を改良する。また、殺菌作用もある。石灰を土にまぜると、酸性土壌が中性、またはアルカリ性になり、作物の出来がよくなるということは、のちに知ったことだが、生石灰を消石灰にするところがおもしろかったのだ。
おじさんは、袋から出した白っぽい石を、田の端の地面に広げた。さわってみると、けっこう固い石だ。
「これは、生石灰っていうもので、石灰石という石を焼いてつくるんだ。これに水をかけるとな⋯⋯」
水路の水をバケツにくんで、広げた生石灰の上にザーッとふりかけた。すると、あの固い石が、モヤモヤと湯気を上げながら、くずれていく。くずれるまえに、ホワーッとふくれあがる。
「気をつけな、熱いよ」
たしかに熱気が伝わってくる。端の1個にさわってみると、「アチッ」と言ってしまうほど熱かった。おじさんは冷めるのを待って、それを田んぼにまいていった。石灰石という石、それを焼いた生石灰、それに水を加えると起こる激しい変化。これも、ものの変化への関心をかきたててくれた。
もうひとつ印象に残るのは火打石のことだ。
おじさんが田んぼや畑の仕事でひと息入れるときは、決まって腰に下げた入れものから火打石と火打金をとり出し、キセルにきざみ煙草をつめた。しっかりふたをした小さな入れものから、指先にほんのひとつまみの黒い綿のようなものをとり出し、火打石と指のあいだに入れて、おさえた。右手で火打金を持ち、左手に火打石を持って、さきほど黒い綿のようなものと火打石をはさんだあたりに、火打石を「カチッ」と打ちつけた。火花が飛んで、綿のようなものに火がついた。
おじさんは右手にキセルを持ち、左手の綿のようなものの火でキセルの雁首のきざみ煙草に火をつけ、おいしそうに煙を吸いこんだ。さらにもう一服というときは、キセルの雁首を、左手の手のひらに打ちつけ、まだ火がついている煙草の小さなかたまりを、手のひらにころがし、右手で雁首に煙草をつめ、左手の火種から火をつけた。その手ぎわのみごとさと、手のひらに火がついたかたまりをのせて、火傷もしない頑丈な手に感心しながら見ていた。
火花から火をつける綿のようなものは「火口」とよび、ホクチとよばれる草の葉の裏にある綿毛や、脱脂綿のような細い植物の繊維に、炭の粉をまぶしたものだと教えてくれた。火花の正体や、火打石と火打金をぶつけるとなぜ火花が出るのかなどを知るのはのちのことだが、当時売られていた火つきの悪いマッチよりも、このほうが確実であることに驚いた。
自然の現象や生きものへの関心は、ほとんど父親から学んだ。わたしが、自然への関心をいまも強くもっているのは、父親が、季節の行事や、山菜採り、キノコ採り、魚釣り、鳥を観る会などに、いつも連れていってくれたことが原点である。また、近所のおじさんや、父の従兄弟から教わったこともたくさんある。これらについて書きだせば、長い長い話になってしまう。
清水三雄先生のもとで爬虫類の相対成長を研究
家から通える大学として、信州大学教育学部に願書を提出した。わたしは、大学へ行って高校とは違う勉強ができるというだけでうれしかった。教師になりたいという意志がはっきりしていたわけではなかった。受験勉強などまったくしていなかったが、幸い入学を許可され、まず松本分校で2年、そのあと長野の本校で2年学ぶことになった。取得する教員免許は中・高理科で生物専攻を希望した。これも幸い希望どおりになった。
中学、高校の免許取得のためには、指導教官に指導を受けることになっていた。わたしは生物学のクラスに属することになった。担当の教員は清水三雄先生だった。4年間、この先生のもとで勉強し、卒業論文を書き、提出するのだ。
清水先生の研究室は生物講義室に接していて、思いのほかせまい部屋だった。講義室をはさんで準備室があって、標本などが並んでいた。この準備室が、わたしたちクラスのメンバーの居場所だった。クラスのメンバーは2年生3人、わたしをふくむ1年生も3人。」
清水先生の当時の研究は、「動物の相対成長」だった。わたしにとって「相対成長」ということばは、はじめてのものだった。相対成長というのは、ある部分が時間にともなってどのくらい変化したかを見るのではなく、身体の各部位の成長が相対的にどう変わっていくのかを、総体的に見ていこうというものだ。清水先生の講義で、それらの研究の意味は少しずつわかっていった。
そのころの清水先生の研究は、鳥類の骨格や各部位の相対的な成長についてだった。何冊かの論文の抜刷をいただいた。鳥類の各部位の測定値の相関を計算し、分類上の種の特性などにもおよんで検討されていた。しかし、わたしにはそれを読みとることはまだ難しかった。
清水先生はわたしたちに向かってはっきりこう言っていた。
「教育の勉強などしなくてもいい。しっかり研究することだ。研究をしっかりしていれば、生徒はそれを見て学ぶから」
このことばどおり、講義は生物学と動物進化にかかわることだった。それらは、わたしに生物学への目を開いてくれた。
清水先生は、わたしに爬虫類の骨格の相対成長についての研究をするようにすすめてくれた。清水先生はトノサマガエルを中心に両生類での研究をすでにやっていたが、爬虫類については手をつけていなかったからであろう。トカゲやカナヘビ、ヤモリならそのへんでかんたんにつかまえられる。わたしはそのテーマでやってみることにした。
トカゲの骨の測定値をまとめ、ふたつの骨の成長の相関係数を求める計算はたいへんだった。まだ電卓などはない時代。手まわしの計算器でガチャガチャ・チーンとやかましい音をたてながら計算をした。この研究の成果はわたしが2年生のとき、信州大学教育学部研究論集に発表されることとなった。清水先生は、ぜんぶ英文にしようと言う。「それは無理です」と言わざるをえなかった。「それではsummaryの部分だけでも書いてみたら」と言われた。
1953年3月、この論文は活字になった。その論文の抜刷はいまも手元にある。
Studies on Kineto-adaptation Ⅳ
On the Index of the Limb Bones in a Kind of Lizard.
Mitsuo SHIMIZU Hiroshi HIRABAYASHI
卒業論文はこの研究の続きであった。
羽田健三研究室での鳥類調査の日々
大学3、4年は、長野市にある教育学部の本校で、教育免許を取得するための講座を受講し、実習をする。松本までは諏訪にある家から通えたが、長野までは無理だった。片道4時間ほどもかかってしまうから、列車で通うことはあきらめた。友人と部屋を借りて自炊生活をすることにした。
松本分校の清水先生が指導教官であることは変わりないが、実質的には、本校の生物研究室が拠点となった。本校の先生は羽田健三先生で、その研究室が日々を過ごすところになった。羽田先生は鳥類の研究で名を知られていた。わたしもその名は知っていた。わたしは父親に野鳥を教わって、鳥を観ることが好きだったから、羽田先生とは話が合った。
羽田先生は鳥の分類の研究もしていたが、おもには生態の研究であり、長野県の湖沼の水鳥の生態調査が多くの論文になっていた。わたしが多少野草の名を知っていることがわかってから、戸隠や黒姫山、妙高山、志賀高原方面の鳥類調査にいっしょにいった。野鳥の観察の記録をとっていくのだ。
植物分布、標高などとともに、季節によってどんな鳥がいるかを調べた。黒姫山の調査にいったとき、朝の列車で出かけ、麓から頂上へと標高による鳥の分布の調査をしながら登っていくうちに、道がわからなくなってしまった。背丈をはるかに超すネマガリダケをかき分けかき分け登った。自分がどこにいるのかわからず、見当もつかない。ネマガリダケは、びっしり生えていて、歩を進めるのもたいへんだった。途中、木によじ登ってまわりを見渡そうとしたが、だめだった。鳥や植物の調査どころではなくなってしまった。
なんと、黒姫山の頂上にたどり着いたら夕方の5時になっていた。それから、山を下って麓に来ても、もう列車もなく、夜を徹して長野まで歩いて帰った。夜が白々と明けるころ、長野に着いた。
志賀高原に、信州大学の自然研究所がつくられた。そこに数日合宿して、鳥や植物の調査にあたった。そのときは天候に恵まれず、ほとんど調査ができなかったことも記憶に残っている。
戸隠探鳥会をはじめる
戸隠高原と、戸隠神社の原生林はたくさんの種類の鳥が生息しているところだった。当時、NHKのラジオ放送で、5月初めの愛鳥週間になると、戸隠高原の小鳥のさえずりの声が実況放送で全国に流れていた。
羽田先生と、その研究室のメンバーに、わたしも加わって、戸隠に鳥や植物の調査にいった。越水ヶ原というところに行ったとき、あたり一面を埋めつくして咲くカタクリの花に心をうばわれた。宿坊に泊まって夜の鳥の調査をしたこともある。夕食のそばがおいしくて、たらふく食べたことも思い出だ。
夜が明けると、小鳥たちがいっせいにさえずりだし、個々の鳥の声を聞きわけることができないほどだった。この豊かな鳥の声を街の人たちにも聞いてもらおうということになった。「戸隠探鳥会」の最初の試みだった。
戸隠で見られる鳥を参加者に説明するために、わたしは鳥の絵を描いた。説明も担当することになった。夕方、長野を出発して歩いて戸隠に行く人もいたし、わたしもそうした。夜10時に宿坊に集合し、夜の鳥の声を聞いたり、説明会を開いたりした。参加者は仮眠をとり、朝4時に宿坊を出た。予想以上の数の参加者だった。
夜明けのみごとな鳥のコーラスを聞き、鳥の姿を探し、朝8時に解散した。いまでも森林植物公園のなかに探鳥会を記念する石碑がある。探鳥会は毎年開催されていったということだ。
羽田先生は、ああしろ、こうしろと言うのではなく、じっさいの行動で、わたしに野外観察や活動のしかたを教えてくれた。わたしは教員になってから、カラスのねぐら集合の研究で学会誌に論文を発表し、また総会で発表もしたが、1962年ごろ、教育に打ちこむことを心に決めて、教育研究のほうに舵をとった。
(次回に続く)
平林浩(ひらばやし・ひろし)
1934年、長野県・諏訪地方生まれ。子ども時代から野山を遊び場とする。1988年まで小学校教諭。退職後は「出前教師」として、地域の子ども・大人といっしょに科学を楽しむ教室を開いている。仮説実験授業研究会、障害者の教育権を実現する会会員。
著書に『仮説実験授業と障害児統合教育』(現代ジャーナリズム出版会)、『平林さん、自然を観る』『作って遊んで大発見! 不思議おもちゃ工作』『しのぶちゃん日記』(以上、太郎次郎社エディタス刊)など、津田道夫との共著に『イメージと科学教育』(績文堂出版)がある。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)



