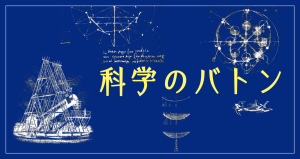本だけ売ってメシが食えるか|第1回|雑本屋としての古本屋になりたい|小国貴司

第1回
雑本屋としての古本屋になりたい
入り口としての本屋
古書店は専門店が多い。なぜだろうか? まずは仕入れのことから考えてみよう。
お客さんから買取をする場合、どんなにその人が専門をもたなくても、「売る」人が、もともとほかの本屋で「買った」人である以上、なんらかの嗜好がかならずある。「雑多にいろんな本を読んでいるんですよー」という人でも、古本屋が見たらそのパターンのようなものはつかめる。そうしてその蔵書は、自然と専門性(もしくはそれらしきもの)を帯びていく。
本集めをする人の、その「嗜好」を買うのが古本屋なのだから、そして古本屋がそこからさらに買取したものを仕分け(店に並べる、均一に出すなど)するわけだから、ひとりのお客さんからの大きな買取があれば、おのずと店じたいがある一定の方向に歩みはじめる。
また古本屋どうしで取引する市場には、そのような買取をしたままの一口もの(ある人の蔵書が、そのまま市場に出品されたもの)がでることもよくあるし、そのような蔵書の一部を、各店が競りあって買っていくのだから、その品ぞろえには、古本屋自身のなんらかの「目利き」を皆無にすることは不可能だろう。そうしてそのようにして手に入れた本は、少ない流通量であればあるほど(そしてもちろん需要はあるという前提で)値付けが強くなる。
この最後の要素がけっこう大きくて、100万円で買ってくれる人がひとりいれば、それは100万の価値になるわけだ。そして100万円の本を1冊売ったほうが、100円の本を大量に売るよりらくなのは明白である。だからこそ、100万円の本を売るために、おのおのの商売が専門化していくことになるのだ。ただでさえ専門性を帯びた本を買い、そしてさらにそこから1冊を選り分ける。古書店が専門化していく所以だ。
では、新刊書店はどうなのか?
これまでの常識で考えれば専門店になるメリットよりも総合書店になるほうのメリットが大きかっただろう。なにより値付けと粗利をコントロールできない新刊では、専門店化して集めることができる売上よりも、各ジャンルのベストセラー、ロングセラー、そして雑誌を効率的に販売したほうが得られるお金は大きい。それなので必然的に総合書店化していきやすいわけだ。
では、うちのお店は古本屋として専門店化していくのか? (ごくごくわずかに)あつかっている新刊では総合書店を目指すのか? いや、まったくの逆である。
古本屋としては、総合書店を目指し、新刊に関しては、専門店化していく。これがうちのお店の現時点での方針だ。
なぜなら、新刊書店はもう総合書店を目指せなくなるし、そうなれば「読書の入り口としての本屋」は、古本屋である。より正確にいえば、うちのお店のような雑本屋としての古本屋でなければ担えなくなると思っているからだ。
もちろん総合書店としての新刊書店がゼロになるわけではない。ただ商店街に1軒はかならずあったような、家から徒歩圏内にあったような書店が、これまでのかたちで存続していく、というのは、これからはよりいっそう厳しくなるだろう。というか、新刊書オンリーで、持ち家でもなく、あるていど若い世代の人間が、家業として本屋を選択する未来というのは、現実的とは思えない。
いっぽうで、ほかにもインカムを得ながら、書店もおこなうというような本屋はこれからも増えるだろうし、そういう人たちは売りたい本もやりたい本屋もビジョンがはっきりしているわけだから、おのずと雑本屋にはならないだろう。
絵本専門店、料理本専門店、文学専門店といったように、少ない坪数でも、あつかうジャンルを絞れば、じゅうぶん全国から集客することは可能だ。いわばそのようなお店では店主の個性そのものがお店の個性となるわけなので、それにマッチするお客さんとの太いつきあいがお店の収益となる。そしてそのようなお店では、もちろんじぶんの売りたいものだけ、勧められるジャンルの本だけをあつかうわけだから、やりがいもひじょうに高いだろう。
いわばマスを相手にせずとも商いとして成立し、不足する収入は、別で得る。生活のための仕事とやりがいのための仕事。その後者を、これからの書店は担っていくのではないか? そう思っている。
でも、それで本当にじゅうぶんか? 僕が個人的に本屋を好きになったきっかけは、専門店ではない。むしろなんでもないようでいて、たしかにあらゆる方向へ本の世界が広がっている。そういう本屋が好きだった。そしてそれを入り口にして、いろいろと細分化された本の世界に向きあっていく人もいる。入り口のための本屋。これからそれを担うのは、雑本屋としての古本屋だと思っている。
だれの心のなかにもある「アビリティ」
東京には新刊の「セレクト書店」が多い。
選書することが、ほぼイコールでいい本屋の条件のように語られる。町にある小さな本屋ですら「いい品ぞろえ」を期待されていて、自分の欲しい本がたまたまそんな本屋にあったりすると「わかっている本屋」と言われる。店主の好みに準じた棚をつくれば、「思いのある本屋」と言われるし、日々配本されてきた本だけを並べている本屋は、金太郎飴と罵られる。
でも、本当にそうなのだろうか? よい本屋=選書している本屋、なのか?
そう思ういっぽうで、どこか見知らぬ本屋に行ったとき、そうやってその本屋の品ぞろえを、だれよりも評価してしまっているのは、ほかならぬ僕自身だ。なんの考えもなしにヘイト本が平積みされまくっていると「おいおい。ちょっとは本を選べよ」と苦笑してしまうし、ふつうでは配本されないような出版社の本が棚に差さっていると、なんだか仕事している本屋だなと思ってしまう。
昔10坪ほどの駅ナカの本屋の棚に『ギンズバーグ詩集』が差さっているのをみて、「本屋としてはわかる。でも商売としては圧倒的にまちがっている」と思った僕は、何様なのだろうか? たぶんちょっと偏屈な、でも偏屈すぎるとはいえない古本屋の店主なんだろう。
本屋は小学校のころから好きだった。母親の買い物につきあって行ったときの楽しみは本屋。そのころのスーパーには、いまでは信じられないことだが、小さい本の売場がかならずあった。どのスーパーに行っても、そこにある小さな本屋の図鑑のコーナーで時間をつぶしていた。本は比較的すんなり買ってもらえるものだったので、小さめの図鑑や、漫画雑誌(小学生のころは『まんがタイム』が大好きだった)、たまに歴史のうんちくが書かれたような文庫本を買ってもらっていた。
8つ離れた兄は、たまに文庫本を買っていて、太宰治『人間失格』の新潮文庫を手にしていた光景はいまでも覚えている。あの真黒な背に書かれた『人間失格』という文字のインパクトに、子ども心に兄が心配になった。「だいじょうぶ。君は失格なんかじゃない」と肩を叩きたい気分にもなったが、それが読書感想文という地獄のために用意された本だったから、まぁ、なんとなく地獄らしくていいか、と思った記憶がある。
じぶんが高校生になったときは、家のとなりに新刊本屋とレンタルビデオ屋(!)で売場を半分ずつシェアしあった店があった。TSUTAYAっぽい店づくりだが、名前は「アビリティ」という本屋だった。あ、たしか中古ゲームも置いてあったことをいま思い出した。その当時のカルチャー界隈の商材で「お金になりそうなものをいっぱい集めてみました!」というお店だったということかもしれない。
お店によくいたのは、20代後半から30代くらいの若いお兄さんたち。おそらく、映画と音楽が好きだったんだろう。CDと映画は、B級アクション映画もふくめて、けっこうとがった品ぞろえだったように思う。
でも、本の売場にこれといった印象はなかった。もしかしたら自分が受け取れなかっただけかもしれないが、少なくとも、いまのような選書センスで勝負するような本屋ではなかった。毎月でる文庫の新刊をチェックして、たまに村上春樹の小説を買うくらいの本屋だった。少なくとも僕にとっては。
でも、不思議なことに、いまでもこの「アビリティ」に行く夢をたまに見る。夢のなかでも、僕は文庫の棚で新刊をチェックして、あまりテンションが上がるわけでもなく、淡々と本を選んでいる。通路が交わるところにある、少し暗くなっている集英社文庫の棚で「なんかおもしろそうな本でてないかなー」と思いながら立ち読みしている夢を見ると、起きてから10秒くらいはしみじみと「いいお店だったよなぁ、アビリティ」と思うのだ。
僕が小学校から高校までを過ごしたのは、80年代後半から90年代中盤の時代。ちょうど出版の売上がそのピークを迎えていたころだ。このころは、おそらく、本をセレクトしていた、という感覚は、本屋にあまりなかったのではないか?
それこそ僕が働いていたリブロや一部の本屋が、当時その選書を売りにできたように、そしてそれがとても新鮮な行為だったように、ほかの大多数の本屋、とくに町の本屋にとっては、本を選ぶことよりも、新しい本が配本されてきたら、古い本を順番に返すことが仕事だった。そして、棚には出版社のランクやおすすめの本をただただ補充する。これが仕事のほとんどだったのではないだろうか。そして、消費者の側も、それを幸福に享受していた時代。
その売上がだんだんと下がっていくにつれ、本屋の競争は激化し、町の本屋でさえ、差別化をしなくてはならなくなった。どこと差別化する? もちろんAmazonと、だ。
いままでただ入れ替えておけばよかった新刊も、それが売れなくなっていくのだから、売れる棚をつくらなければならなくなる。小さな本屋であればあるほど、「何をお店に並べるか?」という個性で勝負しなくてはならなくなる。
でも、僕はあの牧歌的ともいえる青春時代の本屋が好きだ。なにも選んでいないように見える本屋。新しい本が毎日入ってきて、それに押し出されるように既刊が返品されていく本屋。
セレクトされていない本屋、がいまの時代に無理なのであれば、せめてセレクトしていないようでいて、セレクトしている本屋、どこかあの牧歌性を残している本屋。そんな本屋がつくりたい、とそう思う。
みんなだれでももっているでしょ? 心のなかに、あなたの「アビリティ」を。
小国貴司(おくに・たかし)
1980年生まれ。リブロ店長、本店アシスタント・マネージャーを経て、独立。2017年1月、駒込にて古書とセレクトされた新刊を取り扱う書店「BOOKS青いカバ」を開店。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)