科学のバトン│第5回│ヒントは出しても答えは与えない│毛内拡(脳神経科学者)
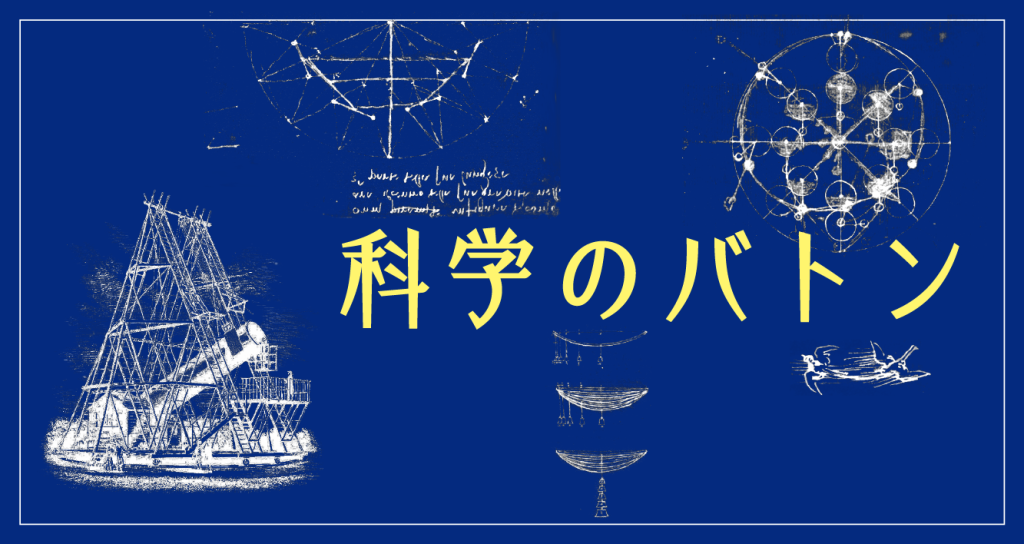
ヒントは出しても答えは与えない
師から教えられたこと
毛内拡(脳神経科学者)
恩師略歴●宮川博義(みやかわ・ひろよし/1951年-):
東京薬科大学名誉教授。東北大学理学部化学科卒業。東北大学医学部医学研究科修了(医学博士)。山形大学医学部、ニューヨーク医科大学を経て、東京薬科大学生命科学部助教授、教授を歴任。脳神経機能学研究室主宰。イメージング技術をもちいてネズミなどの海馬ニューロンの特性を研究してきた。2016年に退職。主著に『ニューロンの生物物理』(井上雅司との共著、丸善出版)がある。
・・・・・・・・・・
はじめまして。私は、都内の大学で脳神経科学の研究をしています。脳細胞や脳内物質など、ハードウェアとしての脳の働きについて研究することをとおして、脳組織がどのように「心の働き」や「人間らしさ」を生みだすのかを解き明かし、「人間とは何か」という大きな問いに少しでも答えを見つけたいと思っています。
幸運なことに先生とよばれる職業につき、小さいながらも研究室を主宰させてもらっています。今回と次回にわたって、この「研究室」にまつわるエピソードを軸にお話をしてみたいと思います。そもそも理系の大学の研究室って、いったいどういうところなのでしょうか。私がめざしている理想の研究室の姿についても、ご紹介したいと思います。その背景には、ひとりの恩師との忘れがたき日々があります。
私にとって「よい先生」とは
ふり返ってみると、これまで多くの「恩師」に恵まれた人生だったと思います。この文章を書くにあたって、あらためて自己分析をしてみましたが、ひょっとするとそれは、単純で人を信じやすく、先生とよばれる人だったらだれでもすぐに影響を受けて、恩師とみなしてしまう私の性格によるのかもしれません。これは得な性格なようですが、自分のなかに確固たる核をもっていないことの裏返しなのかもしれません。もう立派な大人だというのに、いまだに「きっといつか白馬に乗っただれかがやってきて、あっというまにすべてを解決してくれる。早く来てくれないかなあ」などと思っています。どうしてなんでしょう。
お導きくださいと、エサを欲しがる金魚さながら口を開けて待っていますが、ところがどっこい、よい先生ほど、すぐにはエサを与えてくれないものです。よいエサの選び方、そしてエサのとり方を教えてくれるのみです。たしかに、これまで出会ってきた恩師たちはみな、すぐに答えを教えることはせずに、自分で考えるためのあいまいなヒントをくれるだけでした。私が浴びせかける禅問答のようなやりとりにも根気よくつきあってくれました。
結局、白馬の王子さまは待てど暮らせどやってこないので、ない知恵を絞って自分の頭で解決せざるをえない。そんな行き当たりばったりの連続で、ここまでやってきました。いまにして思えば、じつはこれこそが最大の「恩師からの学び」だったのでしょう。ひと言でいえば、「何ごとも自分の頭で考えるのだ」ということです。
脳研究を志した理由
そんな糸の切れた凧のように、風に吹かれるまま、気まぐれにどこへでも飛んでいきそうな私ですが、人生のなかでこれだけは自分の力で最後まで考えぬきたいという問いがあります。それが冒頭に述べた「人間とは何か」というものです。
そのきっかけは高校生のころにさかのぼります。当時所属していたボランティアクラブの活動の一環で、同世代の重度知的障害の人たちといっしょに運動会に参加しました。参加するまえは、かれらと自分とはぜんぜん違うのだろうと偏見をいだいていましたが、かれらも、勝てばうれしいし、負ければくやしいし、お昼になればおなかが空き、トイレにも行きたくなる。そんなあたりまえのことに気づかされると同時に、偏見をいだいていた自分がはずかしく思えました。
そのとき、まだ17歳かそこらでしたが、人生観が一変するような衝撃を受けたことをいまでも覚えています。かれらと私とはほんの少しの違いしかない。何が違うのだろう。「人間とはなんだろう」という問いが頭をもたげて、離れませんでした。
さまざまな書物に答えを探しましが、自分が求めているような解は見つかりませんでした。ただ、調べを進めていくなかで、「脳」こそが、心や私たちの性格などに関与しているかもしれないことがわかりました。私が求める答えは「脳」のなかにあるにちがいない、もし答えがないなら、自分でその謎を解き明かしたいと強く思い、脳の研究を志しました。
病気を治すことに重点をおく医学よりも、基礎的な生物学や生命科学の観点から脳の研究がしたい。インターネットの検索で、「脳 研究 できれば東京」というようなキーワードで引っかかってきたのが、東京薬科大学生命科学部の宮川博義助教授(当時)でした。この先生のもとで勉強したいという強い動機で、進路を選びました。
失敗に大喜びしてくれる師
おそらく、私が宮川先生に惹かれたのは、実験家として一流でありつつも、脳神経のような生命現象に対しても最終的には数学的に理解したいという根本にある思想や哲学の部分なのだと思います。
宮川先生は、少し変わった経歴で、脳神経の研究をはじめるまえは、量子化学とよばれる分野で難しい数式を取り扱うような理論的な研究をされていました。そこから一念発起して、神経科学の実験分野に転向し、長らくアメリカで研究をしたのちに日本に帰ってきて、東京薬科大学生命科学部で教鞭をふるいました。
大学では、ゼミとよばれる縦割りの制度があり、入学すると、自分の好きな教員のもとで卒業するまで面倒を見てもらうことができます。私は、迷うことなく宮川ゼミを選択し、そこからどっぷり9年間、宮川先生にお世話になりました。ゼミでは、週に1回本を輪読したり、議論したりする時間があり、私にとっては夢のような時間でした。
宮川先生は、少年ならだれしももっているヒーロー像のような、いつもニコニコしていて、ポジティブで、温厚でほがらかでやさしい、お日さまのような、私の元気の源のような存在です。いっぽう、よく忘れものをするなどちょっと抜けている部分もあって、お茶目な部分もあったりします。
ところが、研究のこととなると目の色が変わります。わからないことはわかるまでとことん追求する姿は、知的好奇心の塊のようですし、逆にわからないことが増えると、「うーん、わからん」と言いながら目がキラキラしているのも印象的でした。研究が思いどおりの結果にならなかったときは、これはこれでおもしろいと、ものすごく興奮されるのです。私は思いどおりにならなくて残念だと思っていたのに、先生があまりにも喜ぶので、自然と「失敗した」という気持ちもなくなっていました。失敗しても喜んでくれる上司なんて最高じゃないでしょうか。
いま思えば、それは、ものすごく仮説の立て方がじょうずだったのだと思います。私はここから、研究というものには「失敗」という概念はなく、研究の仮説を立てるときは、どっちに転んでもおもしろいと思えるような仮説を立てるべきであることを学びました。
宮川先生の指導のなかでは、とくに、作文に対する親身な指導が印象的でした。理系には国語は必要ないと思ったら大まちがいです。理系ほど国語力が問われるものはありません。研究計画書の最初の原稿は、真っ赤になるまで隅から隅まで添削してくださり、とことん議論して改良を加えます。しかし先生は、できなくてあたりまえと言います。最初からできる人はいない、ただ訓練が必要なのだと。そのあたりの、私の骨身に染みついた研究者としての作文や考え方については、後編の次世代への学び編でくわしく説明したいと思います。
脳科学の裏街道を行く覚悟をくれたことば
もっとも印象的だったエピソードをご紹介しましょう。あるとき、日本でいちばん大きな神経科学の学会に参加したさいに、何千件とある演題のなかで、私の興味がある分野がほんのちょっとしかなく、自信を失いかけたことがありました。宮川先生に「こんなに脳に関する演題があるなかで、自分にとって興味があるものがほんの数件しかない。ほんとうに自分は脳に興味があるといえるのでしょうか」と悩みを打ち明けました。そうしたら先生は、「私から言わせれば、毛内くんが興味のあるもの以外の研究をしているほかの人のほうが、ほんとうに脳に興味があるのか疑問だ」と言い放ったのでした。つまり、私(や先生)が興味をもっていることこそが、脳研究のなかでもっとも重要だと全肯定してくれたわけです。
へたをするとマジョリティに流されてかんたんに自信を失いがちな私にとって、自分のやってきたことに対する確固たる自信やポジティブでありつづける姿勢は、心の底から見習わなければなりません。このひと言は、いまだに脳科学の裏街道を孤独にひた走る私の心の支えになっています。
この脳科学の裏街道を行こうというのも、自分で決めたような気がしていましたが、いまにして思えば、じつは宮川先生が導いてくれたのだと、あとから気づきました。たとえば、ある日、まだ進路に悩む私となにげない雑談をして去っていった先生が学生部屋に忘れていったのは、とある研究論文を集めたファイルでした。それを読んでみると、おもしろいことおもしろいこと。のちに私のライフワークとなるようなアイディアのタネがそこにはつまっていました。意図的に忘れていったのでしょう、私が食いつくのがわかっていながら。そののことを思い出すたびに、してやられた、という気持ちで顔がニヤけてきます。
学部、大学院をとおして、宮川先生のもとで9年間、学ばせてもらいました。

つぎの進路では、これまで取り組んだことのないまったく新しい分野の開拓に取り組む予定でした。しかし、大学院で積みのこしてきた課題もあります。私は先生に、「ひと段落したら大学に遊びにいって、積みのこしてきた課題にも取り組みたい」と相談をしました。そうしたら、「フランス料理のシェフをめざす人が、同時に和食の板前になれるわけがない。まずはフランス料理で一人前になってきてください」とお叱りを受けました。つまり、未練があるのはわかるけど、これから新しいことをはじめると決めたなら、その分野でまず一流になってこい、あれもこれもなんて思う人が一流になれるわけがない、ということなのだと私は解釈しました。わが子を千尋の谷に突き落とす、ということなのかもしれません。それで私の未練は消え去り、新しい分野でやっていく腹が決まったのでした。
いつまでも追いつづける背中
それから3年間、宮川先生が定年退職されるまえに〝一流のフランス料理シェフになろうとしている姿を見せる〟と決めて、がむしゃらに働きました。そして、念願かなって、ギリギリで論文を発表することができました。先生の退職記念の講演会では、研究者をやっている教え子が研究内容について発表しましたが、光栄なことに私もそのなかに入れてもらうことができ、うれしそうに私の話を聞いてくれている先生の顔を見て、涙が出そうになりました。
最終講義で先生が、「卒業生一人ひとりが私の自慢」と満足そうに語っていたのを思い出します。研究室の同窓生は、みなすばらしい方たちばかりです。著名な神経科学の先輩もたくさん輩出し、なかには、王道を行く輝かしい業績を連発するスター選手のような先輩もいます。宮川先生に、自分はこれでいいのかとあせる気持ちもあると相談したら、「あいつにはあいつの得意なやり方があるけど、毛内くんがまねしてもうまくいくものではない」と、温かい励ましのことばをいただきました。自分のやり方を貫きとおせばよいのだと、いつも自分に言い聞かせてがんばっています。
定年退職後は自転車やクラシックギターなど悠々自適な生活を送っている宮川先生は、「現役時代は、忙しくて考える時間がとれなかった問題に、ようやくじっくりと取り組めている」と充実したごようす。つまり、まだまだこれからだよと。いつまでたっても、先生にはかないません。
私自身の研究室の名前は、先生の研究室名からヒントを得て「生体組織機能学研究室」と名づけました。研究室のオフィスも、先生のかつての研究室のレイアウトを思い出しながらまねしています。いちばん楽しかった、あのころの研究室をもういちど。だけど、ただまねするだけじゃなくて、それを自分らしく、さらによいものに発展させていきたいと思っています。そんな私の研究室の話は、また次回に。
(次回に続く)
毛内拡(もうない・ひろむ)
脳神経科学者、お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系助教、博士(理学)。1984年、北海道生まれ。専門は、神経生理学、生物物理学。「脳が生きているとはどういうことか」をスローガンに研究を続ける。著書に、『脳を司る「脳」』(講談社ブルーバックス)、『面白くて眠れなくなる脳科学』(PHP研究所)、『脳研究者の脳の中』(ワニブックスPLUS新書)など。P・バッカラリオほか『頭のなかには何がある?』(太郎次郎社エディタス)の日本版監修も手がける。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)




