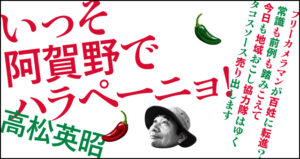他人と生きるための社会学キーワード|第15回(第4期)|「安全・安心」な社会──普遍的な価値か、身勝手な自己保身か|永島郁哉
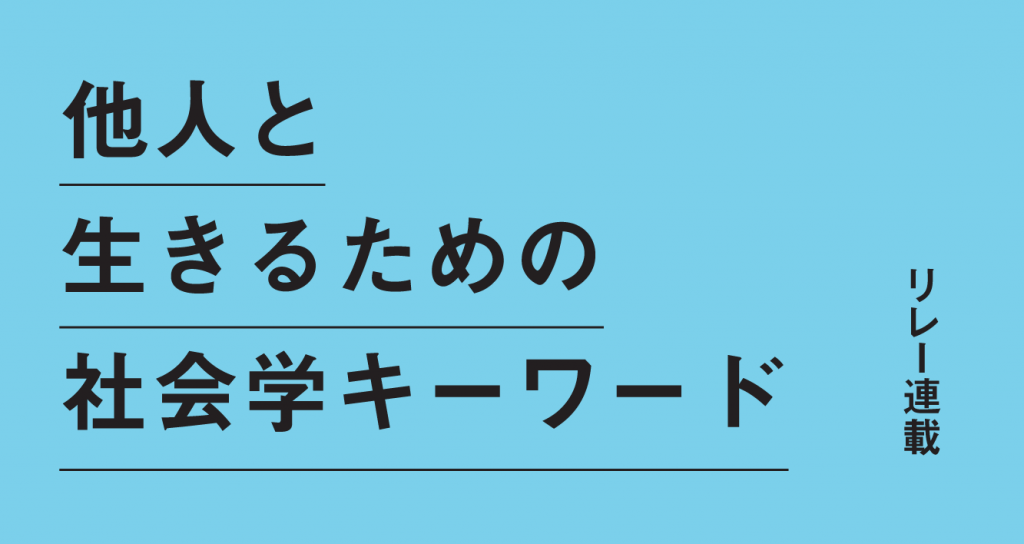
「安全・安心」な社会
普遍的な価値か、身勝手な自己保身か
永島郁哉
2025年の第27回参議院議員通常選挙で「日本人ファースト」を掲げた政党の「躍進」が報じられた。選挙期間中はその標語をめぐり、賛否の両方が激しく議論された。この表現を支持する側から、「日本は日本人のための国だ」「外国人を優遇する政策がある」といった排外主義的主張がおこなわれた。他方で、これに反対する立場からは、「外国人なくして日本はたちゆかない」「外国人も日本の構成員である」といった対抗言説が展開された。
選挙後、政党の代表は、産経新聞のインタビューに対し、「われわれは排外主義ではないし、外国人に来るなとも言っていない。移民を受け入れすぎて失敗している例は少なくない。受け入れる人数を考え、ルールを厳格にしながら、日本人の反感を招かない形で、国民の不安をあおらないように制度設計したいだけだ」(産経新聞2025年8月30日、東京朝刊5面)と述べた。「われわれ」の思いどおりにならない外国人は、「われわれ」の不安をあおるので排除する。「適切」な移民は受け入れるのだから「排外主義」ではない──。そのような思考が公然と表明されている。
これは、特定の新興政党に特有の論理ではけっしてない。2025年7月15日、石破総理大臣は内閣官房に「外国人との秩序ある共生社会推進室」を発足した。この組織は、「外国人施策の司令塔となる事務局組織」と位置づけられたが、その内実は、「一部の外国人による犯罪や迷惑行為、各種制度の不適切な利用」「外国人の社会保険料等の未納付」「外国人による土地等の取得」といった課題に対処するための出入国在留管理の厳格化であった。そこで打ち出されたのは、「国民の皆様方が不安や不公平を感じる状況」に対して「安全・安心の確保」を目指す、というメッセージだった。外国人労働者の受け入れを前提としつつ、「安全・安心」言説によって「望ましくない」とされる人びとの排除を正当化したのである。
「安全・安心」という言葉によって特定の外国人を排除しようとする政策は、これが初めてではない。たとえば、犯罪対策閣僚会議が2003年に発表した『犯罪に強い社会の実現のための行動計画──「世界一安全な国、日本」の復活を目指して』では、外国人犯罪の深刻化が進むなかで犯罪の温床となる「不法滞在者」を5年間で半減させ、国民の安心な暮らしを守ることが確認された。これを受けて法務省は、2004年から2009年にかけて「不法滞在者5年半減計画」を実施し、「来させない」「入らせない」「居させない」を柱とした施策をおこなっている。法務省の発表によれば、事前確認の厳格化、偽造文書鑑識等の強化、警察機関との連携による摘発の強化、出国命令制度の実施等によって、5年間で10.6万人、48.5%の非正規滞在者を削減したという。
これをもって、法務省は「国民が安心して暮らせる社会の実現に貢献した」と述べているが、じつはこの時期、非正規滞在者に対して在留特別許可がさかんに出ていたことが指摘されている(5年間で約5万件)。つまり、10.6万人のうちの無視できない数が「正規化」であった可能性がある(高谷幸『追放と抵抗のポリティクス』ナカニシヤ出版)。法務省はあえてこうした事実を伏せたうえで、あたかも非正規滞在者の排除によって「半減」が実現したかのような語り口を採用した。それは、非正規滞在者の包摂による「安全・安心」ではなく、非正規滞在者の排除による「安全・安心」という物語(ナラティブ)が当初から用意されていたことを意味する。
「望ましくない」外国人の排除による「安全・安心」の確保という考え方は、外国人労働者の受け入れが拡大する現在の日本社会において、これまでになく重要な物語(ナラティブ)として機能しているように思われる。外国人の受け入れそれ自体に反対することは現実的ではなくても、「望ましくない」「好ましくない」外国人の排除は、「国民の安全・安心を守るため」という名目で正当化できるからである。いわば排除の免罪符として「安全・安心」という言葉が必要とされているといえる。
2024年成立の改正入管法では、永住者の在留資格取消事由に公租公課の不履行が追加されたが、その背景のひとつには、外国人に各種保険料や税金の納付義務を遵守させることで「安全・安心」な社会を目指す、という政府の方針があった(『外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ』)。つまり、育成就労や特定技能などの在留資格を通じて今後増加が予想される永住者に対して、かれらの在留資格を取り消す手段を用意しておくことが、「安全・安心」という言葉で根拠づけられたのである。このように、増加する外国人人口を前提に、かれらの管理を強化し、「望ましくない」対象を排除する仕組みが、「安全・安心」言説を通じて制度化された。
* * *
もちろん「安全・安心」は、だれもが追い求める普遍的な価値である。人はだれでも安全な環境で安心して暮らしたいと思うのが普通である。一方で、この言葉が特定の集団に専有されるとき──たとえば「国民の安全・安心」を意味するとき──それはだれかの「安全・安心」のために他者を排除する論理を覆い隠す道具となる。在留資格を失った難民申請者のように、不安定な法的地位のなかで安全や安心を希求する人びとは、「国民の不安をあおるから」「犯罪の温床になるから」という理由で排除される。それによって得られる「安全・安心」の感覚は、普遍的な価値ではけっしてない。
「安全・安心」とは本来、社会全体で共有されるものではないだろうか。それが普遍的な価値たりえるのは、他者の「安全・安心」が自らの「安全・安心」と連続しているという感覚が共有されているときである。もし隣人が不安定な地位におかれ、生活基盤を脅かされているなら、その不安は社会全体の不安であり、わたし自身の不安でもある。逆に、隣人が法的地位や生活保障を得て、安心して暮らせるとき、その「安全・安心」は社会全体のものであり、わたし自身のものでもある。「安全・安心」は排除によって確保されるのではなく、むしろ包摂によって強化される。実際、移民や難民を受け入れる欧州の国々では社会統合政策が積極的に推し進められてきた。それは、かれらがホスト社会に受け入れられ、ライフチャンスを得ることができるという「安全・安心」を確保することが、社会全体にとっての「安全・安心」につながると認識されているからである。
2010年、ドイツのメルケル首相は「多文化主義は失敗した」と発言した。イスラーム人口増加による社会不安がドイツ国内に広がるなかでのコメントだった。これは「移民大量受け入れの失敗」として現在においてもひんぱんに引用されることがあるが、じつは彼女は同じ演説のなかで「イスラームもまたドイツの一部である」とも述べている。その真意は、ドイツがこれまで移民に対し社会統合をあまりにも求めてこなかったことを反省し、かれらをドイツの一部として組み込むための積極的な制度の必要性を説くことであった。その後推進された社会統合政策は同化主義的側面をもっていたが、少なくともそこには、移民の排除ではなく包摂こそが、ふくらむ社会不安を解消する一手になるという発想があった。
外国人労働者の受け入れはもはや既定路線である。しかし、その先にあるはずの統合や包摂をめぐる議論は日本ではほとんど聞かれない。結果として、来日した外国人は管理の対象となり、「国民の不安」が増幅すると、排除というかたちで解決を図ろうとする。この流れのなかで、「安全・安心」という言葉は、外国人と共に生きる社会を築くための共通目標ではなく、「国民の不安」を静めるための統治の道具として機能してしまっている。
「安全・安心」という言葉が使われるとき、それがはたして普遍的な価値なのか、あるいは自己保身のための道具なのか、わたしたちは注意深く見きわめる必要がある。排除ではなく包摂によって、他者の不安もわたしの不安として引き受けるとき、初めてこの言葉は普遍的な力を取り戻すのではないか。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
高谷幸『追放と抵抗のポリティクス──戦後日本の境界と非正規移民』ナカニシヤ出版、2017年
駒井洋監修・加藤丈太郎編『入管の解体と移民庁の創設──出入国在留管理から多文化共生への転換』明石書店、2023年
五十嵐彰『可視化される差別──統計分析が解明する移民・エスニックマイノリティに対する差別と排外主義』新泉社、2025年
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
永島郁哉(ながしま・ふみや)
島根大学教育学部附属教師教育研究センター特任助教。専門分野:国際社会学、共生社会学。
主要著作:
『多様性〈いろいろ〉と凝集性〈まとまり〉の社会学』(共著)、太郎次郎社エディタス
「団地問題研究に対するエスニック境界論の援用可能性──地域社会論の再評価に向けて」『ソシオロジカル・ペーパーズ』第32号、2023年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)