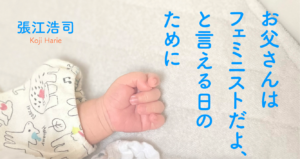いっそ阿賀野でハラペーニョ!|第15回|ネキリムシと支柱立てとジュンサイの6月|高松英昭

第15回
ネキリムシと支柱立てとジュンサイの6月
ここから先は自己責任じゃない、という安堵感
定植作業を終えると、心の底で澱のように溜まっていた不安が体から落ちていくように安堵した。農業用ビニールハウスのなかで育苗していたが、その人工的につくりだした環境から、これからは人間のコントロールが及ばない自然環境のなかでハラペーニョを育てることになる。不確実性が増す一方で、自分がつくりだした環境ではないので、定植した苗が不測の事態で全滅して収穫できなかったとしても、「大自然には勝てませんな」などとうそぶいて責任転嫁しようというよこしまな気持ちが心を軽やかにしている。
私は不安症なところがあるので、育苗しているときは、発芽しなかったり、苗が枯れて全滅している夢を何度か見た。責任転嫁できるものをずっと求めていた。自然というだれもがコントロールできない不確実性の塊のようなものに責任転嫁すれば、自分を責めないですむ。不安感を排出する排水溝のような逃げ道を必要としていたのだ。
路上生活者をテーマに取材していたとき、新宿駅で寝泊まりしていた若者が「明日、アルバイトの面接に行く」と意気揚々としていたが、結局、面接に行かなかったことがあった。理由をたずねると「足の親指が痛かったから」と小さな声で言った。「それはただの言い訳で行きたくなかっただけじゃないの?」と私があっけにとられながら詰問すると、彼は黙り込んだ。
いま思うと、彼は不安だったのだろう。面接に行くことも不安だったし、働きはじめることも不安だったにちがいない。その不安から逃れるために、彼は面接に行かないという選択をした。そして、自分の足の指に責任転嫁した。他者に責任転嫁するのではなく、自分の足の指に責任転嫁した彼は誠実な人柄なのかもしれない。彼が心にため込んだ不安感を軽くさせる言葉をかけてあげればよかったと後悔している。
「地域おこし協力隊の任期中は、失敗できる期間でもあると思う。その失敗が任期終了してから役に立つ経験になればいいじゃない」
阿賀野市として協力隊の活動をどのように考えているかを情報発信しようと、私が所属する企画財政課の課長と打ち合わせをしているときに、課長が言った。地域おこし協力隊員は活動をとおして地域活性化につながるようなイノベーションを求められることが多いが、それが縛りとなって新しいことに挑戦することへの不安の種になっている場合もある。
そもそも、タコスソース事業は「美味しいタコスを食べたい」という私の個人的な想いが起点になっている。地域活性化につながる事業計画になるように肉付けしたが、目的は「美味しいタコスを食べたい」でいいと思っている。個人的な期待や希望はオブラートのように不安を包み込んでくれる。課長は協力隊の活動を、個人の希望が土台になるものと考えているから「失敗できる期間」と言ってくれたのだろう。自分が企画した事業がようやく走りはじめたころだったので、課長の言葉は福音となって不安を溶かしてくれた。課長は舞台俳優みたいに感情豊かに表現する人柄で、戯曲を観劇しているような気分になる。
ただ、「失敗できる期間」とはいえ、畑に定植して、あとは自然まかせで野となれ山となれというわけにはいかない。できるだけ失敗は避けたい。食料が確保できるかどうかわからない不安感から逃れるために農耕は始まった。自然のなかで確実に収穫するための対策は必要なのだ。

支柱と苗をひとつずつひもで結んでいくのだが、そのようすはこのあとに!
ネキリムシと「生と死」の日常性と
定植した翌日、畑に行くと、ところどころで苗が倒れていた。サルが遊び半分に引っこ抜いたのかなと思いながら、マルチ(畝の土を覆うビニール)の上に倒れている苗をつまみ上げると、茎がプツンと切れていた。マルチに穴を開けて定植したところを注意深くのぞくと、地際から茎が切断されていた。もしやと思い、土を少しずつ掘り返していくと、3センチほどのイモムシみたいな幼虫が出てきた。ネキリムシの仕業だった。ネキリムシは蛾の仲間の幼虫で、昼間は土中に潜み、夜になると土から這い出て、地際の茎を食べてプツンと切断してしまうのだ。
殺虫剤を使わずにネキリムシを駆除するには、夜にヘッドライトで照らしながら茎を食べているところを捕殺するのが手っとり早いが、クマやイノシシと出会う危険もあるし、そもそも、夜な夜な暗闇のなかでライトを照らしながら小さなネキリムシを探す根性と気合は私にはない。「ネキリムシを捕殺しないといけないので時間外労働を申請したいのですが」と担当課に相談しても「ほかの手段はないのですか」と、にべもなく却下されるだろう。ネキリムシの食害は、多少のことなら目をつぶることにした。
というのも、定植後は虫の食害にあうこともあるし、根付かずに枯れてしまう苗もあることは予測していたので、補植用の苗をよぶんに作っていた。食害にあった苗を数えてみると15本くらいで、補植用の苗は20本ほどあるのでなんとかなりそうだが、こんなことならもう少し多めに補植用の苗を用意しておけばよかったと後悔した。
人差し指で土をホジホジしながらネキリムシを探しだして捕殺しながら補植するのだが、すでに別の場所に移動しているのか、さすがに簡単には見つからない。砂金を探す金鉱労働者のように指先でホジホジをくり返し、ネキリムシが見つかると宝物をみつけたように感激してしまい、だんだん、ネキリムシが愛おしくなってきた。くるんと丸まって頭と尻をくっつけている姿もかわいい。このままだと、1匹1匹に名前までつけそうになる。
手のひらにネキリムシをのせて、指先でネキリムシをころころと愛でるように転がして、「すまんな」という感情をのせて指の腹で押しつぶした。自分のなかにサイコパス性があるかどうかはわからないが、腕にとまった蚊を当たりまえのように潰すように、日々の暮らしのなかに残虐的な行為は潜んでいる。ただ、それを自覚していないだけだ。農業や狩猟に身近に触れるようになってから、生と死がいたるところに溢れていることに気づかされる。
「できれば熊は撃ちたくないけどね」といった地元猟師の言葉が印象に残っている。自然が濃い場所での暮らしは、自分も生態系を構成する一要素に過ぎないことに気づかされる。ネキリムシを捕殺することは農業をする私の日常であり、自分が殺す側の立場にいることも自覚している。同じ自然のなかにいる生物を愛でもするし、自分の暮らしのために殺すこともある。

支柱用の竹をすべての苗と結ぶ
ネキリムシの食害にあった苗の補植を終えると、竹林から切り出しておいた竹(第13回参照)を支柱にして、苗と結ぶ作業に取りかかった。竹はすっかり乾いて緑茶からカフェオレみたいな色に変色していた。ハラペーニョは生長すると1メートルほどの丈になるから、同じくらいの長さになるようにカットして、苗のわきに竹をさして麻ひもで苗と支柱を結んでいく。ついでに苗のまわりの土を指でホジホジしてネキリムシを探しながら作業しようと考えていたので、ひと手間増えるぶん、ひとつ結ぶのに3分ほどかかるとして、250苗あるから750分、約13時間はかかると見込んだ。勤務時間内の作業で3日ほどかかりそうだった。
化学繊維でできたひもは安価だが、天然素材の麻ひもは収穫後の片づけで畑に落としても、腐敗して土に戻るので都合がよい。麻ひもを枝の上の部分にまわして、苗と支柱のあいだでひもを交差させて8の字をつくり、支柱と結ぶ。枝の上の部分でまわすのはひもがずり落ちないようにするためで、8の字をつくって交差させるのは茎が太くなることを想定して空間をつくり、ひもが茎に食い込まないようにするためである。
知り合いの農家から教えてもらったことで、経験に裏打ちされた職人技のようなものを伝授されたと思っていたが、インターネットで検索したら同じことが出ていた。必要な情報にアクセスできるのは便利だが、なんだか味気なさを感じる。成功と失敗をくり返して生まれた知恵は、先輩農家から教えてもらったほうが「どうしてそうするのか」を体験から聞くことができ、学ぶことも多い。ただ、私の農業知識の半分はインターネットとYouTubeに頼っているのも事実だ。先輩農家も農繁期は忙しいのだ。
今後の段取りを考えながら作業していると、竹が足りないことに気がついた。ハラペーニョの実は肉厚でそこそこ重い。タコスソースの原料にするために赤く熟してから収穫するので、長いあいだ、たくさんの実が枝にぶら下がったままになる。実の重さで枝が折れないように支える必要があった。そのためには、新たに2メートル間隔くらいに支柱となる竹を立てて、そこにひもを張って枝を支えようと考えていた。ひもにはかなりのテンションがかかるはずだから、前回切り出した竹より少し太めのほうがいいだろう。
支柱と苗を結ぶ作業は予定よりも早く終えることができた。あらかじめ必要な長さにひもも切っておいたり、竹をまとめて苗のわきにさしておいてから結んだほうが無駄な動きをせずにすむことに気がついたからで、同じ作業はまとめてするほうが効率がよかった。
あとから考えると「そりゃそうだよね」と思うことでも、「苗と支柱を結ぶ」ということだけに意識を奪われると段取りまで気がまわらないことが多い。農作業を手伝いに行くと、先輩農家から「そんなことしないで、こうしたほうがもっと早いよ」と言われて、「なるほど」と気づくことが多い。それに、苗のまわりの土をホジホジしてネキリムシを探すことも途中でやめていた。見つからないのである。不思議と食害にあったのは定植した翌日だけで、それ以降は茎が切断されることはなかった。


筏を浮かべたジュンサイ採りの場に出くわす
枝を支えるための竹はそんなに多くの数を必要としないし、切り出し作業にも慣れていたので難なく終えることができた。軽トラックに竹を積んで窓を開けて走りはじめると、水田を滑るように抜けて入り込んでくる風が運転席をくるくると包んで心地よい。
ちょっとだけ遠回りしようと、来た道とは違うところを通っていると、長い棒を持って池に筏を浮かべている地元かあさんたちがいた。
「ジュンサイ採りですか」と車を停めて近寄りながら声をかけると、「そうだわね」と地元かあさんが長い棒で器用に筏を操りながら答えた。じゅんさい池と呼ばれる池なのは知っていたので地域のことを紹介する情報発信のネタになるのではないかと思い、軽トラからカメラを持ち出して「市役所で移住定住促進のための情報発信の仕事をしている高松と申します。地域の風土を伝える情報として紹介したいので写真を撮らせていただいてもよろしいでしょうか」とお願いしてみた。「こんなとこ撮ってどうするんだわね」と地元かあさんは笑った。
撮影を断られた雰囲気でもなさそうなので写真を撮りながら話を聞くと、田植えが終わると池に筏を浮かべてジュンサイを採る、地域の伝統的な風習ということだった。冒険小説「ロビンソン漂流記」の挿絵で見たような筏は廃材などを利用して組まれていて、長い棒を使って上手に操らないと池に落ちてしまうようだった。
「少しあげるから家で食べればいいわね」と地元かあさんが、帰りぎわに摘みとったばかりのジュンサイをビニール袋に入れて手渡してくれた。販売することはなく、地元で食べるだけということだったので、門外不出の食材をいただいたようでうれしい。「どうやって食べたらいいのですか」と聞くと、「軽く湯通しして、三杯酢で和えたり、味噌汁に入れて食べたりするけどね」と教えてくれた。出張先で泊まった旅館の夕食で食べたくらいで、ジュンサイを調理したことなどない。
小さな鍋にお湯を沸かしてジュンサイを入れると、手品みたいにぱっとエメラルドグリーンに変色した。使い古した小さな鍋に漂うエメラルドグリーンのジュンサイは、近所の定食屋にドレスを着た結婚式帰りの女性が現れたみたいで、じっと見入ってしまう。いかんいかんとあわてて、ジュンサイを包むゼリー状の膜を落とさないようにざるにあげて冷ます。
三杯酢の作り方がわからないので、グーグルで検索した。地元かあさんに教えてもらいたかったが、「そんなこともわからないの」と言われそうで恥ずかしくて聞けなかったのだ。

(つづく)
高松英昭(たかまつ・ひであき)
1970年生まれ。日本農業新聞を経て、2000年からフリーの写真家として活動を始める。食糧援助をテーマに内戦下のアンゴラ、インドでカースト制度に反対する不可触賤民の抗議運動、ホームレスの人々などを取材。2018年に新潟市にUターン。2023年から新潟県阿賀野市で移住者促進のための情報発信を担当する地域おこし協力隊員として活動中。
著書(写真集)に『STREET PEOPLE』(太郎次郎社エディタス)、『Documentary 写真』(共著)などがある。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)