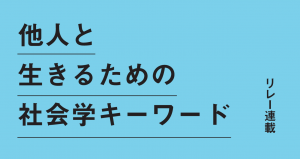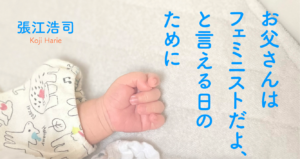いっそ阿賀野でハラペーニョ!|第10回|それ、事業になりますか?|高松英昭
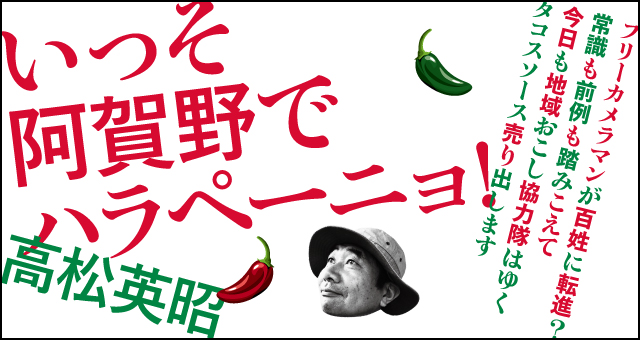
第10回
それ、事業になりますか?
6メートルの対面ヒアリング
予算ヒアリングではタコスソース事業の企画書はすでに提出していたので、企画をより具体的にイメージしてもらうために、ハラペーニョをちゃんと栽培できるのか、市の事業としてタコスソースを売ることができるのか、などの質問を想定して説明することにした。
正面に座っているN課長とH課長補佐とは6メートルほどの距離があった。30人は入れる会議室に5人しかいないのに、他人行儀な距離感である。なんだか、妙に緊張する。となりにいる担当者も大仏のようにじっとして、資料を見つめている。
「事業じゃなくて自分でやることだと思うけどなぁ~」
説明をひととおり終えると、H課長補佐がのけぞるように背もたれに寄りかかりながら言った。語尾の気を抜いてキツくならないようにしながらも、本音を吐露しているのが伝わってきた。
予想外の言葉だった。「それってプライベートでやるもんじゃね」みたいなことを言われるとは思っていなかった。返す言葉がとっさに出てこない。
N課長に目を向けると、授業参観にきた母親のように私を見ている。「さあ、ちゃんと答えるのよ。間違っていても大丈夫だからね」という菩薩みたいな表情になっている。こちらとしては「いまさらですか」と言いたくなる。というのも、私が予算ヒアリングに呼ばれた時点で、課内ではタコスソース事業が認められていると思っていた。いくつかの疑問点に答えられるようにしておけばよいと思っていたのだ。
「自己実現と地域活性化を両輪にしながら、実践的な情報発信ができると思います」。市の事業にふさわしい活動であることをアピールしてみる。「そんなこと言わんでくださいよ~」というのが本音だが。
「事業じゃなくて自分でやることだと思うけどなぁ~」。課長補佐が同じような動作をしながらくり返した。
あとは苦笑いで押しきるしかない。責任をもって事業をやり抜く決意を伝えつつ笑顔も忘れないという、難しい表現力が試されているのだ。
「できるだけ、地域おこし協力隊員が希望する活動をいっしょに取り組んでいきたいと思っています。期待しています。がんばってください」と、N課長が私のぎこちない演技にさっと幕をおろして、予算ヒアリングは終了した。どうやら、承認されたようだ。あとは、市長査定と議会を通れば、事業を具体的に進めることができる。
「使い方を知ってもらわないとね」
「高松さん、タコスソースの使い方をわからない人が多いと思うので、レシピも宣伝する必要がありますね」
会議室を出ると、H課長補佐が話しかけてきた。予算ヒアリングでの雰囲気と違って、魔法が解けたようにいつもの調子になっている。
「そうなんです。タコス以外にもさまざまな料理にも使えることを知ってもらえるように、レシピのPOPも作ろうと思っています」
「それはいいですね。とにかく、使い方を知ってもらわないと買ってもらえませんからね。私もタコスは食べたことないな~」
「いまはタコスブームで、新潟にもタコスを提供する店が増えているんですよ。タコスソースが完成したらご馳走しますね」
H課長補佐は翌年度、市民生活課に異動したが、市役所内で顔を合わせるたびに「タコスソースは順調ですか」と声をかけてくれた。「味がなかなか決まらなくて苦労しています。試作品をいろいろな人に味わってもらって意見を聞いています。ぜひ意見を聞かせてもらいたいのですが」とタコスソースの試作品を渡そうとすると、「店で購入するのを楽しみしているので、それまで待っています」と笑顔で応えた。
「予算ヒアリングのときに、『事業じゃなくて自分でやることだと思うけどな~』とおっしゃっていた、その言葉の意味を教えてください」と、私は単刀直入に聞いてみた。靴のなかに小石が入っているみたいで、ずっと気になっていたのだ。
「市の財政目線になるけど、商売にならずに採算が合わなかったら、市民に受け入れてもらえないと思ったのです。個人の趣味になっていないかが、気になっていたかな。事業の採算性が、市民に受け入れられるかの目安になります」とH課長補佐は言った。

汗かきで、すぐにのどが渇くので、2.5リットルの大型水筒が半日でカラになる
「確定申告書の書き方はわかりますか」
予算ヒアリングのあと、しばらくして、「高松さん、ちょっと時間ありますか」とN課長に声をかけられた。通路にある4人がけの席に向きあって座ると、N課長が税務課からもらってきた確定申告書を机の上に広げた。
「確定申告書の書き方はわかりますか。確定申告書をちゃんと書けるようになれば、経営状況を把握できるようになります」
確定申告書の項目を指さしながら、N課長は言った。そういえば、N課長は税務課長を務めていたこともあると聞いていた。
「フリーランスのカメラマンをしていたので確定申告書は書いていました。年度末になると、いつも領収書を整理するのに苦労していました」
「領収書は月ごとにクリアファイルに入れて整理すれば、あとあと楽になるじゃない。確定申告書で必要経費と収入をちゃんと把握するようにすれば、経営にも役立つから。書き方でわからないことがあれば、私に聞いてくれれば教えるから。まずは、正しい確定申告の書き方を練習しましょう」
「本当ですか」。なんだか確定申告の相談会場にいるみたいで、思わず笑ってしまう。
「本当よ」。N課長も笑っている。
「できれば節税の仕方も教えてもらいたいのですが」。私は少し悪ノリして言った。課長はただ笑っている。
N課長も私に事業経営をちゃんと意識するようにと伝えたかったのだ。それを税務課長だったN課長が確定申告書を持ち出して伝えてくれたのが、なんだか、たまらなく可笑しかった。
卓球でたとえると、係長は相手のボールの勢いを殺して打ち返すカットマンタイプだが、課長は相手のボールの勢いを利用して強いボールを打ち返す前陣速攻型タイプのようだ。予想していないところに、スパンと打ち返してくる。課長補佐はボールに前進回転を加えて打ち返すドライブマンタイプだろう。安易に打ち返すと、ボールが浮いてスマッシュを決められてしまう。私は中学時代に卓球部で前陣速攻型だった。
たしかに、タコスソースをがんばって作りました、だけでは趣味と変わらない。作ることよりも売ることのほうがもっと難しいのだ。
ハラペーニョを産直市場に売り込んだ話
阿賀野市に移住するまえにもハラペーニョを栽培していて、赤く色づくまえの緑のハラペーニョを販売していたことがあった(ちなみに、タコスソースの材料となるチポトレは、赤く完熟したハラペーニョを燻製にしたものだ)。最初は新潟市内にある市民農園で、8畳ほどの畑を借りて栽培していた。
家庭菜園で栽培した野菜でも手続きさえすれば、スーパーマーケットの産直コーナーや農産物直売所で扱ってくれることが多い。当時、私もそこで収穫したハラペーニョを売ることにした。ただ、ジャガイモやタマネギのような馴染みのある野菜ではないので、販売場所を考える必要があった。収穫量も多くないので、実験的に手広くいろいろな店で販売するわけにもいかなかった。
見当をつけたのが、新潟市の中心部にある地元の特産品を集めた観光拠点施設だった。鮮魚や地酒、旬の野菜などが並び、多くの観光客や地元住民でにぎわっていた。そこの産直市場でハラペーニョを販売してみたかったのだ。住宅街にある直売所よりも、お出かけ気分の客が好奇心から「試しに買ってみるか」と、ハラペーニョを手に取る確率が高いと勝手に想像していた。
ただ、人気のお出かけスポットにある産直市場なので、「うちで販売したいと相談にくる農家さんも多くてねえ。売り場にも限りがあるので、いまはお断りしているんですよ」と言われかねない。なんせ、こちらは市民農園で育てたハラペーニョを販売しようとしているのだ。足元を見られたら、それで終わりかもしれない。店長にアポイントメントを取るまえに、周到にプレゼン資料を作成することにした。私は悲観主義で心配性なのである。
まずは、どのように栽培しているかを説明するために、畑の写真を撮影することにした。広角レンズで奥行きを出して、市民農園の小さな畑を大きく見せることにした。できるだけ大きく見せるために、ファインダーをのぞきながら撮影角度も調節した。撮影した写真を確認すると、とても市民農園の小さな畑には見えない。説明するときは市民農園であることは伏せておくことにした。
さらに、枝からぶら下がっているハラペーニョを撮影していると、定年退職して野菜作りを楽しんでいる隣の区画のとーちゃんが「一生懸命撮ってるね~」と話しかけてきた。私はファインダーから目を離さずに「はい~」と気の抜けた返事で応じることにした。とーちゃんに顔を向けたら最後、自分がどれだけ丹精して野菜を育てているかを延々と聞かされることになるのだ。いまはそんな余裕はない。
産直市場の店長は、ブリーチしたロン毛に日焼けサロンで焼いたような黒い顔の、サーファーふうの人だった。店内にある飲食スペースのテーブルに作成した資料とハラペーニョを置いて、「ハラペーニョを栽培している農家は少なく、珍しい商材だと思います」と私は店長に説明した。「商材」という言葉を使うあたりに、私のこざかしさが現れている。
「さわやかな辛みと旨味が楽しめる商材だと思います」。私はこざかしい説明を続けた。
「ハラペーニョは食べたことがないな。少しかじってみてもいいかな」
「どうぞ」と、私は店長にハラペーニョを差し出した。
店長はハラペーニョをつまみ上げると、中央部分をかじった。
「辛っ!」。顔をゆがめて、わずかにせき込む。
「種がついている白いわたの部分は辛いんです」。私はとりつくろうように言ってみた。
「これ食べてみな」。店長は顔をゆがめながら、通りかかった店員にハラペーニョを渡した。
店員はキュウリでもかじるようにして、「おいしいですよ」と言った。
「すごいな」。店長は笑っている。
「中国でもハラペーニョはよく食べますから。辛いものが好きな人が多いです」
サイさんと呼ばれている店員は中国出身で、仕入れなどを担当していた。「お客さんにたくさん宣伝して、ハラペーニョをたくさん売りますね」と、サイさんはわずかに中国語のイントネーションをまじえて微笑みながら私に言った。
こうして、売上が期待できる産直市場でハラペーニョを販売できるようになったのだった。

売り場にだせば売れる、わけじゃない
阿賀野市で計画しているタコスソース事業は、市内にある道の駅で販売することは決まっているので、販路については気分が楽だ。それに、店頭販売の実績があれば、つぎの販路も広げやすくなる。ただし、売る場所を確保しても、ようやくスタートラインに立ったにすぎない。「売る」と「売れる」のあいだには、1文字だけではすまない大きな違いがあることも、産直市場での経験から学んだ。
産直市場では自分で農産物を持ち込み、自分で陳列することになっている。バックヤードに設置されたプリンターで価格とバーコードのラベルを出力し、それを貼る。価格は自分で決めることができる。ただ、あまりにも安い値段で販売すれば、価格破壊が起こり、同じ農産物を販売する農家に迷惑がかかるので、おおよその相場はある。今回はハラペーニョを販売する農家は私だけなので、価格は自由に設定することができた。
とはいえ、ハラペーニョ販売は初めてのうえに、近隣のスーパーや直売所でハラペーニョを見かけることはなかったので、妥当な価格がいくらか見当もつかない。ネットで調べて参考にすることにしたが、一番のポイントは「試しに買ってみようかな」と気軽に手にとれる価格である。ただし、やみくもに少量・安価にすれば、そのぶん、袋詰め作業の手間がかかるし、袋代のコストもふくらむ。
とくに確たる根拠もなかったが、200グラムを200円で販売することにした。200グラムだと袋にハラペーニョが5、6個入り、見栄えもよい。観光客やお出かけ気分の客なら気軽に手に取ってもらえると考えた。
初出荷の日は、早朝5時に起きてハラペーニョを収穫して、自宅の部屋でハラペーニョをデジタル計量器にのせ、いそいそと袋詰めして、16袋ほどを準備した。もちろん、形のよいハラペーニョだけを選んである。初陣は選抜メンバーで臨むことにした。
初出荷で店頭に並べたハラペーニョが完売することはなかった。売れ残った商品は、農家が自分で引き揚げることになっている。傷むまえに、収穫したばかりのものと入れ替える必要があった。腐ったハラペーニョを店頭に置いたままにしておけば、イメージダウンにもなる。
引き揚げたハラペーニョはできるだけ自分で消費するようにしていたが、そんなに毎日は食べられない。収穫量が多くなると出荷量も増えるが、そのぶん売れなければ引き揚げる量も増えるので、廃棄することも多くなっていった。作ったものを廃棄するのは、自分を否定するみたいで悲しかった。
今度のタコスソース事業でも、売り方を工夫する必要があった。予算ヒアリングのあと、H課長補佐が言った「タコスソースの使い方をわからない人が多いと思うので、レシピも宣伝する必要がありますね」というアドバイスは、まさに、そのとおりだったのだ。
(つづく)

無農薬、有機肥料で栽培したので大きさにバラつきがあるが、加工用なので問題ない
高松英昭(たかまつ・ひであき)
1970年生まれ。日本農業新聞を経て、2000年からフリーの写真家として活動を始める。食糧援助をテーマに内戦下のアンゴラ、インドでカースト制度に反対する不可触賤民の抗議運動、ホームレスの人々などを取材。2018年に新潟市にUターン。2023年から新潟県阿賀野市で移住者促進のための情報発信を担当する地域おこし協力隊員として活動中。
著書(写真集)に『STREET PEOPLE』(太郎次郎社エディタス)、『Documentary 写真』(共著)などがある。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)