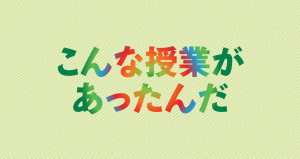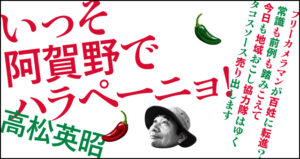拾いもの探偵の取材帳|第2回|ベルベットの握りこぶし|谷本雄治

※一部、刺激の強い写真は小さくしてあります。写真をクリックすると拡大されるので、好奇心旺盛な方はどうぞごらんください
第2回
ベルベットの握りこぶし
異形の落としもの
なんとも奇異な落としものだ。
赤子の手のようであり、何かの力でかためた炎のようにも見える。それがなぜか、木の葉にくっついたまま落ちていた。
オオサンショウウオがふと、頭に浮かんだ。
18世紀のヨーロッパで未知の化石が発掘されたとき、学者らは言った。
「おお、神よ、おのおの方、憐れみたまえ。これは……これこそは……」
「言うまでもありませぬ。〝ノアの方舟〟の大洪水で死んだ赤ん坊の頭骨ですな!」
「いかにも。まさに、その赤ん坊じゃよ」
謎の化石はこうして、旧約聖書にもとづく「洪水の人間の証人」に祭りあげられた。かの地の人びとが生きたオオサンショウウオを見るのは、日本を追放されたシーボルトが持ちかえるまで1世紀ほど待たねばならなかった。そして学界はようやく、オオサンショウウオの化石だったことを知る。
したり顔で「証人」と断じた学者センセイを、笑わば笑え。想像の翼は、広げるだけ広げるのがいい。ちなみにオオサンショウウオの学名にはいまも、「人間の似姿」という意味の属名が使われている。
それはともかく、けったいな拾いものを赤ん坊の手に見立てるのはさすがに無理がありそうだ。オオサンショウウオの逸話よりももっと怪しい。形を伝えるためとはいえ、悪い印象を与えかねない。
植物学者の牧野富太郎は、同じ草や木をいくつも何度も採集した。時期や生えている場所が違えば、見た目も変わる。図鑑に載せるのは、その植物の特徴をもっともよく表すものがふさわしいと考えたからだった。
この拾いものもそうだ。せめてあといくつか、正体を見極めるためのサンプルがほしい。ほかには落ちていないだろうか……。
日ごろの運動不足を補うことも兼ねて、首をぐるりぐるぐる回してみた。
と、あるではないか。まったく同じとは言えずとも、同類と見なしてよそうなものがその場で3個、すぐに見つかった。いびつな形をしたものどもは、それぞれが個性的だった。
あらためて観察すると、赤ん坊の手よりも福助人形の耳に似ている。いやいや、しわだらけの握りこぶしと言うべきか。いずれにしてもふっくらしていて、表面はベルベットを思わせる。
それにしても、こんなに落ちているのは不思議である。
――ん? 落ちる?
せまい範囲でいくつも見つかるということは……上だ、上を見るべきだ。なんとも単純な話である。
顔を、こんどは上に向けた。
あるある。まだあった。福耳や握りこぶしに見える物体がいくつか、木の枝にへばりついていた。
この木が落とし主だということは、もはや疑いようがない。かくして拾いもの探偵の推理は、急展開を迎えた。
落とし主はヌルデの木
どこかで見たような気がする。
そうだ、クルミだ。その木には青梅のような実こそ見えないが、何度か山で見たクルミの木に似ていた。
それなのに、どことなく違う。
ハンディ版の樹木図鑑を開いた。オニグルミ、ニガキ、ウルシ、ニワウルシ、ヌルデなど数種が候補に挙がったが、識別の決め手になったのは葉のようすだ。いずれも複数の小さな葉からなる奇数羽状複葉の木なのに、ヌルデだけ、小葉を支える葉軸に翼がついている。
ということは、奇形物体の落とし主はヌルデの木だ!
――むふふ。これにて一件落着だな。
説明文を読むと、虫が葉にこしらえる虫癭、俗に「虫こぶ」とよばれるものだと判明した。嬰児の嬰をふくむ「癭」を使うため「虫の赤ん坊」も想像させるが、とくに関係はないそうだ。虫が植物にとりつく刺激でこぶができることから、「とり囲む」「とりつく」といった意味で採用した漢字らしい。
虫こぶをつくる虫はアブラムシ、タマバエ、タマバチなどが知られる。ヌルデにはヌルデシロアブラムシが関与するらしく、その虫こぶには「ヌルデノミミフシ」の名がついていた。ミミフシというくらいだから、耳にたとえるのは的はずれでもないということだろう。
だが、異形の虫こぶはほんとうに、そのアブラムシの作品なのか。
ひとつだけ、そーっと割った。
すると――。
いた、いた。虫ぎらいの人が見たら卒倒しそうなくらい、ごちゃごちゃゴマンとアブラムシがいた。ろう細工を思わせる透明感のあるアブラムシの集団が、虫こぶの内部を占拠していた。
――へえ、これがヌルデシロアブラムシか。
この虫がいることで生薬の「五倍子」が生まれ、お歯黒や白髪染め、せきどめ、下痢どめなどになったのだ。知識だけでは埋められなかったパズルのピースが見つかったようで、うれしくなる。
ぼくは若いころから虫や植物の利用に興味があり、薬用昆虫や植物の民間利用に関する本を何冊も読んできた。深く考えずにためこんだ新聞や雑誌の切りぬき記事も多い。だが、そんなのは自己満足だ。
ところが今回はたまたま拾ったヌルデの虫こぶのおかげで、そんなあれこれが「取材帳」となって役立った。読んでは忘れ、また開いて忘れのくり返しだが、こういうこともあるから、拾いもの探偵はやめられない。
それにしても「ヌルデ」とはそもそも、いかなる意味なのか。
それは、ヌルデがウルシ科の樹木であることに関係する。枝を折ると、白い液が出る。それを漆と同じように塗りものに利用したから、「塗り手」がなまってヌルデとなったという説がある。そうかと思えば、その液を「ヌテ(塗料)」に使ったからだとする説もある。
いずれにせよ、なにしろウルシ科だ。ぼくはなんともないが、かぶれる人もいる。手で触れるときには気をつけたほうがいい。
ヌルデは、材としてもよく利用した。日本の真言宗では、ヌルデを護摩木にする。火にくべるとパチパチと勢いよくはぜ、その音で邪気を払う。ヌルデを「ゴマキ」とよぶ地方もあるのは、そんなつながりからだろうか。
見分けられるようになるとヌルデは、身近な木だとわかる。道路脇でよく見る。しかし視界の妨げになるからか、バッサバッサとかんたんに伐られる木であることも知った。
それならと、伐採後に拾った枝のかけらもある。適当に削って、飾りにしたい。
というのも日本には古くから、神棚や家の入り口に「削り花」を飾る風習があるからだ。ヌルデ材を薄く削って菊の花や御幣のようにし、豊作を祈り、魔よけにした。聖徳太子(厩戸王)が四天王像をつくって戦勝を祈願したという伝承もあり、それから「勝つ木」にちなむカツノキ、カチノキの呼び名も生まれた。だからぼくもそれをまねてみたいのだが、いまだに手つかずである。
虫こぶがつくる塩
「ヌルデはなあ、塩の木ともよぶんやで」
「なんで? 木をなめると、しょっぱいんか」
そんなたわいのない会話を友人と交わしてからずっと、「塩の木」が気になっていた。
塩というからには、その理由があるはずだ。手近な本で調べたら、秋にできる実に由来するとわかった。海なし県・信州には、塩がわりにしていた歴史があるという。
味わってみたいという気持ちが、日増しにふくらんだ。結実したヌルデの木はたまに見かけるが、てっぺんにできるようで手が届かない。そうなると、思いはますます募る。
チャンスはふいに訪れた。
なんてことはない。駅まで続くふだんの散歩道の途中で、それほど高くないヌルデの木に実がついていたのである。しかもうまいぐあいに、道から見下ろす位置関係になる。
――なるほど、こういうものか。
まさに、一目瞭然。房状になったヌルデの丸い実のひと粒ずつに、白い粉が吹いたような、ちょっと湿った感じの結晶が張りついていた。
手を伸ばし、舌の先で味わった。
食塩とは異なり、まろやかな酸味がある。その成分はリンゴ酸カルシウムで、腎臓の悪い人に用いるとあとで知った。そうなるとさらに、ありがたみが増す。
いつも持ちあるくピンセットで塩を集めようとしたのだが、みぞれ状なので粉を払いおとすようにはいかない。こんな状態のものを、山国の人びとはどうやって利用したのだろう。
帰宅後にいろいろと調べたが、解は見つからない。それでも乾燥した実が「塩麩子」という生薬になることはわかった。
翌日。その実をいくつか持ちかえり、天日干しにした。一部は塩がついたまま、コップに入れて水を注いだ。コップを軽く振ると、塩は溶けたように見えた。
試しにひとなめ。
――あー。塩水だ!
想像でしかないが、調理するさいにはこうやって塩水として使ったのだろう。
乾燥した実も口に入れたが、やはり塩味があった。保存するなら乾燥品がいちばんだから、塩麩子として下痢・せきどめにしたり、塩として調理に用いたりしたのではないか。
ヌルデの虫こぶを気味が悪いものだと思ったら、独特の塩味にたどり着くことはなかった。ヌルデシロアブラムシにはやっぱり、お礼を言うべきかもしれない。
拾ってきた虫こぶを見たら、いつのまにか出口があって、黒いはねの生えた有翅成虫が群れていた。
シロがクロになるなんて! どこまでも楽しませてくれる虫こぶである。
谷本雄治(たにもと・ゆうじ)
プチ生物研究家・作家。1953年、名古屋市生まれ。田畑や雑木林の周辺に出没し、虫をはじめとする、てのひらサイズの身近な生きものとの対話を試みている。肩書きの「プチ」は、対象の大きさと、研究もどきをたしなむという意味から。家庭菜園ではミニトマト、ナスなどに加えて「悪魔の爪」ツノゴマの栽培に挑戦し、趣味的な“養蚕ごっこ”も楽しむ。著書に、『雑草を攻略するための13の方法 悩み多きプチ菜園家の日々』(山と溪谷社)、『地味にスゴい! 農業をささえる生きもの図鑑』(小峰書店)、『きらわれ虫の真実 なぜ、ヤツらはやってくるのか』(太郎次郎社エディタス)など多数。自由研究っぽい飼育・観察をもとにした、児童向け作品も多い。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)